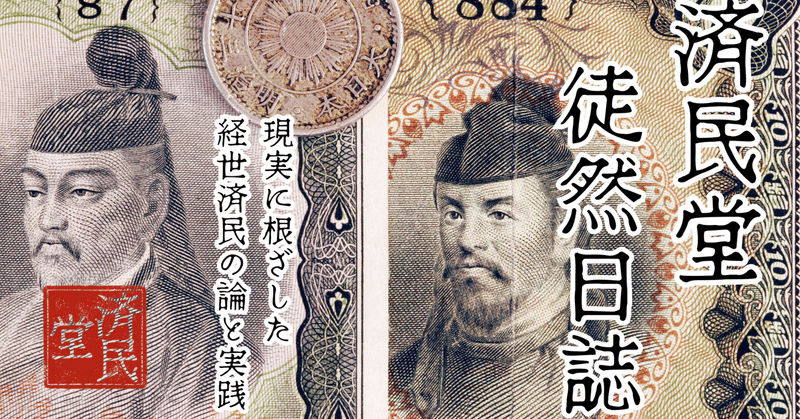
日本の歴史を考え直す その4「多極化時代の日本」
なぜいまさら日本の歴史を考え直さなければならないのかということは、アメリカ覇権の衰退とも大きく関係している。いまの日本人は、インテリであっても「日本がいつ誕生したのか」「日本はどういう国なのか」「どういう原理で統治されているのか」といったことを、歴史的な事実や史料をベースにして語る、ということができない人が多いだろう。これまでの時代にはそれでも問題がなかったのは、ひとえに日本はアメリカの属国としてそういうことを考える必要がなかったからだ。軍事・国防はアメリカが、思想・哲学はソ連による共産思想が戦後の日本に供給されていたので、その土台の上でゴロゴロ寝そべっていればよかったからだ。
冷戦期にアメリカは東北と北海道を支配下におく代わりに、出版やマスコミ、思想・教育面は共産主義にするという密約をソ連と結んでいたらしい。密約があったかどうかはともかく、日本の現実がそうであったことは明らかだろう。その構造の上では、国際社会からも日本は「アメリカの属国」というものとして見られていたし、それでよかった。
しかしアメリカの覇権が衰退しアメリカという看板がなくなると、日本は共産思想にかぶれた極東の訳の分からない島国ということになってしまう。端的にいえば、国際的にはアイデンティティを喪失した意味不明な国になるし、国内には文化も歴史もない空疎な人々が空回りした状態が現出するということだ。これまではアメリカという金魚の糞ぐらいに思われていた日本が、金魚がいなくなってしまったらただの糞になってしまうようなものだ。
最近の日々のニュースを見れば、それがはっきりしているだろう。三島由紀夫の「このまま行ったら「日本」はなくなってしまうのではないかという感を日ましに深くする。日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであろう」という文章そのものの世の中がいまの日本であろう。
とはいえ、では日本の歴史や文化を学ぼうと思って古典や歴史書を読んでみても、固有名詞や事実の羅列、あるいは制度史的な、無味乾燥な法令や制度、古文書の解説が延々と続いており、とても興味を持って読み進めていけるようなものではない、というのが現実であろう。そうなってしまう原因は、大きな「日本史の原理」や「歴史の原理」といったものがわからず、筋書きが見えないからだ。歴史といえばなにか争いが起こって、わちゃわちゃしているうちに立派な人や立派な考え方が出てきて丸く収まる話の連続だと思っている人も多いだろう。私自身もかつてはそのように思っていた時期があった。それこそがマルクス的な進歩史観であり、本来の歴史とはかけ離れた御伽話なのである。戦前でも、これはこれで天皇を西欧的な一神教世界の神に仕立て上げようとして、日本古来の思想や現実を無視して皇国史観を作り上げたため、これも他愛のない作り話にすぎなくなっていた。
こうした妙な御伽話を抜けて、きちんとした歴史観を持つために必要なことは「人間は我欲で動く」、「歴史書には作成者の意図が多分に入り込んでいる」、「権力者は都合の悪い事実を抹殺しようとするが、完璧にはできない」、「常に複数の勢力が権勢を争っている」といったいくつかの法則を理解しておく必要がある。
たとえば日本最初の正史『日本書紀』は、天皇家を礼賛しその正統性を主張するために書かれたと思って読むとわからなくなることが多い。『日本書紀』は戦前の皇国史観では史料的批判を許されず、戦後のマルクス史観では神話・神代の創作物として真っ当に取り上げられなかった。その見方のいずれも読み方として不適当で、書紀は藤原不比等が藤原氏による統治の正統性を主張するために作った書だととらえるべきなのである。本来日本には、蘇我氏や物部氏など、倭国の時代から日本の発展に尽くしてきた豪族たちがいた。しかしそうした勢力を駆逐して権力を握ったのが藤原氏で、その事実を隠蔽するために作った歴史書が日本書紀だと考えるべきなのだ。
蘇我氏といえば、蘇我入鹿が西暦645年の乙巳の変で討たれ、そこから大化の改新が始まった、という話は誰もが知っている。この時入鹿を討ったのが中臣鎌足で(下手人は中大兄皇子だが)、藤原不比等は鎌足の子である。「虫殺しの大化の改新」という年号の語呂合わせもあるように、「邪悪な蘇我氏を討って、中大兄皇子が立派な政治を実現した」というような話になっている。本当は、倭国の小国分立の時代から律令による統一的な政権の樹立に至るまでに道筋を作ったのは蘇我氏や物部氏といった豪族たちだったのに、藤原氏がその功績を横取りしてしまった。そしてその事実を隠蔽し、自らの正統性を主張するために『日本書紀』を作った・・・と考えれば、書かれている内容の解釈がうまく成立するのである。
実際、701年に不比等が大宝律令を制定したのちには、長屋王の変(729年)、承和の変(842年)、応天門の変(866年)、安和の変(969年)などで他氏をどんどん排斥し失脚させていった歴史が展開されている。そして1016年に藤原道長が摂政になり、「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」という権勢を誇るのである。日本書紀ばかりでなく、10世紀初頭にかけて勅命による歴史書の編纂が5回行われ、総称して六国史と呼ばれるが、そのすべてに藤原氏が関与しているのである。(『続日本紀(延暦16(797)年/藤原継縄)、『日本後紀』(承和8(841)年/藤原諸嗣)、『続日本後紀』(貞観11(869)年/藤原良房)、『日本文徳天皇実録』(元慶3(879)年/藤原基経)、『日本三大実録』(延喜元(901)年)/藤原時平))
『日本三大実録』編者の藤原時平は、讒言によって菅原道真を失脚させた人物としても知られる。こうした事実を見るだけでも、いかに歴史が藤原氏によって作られたものであるかということがわかるだろう。
そしてこれが日本史を深く理解する上で欠かせないポイントだが、藤原氏は失脚させた勢力の怨霊に悩まされることになる。この怨霊信仰こそ、日本史をわかるために欠かせない重要なピースであり、日本がいつまで経っても西洋化されない、キリスト教化されなかったということの本質でもある。
先述のとおり藤原時平が菅原道真を失脚させ、太宰府に流したのだから、ふつうに考えれば菅原道真は政治的敗者として葬り去られることになる。だが、太宰府天満宮や湯島天満宮で道真が祭神として祀られていることは誰もが知っている。こうしたことは、西洋的な一神教世界ではありえないことだ。滅ぶ勢力は神の意志にそぐわなかった劣る集団であり、ただモノがうち捨てられるように衰退して滅亡していくのだ、と考えるのが一神教だからだ。日本は多神教的な感覚で、万物に精霊が宿ると考えるから、政治的な敗者となった側にも霊魂が宿っている。そして不遇を託ったまま死ぬと、その霊魂が怨霊となって祟るという信仰がある。日本ではこの怨霊を鎮めるためにさまざまな努力がなされてきたのである。負けた側の人を祀る神社を作るというのはその最たる例であるし、ほかにはすぐれた諡号を追贈したり、物語の上で活躍させて鎮魂するというのもあり、紫式部の『源氏物語』も、なぜ源氏が大活躍する物語を藤原道長がスポンサーになって作らせていたのかということもこれで説明がつくのである。
また日本史の謎として、「聖徳太子非実在説」が数年前に話題となった。聖徳太子といえば「聖徳」といういかにも徳に満ちていたような名前や、10人の話を同時に聞いた、母・間人皇女は西方の救世観音菩薩が皇女の口から胎内に入り厩戸を身籠もった、太子が乗った馬が飛翔したなど、様々な超人伝説でも知られるが、同時に非実在説もささやかれる。
作家の関裕二は、「聖徳太子は藤原氏が蘇我氏の存在を抹殺するために、蘇我氏の功績をまとめて仮託した想像上の人物」で、ただし「蘇我入鹿をモデルにしている」と主張している。私もこの仮説が正しいと思う。「聖徳」という名前自体、『日本書紀』には一度も登場しておらず、後代の『懐風藻』という漢詩集が初出で、「生前不遇を託った人に立派な名称を贈る」という原則が働いているように見える。さらにもう一ひねりあって、一人の人物ではなくて総体としての一族の功績がまとめられているのではないか。蘇我氏の功績など消したいが、実際の事績を無視すると歴史が書けない。そこで、仮想の人物を登場させる。怨霊となると困るので、立派な人だったことにする。そうすると怨霊の鎮魂にもなり、事実も隠蔽でき、一石二鳥ということになるのだ。日本史というものはこういうふうに読んでいかなければまったく面白くないのである。そしてこの読み解き方自体が、日本文化や多神教文明の本質をよく表してもいる。このような大きな仮説を持って取り組まないと、圧倒的な量の無味乾燥な事実と史料の前にワケが分からなくなってしまう。以後私がいろいろ書いていく話の大きな前提として押さえておいて頂きたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
