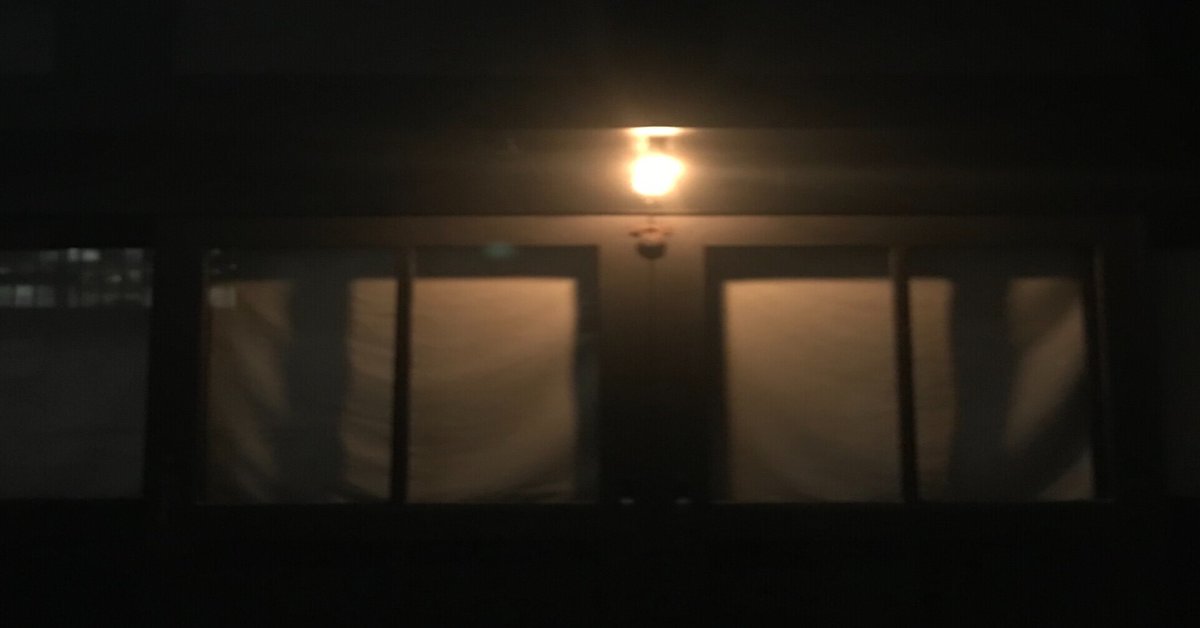
Work|HACCP導入が完全義務化
2018年6月に可決した改正食品衛生法で、2020年6月1日から「HACCP導入の義務化」が始まっています。
そして一年の猶予期間を経て、HACCP導入の義務化となり、全ての食品関連事業者に求められるようになります。これは小規模飲食店にも義務化されるもの。

初めは、なんでも安全・安心のルール、ルールで本当においしいものができるのか?なんて思っていたんですが、取材をしていくと、HACCPに限って言えば、けっしてレストランを苦しめたり、おいしさを阻害するようなものではないなぁと。むしろ、今問題になっている、働き方改革にも関係することような気がします。
HACCPについての一番の誤解は、それ自体が衛生管理調理マニュアルではない、ということ。つまり、芯温70度で1分以上加熱しないといけません、などとはHACCPはひと言も言っていないのです。むしろ理想の料理を作りたいなら、そのおいしさの価値を衛生管理の点でも解析・実証して、実現できるようにしていこう、というものです。
たとえば、前職の食の専門誌『料理王国』(2018年5月号)で取材させてもらった小田急センチュリーホテルさんでは、HACCPの考え方を取り入れています(2018年時点)。例えば、ジビエ以外の塊肉であれば、肉の内部にまで危険な細菌が入り込んでいることはないので、表面を75度1分加熱すれば問題ない、ということを外部組織の力を借りて実証したことで、表面を75度1分で加熱して、芯温53度で火をいれたHACCP対応のローストビーフを出しています。魚も低温で火を入れますが、そのかわり長時間加熱することで、HACCPをクリアしています。
衛生や安全を押し付けるのではなく、いまシェフのみなさんが経験的にやっている安全管理を、ポイントごとに解析・数値化してく。それがリーテルHACCP(飲食店向け)です。しかも、自分たちでチェックポイントを決め、管理することで、全員が監視者になって、全員が改善者になる。それは、Google MAPのようなクラウド型世界に慣れている、デジタルネイティブ世代にも受け入れやすいように思います。
僕個人の考えですが、これからの料理は「実証されたおいしさ」に向かうのではないか、と思っています。これまで数多のシェフの手によって受け継がれてきた技や考え方がなくなるのではなく、なぜおいしいのかがテクノロジーによって解明される。調理や安全管理が、デジタルによって解析・数値化されていけば、業務の効率化にもなり、フードロスの解決にもつながる。未来のレストランは、さまざまなデータによってさらに付加価値がついていく。
それを実現させるためにも、HACCPのような解析・数値化による実証は必要だと思います。何より消費者は「おいしいけど危険」より「おいしくて安全」の方が、いいですから。
お正月の餅つきが中止になったり、おにぎりをゴム手袋をして握ったり。それを時代の流れか、と寂しく思っているのではなく、餅つきを未来へつなぐために、温もりのあるおにぎりの美味しさを伝えるために、それ以外の部分をチェック・管理することでそれを可能にしていく。これなら、未来に向けて食文化を継承していくことが十分にできますし、むしろこれだけ何でも問題になる世界では、それしか方法はないのではないのではないでしょうか。
料理人付き編集者の活動などにご賛同いただけたら、サポートいただけるとうれしいです!
