
Art|ウィズコロナになってから初めて展覧会に行ってきた
毎週火曜日にアートの投稿をしている僕ですが、ウィズコロナの生活になってから、まだ美術展に行ったことがありませんでした。
そして、ようやくなのですが、先日「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」に行ってきました。東京展の会期終了間際、ギリギリです。

展覧会の関連本「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展 完全ガイドブック」を編集したこともあって、noteでも展示作品20点の解説を投稿したりと思い入れのある展覧会です。
日時指定によって向き合い方が強制的に変わる
日時指定の美術展はこれまでの行っているのですが、それは、あくまで「いつでも美術展に行ける」「入場券がなくて入れない」ということはないという前提で、ちょっとしたイレギュラーの回のような認識でした。
しかし、ウィズコロナでは、基本的に美術展は予約して行くものにかわりました。そうすると、「そうだ、明日行こう」みたいなことはなく、基本的には1週間くらい前から予定をあけて観に行くというものにかわりました。
そのため展覧会に行く回数が減ってしまうのですが、行くとなると「楽しみにする時間」がぐっと増えて、「よししっかり観てやろう」という気になります(もちろん以前からしっかり観てやろうとは思っているのですが)。
そのため、展覧会前後の時間の演出にも気を配るようになりました。Gotoイートもやっているので、食事するところも予約するようになりましたし、そこでもまた楽しみが増えたように思います。
気軽に行くものだったから、1日を使って楽しむものへ。ウィズコロナの美術展は、純度が高くなっているように思いました。
展覧会は、すごくよかったです。作品それぞれがよかったということもあるのですが、やっぱり実物は、印刷物やディスプレイで見るのとは違うと改めて痛感しました。そう感じたポイントは3つあります。
1つは「色が違う」です。
もう、当たりまえすぎて「そんなことかよ」って思うかもしれないのですが、まずはこれに尽きます。展覧会のハイライトであるゴッホの《ひまわり》はとくにそれを感じました。
この絵は、美術史の本には必ず載っているし、自分自身も何度も取り上げて、十分に知っている作品でした。この絵を模写したアムステルダムにあるゴッホ美術館の《ひまわり》や、東京・新宿のSOMPO美術館の《ひまわり》を見ていて、僕の中では「いちばん濁った黄色」だったのですが、実際に観た絵は、まったく違って「金」、もしくは後光のような「まぶしい光」でした。
これは、本当に驚いて。今までゴッホの《ひまわり》は「黄色のコンビネーション」というコンセプトの勝利だと思ったのですが、この光を感じさせる絵は、それはみんな驚いたはずです。実際に金をつかったクリムトの作品よりもよっぽど光輝いて見えました。
実物を見ないと、何もわからない。
もう1つは「作品のサイズ」です。
人間の視界にも関係するのですが、全体を認識する際に、1つ1つの絵ごとに作品との物理的な距離が違います。
大きな絵は遠くから見ることになりますし、小さな絵は近くで見ることになります。
大きな絵は、ひとつのポイントを見るのではなく、まずは全体をぼんやりとみる。それはやっぱり細部の認識がかわってきます。
とくに風景画でこれを感じたのですが、この全体をぼんやり観たときに何が見えているのかが、画家の視点なのかと、何年も絵を観てきて初めて気づきました。

トマス・ゲインズバラ 《水飲み場》
1777年以前 ロンドン・ナショナル・ギャラリー
147.3 x 180.3 cm
ゲインズバラの 《水飲み場》は、大きさによって作者の作家性に気づけた絵です。
下のカイプの作品とぼんやりとした視点で見比べたときに、自然のなかに人がいないゲインズバラと、自然を描きながらもあくまでそこにいる人を強く感じるカイプの作品からは、人間の存在をどうとらえるかという視点が盛り込まれているように感じます。

アルベルト・カイプ 《羊飼いに話しかける馬上の男のいる丘陵風景》
1655-60年頃 ロンドン・ナショナル・ギャラリー
135 x 201.5 cm
自然のなかに人間がいるのか、人間が自然と一緒にいるのか。とうぜん現在とは比べ物にならないほど自然への畏怖はあった時代だと思いますが、それであっても、人間が自然のなかでどこに存在しているのか、ということをこの絵は違った視点で描いているように感じます。
これは、本やディスプレイでは気づかなかったことです。
そして最後は「作品を見る角度」です。
これもちょっと情緒的な話して申しわけないのですが、やっぱり本やディスプレイで観たときの印象とは違ったエネルギーを感じました。
じつは、展覧会に行く前に楽しみにしていた絵に、ベラスケスの《マルタとマリアの家のキリスト》がありました。
一方で、展覧会の図録のカバーに使われている作品だけど、それほど期待していなかったのがクリヴェッリの《聖エミディウスを伴う受胎告知》です。
実際に観てみて、その期待とはまるっきり正反対の感情を抱きます。だんぜんに《聖エミディウスを伴う受胎告知》の方が、目の前で物語が起こっているように見えるのです。
これは、2つめの作品のサイズにも関係していて《聖エミディウスを伴う受胎告知》は207 x 146.7 cmと大きな作品であるため下から見上げるように作品を鑑賞します。そうすると精霊がマリアに授ける光が空から降ってくるように見えるのです。
真正面に立てばその奥へと続く道が画面に空間を与えていて、207 x 146.7 cm以上のサイズを感じ、ほんとうにその絵の中にいるように感じます。「またまたぁ、言い過ぎじゃない?」って思うかもしれませんが、これは本当です。
それと、光が壁を抜けたところが反射していて、その光がやけに明るくて、こちらに照らし返しているかのようにも見えたのは、本やディスプレイではまったく気づかなかったところです。
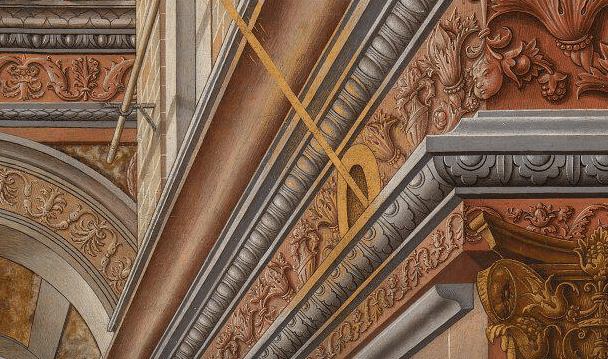
この部分、まったく複製では表現できてません。東京展は終わりましたが、大阪展はありますので、来場されるかたは、絶対に見逃さないでください。
レンブラントの《34歳の肖像》も鑑賞する視点を意識してみると、ちょっと印象が変わります。
この絵は、レンブラントが建てた工房の壁に高く掲げていたものだといわれています。ですので、ちょっとかがんで下から見上げるようにして鑑賞すると、見守られているような柔和さを感じます(さっかくかもしれませんが笑)。
作品がどこに飾られていたのかを意識してみるのはすごく大事。《聖エミディウスを伴う受胎告知》も教会に飾られるために描いたので、基本的に見上げて観るものです。
一方、ベラスケスの《マルタとマリアの家のキリスト》は、比較的小さな作品で、やや世界観が小さく感じてしまいます。さらに、近づいて真正面から見ることが前提になっているので、どうしても空間性の表現に限界があるように感じます。すばらしい作品なのですがね。
そんな感じで、あらためて「実物と複製は感じることが違うな」と感じました。
その一方で、「実物だから良いというわけではない」ことも今回改めて感じもしました。おそらく、今回感じたことは、事前に絵を何度も見たり、作品のことを調べたりしたことが影響していて、それはやっぱり複製で手軽に得られるものなのだと思います。
これも当たり前のことなのですが、美術鑑賞は、リアルに対面するときと、ヴァーチャルで体験するときの相互補完によって、よりよい鑑賞ができるのです。
そう思えば、これまでの展覧会は、知っている作品のうわべだけを「確認」するような鑑賞をしていたかもなぁと反省。
ウィズコロナになって初めての展覧会で、美術鑑賞の根本を改めて感じました。
ーーーーーーーー
東京展は閉幕しましたが、大阪展は11月から。ぜひ興味がある方、観に行ってみてください!
ロンドン・ナショナル・ギャラリー展 大阪展
2020年11月3日(火・祝)〜2021年1月31日(日)
会場/国立国際美術館(大阪・中之島)
ーーーーーー
明日は「Food」。伊勢のクリエイターに選ばれた話を。
料理人付き編集者の活動などにご賛同いただけたら、サポートいただけるとうれしいです!
