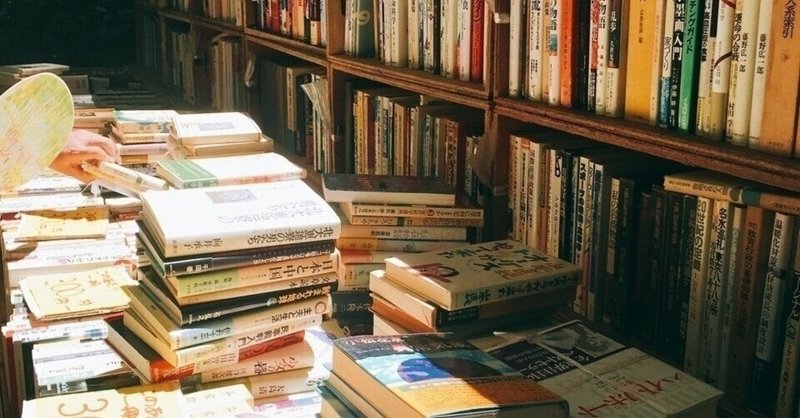
海外へ本を送る便利でお得な方法
日本からイギリスへ引っ越して3ヶ月が経過したえぬいちです。本記事では海外留学、海外転勤などの際に、お気に入りの本を持っていく際のオススメの方法について共有させていただきます。
ズバリ、それは特別郵袋印刷物という日本郵便のサービスを利用することです。ここでは、私が利用した際に、ネット上ではあまり手に入らなかったと思う情報についてまとめました。詳しい情報や最新情報は日本郵便のwebページでご確認ください。また、私の情報は2020年11月頃に利用した際の個人的なものですのでご容赦を。
どんなサービス?
サービス自体は単純明快で、「大量の印刷物」を送る際に便利な方法です。この「大量の印刷物」の中に「本」が含まれているので、海外へ本を送るのに便利!、ってなわけです。ちなみにトランプなんかもOKらしい。
使ったほうがいい理由はズバリ、料金が安いから。例えばヨーロッパに10kgの荷物を送る場合、40%割引くらいになります。すべてのケースについては確認できていませんが、遠くになればなるほど割引率は良くなって、東アジアのような近場はそこまで値段が変わらなくなるみたいです。
ちなみに料金表は日本郵便のwebページを探すと見つかります。探しても見つからないとか印刷が面倒だ、なんて方はお近くの郵便局の窓口でもらえるはずです。
取り扱い郵便局が少ない問題
本来は誰でも使えるサービスではありますが、実際には取り扱いの郵便局が限られているため、「誰でも簡単に使えるサービス」とは言い難いです。
どのくらいの郵便局で対応しているかといえば、概ねの県では県庁所在地にある一番大きな郵便局のみです。もちろん、東京、大阪はかなりの数がありますし、鳥取県なんかだと米子郵便局でも利用できますので地域差は大きいです。(具体的な郵便局の一覧はwebページで確認できます)
ただ確実に言えることは、皆さんの家の最寄りの郵便局で取り扱いしている可能性はかなり低いということになります。
私の場合も取り扱い郵便局までバスで30分程だったので、家や家に近い郵便局まで集荷に来ていただけないか尋ねてみましたが、答えはNoでした。ただこれは、公共交通機関の発達した地域の話です。基本的には同様の回答が得られるとは思いますが、制度が変わったり、他の地域では対応が変わるかもしれないので取り扱い郵便局に問い合わせて損はないと思います。
さらに、少し話がそれますが、このサービス自体がおそらく利用者が非常に少ないサービスなのでしょう。新米の郵便局員の方はこのサービスそのものを知らないというケースも多いです。そういうときは文句を言わず、暖かな声で上司やご年配の局員を呼んでもらえば、何かと丁寧に教えていただけると思います。
重量オーバーに気をつけろ
皆さんも郵便料金の仕組みはご存知かと思いますが、特別郵袋印刷物の場合も重さによって料金が変わってきます。なんで、料金の境界ギリギリを狙って荷物を詰め込むのが人の常でしょう。
ただ、重量の計測では
荷物の中身+ダンボール+郵便局が用意する袋とタグ
を合算したものが採用されます。中身とダンボールの合計は家の体重計で計測して行けばいいのですが、郵便局側が用意した袋とタグを忘れてしまってはアウトです。
記憶が曖昧ではありますが、私は家の体重計で9.9kgにして郵便局に持ってい行った結果、袋とタグ合わせて15gオーバーになった気がします。おかげで、本を一冊諦める羽目に合いました。諦めるのは良いんですが、一度封をしたダンボールを郵便局で開け直すのは面倒なので、ある程度余裕を見ておくことを強く勧めます。これについても事前に郵便局に問い合わせれば、具体的な重量を確認できる可能性もありますね。
包装の仕方
最後に、どんなパッキングをすれば良いかについて簡単に触れておきます。この点については、ネットで検索すると様々な工夫を写真付きで公開している人も多く、参考になるかと思います。
私もネットの情報を参考に、雨対策として本をビニールに入れる、外部からの衝撃対策として頑丈なダンボールを利用するの二点を実践しました。いずれも万が一の対策でしたので、私の場合は特に被害はなかったです。しかし、輸送過程の天気や税関の人の気分次第で、いくらでも本がダメージを受ける可能性は上がります。重量が増えない範囲で簡単にできそうな工夫は少し過剰なくらいがちょうど良いと思います。あと、本当に大事な本や高価な本は自分で運んだほうが良いのは間違いありません。
まとめ
今回は、海外に本を送る際に特別郵袋印刷物というのを選択肢に入れると良いですよ!というお話でした。
取り扱い郵便局まで運ぶ人的コストと特別郵袋印刷物を利用することで得られる減額コストを比較して、見合っているなぁと思った方は利用することをおすすめします。
やっぱり本は紙派の人も、こういうときは電子書籍のほうが利便性は高いなぁと思ってしまいますね。人に貸したりできないのが嫌なんだけれど。
それではまた今度。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
