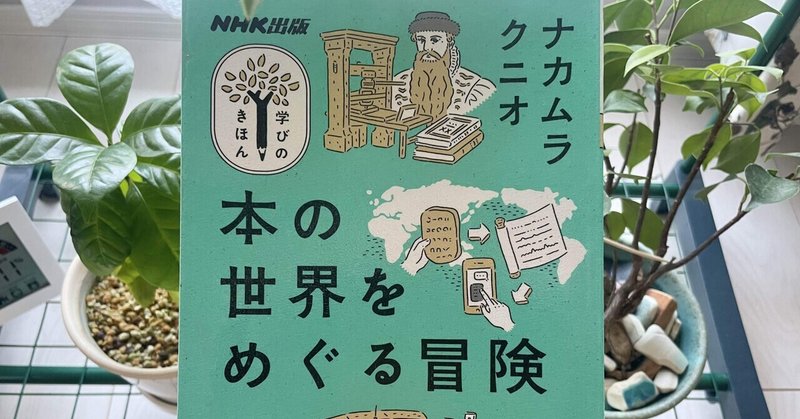
また1つ夢ができた『本の世界をめぐる冒険』を読んで
こんにちは!考えたい人◎えんちゃんです🧏♀️!
今日は久しぶりの私的大ヒット本を記録していきます!
その名もNHK出版 学びのきほん『本の世界をめぐる冒険』ナカムラクニオ著です。
この本では”読書”を知るのではなく、”本”を知ることができます。
本とは何か?本の歴史は?過去現在未来、本との関わり方は?
今までよりも本を身近に感じることができ、もっと本を知りたくなります!
私はこの本を読んで夢ができました!
それでは早速ログしていきます。
第1章 改めて、本ってなに?
この章では、”本”とは広義として情報を伝達するツールと定義しています。
その形は様々あり、語り部や結びも”本”といえるのではないかと。
日本には、今でも贈り物を包む時の「結び」の決まりがあります。代表的な「水引」は、祝儀や不祝儀の際に使われる飾り。贈答品の包み紙などにかける紅白や黒白などのひもで、その意味によって形や色を使い分けています。
数珠やロザリオ、注連縄も結びで表される“本”の1つ。注連縄や水引が”本”である、とは新しい視点でした。そしたら街中にある標識も”本”にあたるのかな?!など、これからモノの見方が変わりそうです。
第2章 本はどのように進化したのか
私たちが今思いつく紙の本は、「ペーパー」の語源である「パピルス」から始まった。このパピルスの面白いエピソードが紹介されていたので記録します。
エジプト人は何かを記憶する時に、パピルスに書いた文字を海綿で消し、その消したインクの入った水を飲む習慣があったのです。漫画「ドラえもん」に「暗記パン」というひみつ道具が登場します。ー中略ー 同じようなことをエジプト人も実際にやっていたなんて、おもしろい偶然です。
えー!暗記パンならぬ暗記水が大昔にすでにあったなんてー!(効果については不問)
そしてエジプトでパピルスが使われている一方、トルコの古代都市では羊皮紙が発展した。羊皮紙はその名の通り、羊の皮でできているそうです!見てみたい触ってみたい!羊皮紙についてもエピソード。
古代ギリシャの哲学者ソクラテス(BC469〜BC399)は、ある人から「先生はどうして書物をお書きにならないのですか」とたずねられた時、「尊い知識を、生きた人間の頭脳から、死んだ獣の皮の上に移すのが嫌だからだ」と答えたと伝えられています。
ソクラテスの哲学は本人による著書はなく、弟子のプラトンによって残されていると有名です。その理由の一説がここに繋がっているとは!おもしろい〜!
第3章 日本の本 クロニクル
ここでは日本で本が広がっていった様子を紹介しています。
まず日本最古の本は聖徳太子著『法華義疏』とのこと、、。聖徳太子が書いた本があるとは知らなかった!聖徳太子の息遣いを感じることができる物が残っているの〜!?ロマンー!
江戸時代で木版印刷による出版が盛んになると、浮世草子、黄表紙、洒落本、滑稽本などが出版され、一般にも広く読まれるようになりました。出版元としては、江戸時代後期の出版プロデューサー蔦屋重三郎(1750〜97)がよく知られています。
時は進んで江戸時代。本の普及に貢献した1人として蔦屋という名前が。やっぱりこれを見てしまうと蔦屋書店ってここから始まっているの!?と思いますよね。
Wikiで調べてみました。
結論から言うと蔦屋重三郎との関係はないようです、、蔦屋ァ。
現代でも、江戸時代を参考とするかのように、本と何かを「兼業」する本屋さんが増えてきています。
江戸時代、本屋は本を売るだけでなく出版・卸売・古本売買・貸本など建業が行われ、多くの人が集まった。現在の兼業例はビールが飲めたり、家具販売、自宅など、、この辺りから私の夢も膨らんできます。この興奮のまま第4章へ!
第4章 本の未来をめぐる冒険
本との付き合い方の例が複数紹介されています。夢が広がりますよ!
まず今私が一番興味がある読書会!
読書会の形も様々で「本の感想を語り合う」「みんなで効率的に読むアウトプット勉強会」「課題本からの気づきを語り合う場の形成」「系読:関係のある書籍を系統立てて学ぶ」「妄読:妄想だけで読まない」「交読:互いに本を紹介し合う」などなど、、どれも面白そうです。意見交換が大好きな私、いつか読書会を主催したい!
体感する本屋として紹介されているのは次の3店
【6次元_荻窪】知らない人同士で集まり、様々な集会が企画されている。
【文喫_六本木】入場料を払うと本が読み放題
【ブックマンション_吉祥寺】84の小さな本屋が集まった空間シェア
どこも面白そう!行ってみたい!
そしてに「人」を借りる図書館も紹介されていました!デンマークのコペンハーゲンに実際にある図書館で、他人と話すことで知識・体験を学べる企画です。
図書館ってほんとに進化していますよね。私が最近利用している図書館もオンラインサービスが便利でヘビロテです。
・読みたい本の蔵書がある確認可、予約可
・同区内にある8カ所以上の区立図書館と連携:読みたい本を同区内で探し、取り寄せることも可能
・本を返却できるポイントも区内各所に設置
・図書館の座席予約も可
★この本を読んで
本の姿と歴史と改めて学ぶことで、本への愛着が深まりました。
そして、私も本との関わり方を提供できる人になりたい!と思いました。
本を身近に感じてほしいな。
本の面白さをもっと知ってほしいな。
本の楽しさをいろんな人と共有したいな。
地域コミュニティの発展に尽力したいな。
心身健康の一助になりたいな。
この休職中、本に助けられ・本に励まされ・本に教わり・本が楽しみでした!
本との関わり方の例を示してくれたこの本には、感謝感謝です。
夢ができた!ありがたい。
物として本を蓄積することは、家の中で場所を取るから非推奨でしたが、これからは夢の一助になると思ってもう少し許容していこうかな!笑
やっぱり司書さんになりたいな〜!
わくわく。
以上、超おすすめ図書の記録でした。
ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
