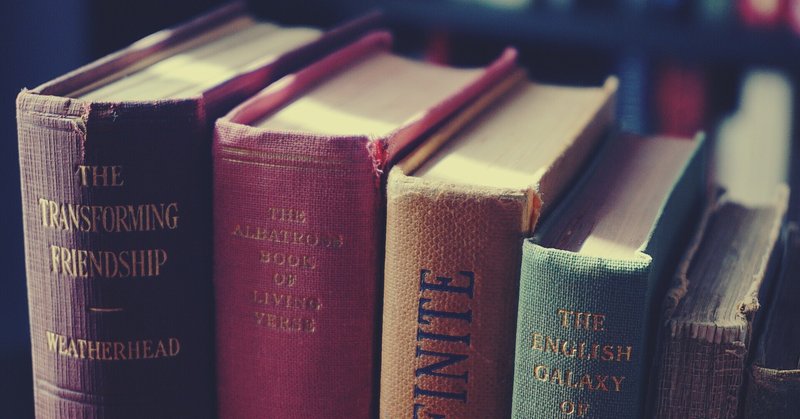
積読があるからこそ、たくさん本が読める。/積読インタビュー vol.3・積読家おくでぃさん
積読家を名乗り、『どうあがいても積読が増える読書会』を主催しているおくでぃさん。ただ、彼は本を積むだけではない。読むスピードも速く、フォロワー35,000人を超える彼のTwitter(現:X)アカウントには、毎日のように読了ポストが投稿されている。しかし彼が読むのは歴史・芸術に関する本や古典が中心で、易々と読めそうにないものばかりだ。なおさら彼の凄さを感じる。そんなおくでぃさんだが、実は“ネイティブの本好き“ではないのだという。
では何をきっかけに本を愛するようになったのか。彼の読書遍歴と積読への想いに迫る。
一行の記述の裏にある膨大な広がりに惹かれて、本が好きになった
おくでぃさんの歴史好きは学生時代からだ。幼少期から社会が好きで、なかでも歴史が好きだった。ほかの教科の授業中にずっと歴史の資料集を読んでいたほどだ。
しかし、大学生になるまでは漫画を読むことはあっても、本に手を伸ばすことはなかったという。本を読むことになったきっかけは、大学の授業がつまらなかったことだった。その退屈な授業を乗り切るための手段として、漫画を読んでやり過ごしていた。ただ、いくら面白くとも毎日のように読んでいると飽きてきてしまう。そこで漫画を買うためによく行っていた本屋で、なんとなく興味のある本を買ってみたのが始まりだった。そこで彼は本を読むことの面白さに気付く。
「教科書や資料集では1行程度でしか触れられないことが、新書では2〜300ページ書かれていたりするんですよね。教科書の少ない記述の裏には、人の行動や意思、思惑といったたくさんの要素が絡み合っていたことに気づきました。そしてその広がりが面白くて、本をたくさん読むようになったんです」
――事実は小説よりも奇なり。
そんな言葉の通り、彼にとっては事実が何よりも面白い。「事実より面白いことがないから事実である歴史書を読む」のだそうだ。一方で、もちろんフィクションにも素晴らしい書物は多い。ただ、そんな作品たちも「事実が陰で支えているからこそ名作とされている作品はままあるのではないか」と彼は考える。たとえば『三国志演義』だ。この作品は『三国志』という歴史書に、フィクションが織り交ぜられて作られている。そのほかにも、フランス革命前後を題材とした『ベルサイユのばら』や、地動説の探究を描いた『チ。-地球の運動について-』など、史実を元にした作品は枚挙にいとまがない。こうした名作をより楽しむためにも、まずは事実を知りたい。その好奇心を満たしてくれるからこそ、歴史書をはじめとする人文書を読むのが楽しくて仕方がないのだという。
人文書のほかにおくでぃさんがよく読むのが古典だ。その背景にも、面白いものを追い求める気持ちがあった。日本だけでも毎日200冊以上の本が出版されている。その膨大な書籍のうち、一年後も書店で売られている本はどれだけあるだろうか。一年生き残るだけでも難しいのに、古典は何十年、何百年と残り続けている。
「それって、たくさんの人が面白いと感じたり、残しておこうとしたからだと思うんですよね。そういう本って面白いに決まってるから、ついつい古典に手を伸ばしてしまいます」
積読は、過去の自分を振り返るツールでもある
おくでぃさんは、月に30冊ほど書籍を購入している。借りるよりも買う派なのだという。図書館も利用できるなかで、本を購入して読むことにこだわるのにも、本で得た情報が関係していた。昔どこかで読んだ本に、「自分で買った本の方が、借りた本に比べて5倍〜10倍記憶に残りやすい」と書いてあった。その本のことはタイトルはおろかジャンルすら覚えていないそうだが、その情報はおくでぃさんの心に深く残っている。「お金はかかっても、記憶を取ろう」と考え、気になる本は購入するようにしているそうだ。
一方で、読むのは最近は月に15冊ほど。十分に多い量だが購入冊数を考えると、一年で180冊ほど積読が増えることとなる。多くの愛書家が悩まされるのが、本の収納スペースの問題だ。おくでぃさんもご多分にもれず、本の置き場所には悩まされているという。電子書籍は何度か使ってみたが自分には合わず、紙の本を買っているというから尚更だ。現在は文庫や新書を中心に買うことで、少しでも場所を取らないようにしている。そんな状況にもかかわらず、読む量をはるかに上回る本を買うのはどうしてなのだろうか。
「一生かけて読むつもりなので、積読が増えていくのはあまり気にならないんですよね。それに最近、本も値上がりしているじゃないですか。きっと10年経つともっと上がっていると思っていて。古典なんかは特に10年経っても古くならないから、今買っておくのが一番安いだろうなと思って買っています」

また、おくでぃさんは、「積読がたくさんあるからこそ、たくさん本を読めている」と語る。彼は積読を「読書の第一段階」と位置付ける。本を読むことは、人間がいて本さえあればできる単純な行動のように思えるが、実際に“読む”という行為に至るまでの道のりは思いのほか長い。まず、その本を知っておく必要がある。その上で、買うのか買わないのかの選別が必要になる。その選別を潜り抜けて購入された本だけが、その人の手元に辿り着く。そこでようやく、読むか読まないかの選択がなされるわけだ。多くの本が家にあることで、ある本に対しては気が乗らず読まないという選択をしたものの、別の本であれば読む選択ができることがある。だが、本の数が少なければ、何も読まずに終わってしまうかもしれない。
だからこそ、多量の積読は多量の読書につながるのだ。
好奇心の赴くままに本を読み漁っているおくでぃさんだが、最近は本の選び方にも変化が出てきた。それまではある本を読んだら、その本の参考文献や、内容に関連する出来事に興味を持つことが多かった。ある領域からまた別の領域に興味が移ることはあったものの、“本”というジャンルの中で完結していたのだ。しかし最近は、実体験を通じて興味を持ったことについての本を買うことが増えてきたのだという。
たとえば、オペラ座に関する展覧会をきっかけにオペラに関する本を読んだり、比叡山の近くを訪れたことで仏教に興味を持ったりしている。
そんなさまざまなことへ興味関心を持つ彼にとっては、積読も興味関心のパロメーターなのだという。
「積読って、自分の興味関心のベクトルが顕在化したものだと思うんです。その時々に自分が興味を持っていたことを、記憶に留めるのは難しいです。でも、たとえばオペラに興味を持ってヴェルディの本を買えば、その興味が形として残ります。オペラに興味あった自分は時間とともにいなくなるかもしれないけれど、積読があることによって、過去何に興味を持っていたか振り返れるんです。ある種の自分史ですよね」
おくでぃさんの積読本
最後に、おくでぃさんイチオシの積読本を紹介してもらった。
水族館の文化史―ひと・動物・モノがおりなす魔術的世界(溝井裕一著/勉誠出版)
本書を手に取ったきっかけは、おくでぃさん自身が水族館を訪れたことだった。美術館やオペラに通ううちに、他の文化的な施設にも関心が湧き、水族館や動物園を訪れるようになった。そうして水族館に足を運ぶうちに、「そういえば、水族館についてあまり知らないな」と思い当たった。
政治や経済を中心とした歴史だけでなく、文化史への興味が強くなっていたこともあって、本書の購入に至ったのだという。
「少しだけ目を通してみたら、古代ローマの時点ですでに、魚の養殖が行われていたみたいなんです。水族館自体も、想像以上に昔からあって驚きました」と、本をめくりながら楽しそうに話してくれた。
このほかにも、ウィメンズウェア100年史(キャリー・ブラックマン著・櫻井真砂美訳・スペースシャワーネットワーク)、メンズウェア100年史(キャリー・ブラックマン著・櫻井真砂美訳・トゥーヴァージンズ)などファッション史に関する本や、東京で暮らしてきた人々の個人史に迫る東京の生活史などを紹介してくれ、文化史への関心の高さが伺えた。政治史や経済史から文化史に興味が移ったように、いつか文化史から別のものに興味が向かうかもしれない。しかし、読書だけはきっと続けていくのだろうと感じた取材だった。これから彼の興味がどう移り変わっていくのか、一フォロワーとして楽しみだ。
おくでぃさんのSNSはこちら
12月からフランスに行きます!せっかくフランスに行くのでできればPCの前にはあまり座らずフランスを楽しみたいので、0.1円でもサポートいただけるとうれしいです!少しでも文章を面白いと思っていただけたらぜひ🙏🏻
