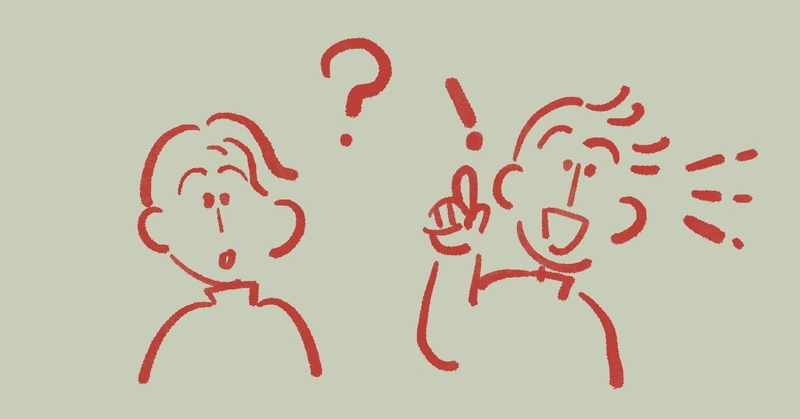
指導の引き出し⑦〜質問力〜
会話が上手い人は、話し上手ではなく、聞き上手である。
正しく聞くことが出来れば、自分の主張を通すことが可能になる。
さて第7回は「質問力」と名付けました。
”指導”と”営業”は共通する部分が多く、そのメソッドを活用することは非常に有効です。
どこが共通するの?
それは、”根幹の想い”です。
「人の役に立ちたい」
この想いがあるかどうかです。
教育という業界に長くいると、その忙しさについつい忘れがちになってしまうことです。その世界に入ろうと決意した当初、おそらくこの想いに近いものを抱いて、スタートをしたはずです。
「未来社会を作る子どもたちの学びを支援したい」
となると、
その現場に発生する「困りごと」「やりたいこと」
これからの”未来”に発生する「困りごと」「やりたいこと」
を解決する(できるようにする)のが、指導です。
…これ、営業と全く変わらないですよね?(と私は思います)
と、前置きが長くなりましたが、言いたいことは
指導と営業は共通する部分が多く、そのメソッドは使える
ということです。
では、今日も引き出しを一つオープンしていきましょう。
質問力は、どの場面でも使えるスキル
「指導の引き出し」ですので、教育の現場でということを念頭に考えると、
●個別指導(面談・進路相談など)
●集団指導(授業・ホームルームなど)
大きく2分されるかと思います。
さらに上記の中で、指導力を問われる難しい案件は、集団指導中に発生する個別案件に対応する場合です。
いわゆる授業妨害や、指導拒否、体調不良、遅刻者対応など。授業はナマモノなので、何が起こるかわかりません。だからこそ経験値や引き出しをどれだけ持っているかは重要です。
基本的に「人」とのかかわりの中で、「質問力」は必要だと思いますが、その前提として必要になるものは何だと思いますか?正直、私はこれがないと、教育を実践するとしても、営業としてもかなり厳しいといえます。
それは
「相手に対して、深く興味や関心を持つことが出来る」こと
センス・才能ではありません。このマインドセットです。
質問をするという行為の前提に、このマインドがなければ、おそらく場繋ぎ、もしくは方向性を外した質問が続き、相手にとって「この人はなんなんだろう?」と不信を招くことになりかねません。
授業や研修を受ける際、あるいは個別での面談や商談を行う際、当然商品となる「講義内容」や「商材」というところも重要ですが、多くの人がその話者の”人間性”を見る傾向があるように感じます。つまり、
「信頼できる人間かどうか」です。
この信頼を短時間で構築していく際に、効果的なのが「質問」なのです。
個別面談時に「指導」はしない。「方向性」を提案する
私の経験は、子ども・保護者との個別面談、三者面談があります。学校生活、家庭生活、そして進路のことなど様々です。
また転校をするかどうかのいわゆる入学前相談(学校見学・教育相談)というのも日常的に行っていました。※多い時に月50~60面談はしていたと思います。
色々なケースは考えられますが、基本的に個別面談時のゴール設定は
「相談する前よりも明るく帰ってもらうこと」
これがポイントです。
こうしたときに大事なのは、現状をどれだけ聞くことが出来るか、そしてその現状に至るまでの背景になっている考え方は何かなどをどれだけ聞けるかなのです。
「現状の把握」をして、「課題や困りごと」を探る。
内容によっては、その相手の「考え方」を聞いていく必要があります。
例えば、進路面談時に「なぜこの学校に行きたいと思ったの?」は、ほとんどの場合で行う質問です。これは、その生徒の「考え方」を知る”質問”として、何気なくほとんどの方がされているのです。
進路が決まっていない(考えられていない)生徒との面談ではどうでしょう?「もう卒業まで時間がないんだから、早く決めないと…」と言いたくなりますが、これは”指導”です。決められない理由があるはずです。なので「何で今進路を迷っているの?」や「進路について、どう思っているの?」
のような「考え」を聞く質問が大事です。
私は、個別面談の際に、必ず意識しているステップとして、
①困りごと・課題、やりたいことの洗い出し
②どうしていきたいかの具体的施策の検討(出来ればスケジュール感)
③本人からの意思表明
④それに対する称賛と支援の声掛け
です。大事なのは①の洗い出しでどれだけ洗いだせるか。
そこで、質問の軸も簡単に決めています。ご参考までに…
【全体的な方向性を、考えていく場合の大きいフレーム】
① どうした?(現状)
② どうしたい?(意志)
③ それをするには、どうしたらよい?(こちらが)(実践への課題)
【会話の中で、解像度を上げていくための質問フレーム】
① なぜ?(理由)
② 例えば?(具体性)
③ ということは?(行動・思考の意思確認)
このフレームに多少の肉づけをするだけで、「質問力」はだいぶ変わると思います。個別面談時には、非常に有効かと思いますので、参考にしてみて下さい。
集団指導(授業・講演)時の「質問力」に興味がある方は、コメントをお願いします。
ある程度、ニースがあるなぁと感じたら、こちらについても『指導の引き出し』に障りだけ追加してみたいと思います。
※正直、自身の商品を明かすことにもなるので(笑)
それでもやはり注意したいのは「定義」
最後の最後に皆さんにこの問いを投げかけます。皆さんの意見も聞きたいです。
このテーマ「質問力」であってます?
言葉を定義することが私の癖で、改めてこれ、”質問”で良かったのかな?と考えてしまうこともあります。もしかしたら…ということで、確実に違うものも含めますが、皆さんはこれに関連する力で、どれが欲しいですか?
質問(力)
疑問(力)
発問(力)
質疑(力)
尋問(力)
諮問(力)
~~(力)と無理やりしましたが、問いに関する言葉はこれだけあります。
一つ一つの言葉の違いを明確にしながら、定義を固めていく作業も自身の中でしていきたいものですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
