
アトランティスロック大陸 4 (1970~72)
風の記憶、岩の夢
My United Stars of Atlantis
谷口江里也 著
©️Elia Taniguchi
目次
第29歌 Lucky man エマーソン、レーク&パーマー 1970
第30歌 Layla エリック・クラプトン(デレク&ドミノス) 1970
第31歌 GOD ジョン・レノン 1970
第32歌 Your Song エルトン・ジョン 1970
第33歌 Birds ニール・ヤング 1970
第34歌 Echos ピンク・フロイド 1971
第35歌 Get it on T・レックス 1971
第36歌 You've Got a Friend キャロル・キング 1971
第37歌 STARMAN デビッド・ボウイ 1972
第38歌 While my Guitar gently weeps ジョージ・ハリスン 1972
第29歌 Lucky man 1970
エマーソン、レーク&パーマー
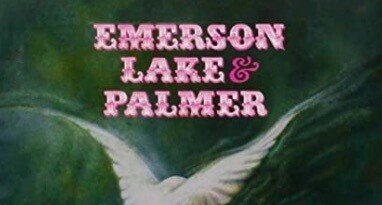
彼は白馬を持っていた
女性だってたくさんいた
誰もがサテンのドレスに身を包み
ドアの向こうで控えていた
ああ、なんと幸運な男だったのだろう彼は
ああ、なんと幸運な男だったのだろう彼は
リードギタリストはおろか、リズムギタリストさえいない、それまでのロックバンドの概念に、真っ向から戦いを挑むスーパーバンドが登場した。エマーソン、レイク&パーマー。
ナイスのキーボードのキース・エマーソン、キングクリムゾンのベースのグレッグ・レイク、そしてアトミック・ルースターのドラムのカール・パーマー。スピード感溢れる、重厚かつ繊細な壮大な音の饗宴が、たった三人の男たちによって多彩に繰り広げられる。
それまでにも、クラプトンのクリームやジミ・ヘンドリックスのエクスペリエンスのように、3人編成のバンドはあったが、ELPはどうやら、それらとは全く異なるコンセプトを持っているように思われた。
クラプトンやジミ・ヘンドリックスの場合には、必要最小限の楽器による最大限のパフォーマンスを目指して、一騎当千のつわものたちが一切の邪魔者を排除した真剣勝負を繰り広げるといった、ある種の一途さのようなものがあったが、ELPは、そんな求道者のような風情とは無縁な場所にいるようだった。
私が彼らを観たのは、ドームが出来るはるか以前の後楽園球場だったが、そのころはまだ球場でのコンサートというのは珍しく、後にストーンズが構築するような巨大なセットもなかったので、演奏が始まる前、フィールドの中にポツンと設置されたステージを見て、果たしてこれでと、なんだか不安な気がしたのを覚えている。
しかし、手を振りながら颯爽と現れたキース・エマーソンが、いきなり鍵盤を叩き始めると、彼らはそんな危惧を、たちまちぶっ飛ばしてしまった。ピアノとオルガンとシンセサイザーの上を! 長い髪を風になびかせ縦横無尽に、まるで牛若丸か体操選手のように派手に飛び回り、ピアノに飛びつき、オルガンを揺すり、挙げ句の果てにナイフをキーボードに突き立てる。
神出鬼没のエマーソン、連打連打のカール・パーマーとは対称的に、弁慶のようにステージの中央に仁王立ちになり、キング・クリムゾンのアルバムでもおなじみの、強くゆったりとしたヴォーカルで会場を満たすグレッグ・レイク。
明らかに、それは一つのショーだった。そして、どことなくアーサー王物語の円卓の騎士を彷彿とさせる連中によって奏でられる、過激かつ華麗なロック・シンフォニー。
極めてヨーロッパ的なグラウンドの気配を強く漂わせた彼ら、とりわけキース・エマーソンは、ゴシックやバロックの大聖堂の荘厳さを演出する最大の武器であるオルガンが持つ空間的な広がりと、クラシック音楽を支える構成力を活用して、ロックサウンドの中にヨーロッパ的なロマンチシズムを再構築することに成功した。
そして、その再構築のために彼らが果敢に用いたもう一つの、極めて先鋭的な武器があった。シンセサイザーである。当時まだ、ほとんど効果音的なものにしか使われていなかったこの楽器の可能性に眼を留め、そしてそれを最大限に発揮させたことで彼らのサウンドは、エレキギターの不在を補って余りあるほどのパワーと、独自の表現力を獲得した。
彼は連戦の旅に出た。
彼の故郷と王のために
バルビゾナと彼自身の名誉のために
人々は彼を讃えて唱ったものだ
ああ、なんと幸運な男だったのだろう彼は
ああ、なんと幸運な男だったのだろう彼は
考えてみればそれは、アトランティスの歴史の一つの隠れた分岐点だったかもしれない。何故なら、シンセサイザーの登場は、もし望みさえすれば、たった一人でも壮大なロックサウンドを創り出すことが可能だということの、一つの証明でもあったからだ。
古くからの楽器であるオルガンもまた、彼らによって、エレクトリックサウンドのメイン楽器として用いられることで、それが本来持つ空間性が、圧倒的なパワーと共に見事に蘇った。
そしてピアノ。この楽器の繊細かつ壮麗な表現力もまた、クラッシカルな語彙を豊富に持つキース・エマーソンの手によって効果的に用いられると共に、鍵盤という、一種の打楽器としての側面が強調されたことで、エレクトリックサウンドの中での新たな生命力を得た。
つまりキース・エマーソンは、オルガン、ピアノという、西欧音楽の歴史の中核を担ってきた主役たちを電気的に復活させ、それにシンセサイザーという、新たな時代が生んだモンスター的な寵児を加え、歴代の鍵盤楽器をステージに勢揃いさせて、ロックシーンに新たな音の景色を描いて見せたのだ。
ここから先は
¥ 200
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
