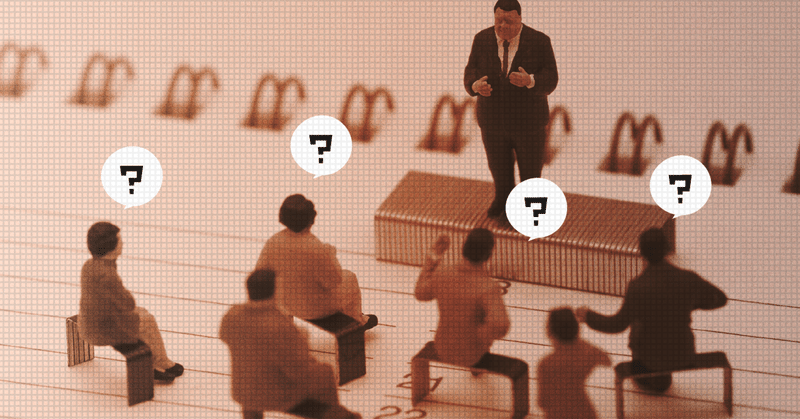
発問は何のためにするの?
教師になったばかりの頃は、深く考えることなく、子どもとやり取りしていました。
その後、教師の言葉は指示や説明、発問に分類できることを知り、なるほどと思いました。このことについては、教育実習生にもよく話をしていました。使い分けることで、子どもへの接し方が変わった実感があったからです。
この中の「発問」に関する本を最近読み、「おぉ!」と感じた文章があったので共有します。
発問が他の一般の問と決定的に異なるところは、教師の教えたいものを子どもの学びたいものにする、教科内容に向かって子どもが自ら働きかけていくように刺激し、方向づける、子どもに自問自答の能力を育てていく、そのための媒介項であるという点である。つまり、最終的には子どもが教師から独立して自力で諸々の対象に立ち向かっていくことができるようになることを目ざして、教師は問を発していく。教師の問が不要になることを目ざして教師は問を発していく。問によって子どもに問い方、『学問のし方』を教えていく。これが発問の特質である。
■インパクトと納得感
この中の、「教師の問が不要になることを目ざして教師は問を発していく。」という部分には鳥肌が立つ思いでした。
私は教師であった時、発問を工夫するということを繰り返してきました。それは、研究授業の準備段階や授業後の協議会において、今日の発問はどうだったかがよく話題に上がっていたからだと思います。その積み重ねにより、「教師が発問を工夫すること」は当たり前のことだと思っていました。そして、「教師が発問をしないこと」などは考えたことがありませんでした。
そんな私に、上記した一文は非常に大きなインパクトを与えました。そして同時に、大きな納得感も得ることができました。
■答えではなく問いかける
今の私の職務でも同様に考えることができると思っています。
「このような時、どうすれば良いですか?」と教師に聞かれることがよくあります。そんな時、「こうしてください。」というのは簡単ですし、質問した方もそれを求めていると思います。
しかし、これで良いのかと思って色々悩み、教師は専門職としてリフレクションを重視するべきだとという考えに辿り着き、「答えを与えるのではなく問いかける」ことを大切にしてきました。ですが、それはまだまだ型にはまっていたように思います。
■「なぜ問いかけるのか?」
リフレクションを促すという視点も大事ですが、最終的には問いかけないことをイメージすることにより、何をどのように問うかがこれまでよりも明確になってきているように感じます。
指導主事はなぜ問いかけるのか。これについて、ビジョンを明確にできるように、ゆっくり考えていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
