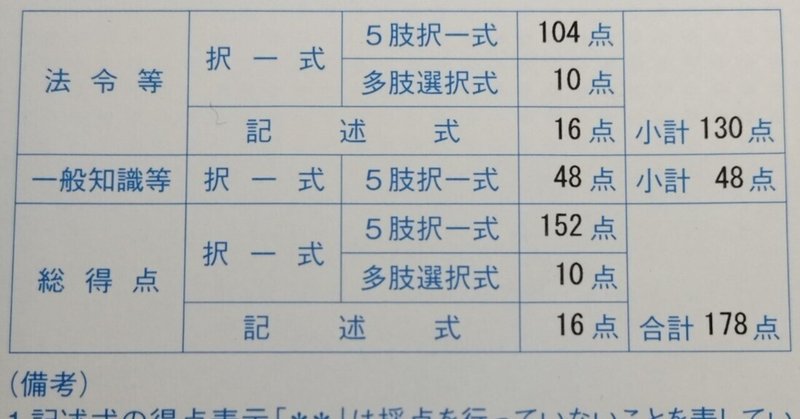
178点にならないために…「時効編」
民法の「時効」について思うこと
総則で最初に「時効」は習いますが、
物権や債権でも登場します。
年数が出てくるので、
問題が作りやすいようですが、
受験生で得意な人は少ないようです。
参考書や模試の解説に掲載されている
正答率を見ても、
「時効」が絡むだけで他の問題よりも格段に
正答率が下がっていることからも、
そのことが分かります。
そして、ほぼ毎年、
時効の問題は試験で出題されています。
これは、
時効の問題を解けるようにならなければ、
民法で9問中8問正解することが
出来なくなることを意味しています。
*民法では、いわゆるCランクの問題が
1~2問出題されますが、
おそらく解けないからです。
(正答率20%台)
令和5年度試験で合格率と合格者数を
増やし過ぎたため、令和6年度試験は
難しくなります。
(合格率が13.9%よりも高くなることは
決して起こりえない)
つまり、時効の問題を取りこぼした受験生が
合格することはない、と言えると思います。
「民法は9問中7問で取れれば御の字」
という考えだと、
私のような178点コースになってしまいます。
Aランクの「時効」
では、どう対応するべきか。
1つは、満点(9/9)を取りに行くという考え方。
これが一番良くない考え方だと思います。
何より、タイパが良くありません。
行政書士試験は民法だけでなく、
行政法・憲法・商法・会社法等、
やるべきことは、いくらでもあります。
そもそも、300点中200点台後半を
取りに行く試験ではありません。
Cランクは落としても良い、
という考え方が大切です。
これは、逆を言えば、
「A・Bランクの問題は絶対に落とさない」
ということです。
「時効」は当然Aランク。
受験生で時効の問題を解いたことがない
という人はいないと思います。
それでも正答率が低いのは、
民法全体の中での「時効」を
捉えきれていないからなのだと思います。
「時効」の勉強方法
民法の勉強をするときは、
総則→物権→債権という
流れの方が多いと思います。
*範囲が広めの、
債権からやっていくのもありだと思います。
まずは、「時効」の問題が出てくるごとに、
付箋を付けるのが良いかと思います。
ノートに書き留めるのも、ありだと思いますが、
試験直前に覚えきれなかった箇所を
最終でまとめるときで良いかなと思います。
*試験数カ月前からノートを作ってしまうと、
ページ数が膨大に…
1回目→付箋を付ける
2回目→付箋の箇所のみチェックすることで、
「時効」すべてを横断的に復習できます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
