
古楽と古楽器の音色に惹かれたチェンバロ・古楽ハープ奏者 曽根田駿
こんにちは!note更新担当のたぬ子です。
今回は、チェンバロ・古楽ハープ奏者として全国各地で演奏されている、曽根田駿さんに、楽器を始められたきっけや、2種類の楽器を演奏することについてお伺いしました。
[プロフィール]
■氏名
曽根田 駿(そねだ はやお)
■ジャンル
音楽(チェンバロ、古楽ハープ)
■連絡先
Mail:event.hs831.cembalo@gmail.com
■経歴
愛媛県松山市出身。東京芸術大学音楽学部器楽科チェンバロ専攻卒業。
2015年より渡仏しリヨン国立高等音楽院CNSMDLのチェンバロ専攻、古楽ハープ専攻で演奏家ディプロマを取得した。
2020年に同校のチェンバロ(通奏低音/コレペティ)専攻修士課程を修了し完全帰国した。2020年度フランス音楽芸術著作権管理協会アダミADAMIより奨学金を受ける。
ピアノを冨永啓子氏、チェンバロを石川陽子、大塚直哉、西山まりえ、Y・レヒシュタイナー、J.-M.エイム、D.ベルナー、A.-C.ヴィネイの各氏に師事。古楽ハープを西山まりえ、A.モイヨンの各氏に師事。
現在は千葉県松戸市を拠点として、2種類の楽器のソロ、アンサンブルの奏者として活動する傍ら、レッスンや講座を行って教育活動にも力を入れている。
■SNS
・Twitter(@Hayasone1)
・Instagram(@hayaosoneda)
・ブログ(pas à pas)
高校でチェンバロに出会い、大学で古楽ハープと出会う

ー チェンバロと古楽ハープを始められたきっかけを教えてください。
チェンバロは、高校の音楽室にあったんです。
元々、音大に進学したいと思っていたんですけど、当時習っていたピアノはそのレベルには達していないと思っていて。
そんな時、音楽室にチェンバロがあるんだし、バロック時代の音楽も好きだし「チェンバロやってみようかな」と無謀にもピアノから転向することにしました。学校にチェンバロがなければ、出てこなかった発想だと思いますね。
古楽ハープは、芸大在学中にチェンバロと古楽ハープ奏者の西山まりえさんと出会って、西山さんのところへレッスンへ行くうちに、古楽ハープに興味をもちました。
2つの楽器は、共通のレパートリーが多いので、興味が湧きやすかったんだと思います。
ー ピアノからチェンバロへ転向したことで、苦労したことはありますか。
指を動かして鍵盤を弾くというのは一緒なんですけど、タッチも発音の機構も全然違うので、慣れるのに時間がかかりました。
ー タッチの違いを具体的に教えていただけますか。
ピアノは、ハンマーで弦を打って音を出してるので、鍵盤を強く押せば強い音が出て、弱く押せば弱い音が出る仕組みなんですけど。
チェンバロは撥弦楽器と言って、弦を爪で弾いて音を出してるので、ピアノほど明確な強弱がありません。鍵盤の先に爪が付いていて、その爪でプチっと弦を弾くという感じなんです。
ー チェンバロでは、どのように強弱を表現されているのですか。
ピアノに比べるとクリアにf、クリアにpということはできませんが、タッチのスピードなどで相対的に強弱をつけることはできます。
なのでタッチの工夫をしつつ、曲全体の強弱のバランスを取りながら演奏していますね。
ー 先ほど「チェンバロと古楽ハープは共通のレパートリーが多い」と、お伺いしましたが、それは両楽器とも弦を弾いて音を出すからですか。
バロック時代は、楽器のカテゴライズが緩やかで、1度で和音が出せるオルガンやチェンバロ、ハープ、リュート、ギターなどは割りと同じ種類の楽器として扱われることが多かったんですよね。鍵盤楽器のための曲集にハープの曲が混じっていたり、リュートの曲が鍵盤用に編曲されることもよくありました。
なのでチェンバロと古楽ハープは、弦が張られていて音階の並びも一緒という点では、とても近い楽器と言えますね。
ー 2つの楽器を演奏することで、互いの演奏に何か変化はありましたか。
チェンバロは鍵盤をとおして弦を弾くので、表現をする上で指と弦の距離感が出てしまいますが、ハープは直接指で弦を弾くので、自分の力加減が音の強弱にはっきりと反映されます。
チェンバロを弾く時には、弦に直接触れるハープを演奏することで得た感覚や強弱に対するアプローチの仕方が、活かされていますね。
ハープは、ポリフォニーという異なる旋律がそれぞれ進行していく音楽の分野が苦手なんですけど。古い時代の音楽は、それぞれの旋律が同程度の重要性をもっているので、どのパートでも綺麗に弾けることが重要なんですよね。
ですが、ハープは和音を弾くのが綺麗な楽器なので、和音以外のパートだったり、他の楽器とのハーモニーについて認識が甘くなりやすいんです。逆に鍵盤楽器は、その辺りの整理がしやすい楽器なので、ハープを演奏する時はチェンバロの演奏経験が役に立ちますね。
ある作品との衝撃的な出会い

ー 幼い頃から音楽に興味がありましたか。
4歳ぐらいからピアノを習っていましたけど、音楽家になろうと思って続けてたわけではなかったし、正直練習もそんなにするタイプではなかったです。
それが中学生の時に『のだめカンタービレ』と出会って「クラシック音楽って、こんな風に楽しんで聴いたり弾いたりできるものなんだ!」と、衝撃を受けて「音楽の道に進みたい!」と思い始めたんですよね。
ー 『のだめカンタービレ』は、タイプの違う2人が主人公でしたがどちらに惹かれたのですか。
古楽器の場合は、クラシック音楽よりも前の作品を演奏することが多いので、リサーチや知識が必要なんですよね。なので、そういう意味では千秋先輩のように、机に向かって資料を読んだり、資料を読むために外国語を勉強することも大事です。
でも、お客さまに披露する時にはエンターテインメント性が必要なので、のだめちゃんみたいに自分の感情を乗せた表現をすることも重要です。
勉強して知っているからこそできる表現もあるので、どちらにも惹かれました。
集中して音楽を楽しむ

ー 演奏中に大切にされていることはありますか。
とにかく集中することですね。我を出さないというか、音楽に没頭している時じゃないといい演奏ってできなくて、自分のことをよく見せようとか「自分ってすごいでしょ」なんてことを思ってると、絶対失敗するんですよ。お客さんとしても「そういうのを見せられても…」となってしまいますしね。
作品の良さを伝えるためにどう表現したらいいのかと、作品のことだけを考えて集中して演奏している時の方が、後で録音を聴いてもいい演奏になっているなと思うんですよ。
ー では、演奏のために普段から心がけていることはありますか。
音楽を楽しめるところで練習を止めています。譜読みも仕上がっているのに、無理矢理粗を見つけるような練習をすると、すごく細かい箇所ばかりを練習することになってしまって、スケールの小さい演奏になってしまうんですよ。
かと言って、全然練習しないのも下手になっていくので、バランスが難しいんですけど。修行にならないように、曲の方向性がある程度見えてきたら、調べものをしたりリフレッシュするなど、少し練習から離れますね。
柔らかな音色が魅力の古楽ハープ

ー 現代のハープと古楽ハープの違いを教えてください。
大雑把に古楽ハープと言っているんですけど、18世紀まではハープは未発達な楽器で、小さい膝で抱えて弾くようなタイプや、複数列張られているタイプなど、ピアノと同じ音の並びを確保しようと様々な試みがなされていたんですね。
弦が3列あって、右と左にピアノの白鍵にあたる”ドレミファソラシド”の弦、真ん中に黒鍵の♯や♭の弦があって、指を左右の弦の間から入れて真ん中の弦を弾く楽器もあります。
弦の配置のほかに、弦の材質も違いますね。古楽ハープは、ガット弦という羊の腸などを結ってできる弦を使っているので、温度や湿度変化に過敏なんですけど、非常に柔らかい音を鳴らすことができます。
なので現代のハープに比べると、古楽ハープの音色は柔らかな印象を受ける楽器になるかなと思います。
長い歴史を持つ古楽の魅力を伝えたい

ー 今後愛媛でやりたいことを教えてください。
とにかく今は、できるだけいろいろな種類の公演をしたいですね。
6月の演奏会では、妻と一緒に18世紀のイタリア音楽を特集しましたし、7月の演奏は17世紀を中心にチェコの音楽を特集しました。
僕の専門は、クラシック音楽と言われるモーツァルトやベートーヴェン、バッハよりも前の時代の音楽で、時代ごとに流行りの音楽が作られていました。幸いなことに、今でも多くの楽譜が残っているので、様々な時代のいろいろな種類の音楽を紹介したいと思っています。
絵しりとり 車海老 ⇒ ビ○○○○
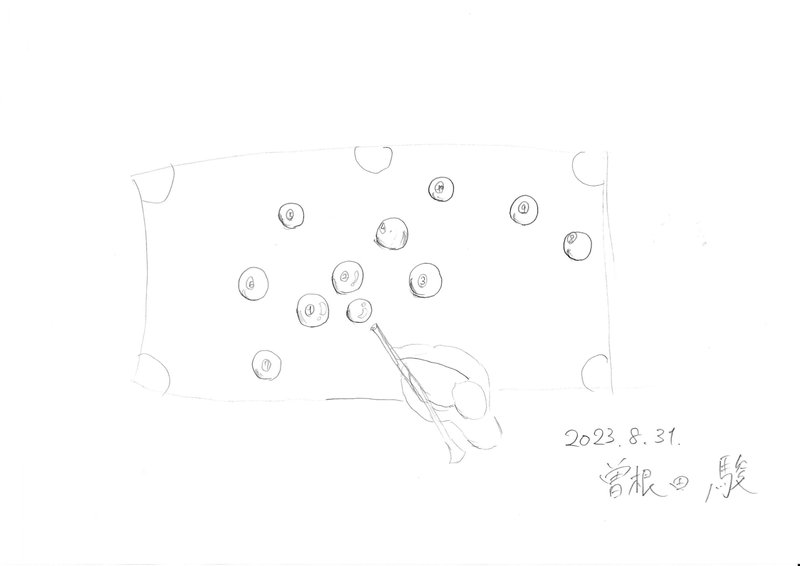
※当アカウントが掲載している写真・本文等の無断転載・無断使用は、ご遠慮ください。
