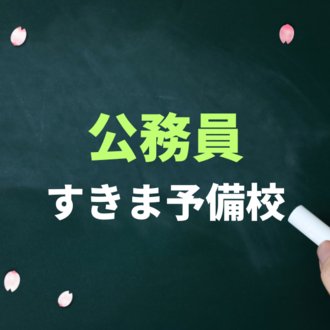【無料体験版】公務員試験生物(細胞)
このnoteでは、ワンコインで公務員試験でよく出る知識を解説します。
ながら勉強とか、スキマ時間勉強で気軽に1点とりましょう!
このnoteはお試し版ということで、無料公開しています。
その他のテーマについては、メンバーシップで読み放題としています。
スキマ時間でコスパよく自然科学の実力を習得できるので、是非とも読んでいただき、他の受験生に差をつけてくださいね!
お題
ここでは、実際の過去問をピックアップして紹介します。
※試験問題が公開されている試験の問題を中心に取り上げます。
公務員試験ではどの程度の広さと深さで問題が出題されているのかを知ることができます。
細胞の構造に関する記述として、妥当なのはどれか。
1.細胞は、細胞膜に包まれて周囲から独立したまとまりをつくり、細胞膜は、物質を細胞内に取り込んだり逆に排出したりして細胞内部の環境を保っている。
2.動物の細胞では、細胞壁と呼ばれるかたい層があり、細胞壁は、セルロースなどを主成分とした繊維質の物質からできている。
3.ゴルジ体は、粒状又は棒状の形をしており、酸素を消費しながら有機物を分解してエ ネルギーを取り出す呼吸をしている。
4.中心体は、成熟した植物細胞では大きく発達することが多く、液胞膜で包まれ、中は細胞液で満たされている。
5.細菌やラン藻などの真核生物には、ミトコンドリアや葉緑体のような細胞小器官は存在しない。
選択肢を読んでもらうとわかると思いますが、一つの選択肢で一つの細胞小器官の知識を聞いています。
生物やったことある人はすぐ解けたと思いますが、やったことない人はちんぷんかんだったかもです。
ただ、正解の選択肢は非常にユルフワなので、自信なくとも正答一本釣りできた人も多いはず。
もう一点、つい最近の問題も置いておきます。
文章の長さが短くなっていて、内容も明らかに一問一答に近づいていることを認識しましょう。
細胞の構造に関する記述として、妥当なのはどれか。
1 生物の細胞には、核をもたない真核細胞と、核をもつ原核細胞がある。
2 細胞液は、中心体やゴルジ体などの細胞小器官の間を満たす成分である。
3 細胞壁は、植物や菌類などに見られ、細胞膜の内側にある。
4 ミトコンドリアは、核のDNAとは別に独自のDNAをもつ。
5 液胞は、成熟した動物細胞で大きく発達している。
いずれにしても大事なことは、
これ、ちょっとやればすぐできるんじゃね?
の素敵な第六感です。
そう、簡単なんです。
要領よくちょっと勉強した人は1点取れてしまい、何も考えずに捨ててしまった人は1点ロスしてしまったかもしれない・・・そんな問題です。
ということで、この問題だけでなく、この単元を全部マスターするための知識を合わせて勉強してみましょう。
細胞の学習のポイント
まずは脳筋プレーで細胞の絵を覚えよ
このテーマは何はともあれ細胞のイメージを掴むところからスタートです。

ここはコツもへったくれもなく、脳筋プレー上等で細胞の模式図を何度もノートや画用紙に書きまくって、ついでに細胞小器官の名称も覚えてしまうしかないです。
気合いで頑張りましょう!
細胞の構造の理解のしかたについて簡単に触れておきます(何度も図と行き来して読んでちょ)。
一般的な動物細胞だと、表面が細胞膜で覆われていて、内部に細胞質基質 (細胞小器官を含む液体で、要はこれが細胞質)が含まれる形です。
植物や微生物の細胞では、細胞膜のさらに外側に細胞壁が存在します。
この点に注意しながら図を覚えましょう。
繰り返ししつこくて恐縮ですが、この分野は絵が頭に浮かばないと細かい用語は何も頭に入ってきません!
まずは細胞の絵を早急に覚えてください!
リン脂質二重層でできた細胞膜
細胞膜はリン脂質二重層と呼ばれる脂質でできた膜です。
とにかくこいつが猛烈に強いバリアーで、ATフィールド並みに何でも跳ね返すと覚えてください。

ただ何も通さないだけでは生きものであるとは言えないですよね?
そこで、なんと生存に必要なものは取り入れて不要なものは排出するフィルターのようなものがついています。
このフィルターがチャネルとポンプと呼ばれる2つのたんぱく質です。
❶チャネル:タンパク質でできた孔(あな)
物質の形で通過するものを選別します。
チャネルによる物質のやりとりはエネルギー不要な受動輸送と呼ばれる。
❷ポンプ:タンパク質でできた水質維持装置
細胞の外側にNa+を3の割合で排出して、細胞の内側にK+を2の割合で取り込む装置です。ポンプによる物質のやりとりはエネルギー必要な能動輸送と呼ばれる。
ちょっと余談ですが、ポンプの作用の結果、細胞の外はナトリウムが多く内側はカリウムが多い液体ができあがります。
イメージ的には、細胞の起源とも考えられている海水のような外部環境を作り出した感じです。
たんぱく質合成に関係する細胞小器官
ここからはたんぱく質をつくるための役者として、核&核小体、リボソーム、小胞体、ゴルジ体をご紹介します。
私もあなたも、みんなたんぱく質でできていまふ(AIでなければ笑)。専門的になるので詳しくは割愛しますが、たんぱく質は生命現象の大元なのです。
たんぱく質の設計図が含まれる核

核の中には鎖状DNA(デオキシリボ核酸)が収容されており、DNAに生命の設計図となる『遺伝子』の情報が書き込まれています。
生命の設計図って、具体的に何ぞ?
と思った方は鋭い。
具体的には、たんぱく質の作り方設計図です。
核小体(仁)
核内部に存在していて、リボソームのパーツであるrRNAの合成が作られている。
たんぱく質製造装置のリボソーム
細胞図をよくみると、核とか小胞体に粒々がついていると思いますが、これがリボソームです。
リボソームはタンパク質製造装置で、もうもう、生き物にとってめちゃクソ大切です。
リボソームで作られたタンパク質は小胞体へと送られます。
配送仕分けセンターの小胞体

リボソームで作られたたんぱく質をゴルジ体へ送ります(これだけかい!)。
細胞全体をたんぱく質製造工場だとすると、小胞体はたんぱく質を次のラインにおくるベルトコンベア的な存在です。
たんぱく質を加工するゴルジ体

小胞体から送られてきたタンパク質に対して加工や修飾を施し、加工が完了したたんぱく質の細胞外への分泌や輸送を行う。
細胞全体をたんぱく質の製造工場だとすると、ゴルジ体は出荷前の荷詰めを行うところと例えるとよきです。
代謝に関係する細胞小器官
代謝とは同化と異化のことです。
生体内で複雑な物質を分解する過程を異化、小さな物質から複雑な物質を組み立てることを同化といいます。異化ではエネルギーが得られるのに対し、同化ではエネルギーが必要であるということも合わせて覚えておきましょう。
同化と異化に関係する細胞小器官がミトコンドリアと葉緑体です。
ミトコンドリア

酸素を消費しながら糖であるグルコース(C6H12O6)を分解して、細胞の活動に必要なエネルギーであるATPを合成する。好気呼吸の場である。
ミトコンドリアは細胞とは別に独自の環状DNAを持ち、2重膜構造を持つ。
葉緑体(植物細胞のみ存在)

光のエネルギーを利用して二酸化炭素CO2からグルコースC6H12O6を合成する、光合成の場である。このグルコースを元にしてデンプンを合成する。
葉緑体も細胞とは別に独自の環状DNAを持ち、2重膜構造を持つ。
細胞分裂に関係する細胞小器官

中心体(星状体)
中心体は細胞分裂の際に、染色体を移動させる役割を果たす紡錘糸の基点となる。
補足
中心体は動物の細胞にのみ存在し、植物をはじめとする他の生物は中心体なしに紡錘糸が形成される
紡錘糸
細胞分裂の際に染色体を移動させるタンパク質でできたワイヤーのような存在。
染色体というのは、DNAなどの遺伝物質が細胞分裂にあたって高度凝縮してまとめられたもののことです。

その他の細胞小器官
ここに挙げたものは一問一答的に覚えておけばOKです。
リソソーム
内部が強酸性であり、あらゆる物質を分解するリソソーム酵素を含む。細胞内消化という異物や不要物の分解を行う。
※リボソームとは全く違うので、絶対に混同しないようにしてください。
液胞(成熟植物細胞のみ存在)
成熟した植物細胞にのみ存在する細胞小器官であり、内部は細胞液が含まれている。
細胞液は細胞内分解の機能(リソソーム的な機能)と物質貯蔵機能を兼ね備えた珍しい小器官である。
細胞壁(植物細胞と微生物の細胞に存在)
植物の細胞壁はセルロースと呼ばれる糖質の一種によって構成されている強固な壁で、細胞の保護の役割を果たしている。
しかし、細胞壁は細胞膜と違って物質の透過性は非常に高く、様々な物質が通過可能である。
真核生物と原核生物の分類
生物は大きく原核生物と真核生物に分けることができる。
原核生物は細菌類(大腸菌など) の原始的な生物であり、真核生物は動植物をはじめとした原核生物以外の生物を指す。
原核生物を構成する細胞を原核細胞、真核生物を構成する細胞を真核細胞とよび、DNA の構造や 細胞小器官の有無に関して大きな違いがある。
ここでしっかりと覚えておいてほしい知識が、原核生物はリボソーム以外の細胞小器官を持たないこと。原核生物はこれまで解説してきたものを何にも持たない生物なのです。
そしてもう一つ追加で覚えておいてほしいのが、原核のDNAは環状ですが、真核のほうは線状です。

補足
肉眼では確認できない生物を微生物と呼び、微生物は、原核生物(細菌)、真核生物 (真菌など)、ウイルスに大別される。ただし、ウイルスは生物に分類されない。
解説
細胞の構造に関する記述として、妥当なのはどれか。
1.細胞は、細胞膜に包まれて周囲から独立したまとまりをつくり、細胞膜は、物質を細胞内に取り込んだり逆に排出したりして細胞内部の環境を保っている。
2.動物の細胞では、細胞壁と呼ばれるかたい層があり、細胞壁は、セルロースなどを主成分とした繊維質の物質からできている。
3.ゴルジ体は、粒状又は棒状の形をしており、酸素を消費しながら有機物を分解してエ ネルギーを取り出す呼吸をしている。
4.中心体は、成熟した植物細胞では大きく発達することが多く、液胞膜で包まれ、中は 細胞液で満たされている。
5.細菌やラン藻などの真核生物には、ミトコンドリアや葉緑体のような細胞小器官は存在しない。
細胞・細胞膜に関する説明として、これがドンピシャで正解!
動物の細胞には細胞壁はありません。
これはゴルジ体ではなく、ミトコンドリアの説明です。
中心体は成熟した植物細胞には存在しない。また、この記述は液胞に関する説明です。
細菌やラン藻は真核生物ではなく、原核生物。
さあ、もう一本の方も答えを見ていきましょう。
細胞の構造に関する記述として、妥当なのはどれか。
1.生物の細胞には、核をもたない真核細胞と、核をもつ原核細胞がある。
2.細胞液は、中心体やゴルジ体などの細胞小器官の間を満たす成分である。 3.細胞壁は、植物や菌類などに見られ、細胞膜の内側にある。
4.ミトコンドリアは、核のDNAとは別に独自のDNAをもつ。
5.液胞は、成熟した動物細胞で大きく発達している。
これはもはやお決まりのパターンで、原核と真核を逆にしている。核をもたない原核細胞と、核をもつ真核細胞がある。
これは微妙に細かいことを聞いていますが、細胞小器官の間を満たす成分は細胞質です。細胞液は液胞の中に含まれる液体を指します。
細胞壁は細胞の外側を覆います。
これが正解です。
液胞は動物細胞にはないですね。成熟した植物細胞で大きく発達です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?