
むつだの「チャイナマガジン」⑥
不定期配信・むつだの「チャイナマガジン」
~赤い顔で歌う、黒い顔で歌う~
2010年12月17日
最近、関心したこと、というか文化に触れたなぁ~と実感したことが一つ。
会社のHP改修にあたり、制作パートナーを探していたときのこと。
数社に声をかけて、コンセプトも伝え、提案を依頼し、提案内容からそのうちの1社に絞る。
ただ、見積りが若干折り合わず、仕方ないのでもう一度その制作パートナー担当者を呼びつけ、交渉をすることに。
その価格交渉の会議に臨む直前、同席する現地スタッフから、こんなことを言われました。
「我们今天唱红脸,你来唱黑脸好吗?」
(本日、私たちは赤い顔で歌うから、陸田さんは黒い顔で歌ってもらえますか?)
・・・は?なにそれ。
歌えばいいの?ガングロで?松崎しげる?
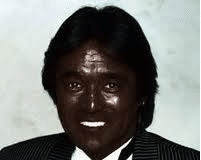
当然、そういうことではない。
よくよく聞くと、彼はパートナー寄りで、
進捗に前向きな姿勢を見せて、纏め上げようとするから、陸田には、会社の方針上、予算を厳しく見ているという背景で終始、厳しい顔をしながら、この見積りではオタクに依頼できないよっていう感じにゴネ役を演じてください。ということだったらしい。
拙いながらも、その商談では、なんとかその役回りを演じきって無事交渉終了。交渉もまとまって、予算内に抑えることができました。
確かに、全員で「こんな見積りじゃ出せねーよ!持ち帰りじゃボケ!」ってやると、雰囲気も悪くなるし、「けっ、けち臭いクライアントだからもういいや」って感じで、いい感じにまとまらない可能性がある。
逆に、こちらの担当者は前向きで、
「上はああ言いますが、僕としては御社にお願いしたい一心です!是非やりましょう」みたいな感じだと、先方も、「じゃあ、なんとか頑張ってみます」ってなるかも。
ここで、日本との大きなGAPを感じたわけです。
少なくともこれまで参加してきた日本での商談では
会議の進め方とか、落としどころなんかを共有して臨むことはあっても、誰がどんな役回りを演じるかって話をしたことは非常に少なかった気がします。
日本人は演じるにも、会議の雰囲気を見ながら臨機応変に対応する、みたいな感じでやるもんだから、チームワークが形成されるのに時間がかかったりそもそも空気が読めるようになり、そこで演じ分けるのはホント熟練の技だったりする。
中国人に感心するのは、その交渉連携の組み立ての早さ。
「红脸(ホンリェン)」「黑脸(ヘイリェン)」っていう共通の認識ワードがあるので多分、中国人同士だったなら、ものの数秒あればチームがあまり見知らぬ同士だろうが、誰が何を演じるのかポジショニングをサクッと決めて交渉・商談に臨んでくるんだろうな~。
周りの人間、数人にこのことを確認したところ中国人の間では交渉の際の常識らしい。常識だということから深読みすると、それを察した商談テクニックが必要なのかもな~・・・。
後で知りましたが、この「红脸(ホンリェン)」「黑脸(ヘイリェン)」とは京劇から来ているということでした。なるほど動詞が「歌う」であるということも、納得。
私自身、京劇、見たことないですが、どうやら顔の色がその性格を表すらしい。百度知道(yahoo知恵袋みたいなもの)で調べたところ
・黑脸(ヘイリェン):正直、公正、率直、強情 →(黒)武将でいうと趙飛、夏侯惇など
・红脸(ホンリェン):義理堅く、正義感が強い →(赤)武将でいうと関羽、姜維など
とのことです。
ちなみに、「白脸(バイリェン)」ってのもあって、腹黒のボス格を指すらしい。武将でいうと曹操などですって。

今後、中国人と商談に臨む際「黒い顔で歌ってね」といわれて間違っても、愛のメロディを歌ってはいけませんよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
