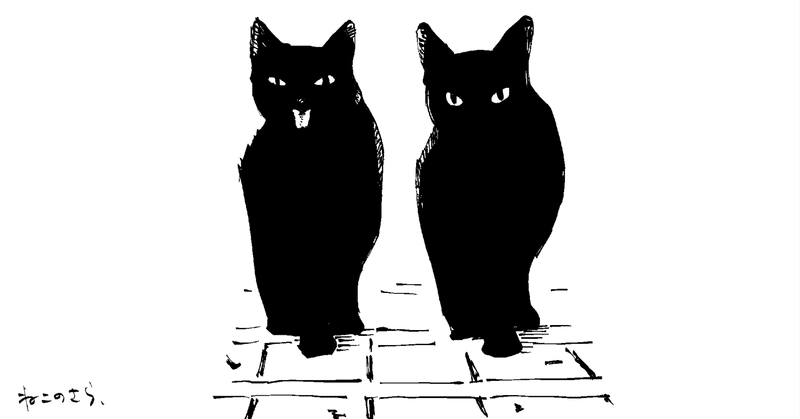
ポジティブな意味で「ダブルスタンダードを持つ」と言う話
私は日本企業に20年以上勤めていて
転職をしたことがなく、
30代で3回産休と育休をとって
ワーママをやっていました。
今もワーママといえばまあそうなんですが、
保育園や学童の送り迎えの時間にピリピリして
どうやれば制限時間の中でタスクをこなしていけるのか、
帰ってからも子供にご飯を食べさせて
お風呂に入れて
明日の準備をして
そして自分のこともかろうじてやっておく、
と言うギリギリな感じは今はありません。
真ん中の息子が小学校高学年にさしかかり
末っ子も小学校に慣れてきて、
さあ手が離れてきたぞ、と言うときに直面したのが
息子の不登校でした。
時短とか効率とか課題解決とか。
そう言うキーワードの中にどっぷり入っていて
全く時短も効率も通用しないところに
ぽっかり入ってしまった、と言うのでしょうか。
最初、息子の状態を理解することに
とても時間がかかりました。
今までと同じように
また「普通に」学校に通えるようになる、と
思い込んでいました。
しかし、息子にとっては
ずっと異常事態が続いており、
それは息子にとって「普通」の生活ではありませんでした。
他の子どもたちや先生が
どういう経緯で意思疎通しているのか
自分は何を求められているのか見失うことが日常茶飯事で
頑張っていることに対して(漢字を丁寧に丁寧に書くとか)
そんなに時間をかけてやらなくて良い、
もっと早く切り上げるように、とたしなめられると言う事が続いており
その積み重ねの中で、学校に行けない状態にまで追い詰められていました。
息子から見えている風景はこんな風だと最初に諭してくれたのは
市のこども支援の職員であり、
私はその人が言ってくれたことや
その人との出会いにとても感謝しているのですが
一方で、どうしてもっと早く気づけなかったんだろう?
と思う気持ちもありました。
5歳の頃には息子は発達障害の傾向があることが
分かっていたのですが、
診断がつかないグレーゾーンであり
たくさんの情報の中から必要な情報を取り出すことが難しいこと
たくさん配られるプリントに手が負えなくなってぐしゃぐしゃになってること
時間割を合わすことができずに教科書を全て毎日持っていくことなど
それが発達障害の影響で本人が苦労していることに
気づけずにいました。
効率とか生産性とか
役に立つことなのか、立たないとなのかと言うことの
価値観だけの中にいたその時の私が
どうしたら気づけたんだろう、と今も考えています。
ヒントとして思っているのは
1つの価値観だけに縛られないことではないか、と思います。
マザーハウスという
「途上国から世界に通用するブランドをつくる」
という理念を掲げている企業の
副社長、山崎大祐さんのマーケティングの講義を
2023年に伺った際、
「経済合理性がある」ことと「経済合理性がない」こと
どちらの価値観も両立させていて
いわゆるダブルスタンダードをやっているんですよね
というようなことをおっしゃっていて
いたずらっぽく笑っておられらことが心に残っています。
ガチガチに固めないしなやかさを持っているから
新しい価値を発信できるんだなと思いました。
子育てはマーケティングではないので
余計に遊びを持つというか
どの価値観だって絶対ではないという
達観のような視点が必要だなと思っています。
心に病を抱えるって
前に進んでいるのやら後ろに進んでいるのやら、
当人も家族にとっても進んだ距離とか
成長とか進歩とか効率とかいった基準で考え出すと
余計に苦しくなってしまう事があります。
とはいえ、生活を支えていくための経済合理性といのも
とても大事で、
その中で生きることを否定もせずに
同時に別の物差しを持てるように、と
今少しずつ修行中です。
きっと人にはそれぞれの
「生きていく上での知恵」
があるんでしょうね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
