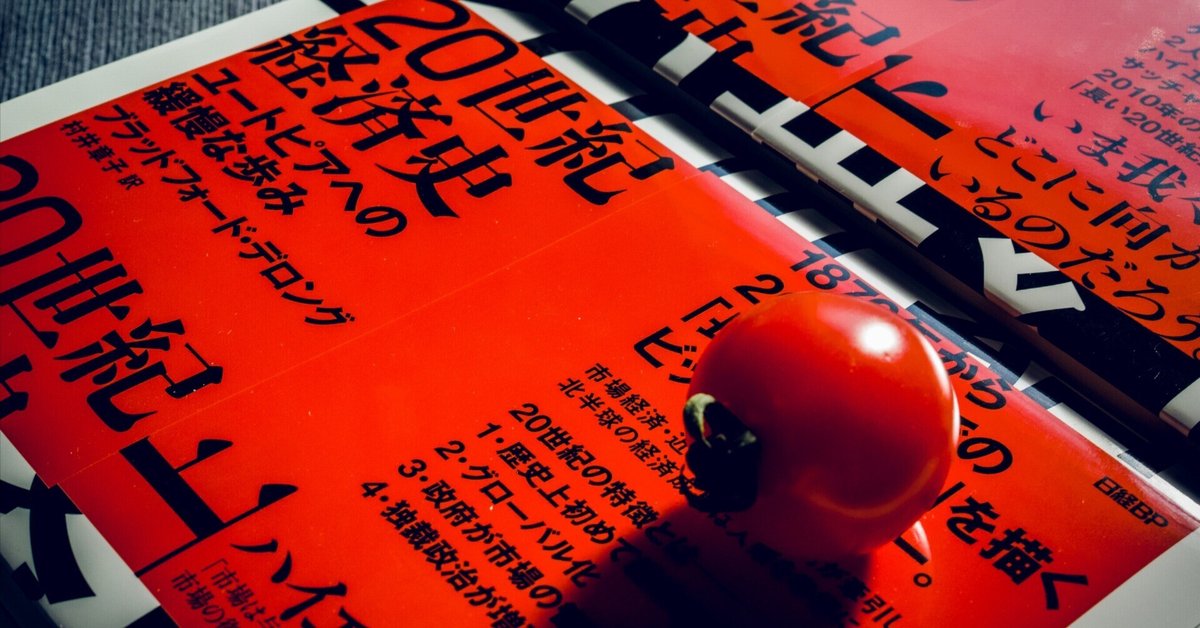
ノア・スミス「書評:ブラッドフォード・デロング『20世紀経済史――ユートピアへの緩慢な歩み』」(2022年6月12日)
「きれい……みんなが死んだ場所なのに」(中川典子)
出版前の本の書評を書くのは,これがはじめてかも! ありがたいことに,ポッドキャストのホスト役をいっしょにやっているブラッド・デロングの近刊を一冊確保できた.出版予定日は9月6日だ.それまでの場つなぎとして,高まってるみんなの期待をこの書評で支えられたらいいなと思う.
ブラッド・デロングは現在経済史に関して百科事典のように通暁してる.それでいて,読者をおじけづかせない文体の書き手でもある――かく言うぼくが経済学ブロガーになりたいと思った最初のきっかけは,2000年代中盤に彼のブログを読んだときのことだった.彼の本を読み始めると,その「デロング節」にどんどん引き込まれてしまう――愉快な事実を次から次に繰り出しつつ,デロングのありとあらゆる知識をその物語で統合してみせる.読みはじめは少しばかりとっつきにくく感じるかもしれないけれど,慣れてしまえば読み手の労力に大いに報いる体験を与えてくれる.
ただ,デロングは経済史家ではあるものの,経済史は本書の一部しか占めていない.大半は,政治経済史だ.どうして世界が工業化して豊かになったのかに関する本はたくさんある――ほんの一握りだけ挙げてみよう:
マーク・コヤマとジャレド・ルービンの『「経済成長」の起源』
グレゴリー・クラークの『10万年の世界経済史』
Joel Mokyr の『成長の文化』(邦訳なし; A Culture of Growth)
ロバート・アレンの『世界的な視座から見たイギリス産業革命』(邦訳なし; The British Industrial Revolution in Global Perspective)
ロバート・ゴードンの『アメリカ経済: 成長の終焉』
でも,デロングの『20世紀経済史』では,世界がどうやって豊かになったのかって話にほんの一部しか割いていない.大半は,人類がそうやって手にした富でなにをすることに決めたのか,そして,成長を続けるべくどんな種類のシステムを発展させてきたのかって話だ.つまり,本書は政治経済の本なんだ.
世界はどうして豊かになったんだろう? デロングの主張では,1870年以後になってようやく技術進歩が加速して人類の人口増加を追い越せるところまで達した.そのおかげで,人類はマルサスの制約から自由になった.デロングの考えでは,この技術進歩の加速は3つの主要イノベーションに起因している:産業技術研究所,現代企業,蒸気船に支えられたグローバル化,この3つだ.この3点がたしかに主要な原因だというもうちょっと確固とした証明がほしかったところではあるけれど,これを主張するデロングの論証はかなり説得力がある.
ちょうどこうした要因が登場した時期に全要素生産性が劇的に加速したことをデロングは示している――全要素生産性を,デロングは「知識インデックスの価値」と呼んでいる (”value of knowledge index).デロングによれば,この加速は2000年代中盤まで継続した.それで,1870年から2010年までを「長い20世紀」と彼はとらえている.その特徴は,急速な生産性成長と,それにともなう社会・政治的な大変化だ.
本書の大半は,そうした政治的な大変動に関心を集中させている.デロングの言う「長い20世紀」には,いろんなイデオロギーが発展した.たとえば,自由民主主義,自由市場リバタリアニズム,共産主義とファシズムがそうだ.これは,完全に当然の事態だった.成長が急速に加速したために,人類は次々と新たな事態に出くわすことになった――それまで想像もおよばなかった富を新たに見出し,それまでになかった社会組織のさまざまな新しい形態,新しい問題,新しい機会,そして経済的な力の新しい分布に,人類は取り組まなくてはいけなくなった.もちろん,そうした取り組み方に関する大思想もたくさん生まれることになったし,その一部にはどうかしているものやダメなものも含まれていた.
デロングは20世紀の政治経済思想家ふたりのレンズをとおして,こういういろんなアイディアの隆盛と(たまにおきた)没落とを物語っている――ふたりの思想家とは,フリードリッヒ・ハイエクと,カール・ポランニーだ.ハイエクは市場原理主義者で,基本的にはこういう考えを唱えていた――社会になしうる最善のやり方が市場だ.他方,ポランニーはこう唱えた――特定の普遍的価値を守るために市場はさまざまな社会的保護で和らげる必要がある.その価値とは,雇用の安定や,まっとうな賃金や,共同体に属している実感だ.無理してなぞらえれば,この2つの極は1980年代の共和党と民主党におおまかに対応しているともみなせる.ただ,デロングはハイエクとポランニーを弁証法的な対立者とは見ていない――そうじゃなくて,ハイエクとポランニーの枠組みを使って,20世紀に人々が着想を得た他のいろんな政治経済思想をデロングは吟味して評価しているんだ.
そうすることで,デロングは現代史に一種のリズムを打ち立てている.ハイエク流の自由市場は成長を生み出すけれど,人々はそれ以上のことを求める――ポランニー流の社会的保護を,人々はのぞむ.それで,人々は共産主義やファシズムや自由民主主義といったシステムをつくりだす.そうしたシステムは,市場がおのずともたらす格差を和らげてよりよい社会をつくりだすことを意図して設計されている.ときにそうしたシステムがうまくいくこともあるけれど,破滅と悲嘆に終わることも多い.この物語は2010年で終わる.そこでおおよそ主流となっているのは,自由民主主義だ.そして,それまでのどんな時代の基準と比べても,人々は驚くほど豊かに暮らしている.でも,それでも人々は満足していない.こうした豊かさと自由があってもなお,「自分はユートピアに暮らしているんだ」なんて人々が実感するにいたってはいない.もしかすると,あともう一度,とてつもなく飛躍的に豊かさが増せば,それでついに人類は満足するのかもしれない.でも,そんな機会はこないのかもしれない.生産性成長は減速しているし,20世紀のような時代を再び迎えることがあるのかどうかははっきりしない.
それゆえに,本書は不吉な言葉で締めくくられる――人類はいまだに自分たちの社会にすごく不満を抱いていて,その結果として,きっとまた新しい政治経済の思想をつくりだそうとするにちがいない.もし歴史がなんらかの手引きになるとしたら,この道筋は危険に満ちあふれているとは言えるだろう.
本書は,なにか中核となる説を提唱する本とはちがう.そうじゃなくて,特定のレンズ越しに近い過去を眺めるように誘う本だ.デロングは,いまやぼくらの大半がよく知ってるあれこれの出来事を語る――ヨーロッパ帝国主義,世界大戦,植民地解放,グローバル化,大不況,などなど.きっと,読者は本書からいくつか興味を引く歴史の断片を知るだろう――率直に言って,興味をそそるちょっとした逸話や事実を数え切れないほど熟知して話にちりばめることにかけて,デロングは超人的な能力を発揮してみせる.でも,全体として,本書を読むなによりの理由は,現代史を理解する視角をあらたにすることにこそある――1870年以降の世界の物語を統合する基軸に急速な経済成長を据えて現代史を理解すること,それが本書を読む理由だ.
そうやって歴史を見る視角を変えてみるのは,有用な練習だとぼくは思う.ぼくは唯物論者とはちがうけれど,物質的な環境・状況が変われば,人類が適応しないといけない条件もまるっきり変わってくる.もちろん,これは双方向のプロセスだ――社会組織も技術進歩に影響を及ぼすことがある.でも,テクノロジーはどこか魔法みたいなところがあって,世界中にすごく迅速に広まっていく.だから,たとえばどこかで冷蔵庫が発明されると,じきに世界中の人たちが冷蔵庫をほしがるようになる.もちろん,どこかの一国がものすごく重要な存在となって技術進歩を推し進めることもある――ちょうど,20世紀のアメリカがそうだった.でも,全体として,テクノロジーは十分に世界規模の存在で,その成り立ちに関してどこかひとつの社会が下す選択に左右されすぎることはない.
つまるところ,これこそ,ぼくが「テクノロジー決定論者」とよく自称してる理由だ.べつにテクノロジーが社会のなにもかもを決定するからじゃない(そんなことないのはわかりきってる).そうじゃなくて,テクノロジーはひとつひとつの社会からおおよそ超越しているからだ.本書は,この種のテクノロジー決定論のレンズ越しに歴史を見るよう読者をうながしているとぼくは理解している.
デロングの歴史観は,力強い楽観をともなっている.多くの人たちにとって,20世紀におきたおぞましい出来事の数々を――強制収容所や都市爆撃や略奪で荒廃した景観などなどを――眺めながらも〔原罪のような〕《人間の堕落》の物語をそこに見出さずにいるのは,むずかしい.ときに,こんなことを問いかける人もいる.「お互いに殺し合ったり世界を破壊したりするのをもっとうまくやる方法をもたらすだけなら,いったいテクノロジーの使い途とはなんなんだ?」 でも,デロングにとって,20世紀のいろんな怪物たちは,根底においていい方に向かっている傾向に対する適応不全な反応にすぎない――悲惨な窮乏状態から人類がしだいに抜け出ていき,ついにはマルサスの悪魔を打ち倒す最終的な勝利に向かう傾向にうまく適応しそこなった反応でしかないんだ(ちなみに,なぜ「最終的勝利」かというと,かりに技術進歩が徐々に小幅になっていっても,出生率の低下によって,人類が持続可能になるからだ).
たしかに,20世紀には大勢の人たちが虐殺と暴虐に苦しめられた.でも,ものすごく大勢の人たちが,祖先たちには夢見ることもかなわなかった物質的な生活水準を享受できるようになった.つまりは,こうなった:

そうだね,これで地上が楽園になったわけじゃない.でも,大半の人たちにとって,地上は地獄じゃなくなった.人類の旅路はここで終わらないけれど,それでも勝利の物語であることに変わりはない.もしかすると,この進歩は持続可能かもしれないし,そうじゃないかもしれない.確かなのは,進歩を持続可能にするためにぼくらが戦うだろうってことだ〔日本語版記事〕.ただ,その戦いが最終的に失敗に終わったとしても,少なくとも短い間は,ものすごく多くの人間がまるっきりのゴミじゃない生活を送れるようになった.
ぼくなら,これを「勝ち」と呼ぶ.
ともあれ,本書を強くおすすめする.20世紀は――「長い20世紀」のバージョンですらも――いまやはっきりと過去になった.あの時代がいったいどんな意味をもっていたのかを振り返って考察するすばらしい機会を,本書は提供してくれる.

[Noah Smith, "Book review: (Slouching Towards Utopia'", Noahpinion, June 12, 2022]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
