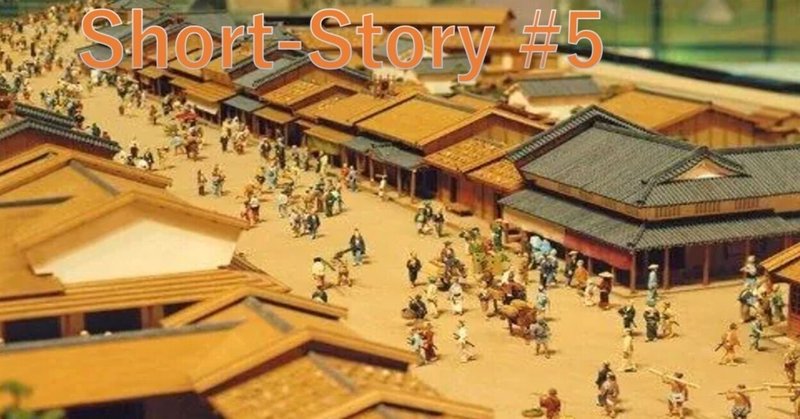
The edge of お江戸-5
野グソが取り持つ縁でツレとなった嘉兵衛と吉次郎。
東照宮での参詣もそこそこに、“天啓”を得たと思い込んでいる嘉兵衛はお参りの最中、瞼の裏に立ち現れた嘉兵衛が勝手に家康公と思い込んでいる幻影の翁を追って筆を走らせた。
吉次郎と二人、江戸への道中に一泊した旅籠で徹夜した翌朝、嘉兵衛はもう話を書き上げていた。
起きてきた吉次郎が目を丸くする。
「すげぇな、おい・・・そういや何か一人で泊まったような気がすんのは、
そのせいか。ゆんべっから俺たち、一言も会話してねぇもんな」
「ごっつ眠いわ・・ちょっとだけ横んなってもえぇ?」
「駄目だ、俺ぁ早く彫りてぇんだ。さっさと帰るぜ?」
“眠い”と渋る嘉兵衛を引きずるようにして吉次郎は江戸路を急ぐ。
道すがら、手にした1本のすすきで道端の草々をぺしぺし叩きながら話す吉次郎の身の上を、嘉兵衛は何回もあくびをしながら聞いた。
町人として薪屋の家に生まれ、兄弟は上に姉が一人、どこやらに嫁いでいるそうだ。
早くに二親を失くし天涯孤独な嘉兵衛と違い、両親ともに健在だが、親父さんとは4年ほど前に喧嘩して以来絶縁状態となり、それから実家には帰っていないという。
「せっかく親御はんいてはんのに、バチ当たるで?」
「うるせぇよ、あんな頑固モンの相手なんざしてられっか。
それよりおっちゃん、」
「おっちゃん?わい25だっせ?あンたより2つ上なだけや。それつかまえて
おっちゃん呼ばわりかいな!」
「そんだけ老けた顔してりゃ上等だよ」
「いやそんな、高級な顔はしてへんけど。老けて見えるんかな?やっぱり。
大坂でもよぅ言われててん」
「さばのよみようもねぇよな。逆さばだったらよみ放題だけどな」
「あンた、ほんまに身もふたもないな」
「江戸へいったら泊る所ねぇだろう?しばらくウチにいなよ」
「え?いいんだっか?」
「もちろんよ。絵を彫らしてくれるお礼だ。好きなだけ居な」
「そらありがたいわ!おおきに!」
「んじゃ野グソしてくら」
「・・またかぃな」
道端の草むらへと向かう吉次郎の背中を見ながら、嘉兵衛はつこうとしたため息があくびに発展したので、そのまましばらくの間、道端で快晴の空を見上げて大口を開き続けた。
大坂から東照宮参りへ一人旅した嘉兵衛、本殿にお参りした後出会った時、野グソしたての吉次郎から“京や大坂じゃ出かけた時もよおしたら、出すもん出さずに垂れ流しながら歩くのか”と言われ、“辻便所行ったらいいだけや”とこともなげに答えていたが、この時代、“公衆便所”的なものは江戸には無かったという。
花の都、京ではあちこちで四季折々の花見の催しが引きも切らず、大勢の人が集まる機会が度々あって、そんな中もよおした人達のたくさんの“生ぬるいもの”が道のあちこちでとぐろを巻いているのはよろしかず、という事もあってか、早い時期から街の至る所に“辻便所”なるものがあった。
江戸に同じものが設置されるようになったのは江戸時代後期からで、それまでは“出物腫物ところ選ばず”とばかり、道端や茂みの中でいたすのが江戸においては普通だったという。
排泄物であれば米や野菜を育てるのに下肥として肥料に使える為、一般家庭、といっても当時の庶民の暮らしと言えば長屋暮らしが大半で、それも一世帯に一つ厠がついていたわけでもなく、ほぼ全ての長屋で共用の厠が一長屋につき一つある、といった具合で、そこから肥料用としていくばくかの金と引き換えに長屋中の排泄物が徴収されていくのは、江戸も京も変わらない。
糞尿の徴収・運搬で財を成した豪農もあり、肥料としての排泄物は商品として流通し、この時代、糞尿相場といってもいいような一つの市場が形成されていた。
京では早くから辻便所の物も商品として流通していたが、そういった公衆文化がない江戸で辻々からも商品が流通するようになるのは、京よりかなり遅れての事だった。
ともかく、道端や草むらで用を足すという普段通りの事をしているだけなのに、変人じみた事をしてると嘉兵衛に思われてる気がして吉次郎は今一つ釈然としなかったが、雲一つない青空の下、尻を出して思い切りきばれる気持ちよさは何物にも代え難く、そのような妙な雑念はあっと言う間にどこかへ吹き飛んでしまうのだった。
「下痢でもしてはんの?」
「なんで?」
「10回以上野グソ行っとったやん」
二人が江戸に入り、吉次郎の貧相な長屋へとついた時には日も落ちていて、行灯に火をいれながら吉次郎は背中で答えた。
「下痢じゃねぇよ。いやなに、1回1回はたいした量じゃねんだ。ただ空の下
でケツ出して思いっきりキバれンのが気持ち良くてよ。
つい何回もいっちまった」
と振り返ると畳の上で両手両足を投げ出すように大の字になった嘉兵衛が、もういびきをかいている。
苦笑しながら吉次郎は自分の上っ張りをかけてやり、嘉兵衛の荷からト書きの束を取り出すと、「クソして寝るだけが能じゃねぇよ?」と独り言を一つ、行灯の火の下、床から拾い上げた50cmほどの物差しで右肩をトントン叩きながら一枚一枚ト書きにじっくり目を通しつつ絵の構想を練り始めた。
夜半過ぎ、木版彫りの道具一式取り出して仕事にとりかかった吉次郎、スズメの鳴声にも気が付かず、格子から聞こえてくる、部屋を出てすぐの所にある井戸の周りに集まった長屋のかみさん連中の声で朝がきたのを知りつつ、まだ薄暗い中、彫り刀を動かす手は一時も止まらない。
(日が出てくりゃ、油代を気にしなくてよくなら)と、今にも消え入りそうな行灯の火の下で、ゆっくり丁寧に木を削り続けた。
「ちょいとお妙ちゃん、あれん時もうちょっと声落としてくんない?
毎晩、毎晩、」
「ちょっと紗代姐さん!やめて下さい!みんなの前で」
「ええっ?お妙ちゃん!」
「違うんです!紗代姐さんが大げさに言ってるだけで、」
「所帯かまえて三月にもなろうってのにまだ飽きないのかい?
好きだねあンたも」
「違いますっ!うちの人が・・くるから、仕方なく・・」
「早くうまく断れるようんなっときな、あとあと苦労すっから」
「苦労って?どんな苦労ね?」
「早く終わりやがれってやつさ」
「長かったのかい?あンたの旦那」
「長いなんてもんじゃないよ、何がおもしろいんだか半刻(約1時間)近く
も上でハァハァやってやがってさ」
「半刻?大店の丁稚じゃあるまいし、
冗談じゃないねそんなご奉公は」
「あれぁおもしろくてやるもんじゃないだろう?それにしても毎度毎度半刻
もかかってたのかぃ?」
「さぁ?」
「なんだい、さぁってな?」
「知らないよ、いつも途中から寝てたもん」
「何知らん顔してネギなんか洗ってんのサ!お妙ちゃん!
あンたんとこも半刻かい?」
「・・そんなに長くできません」
「うちのはあっと言う間だったから楽だったけどねぇ。
毎晩じゃ体が持たないだろう?」
「毎晩なんかじゃありませんよ」
「でかいのかね?アレは?」
「知りません!」
「で?どんな声さ?」
「こんな感じ?」
「ちょっと!やめて下さいってば!紗代姐さんっ!」
隣に住んでる紗代のあえぎ声とそれに続く嬌声を耳にしながら、真剣な表情で木を削る吉次郎の傍ら、木くずの山で丸まっている薄い皮一枚一枚の黄みの混じった白い地肌が、うっすらとした蜜柑色を浮かべ始めていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
