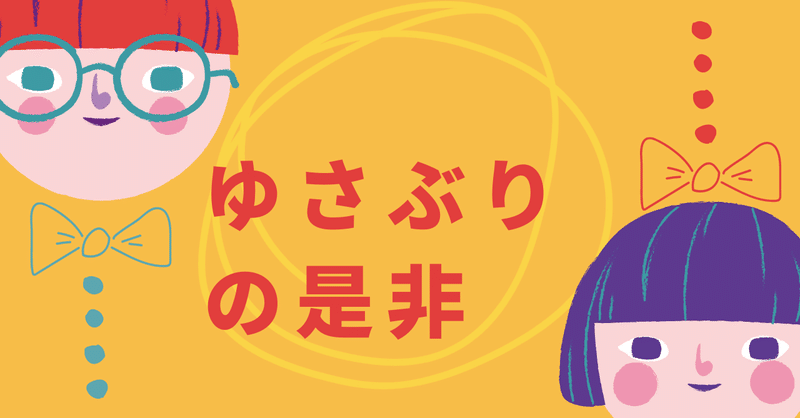
ゆさぶりを改めて考える
吉本均氏は「ゆさぶり」について次のように書いている。
なぜ、わたしたちは「ゆさぶり」という比喩を使うのか、そのわけを授業論の立場から明らかにしてくい必要がある。
たとえば子どもを学習の主体としてとらえるがゆえに、教師は子どもを「外側から押したり引いたりする」ということが必要になってくるのではないか。
子どもはこの種の「ゆさぶり」に誘発され、刺激されて、自ら教材に立ち向かう自己活動を開始するのではないか。
もちろん、この際、子どもの自己活動の方向性を問題にしていかなければならないことは言うまでもない。
ゆさぶって方向付けるという教師の指導性、これが子どもの自己活動を組織する指導性だと思うからである。そして、内容抜きの「ゆさぶり」を機能主義的、心理主義的と指摘している。
【学力と学習集団の理論】
「ゆさぶり」のみに固執して考えると、ゆさぶった後の子どもたちの感動や喜びの「理由」は問われないことになり、どのような内容であっても感動させたり、喜ばせたりすればよいことになる。
どのような内容に気づいた、知ったがゆえの感動・喜びなのかを明らかにすることによって、その「ゆさぶり」の妥当性を検討することが必要である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
