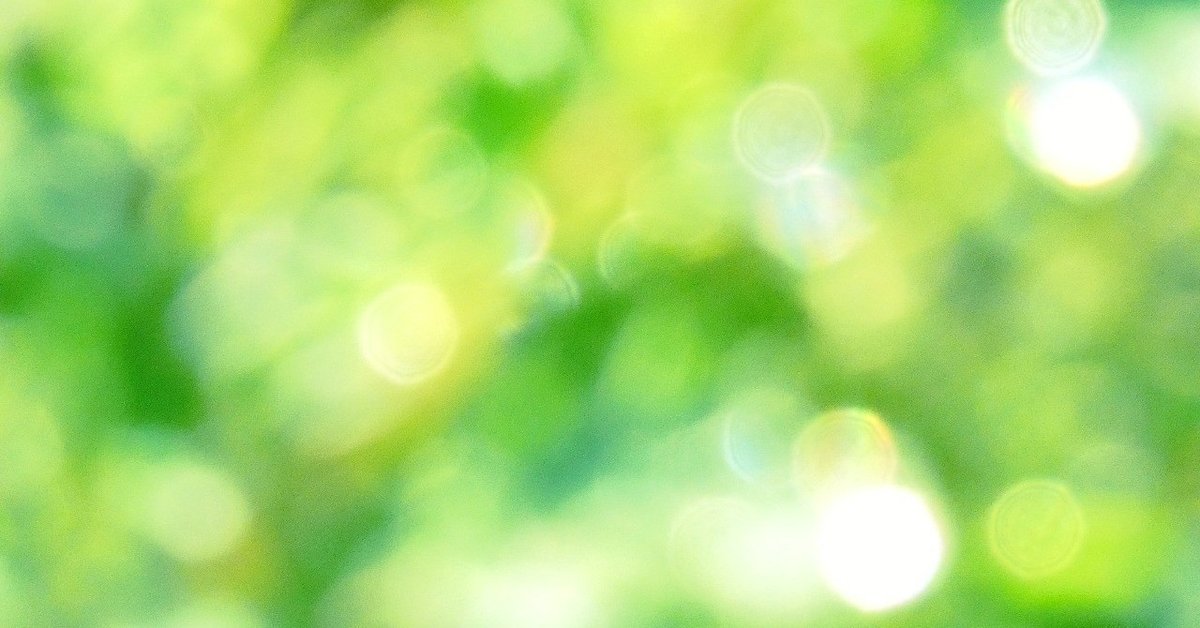
かみさまへ6
土曜日の今日もパートがある。子どもたちが休みの時はなるべく私も休むようにしているのだが 今月は売り出しがあるので 初日の今日は全員が出勤することになっている。
「じゃ行ってくるね。」
「いってらっしゃーい。頑張ってねー。」
朝食を作り、智弘とまだ布団の中にいる子どもたちに声を掛けて出掛ける。舞花が布団の中から返事をしてくれた。可愛いなぁと思う。
土曜日だから道路が空いている。いつもは待たされる交差点の信号も今日はすんなり通れた。運転している時間は自分と会話が出来るから好き。ごちゃごちゃしている頭の中を整理していく。
少し春めいてきた街のなかを 家族の休日に仕事に出ることに小さな罪悪感をもちながらも 家事と育児から解放されて一人の女として一日を過ごせることに少し開放的な気持ちになる。そんなことを考えながら車を駐車場に入れるといつもの時間より少し早く着いた。
「おはようございます。」
ロッカーに荷物を入れていると黒崎君が来た。
「おはようございます。」
「昨日はどうだった?まだ一日しか働いてないけど慣れたかな。」
「そうですね。皆さん優しいし、大変なことはなかったです。」
「黒崎君はお酒詳しいの?」
そつなくお客さんに対応するのは やはりある程度お酒に詳しくないと出来ない。
「好きなんです。あっと、おれは飲みませんが、父がソムリエなんで。」
「へー。そうだったんだ。だからかぁ。」
「だから?」
「なんか、お酒のことをとても大事に扱ってる感じがしてたから。」
「そうですか。自分じゃわからないですけど。」
「お父さんがソムリエなんて素敵。」
「母もお酒が好きなんで 自然といろいろ覚えました。」
そういってはにかむ彼はとてもかわいらしく
瑞木も高校生になったらこんなふうになるのかな。なってくれたら嬉しいなと思った。
「おはようございます。」
お店に出ていくと 珍しくお客がいた。お酒は重いので、買い物する人はみんな最後に買って帰るため 普段ならこの時間にはほとんど来ない。
「ありがとうございました。」
レジで商品を手渡そうとすると
「すみません、帰りまで置かせておいてもらいたいんだけど大丈夫かしら?」
「かしこまりました。お名前を頂戴してもよろしいでしょうか。」
お目当ての商品が無くなる前に買っておこうと言う人は 先に来てお取り置きしておくので 今朝はそんなやりとりもいくつかあった。
「これは 余韻のあるふくよかな味わいで、カシスのような華やかな香りのワインです。お客様が本日飲むのにぴったりかと思います。」
黒崎君がお客にワインの説明をしている。お父さんがいくらソムリエだからといっても興味なくちゃワインのことなんて覚えないよね。なめらかな口調に感心しながら眺めていた。わたしなんて売り出しの商品を覚えるのだけでいっぱいいっぱいで詳しい説明を求められるとあたふたしちゃうのにすごいなぁ。
今日のお客さんも 黒崎君に選んでもらったお酒を胸にやはりとても嬉しそうに見えた。
「すみません、おすすめのワインはどれですか?」
不意に後ろから声を掛けられた。
「はい、この中ですとこちらが飲みやすいと思います。」
「わたしは 少し渋みのあるものが好きなんですが。」
渋み。まいった渋みかぁ。どれかなぁ・・。
どぎまぎして裏のラベルを見る。そんなことでわかるんだったらお客さんも見てるはずだよね。と焦りつつ平静を装う。
「渋みのあるのは・・」
「渋みのあるものはこちらになります。このワインは少しスモーキーな香りと渋みが感じられアオカビのチーズとよく合います。」
さっと黒崎君が答える。
「わ、ちょうどブルーチーズがあるの。これにするわ。」
お客様は「ありがとう。」と言ってレジに並んだ。
「ありがとう黒崎君。助かりました。」
「宮園さんがあたふたしてるのが見えたから。」と言って笑った。
「わたし、人と話すのが苦手で。ワインも全然覚えられなくて。全く何でここで働いてるんだろうって自分でもあきれちゃう。」
「でも、これすごくいいと思います。」と言って昨日わたしが作ったポップを指さした。
「ありがとう。こういうのは好き。で、なるべく質問されないようにと思って 見やすさと分かりやすさと簡潔な説明を心がけてるんだけどね。」
「ぷっ。なるほど。なるべく話しかけられないようにと思って書くとこんな風にうまく書けるんですね。」
わたしはいったい何を言ってるのだろう。言わなくてもいいことばかり言ってしまって。
耳なじみのいい声に 頑なな心が少しオープンになる。
でもそんな話を聞いても、わたしが商品の説明をできないのを見ても 黒崎君の周りはやっぱりあたたかく静かだった。
「宮園さん、これ倉庫から持ってきてくれる?」と遠くから吉中さんが大きな声を出した。店内にいたお客様が一瞬びっくりしてて
すいません。うるさくてごめんなさい。って思う。
「はい、行ってきます。」
静かに答えて台車を押し倉庫まで行く。そこにはずらっと段ボールや木箱が並んでいてお酒やワインが入っている。
わたしは瓶が好き。食べ物や飲み物が瓶に入っているとそれだけでおいしそうに感じる。
だから このショッピングモールが出来てまもなく 舞花と瑞木を連れて歩いた時に見た いろんな種類のいろんな色のいろんな国の瓶が並ぶこのお店で働いてみたいと思ったのだ。
瓶の触った感じも好き。ひんやりとしているのだけれどあたたかみがあって 夏は見ているだけで涼しくなるし、冬はグラスにキャンドルを灯したなら ガラスに反射する炎の光のゆらめきをいつまででも眺めていられる。
今日は勤務時間が長いため 1時間の休憩がある。先に黒崎君が入り、わたしも30分ずらして休憩をもらった。お店のすぐ隣がコーヒーショップなので わたしは大概の休憩時間をここで過ごす。昼過ぎで少し人もまばらになったコーヒーショップに行くと黒崎君もいた。
「隣いいかな?」
「あっ 大丈夫です。」
「さっきは本当にありがとう。」
「いえ。」
「凄いね、黒崎君。ほんとにいろいろ知ってるんだね。」
「父の説明も何度も聞いてるし、何より好きなんです。その日のその人にぴったりなお酒を選んでお届けするのが。」
なんだかミキみたい。その人のこころにぴったり寄り添ううたを歌うミキ。その人にぴったりなお酒を届ける黒崎君。
「そうなんだね。もうしっかりソムリエなんだ。」
「父がワインの香りをかぐだけで そのブドウの育った畑や情景が浮かんでくるんだって言ってて それに凄い感動して興味を持つようになったんです。」
「香りから 風景が浮かぶ?」
「そう、でもそこに行きつくためにはとにかく五感を鋭く磨くことが必要だって。父が言ってました。」
「視覚、とか 聴覚とか?」
「そうです、全ての感覚を研ぎ澄まして感じるんだって。」
「へー、なんかすごいね。」
「まだワインのことはあんまり分からないけど 自分の感覚をつきつめてみてたら、目の前の人のこころの形とかものの形が見えるようになったんです。見えている形とは違う、なんというかそのものの本当の形というのか。だからこころの形に ぴったりとマッチングする形のお酒を探すんです。」
「へー、こころの形!?そうなの?」
では今、わたしのこころは彼にはどんな形に見えてるんだろう。
「ぴったりの形を見つけられて その人に届けられた時がすっごい嬉しいんです。」
ほんとに嬉しそうに照れながら話す彼を見ていた。
「あっ、変なこと言ってすみません。」
「ううん、わたしの従姉もいつもその時の気持ちにぴったりの歌を歌ってくれるの。きっと彼女にも見えてるんだと思う。」
「そうなんですね。宮園さんの従姉さんにもそんな人がいるんですか。」
「ん。歌を歌うの。同じ歌でも聴く日によってなんか違うんだ。」
「へぇ、すごいですね。聴いてみたいなぁ」
「うん、黒崎君にはいつか聴いてもらいたい。」
ミキの歌は、もしかしたら彼女の祈りなのかもしれない。と、ふと思った。
「じゃあいつか聴けそうですね。そろそろ時間なんで先に行きます。ごゆっくりどうぞ」
「あっ、あと、今度から宮園さんではなく もとこさんて呼んでもいいですか?」
「いいよ。」
「元カノが宮園だったんで。」そう言ってさわやかに笑った。
やっぱり彼の周りの空気は静かで 近くにいるだけでわたしも静かになっていくのがわかる。きっとああいう子に動物は寄って行くんだろうなぁなんて思う。どんな育て方をしたらあんなに穏やかな子になるんだろう。五感が鋭いという黒崎君のお父さんと お酒が好きだというお母さんを想う。
「ただいまー。」
「お帰りー。」
部屋の中から子どもたちが答える。
「お留守番ありがとね。」
「うん。」
「今日はパパとどこか行った?」
「うーんと、ママの働いてるところまで行ってお昼食べてきた。」
「えっ そうなの?」
「うん。」
智弘が答える。
「寄ってくれればよかったのに。」
「いいよ。恥ずかしいもん。」
舞花が言う。母親が外で働いている姿を見るのがなんとなく気恥ずかしいのだろう。
「そっか。じゃぁ今日は何ご飯つくろうかなー。」
「んーとね ハンバーグ!」
瑞木が代わりに応える。
「昨日も食べたじゃん。」
「僕は毎日でもいいんだよ。」
「みんなが嫌なの。」
瑞木の言葉に舞花がぴしゃりと言う。これがうちの日常だ。みんながこうやって怒ったり笑ったり元気でいることは、慣れてしまうと日常に埋もれてしまうが決して当たり前ではない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
