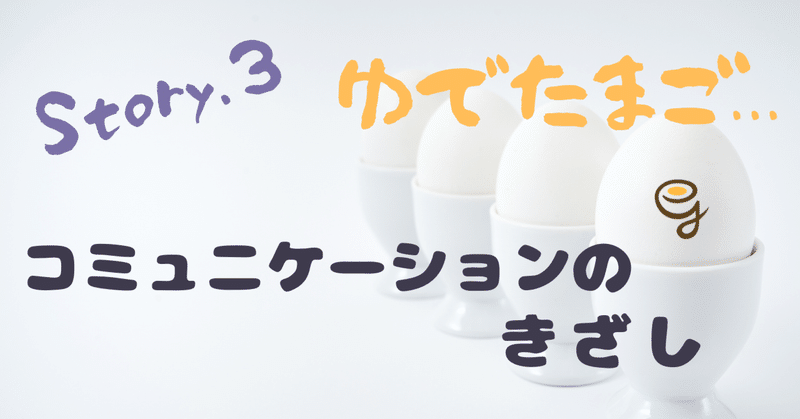
【3】コミュニケーションのきざし
息子が2歳半のときのエピソード。自閉症の子供でも、伝える側の私がタイミングをうまくつかむことができれば、理解できるんだ、ということがわかったんです。
そのお話を書いていきます。

私の親戚に地域の子供対象のサッカーのコーチをしている人(Sパパ)がいる。親戚のS君(親戚の二つうえのお兄ちゃん)のお父さん、Sパパだ。
Sパパは、よくうちの息子とも遊んでくれていた。そのうち息子がよく遊んでもらっていたのがサッカーだった。
家族以外の人と接することも息子には良い影響がありそうだなとは感じていた。
息子は、保育園ではいつもひとりでサッカーのドリブルをしているようだった。いつも見ている私にはそれほど驚くことではなかったが、たまたま見かけた園長先生が息子のドリブルの速さに驚いて教えてくれた。
別の同じ年の子供と比較しても早いが、さらに年上の年長の子達よりもボールの扱いがうまかったらしい。
息子は、2歳半でサッカーのドリブルができて、まぁまぁ早い方だったのだ。

ある日のこと。
私は、息子の様子を見に行ったときに、Sパパに聞いてみた。
息子と親以外の人とのコミュニケーションが成立しているのかを確かめるためにあえて聞いてみたのだ。
私『アッキーはボール蹴ってパスできてる?』
Sパパ『できてるよ。』
『アッキー!ボールこっちに蹴ってみろ!パス!』『ほら!』
このやり取りが普通に見えた。まるで健常児を見るかのようだった。
この時、コミュニケーションがなぜできているのかはわからないがとりあえずできていた。不思議だった。このコミュニケーションはノリなのか何なのか成立していた。
普段のような「会話」としてのコミュニケーションができているかはわからないけれど、ボールをパスしたり、ドリブルしたりする上での必要なやり取りはとりあえずできていた。
Sパパと息子とのコミュニケーションでは、いつもオーバーアクションが加わっているから、そのパフォーマンスが解りやすかったのだろうか。

一方、親の私は息子が他の子どもたちと様子が違うことから、この時期は自閉症かもしれない…… と無意識に先入観をもって、関わっていたのかもしれない。
Sパパの息子への接し方はそういったものがなく、「普通」に接してくれていた。この前提の違うやり取りが、息子にとって届き方が違っていたのかもしれなかった。
私が、Sパパが息子に接してくれているのを見守っていて、
そこで初めて、コミュニケーションが成り立っていると思えた息子の姿を目
にした。
普段は、息子のできてないことにばかり目がいきがちな私は、
息子が「コミュニケーションができている」その場面があることに気づけた
この一瞬に驚かされた。
そして意外だったことは、正直嬉しい気持ちよりも、
この大切な気づきを、これからの息子のために活かしたい!!
と思う気持ちの方に強く強く意識が向かっていたんだと今でも思い返す。
この現象はその時はただただ不思議。なんで出来たのか……??
たぶん、リラックスした状態だと奇跡的にうまくいくのかもしれない?
(私は、自閉症は常に緊張状態にあると思っていた。)
偶然だと思っていたけど、条件が揃えばできるときがあるのかな??
もしそうなら、また条件が揃えば出来ることが増えるかもしれない。
この偶然のようなタイミングをしっかり覚えておこう!
その場の雰囲気でたまたまコミュニケーションがうまくできてしまった偶然なのではなく、必然につなげられる可能性を感じた出来事だった。
この時、息子とコミュニケーションをとるときにはタイミングが重要で、『理解できている』こともあることを、私がしっかりと気づけた瞬間だった。
そう思って過ごすものの、そうは言ってもつかの間。
悪い時があると、つい良かったタイミングを私自身が忘れてしまってまた元に戻る。
「できていた」という素敵なタイミングがあったことを忘れてしまうのだ。
私の感情はいつもアップダウンしていた。

脳の構造の本を読み漁ったりしたが参考にならなかった。
この時が一番苦しかった。息子と他の子との比較や気持ちの焦り・・・。
でも、この偶然できたように思えたタイミングの経験が、のちに私と息子に大きな変化を与えてくれることになった。
私の気持ちがアップダウンしながらも息子をみていて、息子が理解できている様子がみてとれるときは、
例えていうと、「つながりのある長編」ではなくて、「ショートストーリー的な短編」なら理解できていると感じる場面が多いことに気づけた。

息子が先入観を持たずに接してくれている親戚のSパパとのサッカーをしている様子を見ていて気づけた、「コミュニケーションが取れている場面」を通して、
自閉症児はオーバーアクションのほうが記憶にとどまる
短く端的に伝える方が記憶にとどまる。
そして、この繰り返しで感情を通して記憶する、その記憶を引き出して行動に結び付けさせることがポイントになる。
繰り返しと感情と行動!!
このときの気づきが、小学校低学年時代のテストでも役立ってくれることになる。そのエピソードについては、また別の記事でお話させてもらいます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
