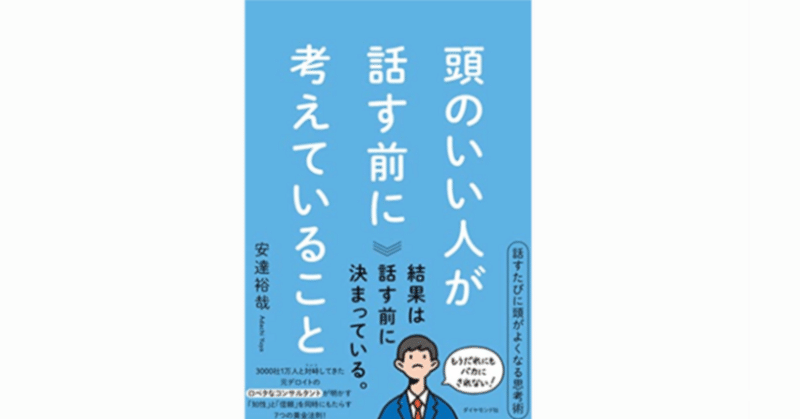
『頭のいい人が考える前に話すこと』を読んでみた
本業でも翻訳でも言葉を丁寧に扱う場面が多いのだが、話をする前になかなか頭の中で考えがまとまらず、そのまま話し始めたらグダグダになってしまった、という苦い経験が何度もある。
それを何とか克服したいと思って手にした1冊。
この本の中に出てくる「残念な人の例」の中に、自分もあてはまることが少なからずあった。「自分の理解できたことだけを切り取る人」「他人が話すときに自分が話すことを考えてしまう人」「何かを教えてもらうときに何がわからないのかがわからなくて質問ができない」…。まさしく私だ、と心に突き刺さる。
なぜ、考えが自分の頭の中でうまくまとまらないのか?という漠然とした疑問がずっとあったが、その答えはこれらに大きく関係している気がした。
その課題を解決するため、さらにコミュニケーション能力を高めるために必要なこととして、この本で述べていることをかいつまんでみた。
【話を聞くとき】
・自分の頭の中を白紙状態にして、相手が何を言いたいのかに意識を集中させる。
・相手を肯定したり否定したり、評価したりしない。自分の意見を挟まずに最後まで聞き切る。
・返答は、アドバイスではなく、話の内容を自分なりに整理したことにする。
・二人で思考を深く掘り下げるための質問:
①過去に何をしたか
②そのときどんな状況だったのか(今どんな状況なのか)
③その状況に対してどんなアクションを取った(取っている)のか
④そのアクションによる成果や結果はどんなものがあったのか
⑤もし~だったらどうなるだろうか(自分が相手の立場だったらこう思うがどうだろうか)→仮説を立ててみる
【わからないことを教わるとき】
・質問の意図を相手がすぐわかるようにする :
①質問するのは一度にひとつだけ、単純な(具体的な)要素に分解する
②わからないことに関しては、わからないと思った経緯を説明する
・時間が許すときは、深く掘り下げるための質問(前述)を取り入れる
・頭のいい人の輪に入る
【自分が話す前に考えること】
・物事を客観的に、さまざまな視点からとらえる(反対意見の可能性も考える)
・「事実」「感想」「意見」を区別。「事実」を踏まえて論理的な「意見」を導く
・「言語化」という行為によるコスト(労力)をどちらが負担しているかを意識する
・言語化のコストは自分が進んで払うようにする(自分が賢くなるために)
・言葉を再定義する「〇〇ではなく、△△である」→「良い〇〇とは、悪い〇〇とは」
(言葉そのものの意味があいまいな場合、その言葉の本来の意味を再確認することも有用)
【語彙力アップのために】
・ネーミングの癖をつける
・貧弱な言葉を具体的な言葉に置き換える
・「読書ノート」「ノウハウメモ」を作る
こう列挙してみると、今の自分の課題として、その時々のメンタルや話の内容によって「頭を白紙にして聞き切る」の達成度が大きく変化していることに気づく。
ただ自分の場合、周囲の雑音が気になると話し手の声が聞き取れなくなる体質なのもあり、そういう時は「今なんて言った?」と聞き返せずに流してしまうこともあるという問題もあり、結果聞き取れたことだけを切り取ってしまうことも多い。そこでいかに勇気をもって「もう一回言ってもらえますか」を言えるかも大事になってくると思う。
雑念が消えない、話の内容が集中力を保てるようなものではない、といった状況で、いかに頭を白紙にすることができるのか?その対策としては、まず相手の話を聞く前に、「be here now」のマインドを固めておくことが必須だと思う。
また、話を聞く間は自分が話し手になりきってみるというのも、集中力を高めるためにはありかもしれない。
思考を深く掘り下げるための質問、「事実」と「意見」の区別も特に意識する必要がある。また、日常的な語彙力アップに関しては翻訳で培われている部分もあるが、自分の意見を述べているわけではないので、そのために読書ノートなどのような「まとめ+所感メモ」といったものも都度残しておこうと思う。ということで、このページを書き起こしてみたわけである。
この本の最後の方で紹介していた外山滋比古さんの『思考の整理学』もとても興味深い。近いうちに読んで自分なりのメモを残そうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
