
“僕は大バカだ! クソったれの大バカだ!”~『リコリス・ピザ』公開記念🍕『ポール・トーマス・アンダーソン』より、ジョシュ&ベニー・サフディの序文をためし読み公開
世界三大映画祭を制した若き巨匠、ポール・トーマス・アンダーソンによる待望の最新作『リコリス・ピザ』が本日7月1日に劇場公開されました。
1970年代のハリウッド近郊、サンフェルナンド・バレーで偶然出会い、すれ違い、歩み寄っていくアラナ(アラナ・ハイム)とゲイリー(クーパー・ホフマン)の恋模様をみずみずしく描き出す――。
このたびは『リコリス・ピザ』の公開を記念し、日本劇場未公開の『ハードエイト』から『ファントム・スレッド』まで、PTAの全過去作を300点の豪華図版・共同制作者たちのインタビューとともに網羅した決定版書籍『ポール・トーマス・アンダーソン ザ・マスターワークス』(アダム・ネイマン著、井原慶一郎訳)より、序文を全文ためし読み公開いたします。

本書に序文を寄稿したのは、『グッド・タイム』『アンカット・ダイヤモンド』などの作品で知られるジョシュ&ベニー・サフディ兄弟。少年時代に初めて見たPTA作品『ブギーナイツ』がいかに衝撃的だったかが綴られています(「それは深い人生経験を感じさせる表現だった。とても26歳の若者が作った映画とは思えなかった」)。
ついに日本公開となった“極上のピザ”をよりおいしく堪能するための前菜として、あるいは食後の余韻を味わうためのデザートとして、この機会に書籍『ポール・トーマス・アンダーソン』をぜひお楽しみください。
* * *
序文
ジョシュ&ベニー・サフディ
「酔ってるだけだよ、ほんとに。何だか頭がぐるぐるしちゃって。酒が回って――ほんとに酔ってて。ダーク、ただ酔ってるだけなんだ。僕は今クレージーだよ。ほんとバカみたいだ」
ダークは、自分の栄光の年の終わりを記念する真夜中のカウントダウンを逃さないように、急いで大晦日のパーティーへと戻る。スコティは、質の悪い塗装を施され、まだ乾いてもいない、ダーク・ディグラー気取りのスポーツカーとともに独り駐車場に取り残される。スコティは車に乗り込み(実際は彼が主張するほど酔っていなかっただろう)、「僕は大バカ(fuckin' idiot)だ! 大バカだよ。あきれたバカだ! ほんとに何てバカだ! どうしようもないバカだ! クソったれの大バカだ!」と涙にむせびながら言う。それから、軽快なザ・ワッツ・103rd・ストリート・リズム・バンドのサウンドトラックが流れ、そのクールで自由放任主義を感じさせる音楽によって、スコティとともに観客が感じていた孤独は――いつか再び戻ってくると知りながら――心の奥底へと追いやられる。
初めて『ブギーナイツ』を見たとき、私は14歳くらいだった。ポール・トーマス・アンダーソンの映画を見たのは、それが初めての経験だった。ちょうどその時期と、成人向け深夜番組――アル・ゴールドスタインと彼がホストを務める視聴者制作のケーブルテレビ番組「ミッドナイト・ブルー」(数年後にフランク・T・J・マッキーのコマーシャルを流していたとしても何ら不思議はなかっただろう)――に興味を持ち始めた時期が重なっていた。『ブギーナイツ』は、ポルノへの興味と執着をおおっぴらに語っていた映画だった。私のなかでは「ミッドナイト・ブルー」と『ブギーナイツ』はかなりの程度において重なり合っていた。
この映画が私たちについて何を教えてくれるのかはよくわからなかったが、ダークの上昇志向(「本物のイタリア製の革のソファ」)に共感する一方で、本当に心に響いたのは、スコティであり、ローラーガールであり、バック・スウォープであり、カート・ロングジョン――リトル・ビルの妻が見ず知らずの男とセックスしているそばで彼と照明の話をしようとする――だった。アンダーソンの映画には、まるで自分の映画の主役を演じているかのような印象的な脇役が多く登場する。
私は10代の若者で、フィリップ・シーモア・ホフマンが演じる件の場面(「僕は大バカ(fuckin' idiot)だ!」)を繰り返し見たのを覚えている。私はビデオでその場面を見て――その場面だけを何度も繰り返して見て――その意味を「理解」しようとしていた。そこには、「ハリウッド・スタイル」で語られた映画のなかに、普遍的な人間性の表現があった。
それは深い人生経験を感じさせる表現だった。とても26歳の若者が作った映画とは思えなかった。『パンチドランク・ラブ』が公開されたとき、私は18歳だった。私たちはアダム・サンドラーとともに成長した。とりわけ彼の最初の2枚のコメディ・アルバムは夢中で聴いた。そのCDケースは私たちの記念碑だった。そして、彼が主演する映画がやってきた。それらは、いつでも完璧だった。若者だった私たちはコメディが大好きだった。コメディこそが「映画」だった。もっとよく人生を理解するために、父親が私たちに見せてくれる真面目な作品は「映画」ではなく、ただの「人生」だった。それらを映画と呼ぶことはなかった。それらは、私たちを笑わせるために存在するのではなく、漠然とした状況のなかで何らかの答えを見出すために存在した。そうした作品は私たちを感動させたが、サンドラーこそが私たちの最初の宗教だった。彼が伝えるのは、世間のあらゆる人や物が敵対してくる状況に対して、そのピンチを彼独自の奇妙なやり方で切り抜ける不条理譚だった。

成長するにつれて、父親が執着していたようなタイプの映画が、ときどき脇道に逸れて見る映画になった。そのなかにはポール・トーマス・アンダーソンによる映画も含まれていた。『ブギーナイツ』のような映画を見ることで、ロバート・アルトマンといった1970年代の映画監督たちによる一連の映画への扉が開かれた。言うなれば、『ブギーナイツ』は、父親が作った通路ではなく、自分たち自身の通路に進むための入り口――地下へと通じるマンホールの蓋――だったのだ。もちろん、私たちはサンドラーの映画を見続けていた。だが、それらは違う意味を持ち始めていた。それらは、私たちにとって「ピュア」なものになったのである(そして、これからもずっとそうであり続けるだろう)。元はと言えば、私たちの目をサンドラーに向けさせたのは父親だった。だから、『パンチドランク・ラブ』が公開されたとき、私たちがどれだけ驚いたかは想像してもらえるだろう。それは確かに「サンドラー」映画だったが、リアリズムとフォーマリズムのレンズを通して描き出されていた。ハッピー・ギルモア(『俺は飛ばし屋/プロゴルファー・ギル』の主人公)は、パットの仕方を覚えたのだ!
目を見張る場面として、誰もがバリーが怒りを爆発させて引き戸のガラスを叩き割る場面を挙げるが、私たちの心が圧倒されたのは、最初のデートのレストランでの場面である。それは、繊細ではあるが、くっきりとした――『ブギーナイツ』でホフマンが、車のなかを覗くために前かがみになったウォールバーグの背中にそっと手を置く仕草のような――ミクロな演技だった。例えば、リナが、ハンマーで窓を粉々にしたというバリーの子供時代のエピソードを持ち出したとき、サンドラーがおこなう腕を素早く急に動かす仕草――あるいは、トイレを破壊したことでマネージャーに詰め寄られたときの足をわずかに跳ね上げる動き――もしくは、トイレを破壊する行為それ自体!
サンドラーの怒りや隠れた狂気は、アンダーソンの微視的なレンズを通じて表現されていた。それでも――もちろん――おかしくて、楽しめるものになっていた。しかし、そうした表現は、私たち自身の日常の抑圧にも目を向けさせるものだった。また、それは、私たちがサンドラーの以前の映画を新しい目で見ることを余儀なくさせた。世界はもはや互いに分裂してはいなかった。それらは共存することができた。
こうした認識が持てたのは、すべてアンダーソンのお陰である。
彼には多くのことを教えられてきた。ドキュメンタリー風の演出。風変わりな人たちの人生を共感のこもった寓話として巧みに語ること。いくつもの物語を収録した一冊の大きな本のように、一連の同じ俳優を作品ごとにシャッフルして、違った役を演じさせること――ファスビンダー、カサヴェテス、アルトマン、サンドラーの映画のように。理想の「一発」を求めて、何百もの爆竹の音を録音すること。まるで制御された実験のように、安定した構図のフレームのなかで演技がより生き生きとしたものになること。内容と完全に一致しているように見えるフォーマリズム。そのフォーマリズムのなかに見出すことができるリアリズム。強迫観念の共有。『ファントム・スレッド』、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』、『ザ・マスター』といった傑作において――まさに映画を作るという行為に他ならない――創造的で複雑な心の謎を映し出すこと。彼の作る映画が毎回1つの重要な出来事になること。
いつも先頭を走り続けること。
* * *
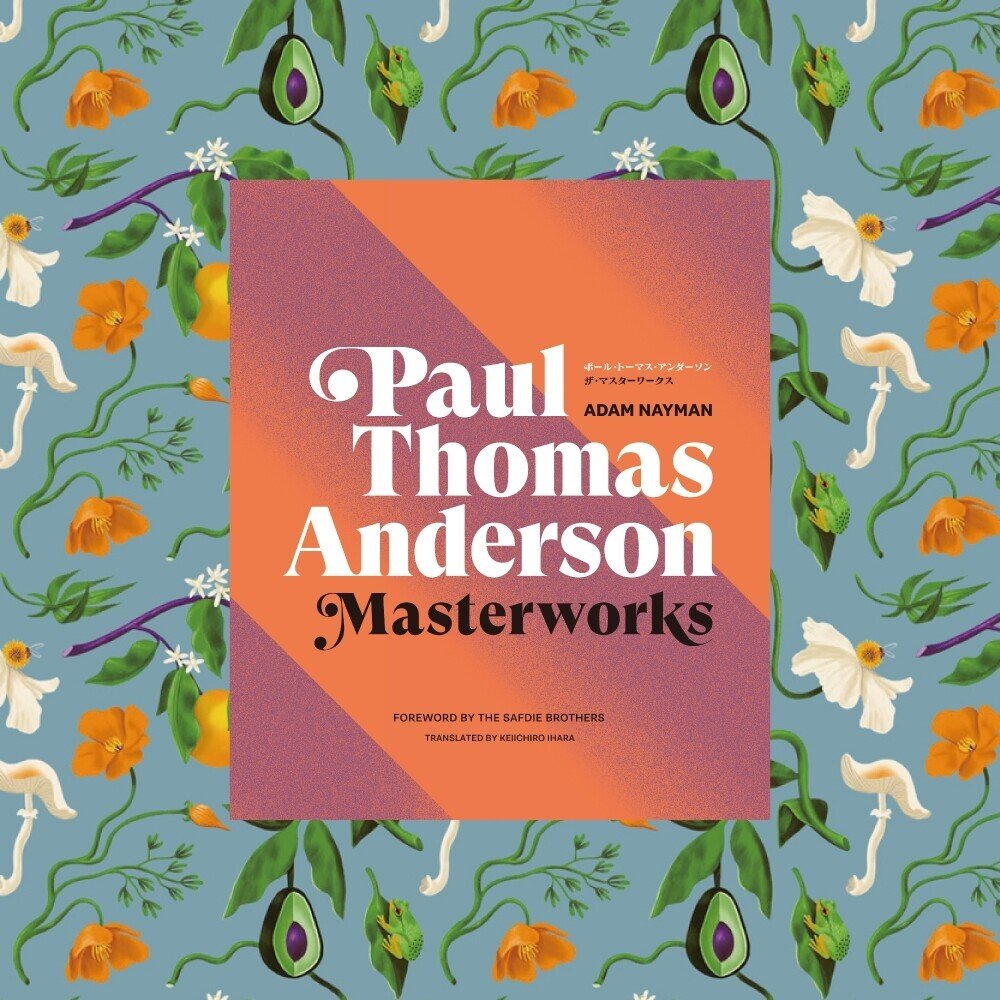
《書誌情報》
『ポール・トーマス・アンダーソン ザ・マスターワークス』
アダム・ネイマン=著 井原慶一郎=訳
B5変型・並製・オールカラー288ページ
本体4,500円+税 ISBN: 978-4-86647-155-6
〈内容紹介〉
■名場面スチール/描き下ろしイラスト/映画ポスターなど豊富なビジュアル300点&PTAの共同制作者たちのインタビューも収めた豪華決定版。
「カメラがプールに入る瞬間にカットしていると思われているが、そうではないんだ。私たち――グリップのジョーイ・ディアンダと私――は水中マウントを取り付けたカメラを持って、実際にプールに飛び込んでいるんだよ。少し経ってから水面ぎりぎりのところにカメラを出して、ショットを続けるようにしてね」
――ロバート・エルスウィット(撮影監督)、『ブギーナイツ』のプールの場面について
「その場面についてあとでポールに尋ねたとき、私は「あなたは知っていたはずだけど、この場面には終わりがないと感じたわ」と言いました。彼は「君の言うとおり。こうしたことが起こるのを期待していたから、明確な終わりはあえて書かなかったんだ」と答えました。こういうところがポールの天才的なところだと思います」
――ヴィッキー・クリープス(俳優)、『ファントム・スレッド』でのアドリブについて
■コラム「PTAのムービー・コレクション」では、ロバート・アルトマン、マーティン・スコセッシなど、P・T・アンダーソンに影響を与えた過去作品との関係をひも解く。
■レディオヘッドやハイムほか、PTAが監督したミュージック・ビデオも紹介。
* * *
本書より、「ショットのためなら何でもする」をためし読み公開中🎥
