
複利って一体何なのさ?幻?!途中利確から乗り換え後のパフォーマンスをガチホと比較!
初めに。
前回note第二弾読んで頂いた方々、すみませんでした。構想としてもっと意味のあるものを書かなくてはということで書き直しになりました。
『含み益』同士で比べること自体や計算結果などは間違いではなかったのですが、
投資が『資産を増やすのが目的』とするならば含み益をニマニマ『鑑賞』していてもしょうがないです。
結局どれくらい資産が増えるのか?
つまり『全売却後の資産』で比べてこそというご指摘を受け、検証のエンドポイントを全利確同士でのパフォーマンスの比較に変えました。
さあ気を取り直して、
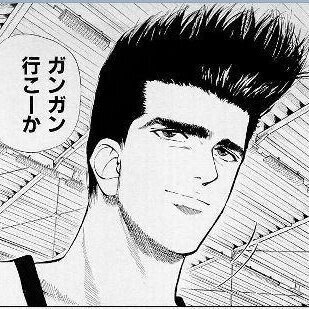
今回noteを初めて読む方に説明させて頂きますと、
前回のそのノート第二弾📔は何をテーマにしてたのかというと、
含み益のAを一旦全利確、その資金でBへ乗り換え。
Aをそのまま保有していた場合のパフォーマンスに乗り換えたBが追いつくにはどれくらいの差Δが必要か??
についてでした。
ガチホAと乗り換えBの最終的な⚠️『含み益』に合わせ計算していましたが、
今回のゴールは
最終的な✅『利確後の資産』を比較します。

目次
1️⃣前提及び、具体的検証方法
2️⃣結果
3️⃣考察
4️⃣実際の計算の仕方について
5️⃣おまけ 3バガー テンバガー編
1️⃣前提及び検証方法
・源泉徴収ありとする
・税金は20%とする
・売買手数料は計算には含めない
・ゴールはAとBの利確後の総資産とする
・結果は小数点第二以下は四捨五入
これから検証する内容の具体例を示します
含み益20%の銘柄Aを一旦売却、その資金で銘柄Bへ乗り換える。 乗り換え後から銘柄Aがさらに30%上昇したと仮定。
Aをホールド続け、その仮定した上昇後に売却した場合に到達する資産額に、Bが到達するにはどれくらいの上昇(%)が必要になるか?
少しわかりにくいので、簡単にいうと
含み益のある持株Aを途中で売ってBに乗り換えた場合、
「銘柄Aを売らずにそのまま持ち続けた場合」に対して、
乗り換えBが追いつくべきノルマΔを数字で示したいと思います。
つまり、これによりガチホvs乗り換えのパフォーマンスの差の一端を見ることができます。
この結果を通じてガチホによる複利の効果の影響の大小を知り、
利確や乗り換えの戦略に役立てていくのが目的です。
2️⃣結果

※わかりやすくするため元本を100とし、 ()内を変化後の資産額とします
✅含み益+10%の銘柄A(110)
そこからホールドしさらに10%-100%上昇し、利確した際の資産額。
ホールドせず利確した資金で乗り換えたBがAガチホの資産額に追いつくのに必要な上昇率は??
+10%(121) 10% vs 10.2% Δ0.2%
+20%(132) 20%vs 20.4% Δ0.4%
+30%(143) 30% vs 30.6% Δ0.6%
+50%(165) 50%vs 50.9% Δ0.9%
+100%(220) 100% vs 101.9% Δ1.9%
✅同様に含み益+20%(株価120)の時点からのガチホAと乗り換えBの比較
+10%(132) 10%vs 10.3% Δ0.3%
+20%(144) 20%vs 20.7% Δ0.7%
+30%(156) 30%vs 31.0% Δ1.0%
+50%(180) 50%vs 51.7% Δ1.7%
+100%(240) 100% vs 103.4% Δ3.4%
✅同様に含み益+30%(130)からのABの比較
+10%(143) 10%vs 10.5% Δ0.5%
+20%(156) 20%vs 21.0% Δ1.0%
+30%(169) 30%vs 31.5% Δ1.5%
+50%(195) 50%vs 52.4% Δ2.4%
+100%(260) 100%vs 104.9% Δ4.9%
✅同様に含み益+50%(150)からのABの比較
+10%(165) 10%vs 10.7% Δ0.7%
+20%(180) 20%vs 21.4% Δ1.4%
+30%(195) 30%vs 32.1% Δ2.1%
+50%(225) 50%vs 53.6% Δ3.6%
+100%(300) 100%vs 107.1% Δ7.1%
✅同様に含み益+100%(200)からのAB比較
+10%(220) 10%vs 11.1% Δ1.1%
+20%(240) 20%vs 22.2% Δ2.2%
+30%(260) 30%vs 33.3% Δ3.3%
+50%(300) 50%vs 55.6% Δ5.6%
+100%(400) 100% vs 111.1% Δ11.1%
今回の前提を与えてくれたアルセーヌhttps://twitter.com/arsenelupin_1?s=21さんの計算表も参考に乗せておきます✅

確かに含み益が大きくなるほど、またそこから上昇していくほどAとBの差が開いていくのがわかりますが・・・
この数字の差みなさんはどう思いますか?
解釈は僕はとても難しいと感じました
3️⃣考察

検証結果を言葉にすれば確かに幻となった第二回note同様に、
『乗り換える以上はBがAをアウトパフォームしなければ意味がない』
という結論は変わらないのですが、
まるで印象が真逆に。
とてもじゃないけどドヤれる程の数字の差=ハードルがない。
ある意味これ衝撃じゃないですか?
複利信者だった僕からすれば脳天に⚡️が落ちましたよ。
複利を捨てて乗り換えてアウトパフォームするのは相当なハンデだと思ってました。
ある時まで気づかなかったんです。
複利とは上昇によって取られるべき税金の内部留保
だって。
つまり税金の先送り。 それによって雪だるまを大きくしてるわけです。
ただ雪ダルマで大きくなるのは利益だけじゃない。税金もデカくなる。
僕が見誤っていたのはそのデカくなり方も半端ないってこと。
だから前回のAとBのゴールを含み益で比べた場合と、
今回のように売却後で比べた時にこんなにも数字に差がでてしまう。
よく『含み益は幻』といいますが(下落で消えてしまうこと)
、それとは違う意味で『含み益は幻』ということを今回思い知ってしまいました。
そして含み益という形で虚勢を張っていた『複利』 が売却され税を引かれ裸にされると、こんなにも地味なパフォーマンス差になってしまうなんて。
僕はこういう比較対象がいなければ気がつきませんでした(頭の良い人は無意識に気づいていたと思います)
で、最近のテーマ、フルインベストメント、さあ、なにを売って何を買う?
今回の結果を踏まえて考えると、よほどの含み益でなければ乗り換えにはそんなに神経質にならなくてもいいかもしれないと思いました。
勝負を分ける要素は純粋にAとBのパフォーマンス自体の方が大きいですね
含み益30%ぐらいまでなら、僕なら純粋に勝てそうな奴を見つければ乗り換えると思う。
しかし後述しますが、この検証結果をこのように捉えて差し支えないのかなんか引っかかります。
あと考えておくべきは、これからのA、Bのパフォーマンスを考えるに当たって、いつ何を持ってアウトパフォームとするのか?
乗り換え戦略の考察は色々あると思います。
じっちゃま的な決算励行主義でいけば決算ピカピカの奴らを乗り換えるなんてナンセンスでしょうし、

NUKさん的なモメンタム投資で攻めから攻めへと乗り換える戦略もありますし、
下落耐性を重視しグロースからバリューへ、後々の調整局面でのアウトパフォームを狙う戦略もあると思います。
またディフェンス面を考慮すれば、グロースを貫くにしても「決算が良い」ほうがいいですし、小型よりも中大型の方がいいのかなとか。
他そこにテーマ株で今特需なのか?特需は関係ないのか?今後の米中摩擦のリスクは?とか色々なことを考え乗り換えるのが良いかなと。
コロナ相場も進み、
これから先の乗り換えは攻撃面だけでなく徐々にディフェンスを意識する局面になってきていると僕は考えています。
ただここまでの僕の論調に自ら入れる注意点としては、
今回検証した数字の差を小さいと考え、
簡単に短期で取り返せると思ってしまう
のは・・・
今が『バブルだから』ってのはあると思います
SP&500の年利にあたる7%くらいをわずか1日で取り返せてしまうような狂った相場ですからね
また、複利を考える時、相手を変動するBではなく動かない相手=キャッシュにするとだいぶ見方は変わります。
第一回noteの原資抜きでのパフォーマンス検証がそれに近いかと思います。
ひょっとしたら本検証の前提のAとBがほぼ同等のパフォーマンスを示す前提で全てを計算しているのでその辺りが無理がある検証なのかもしれないです。
この辺の解釈や結果に対しての本当の正しい解釈がガチもんの天才じゃないと難しいと思っています。
あとは思考のトリックと言いますか、
この手の検証は前提条件などで結果を誘導する何かを見落としてる可能性があります。
なので今回の結果は結果ですが・・それを=複利は無視しても差し支えないものだぞ!と結びつけるのはやめておきます。
ひとまず今回の前提条件と検証でこういう結果が出たということに留めておきます。
予防線になってしまって見苦しいんですが、検証の仕方を含め本当に難しいんですよね凡人には
この先は誰かガチの天才にバトンタッチで。

4️⃣実際の計算方法
例 含み益20%からのガチホAと乗り換えBのパフォーマンス比較 +30%の場合
Aを100とすると、
含み益20%=120
そこで売却 100+(120-100)✖️0.8=116
その116でBに乗り換え
Aを売却せず+30%上昇したところで売却(ゴール)
120✖️1.3=156→売却すると資産は100+(56✖️0.8)=144.8となる
次にBを売却した際にその144.8に追いつくYを求めると
116+(Y-116)✖️0.8=144.8となる
Y=152となる ⚠️売却後Aと同じ資産になるBは156ではない
116から152へ必要な上昇率は152/116✖️100=31.03•••四捨五入して31.0%
Aの上昇30%に対してΔ1.0%多く必要になります。
5️⃣おまけ
2バガーじゃ物足りないアキ46さんや
SQでテンバガーを達成しているズッ友hiroさんのために『3バガー とテンバガー』にて同検証を貼っておきます。
✅含み益+200%からABの比較
+10%(330) Δ1.5% +20%(360) Δ3.1% +30%(390) Δ4.6% +50%(450) Δ7.7% +100%(600) Δ15.4%
✅含み益+900%
+10%(1100) Δ2.2% +20% (1200) Δ4.4% +30%(1300) Δ6.6% +50%(1500) Δ11% +100%(2000) Δ22.0%
改めてテンバガーてヤバいですね
+10%上がるだけで含み益が元本分上がるw
Δよりも()内の変化に目がいってしまうw
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
