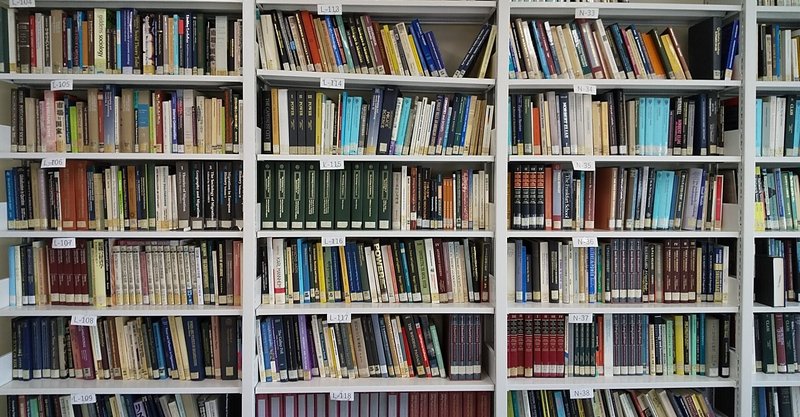
知・ヒト・モノのキュレーション
時代の変革期に、今、①社会課題を見つける「観察力」と「分析力」、②当事者と対象に思いをめぐらす「想像力」、③それらを伝える「表現力」・「発信力」、③人と社会を巻き込んで動かす「行動力」を持った人材が必要とされています。そのような人材は、学問的な知とさまざまな現場にある知をキュレーションします。キュレーション[curation]とは、無数の情報の中から、自分の価値観に基づいて情報を拾い上げ、新たな意味を与えて、多くの人と共有すること。知と人のキュレーションにより、社会を変えるソーシャル・イノベータを私は2016年に「知のキュレーター」と名付けました。
さまざまな社会的課題の解決には、人と知のキュレーション、大学と企業や社団法人等多様なステークホルダーによる「共創」が必要です。そして、その共創には、部分しか知らない専門家ではなく、全体を掴むことのできる人が必要です(清水・前川、1998)。部分に詳しい専門家だけを集めると「競争」になりますが、共感する「場」を共有していれば、そして、全体を掴む人がいれば「共創」になります。清水・前川(1998)は、20世紀末に既に、地域社会のコミュニティのあり方や生活に根ざしつつ、地球環境をも視野にいれた産官学の「共創」的ネットワークの構築の必要性を語っています。
そこで重要なのが「場」です。清水博(2003)は、人間が生きていくうえで重要な「場」として、「生活の場」と「人生の場」という二種類の場があると論じています。「生活の場」とは即興的な生活体験がリアルタイムにおこなわれている場であり、「人生の場」は、多様な「生活の場」におけるさまざまな生活体験を反省的に振り返ってその生活体験を編纂し、人生という個人の歴史を編成する「場」です。この編纂というプロセスにおいては、「人生はかくあるべきである」という哲学や「人生をこう生きたい」という願望があり、さらに、創造には「世のため、人のため」という志や使命感が存在すると主張します。
知のキュレーション、共創、今を生きる大切なキーワードと思います。
引用
・清水博・前川正雄(1998)『競争から共創へ』岩波書店
・清水博(2003)『場の思想』東京大学出版
※知のキュレーター:「現実社会はさまざまな問題を抱えますが、その改善や解決のために、多様な専門領域で深められてきた専門知から学際的な統合知を構築し、国内外の多様なアクターと協働して、共創知に鍛え上げるこの過程を「知のキュレーション」と呼びます。改組による新たな体制で私たちが目指しているのは、人類が直面している諸課題の解決方法を模索する「人間科学版・知のキュレーター」の養成です。そしてこの「知のキュレーション」を教育、研究、社会貢献に活かそうとしているのです。」
大阪大学人間科学部学部長挨拶より
https://www.hus.osaka-u.ac.jp/ja/content/dean_greetings.html
参考
・稲場圭信「共生社会にむけての共創」、志水宏吉ほか編『共生学宣言』(2020)大阪大学出版会、pp.193-213.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
