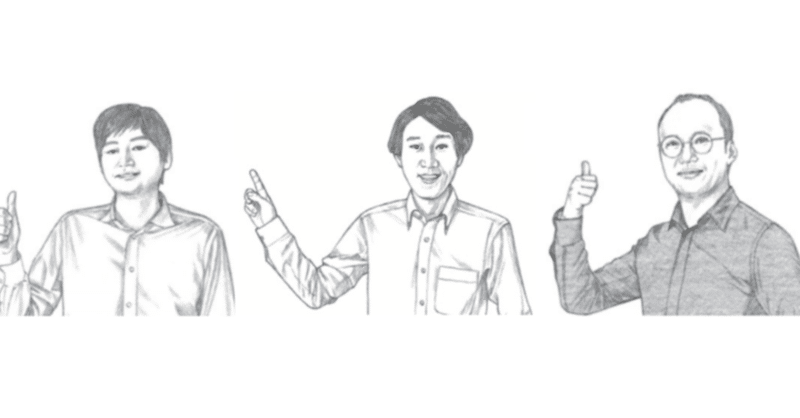
いちばんやさしいアジャイル開発の教本の現場から 第一話: 「本を書く」という体験 #アジャイルのやさしい本
はじめに
この記事はいちばんやさしいdora_e_mの Advent Calendar 2020、要するに一人アドベントカレンダーの14日目のために書いた記事だ。
今日から5日間は「いちばんやさしいアジャイル開発の教本の現場から」と題して、私が共著者の一人として名を連ねている「いちばんやさしいアジャイル開発の教本」にまつわる話をしていく。第一話では「本を書く」という体験が自分にとってどういうものだったのか、あらためてふりかえってみる。
自らの経験やスキルを書籍の形でまとめてみたいと考えている人、また書籍の形という限定はないが、何らかのアウトプットとして言語化したいと考えている人にとって参考になるのであれば幸いである。
「いちばんやさしいアジャイル開発の教本」とは
インプレス社が刊行する人気シリーズ、「いちばんやさしい教本」。まだアジャイル開発が届いていない現場に届ける、「いちばんやさしい」本だ。
5/1の発刊以降、多くの方に手に取っていただき、大変感謝している。
経験が浅いからこそ、初学者目線で書ける

2019年の夏、市谷さんから「アジャイルがまだ届いていない現場に届けたい。そのための本を一緒に書かないか」という旨のお誘いをいただいた。
書籍を執筆したことなどないし、アジャイル開発の知見にしたって市谷さんやもう一人の共著者である新井さんと比べると全然足りない。それでも、「自分だからこそ書けることがあるし、書くべきだ」という自信というか使命感のようなものがあった。
「どうチームに働きかけたらよいか悩んでるんです…(エンジニア)」
「(チームでアジャイルを採用しているけど)そもそも開発のことがよくわからないんです(非エンジニア)」
「よくアジャイルって聞くけど、よくわかってないんだよね(マネージャー)」
私の周りにいた、アジャイルに向き合おうとしながらも、なかなかとっかかりがなく二の足を踏んでいる人たち。その人たちに向けて、いかに一歩を踏み出すかを書くことは自分の使命なのではないか。経験値が他の二人より浅いからこそ、初期段階でのつまづきや当時アジャイルに対して感じた疑問が鮮やかに記憶されているのだ。
こうして、私は「いちばんやさしいアジャイル開発の教本」の執筆の旅に出ることを決意した。
境目をなくす

本書で私が目指したのは、一言でいうと「境目をなくす」ことだ。
知識の境目
・ソフトウェア開発の前提知識、経験を問わない
経験の境目
・経験者の手ほどきがなくとも1人で始められる
流派の境目
・「これはスクラム」「これはXP」「これはリーンだからアジャイルじゃない」をなくす
アジャイルソフトウェア開発宣言が世に出てから20年弱、その短い歴史の中で目まぐるしく進歩してきたアジャイルは、「経験している現場」とそれ以外で境目ができている。実践しているところはどんどん先に行き、そうでない現場は「速くて安くてうまいやつだっけ?でもうちには合わないだろうね」という認識から抜けでていなかったりする。この分断を乗り越えたかった。
そのため、「アジャイルとは何なのか」「なぜアジャイルなのか」の説明をかなり丁寧に行っている。いや、それどころか「ソフトウェア開発を取り巻く環境」という、アジャイルの手前の部分での解説さえ行っている。
正直、ちょっとやりすぎたかな?という心配がないわけではなかったが、Amazonのレビューで下記のように好意的なコメントがあり、「よかった、伝わった!」と胸をなでおろしたのは記憶に新しいところ。
なぜアジャイル開発なのかを説明するのに60ページくらい使っていて、この本の大きな特徴ではないかと思います。時代の変化が激しくユーザのニーズもよく分からない状況(例えば口ではサラダマックを食べたいと言っておきながら実際にはメガマックを買うような状況)に対処していかなければならず、そのためには変化やフィードバックに対して常に素早く(Agileに)反応できるようなやり方にしないとダメだよねというようなことが説明されています。
そして、「易しい」だけではなく、アジャイルとは何ぞやをおぼろげにつかみ、一歩を踏み出した人たちが次のステップへと向かうための足掛かりを用意する、という「優しさ」も意識して執筆した。
ワンポイントに凝縮したエッセンス
・「いちばんやさしい」の次のステップになるようなものを本の中の「ワンポイント」に込めている
源流を辿る旅への誘い
・参考文献に記載したものは、ぜひ機会があれば手にとってもらいたい
初稿を書きあげるまで

市谷さん、新井さんと直接顔を突き合わせて打合せを行ったのは2-3回だったと記憶している。あとはほとんど、Facebookのメッセンジャー、そしてGoogle Drive上でやりとりを進めていた。
作業は、自宅だったりコワーキングスペースだったり。基本的には土日に少しずつ執筆を進めていた。
町田のコワーキングスペース、AGORAを初利用。これは良い。広々とした空間に様々な座席があり気分転換できながら作業できる。 pic.twitter.com/YJre74scUh
— ikuodanaka/ いちやさアジャイル (@dora_e_m) November 3, 2019
11月中に初稿を終え、「書籍の執筆」というものを経験したことがない自分は、この時点では「いやー頑張った!出版が楽しみだなー」とのんきに構えていた。
レビュー→修正のサイクル、始まる

こちらは、初稿を書きあげてから脱稿するまでのおおまかな推敲サイクルを表した図だ。そう、初稿を書いてからが本番だったのだ!
自信満々で書いた内容のファクトが示せていなかったり、想定読者とギャップのある内容になっていたり…
また、執筆陣で話し合い、小田中の担当をCh1-3からCh1-3 + 5に変更したのも大きかった。「自分は、世の中に出版される本を執筆しているんだ」という高揚感に包まれていたため、「うっひょー自分のパート増えるなんてラッキー!」などとのんきに構えていたのだが、執筆だけではなくレビューされる分量も増える、ということが頭から抜けていた。
推敲を通して学びを深める

執筆し、レビューを受け、推敲し…というサイクルを回すのはかなり大変な作業だった。自分としてはベストを尽くしたはずの文章や構成に綻びが見つかるというのは、自分の文章や判断力への自信を失うには十分な出来事だ。
しかし、だからこそレビューをやる意義がある。私が一人で書いているのでは気づけなかったことに気づき、そこを磨き込む機会となるのだ。私一人では到達できないクオリティにまで押し上げることができるのだ。
そして、このレビューと推敲の工程を繰り返すことで、執筆対象(今回の場合、アジャイル開発)に対する自分自身の理解が深まっていくのを感じた。
いや、他者からのレビューを待たずとも、自分自身で見直したときでさえ、それは起こるのだ。
その理解が深まっていくプロセスを下図にまとめた。

今回でいえば、「なぜアジャイル開発なのか」という部分の説得力を補強するために、過去のアジャイル開発関連の書籍のみならず政府の白書をあたったり、海外の調査結果を調査したりといった作業を行った。また、界隈で「通説」になっていることに対してもその根拠を示す文章というものを改めて探し求めた。この過程は、間違いなく私自身がアジャイルへの理解を深めることの一助となった。
そしてこの執筆経験を通して、通説とされていることであってもエビデンスを明確にしよう、一次情報にあたろう、ということへの意識が高まった。この習慣は、執筆以外の場面でも有効なものだ。
まとめ:本を書くという体験
「アジャイルが届いていない現場へ届ける」というビジョンへの共感、そこに対して自分が参加する必然性を感じられたことから、この執筆の旅は始めった。
界隈では「当たり前」になっている前提から丁寧に解説する易しい本を、また一歩踏み出したあとにも読者によりそう優しい本を目指して執筆した。
レビューと推敲を繰り返していく中で、自分自身が執筆対象であるアジャイルへの理解を深めていった。
そして出来上がった本だが、自分自身、頻繁に参照するようなものになっている。手間暇をかけ推敲し、ノウハウを結晶化しただけあって、レファレンスとして実に有用なのだ。執筆した本が自分の役に立つということは、まったく想像していなかった。(だって、自分にとっては知っていることのはずだから、わざわざ読むことはないだろうとおもっていたのだ)
執筆、いやアウトプットという行為はそのものがインプットとなりうる。アウトプット対象に対する自身の理解を数段引き上げてくれるのだ。そして、そのアウトプットは、自分自身にとってのレファレンスとなる。何か執筆してみたい、アウトプットしてみたい。うっすらとでも考えている人は、ぜひトライしてみてほしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
