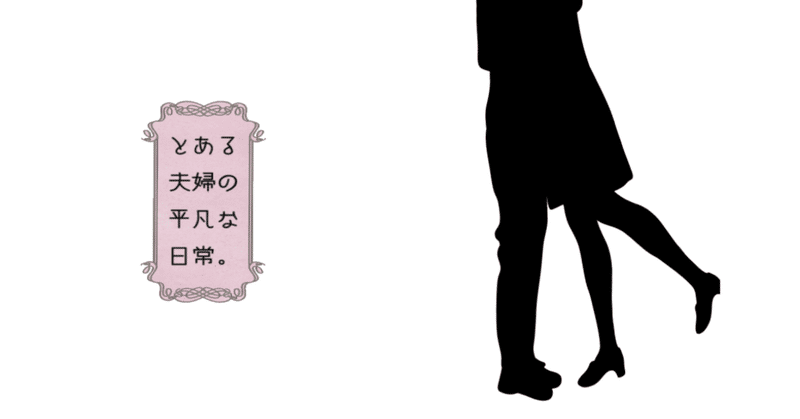
【連作短編】Shepherd that doesn’t bark:四月 後編【小説】
昨日の夜のことだった。
晩御飯を食べ終わり、さて洗い物でもなんて台所に向かったときに着信音が響く。
テーブルに置きっぱなしにしていたスマートフォンを夫に見てもらう。
「お母さんからだ」
「スピーカーモードにして、出て」
珍しい。
特筆して仲が良くも悪くもないけれど、こうして急に掛かってくるのは何かあったのだろう。
洗い物の手を休めることなく、電話に出る。
「もしもし」
「もしも……げほっごほっごほ……」
「ちょっと、お母さん、大丈夫?」
出るや否や咳き込む母にどうしたのかと驚いた。
「ええ、ちょっと風邪引いちゃって」
「珍しいね」
「そうなのよ。こんなに動けないなんて……あなたが生まれる前にもあったかしらってくらい」
自嘲気味に笑い声をあげる母に、少し安堵する。
母だってずいぶんな歳だ。体力の衰えだってあるだろう。
それにしたって、動けない、なんて言うのは初めて聞いた。
そんなことを考えていると、夫が横から割って入る。こういう時、この人はでしゃばりなのだ。
「お義母さん、ご無沙汰してます」
「あら! 元気にしてる?」
「僕たちは元気そのものですよ。すいません、二人揃って出不精でそちらにも伺わず……」
「いいの、いいの。そういうのは気が向いたときに顔を出してくれれば。元気にしているのがいちば……ごほっ」
言いながら咳き込んでしまう母に、夫が慌てて声をかける。
話を促すと、病院にはきちんと行ったらしい。
これだけ体調を壊すことが稀な母は、ついでにしっかりと色々な検査もしてもらい、結果、肉体そのものは年齢以上に健康そうだが季節の変わり目で風邪を引いたのだろう、ということで落ち着いた。
医者が言うには、年齢もあるのだから少しゆっくりしてちゃんと治さないと、とのことだった。
ところがどっこい、休んでられないのが主婦である。
炊事洗濯掃除。ただでさえ日常的にやることは多いのに、この季節ともなれば衣替えやらなんやら。
この時期を逃すとどうにも模様替えだってできない。
家の安寧を守るため、やることは山のようにあるのだ。
そんなこんなで休み初めて早三日。
問題なのは定年退職した父親だった。
昔がたきの亭主関白な家庭につきもののどっしり構えて家では何もしない父親。
溜まりに溜まった洗濯物。食材の乏しくなってきた冷蔵庫。
なんとか洗い物はしているようだし、自分で食べるものくらいは各自でどうにかしているが、減っていくカップ麺を見るたび、母は父が心配でちっとも休まらない。
こうして話を聞いている間にも、母は父の心配ばかりしている。
そんな場合じゃないだろうに。
そこでとうとうわたしに連絡が来たわけだ。
「ごめんなさいね……どうにも体が言う事を聞かなくて」
「お大事になさってください」
「もっと早く連絡くれていいのに」
「だって、ねえ……?」
なにが、ねえ、なんだかわからない!
そう言いたくなるのを我慢しながら、朝一番でそっちに向かうことを伝えると電話を切った。
「ほんと、お父さん何もしないんだから! お母さんもお母さんよ!」
「まあまあ」
ぷりぷりと怒る私を宥めながら、夫は会社に連絡を入れていた。
夫は夫で思うところがあるらしく、明日はさすがに休めないけど、というものの、それ以降は休みを取ろうとしてくれていた。
なにもそこまでと思うけれど。
にしても、急に決まった帰省。
新幹線で一時間。
母のピンチに駆けつけることができるのは娘冥利に尽きるけれど、あの父に会うと思うと少し気が重い。
そんな気持ちを振り切るかのように、この日は早めに寝ることにした。
そんなこんながあって、今である。
案の定、父はまったく動かない。
待てをされた犬だってもっと動く。
なんだ、この生き物は?
ハシビロコウの方が動くんじゃないのか?
ああもう、イライラする。
洗濯物を干し終わり、居間に掃除機をかけることにする。
一応ゴミ自体は分別されてまとめてあるし、ゴミ出しくらいはしていたようだ。
それにしてもたった三日とはいえ埃が目立つ。
旧式の掃除機はわたしが子供のころに新調して以来そのままで、ところどころ経年劣化で割れたところをガムテープや接着剤で補修している。
別に経済的に苦しいことはなかったはず、というか、裕福な方だと思っているのだけれど、母の良いところなのか悪いところなのか、こうして使えるものはなんでも使う人だったのを思い出す。
今時の掃除機とは違って、ごうごうと音を立てて、とんでもない吸引力で埃を吸ってくれるところが結構好きだ。
しかし、この父親。
なんということでしょう。
これだけ騒音を立てて横でいそいそと動いるのに、テレビから全く目を離さない。
いらっときてわざと足元を通るフリをすれば、子供のようにひょいと足をあげる。
昔なにかで見たような、お父さん邪魔ですから散歩でも行ってきてください、なんてのはこういう時に吐くセリフなのだな、と一人納得してしまう。
我が父といえど、よくもまあこれまでこんな態度をしてきたものだ。
そりゃあ子供のころはわたしだって率先して家事を手伝うことは少なかったけど、それでも人並みにはやっていたし、一人暮らしをして困らない程度には手伝いから学んでいた。
母は一体この父のどこが良かったのだろう。
全国の主婦、または主夫のみなさんの意見を聞いてみたい。
掃除機をかけ終わって、ふう、と一息ついた。
これみよがしに大きく息を吐くもんだから、わたしも性格が悪い。
休憩がてら、お茶でも飲もう。
「お父さん、お茶淹れるけど飲む?」
「ああ」
まだ薬が効いて寝ているだろう母と自分の分だけ淹れるのもなんだから声をかけるとこれである。
我ながら渋い顔をしながら台所へ向かった。
勝手知ったるなんとやら。
戸棚を開けて茶葉と急須を取り出す。
すると不意に後ろから声がかかった。
「……そこにあったのか」
びっくりして振り向くと、父が台所の入り口の暖簾をかき分けて立っていた。
「俺が淹れてもいいか?」
そりゃあいいけど。
どういう風の吹き回しだろう。
というか、生まれてこの方、この人がお茶を淹れているところなんて見たことがないのだけど。
うん、と一言返すと、出しっぱなしのヤカンに水を汲み、火をつけ始めた。
「仲良くやっているのか」
急になんだ。
と、思ったが、夫婦仲のことなんだろうと予測変換。
相変わらず言葉足らずだけど、慣れたもんだ。
「仲良くやってるよ」
「家事とかは……どうしているんだ」
「そりゃああっちが仕事だし、わたしが主にやっているけど」
何が言いたいのかよくわからない。
そうか、と言ったきりなんだか煮え切らない顔をしながらコンロの火を見つめる父。
「彼は、家事ができるのか?」
「まあ、人並みに」
「そうか……」
これまた唐突に言ったかと思えば、また口を閉じる。
心なししょんぼりしているように見えるのは気のせいだろうか。
そんな姿が夫と重なって、少し面白い。
夫はまだ仕事中だろうか。
あの人のことだから、お昼もちゃんと作って食べるだろう。
たまの一人だから、簡単に済ませたり、それとも妙に凝ったものを食べたりするのだろうか。
あとで聞いてみよう。
そんな風に愛しい夫に想いを馳せていると、また父の口が開いた。
「迷惑かけて、すまん」
「ええっ」
驚きも束の間、父は続けて話しだす。
母と出会う前、一人暮らしのころはきちんと一人でできていた。
そりゃあそうだ。父だって、なにも坊ちゃん育ちでもなければ一流の上場企業にいたわけでもない。
どちらかというと母の方がお嬢様育ちで、蝶よ花よと育てられてきたという。
事務員だった母と、一般的な社員だった父。
なんの変哲もない出会いとお付き合いを経て結婚生活が始まる。
意外だったのは、同棲初期は父が母に家事を教えていたこと。
花嫁修行と称して料理教室なんかに通いたがる母を諌めて、料理番組を撮り溜めしたり、雑誌を買ってきてみたり、父はあの手この手で教えてみたらしい。
母方の実家の反対を押し切っての結婚だったし、父方の祖父母はその頃には亡くなっていた。
父だってそんなに収入があるわけでもなかったため、将来を見越した節約だったらしい。
こうがそうして、父と母はその二人の時間を楽しんだ。
そして、わたしが母に宿る。
その頃には一通りができるようになっていた母を、さすがに孫が出来たとなると協力的になった母の実家に手伝って貰い、父は仕事に明け暮れることにした。
家も建てて、わたしが将来困らないように、二人目三人目ができてもいいようにと、しゃかりきになって働いた。
わたしが幼稚園を卒園するくらいになると、父も母も次の子は諦めて、今度は自分達が歳を取ったときの老人ホーム代やわたしの学費のためにと考えた。
それでも、休みは家族のために時間を作ろうとは思っていたけど、頑張りすぎるうちに立場が上がってしまい、そうも行かない。
いつの間にか家のことは母任せになっていて、あっという間にわたしは大きくなり、知らないうちに何を話したらいいかわからなくなって、そのうちに家を出たわたしは、わたしの幸せを得ることができた。
「仕事を辞めてみれば、時代は変わったもんだ。家の機械の使い方がまるでわからん」
そう言って、父はバツが悪そうに笑った。
「説明書を読もうにも、それもどこにあるかわからないし、母さんに聞こうとしても気恥ずかしくて。
そうこうしているうちに体調を崩させてしまった。あの状態で心配もかけられんと思っていたら、このざまだよ」
しゅん、と肩を落とす父は、子どもの頃に思った父の姿ではなかった。
背広を来て、わたしが起きる頃には、行ってきます、とわたしを撫でて出る父。
それを寝ぼけ眼で見送るわたし。
いってらっしゃい、と笑顔で見送る母。
ただいま、と帰ってきてわたしを撫でる。
まるで散歩にでも行ってきたかのように、当たり前のような仏頂面で帰ってくる。
わたしが寝るまで、寝ていなかった。
きっと、そうして忙しい時間の合間を縫って、わたしを見ていた。
母とのコミュニケーションを取っていた。
わたしは、それに気付かなかった。
ひどい娘だ。
そんなこと、考えもせずに邪険に思っていたのだから。
「お父さん、わたし、気付かなくて……」
「ああ、いいんだよ。今はこんなだけど、格好つけたかったんだ。父親として」
いつの間にか音を立てて鳴るヤカンを少し落ち着かせ、お茶を淹れながら笑う父。
「ほら、飲みなさい」
ことり、と置かれた湯呑み。
それにそっと手をやり、冷ましてから口にする。
ほんのりと甘く、香ばしい苦味。
「おいしい」
「なかなかだろ?」
本当に美味しい。
淹れ方が上手なんだ。
得意げになる父の笑顔に、安堵する。
すると、廊下から足音が聞こえてきた。
「あら、二人ともここにいたの」
「お母さん、起きて大丈夫?」
よく寝たわあ、と伸びをして入ってくる母は顔色もずいぶん良くなって、咳も少なくなっていた。
「母さん、お茶飲むか?」
「珍しい! お父さんのお茶美味しいのよねえ」
ふふふ、と微笑みながら椅子に座る母に、父がお茶をいれて渡す。
「ああ、ほんとに美味しい。これだけはお父さんに叶わないわねえ」
ほうと息を吐く母の目は、どこか遠い思い出に想いを馳せているようだった。
わたしは、そうだ、と思いつく。
予定変更。
洗濯物はまだ残っているし、掃除だってまだするところはある。
頭の中でかしゃかしゃと計算して予定を組み直す。
夫にノートパソコンとラベル作る機械を持ってきてもらうようにしないと。
「お父さん」
「ん?」
「教えたら覚える気ある?」
「そりゃあ、あるさ」
なんの話、と母が首を傾げる。
「今時の機械はすごいんだから。説明書なんていらないよ」
「そうなのか?」
私も混ぜなさい、と母が口を尖らすので、家事を教えるの、と言うと母は他人事のように、助かるわ〜と笑った。
「よし、新入社員の気持ちで頑張るか」
「お父さん譲りで、仕事は出来る女だったので先輩に任せてください!」
茶化してそういうと、父は、よろしく先輩、と言って笑った。
「お父さんの料理、楽しみだわ〜」
まだ少し熱があるのだろう。
ぽわぽわと喋る母は、なんだか普通の女性のようだ。
きっと、父と出会ったころはこんな感じだったのだろう。
だって、父もにこにこと笑っているのだから。
そうと決まれば、と相談会が始まる。
時折、そういえば、と思い出話に花を咲かせる。
大人になっても、実家は実家なのだな、と嬉しくなる。
わたしが生まれて、育った家。
子どものころとはやっぱり少し関係は変わるけれど、これはこれで良いものだ。
わたしと夫も、きっとこういう夫婦になるのだろう。
形はちょっと違うかもしれないけれど、いろんなことを乗り越えながら、一緒に生きていく。
そう思うと、胸が高鳴って、早く夫に会いたくなった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
