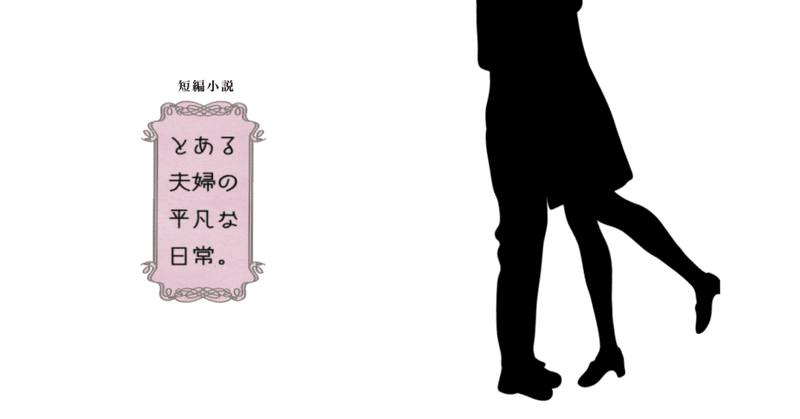
【短編】migratory birds in books:三月 後編【小説】
彼は、まず本屋に行った。
適当に見るだけのつもりだったけど、なんとなく気になって一冊、手に取る。
ぱらぱらと捲ってそれが自分の好きな文章だったからレジに向かった。
そして喫茶店に向かう。
喫茶店は混んでいた。
運良く空いた席があって案内されて、コーヒーを頼む。
購入した本をまた、ゆっくりと捲る。
読み始めると夢中になってしまって、このままでは連絡が来ても気付かない、と思った彼は、スマートフォンを机に。
そこで一人の男性が目に入る。
どうやら席が空いてないから相席の確認待ちをしているらしい。
彼は、コーヒーのおかわりを頼むついでに、その男性をこちらに案内するように言った。
男性は、ぎろぎろと猛禽類のような目をしていて、そのへの字に曲がった口は厳格そうな性格を表しているようだったという。
男性は言った。
「ここで会ったのも何かの縁と思って、相談に乗ってくれ」
……なんて、すぐに影響されてだめね。
モノローグが推理小説の一部みたいになる。
「その人が梟?」
紅茶に口をつける。
美味しくて淹れられてる。よかった。
「そうそう」
と、言いながら、夫はまだ必死に冷ましている最中だ。
「それで、相談ってなんだったの?」
問いかけると旦那は腕を組みながら、うーん、と首を傾げてしまった。
「最近の本の流行について聞かれたんだけど……」
「どんな本を買うか悩んでいたってこと?」
「と、いうよりは、最近の流行についていけないというか。最近の本の表紙を見て気後れするって言ってたよ」
「ああ、なるほど」
それなら、なんとなくわかる。
本だけではなくて、ファッションや音楽でもそうだ。
どんどん新しい文化が生まれては消えていく。
そんな資本主義の淘汰の中で忙しなく生きていると、ふと立ち止まったとき、あれ、わたしどこにいるの、なんて、思うことがあった。
特に私はロングスリーパーなこともあって、一日の半分近くは寝ている。
それを意識すると、寝ている間になにか置いていかれたような焦りを感じるのだ。
「きっと、あの人は不安だったんだな。
俺も歳を感じるようになってわかったことがある」
どことなく寂しい目で彼は言った。
そうだ。彼は私より十年以上、歳を取っている。私とは違う感覚があるのだろう。
「老いを感じるんだ。
地続きの毎日の中ではわからないのに、ふと立ち止まって周りを見渡したときに。
歳を取った、ではなくて、老いたな、って」
悲しそうな顔で、遠くを見つめる彼。
「がむしゃらに、ひとつひとつ拾い集めるように丁寧に生きてきたつもりなのに、どこかに何かを忘れてきたんじゃないか。何か間違えていて、それに気付いていないんじゃないかって、自分の歩んできた道が不安になる」
ああ、今なんだな、と思った。
彼は、今まさに老いを感じている。
そして彼はその男性にもきっと私みたいにそう思ったに違いない。
きっと、彼は自信がなくなっているのだ。
足元を確認してみたら、いつも通り踏み締め固められているはずなのになんとなく疑ってしまう。
まるでそれは漢字のゲシュタルト崩壊のように。
これであっているのか、これでいいのか。
そんな自問自答を繰り返すときが人にはある。
だから……
「あなたは立派にやっているわ。
できることをして、やれることをして、やりたいことをして、そうやって生きてきたのを私は知っている」
「そう、かな」
わたしは立ち上がって彼の後ろに回る。
そしてその頭を抱きしめた。
頬につんつんした髪の毛があたって、ちょっくすぐったい。
「だから、私がここにいる。
あなたから見た私は幸せそうじゃないかしら?」
「君はいつもにこにこと笑顔で、こっちまで嬉しくなってくるよ」
「それをくれているのは誰でもないあなたなのよ?」
そっか、と彼は呟いた。
きっと、弱気になっているだけなのだ。
面倒臭い生き物なんだ。男の子って。
「女一人幸せにしてんだから、うだうだ言ってんじゃないの! 誇りに思いなさい!」
抱き締めるのをやめて、ばしんと背中を叩く。
こういうときはこれでいい、はず。
「いっ!?」
驚いて振り向く彼の瞳には光が戻っていて、わたしは自分の行動が間違っていないことに安堵する。
「それで? 梟の人にはどう言ったの?」
「ああ……その人を見てたら、父さんを思い出して。なんだか素直に話せたんだ」
「なるほど」
そう言うと彼は怪訝な顔をする。
だから、わたしは続けた。
「その人に、あなたが歩んできた人生は間違ってないよって言ったんじゃないの?
きっと意味があるよって」
「……なんでわかるの?」
だって、そうじゃないか。
彼は、自分の両親を敬遠する。
それは幼少期のころの出来事だったり、親に対する反抗心の残りだったり、負い目だったり、色々だ。
だけど、彼の話す両親の話は決して嫌っているように聞こえたことはなかった。
ないがしろにされて、辛いことが多かったろう彼は、一人の人間として親を見ることでその束縛から解消された。
そして、同じく一人の人間として親の弱さを知った。
だからこそ、そのコントラストは際立つのだ。
彼らの好きなところ。嫌いなところ。
家族という足枷が、それを素直に発芽させることを拒む。
それでも長い時間一緒にいたという事実は変わらなくて、人として付き合える距離が今の状態なのだろう。
そんな彼が父親について語るのは、決まって三つ。
厳格だった性格。
物怖じしない行動力。
そして、芸術。
何度となく聞いた、父親の絵の話。
彼は、父親のそういうところを尊敬しているのだ。
だから、あなたがどうするかなんて、わかる。
それはわたしにもしてくれていたことなのだから。
わたしが落ち込んだとき、つらいとき、慰めてくれる。
君は間違ってないよ、君のおかげで幸せだよ、と。
君がやっていることには意味があるんだよ、と。
でなければ、わたしはこんなに笑顔で幸せな人生を歩んでいない。
「わかるわよ」
でなければ、わたしは耐えることができない。
「だって、大好きなあなたのことだもの」
だって、あなたはきっとわたしより先に死んでしまうのだから。
歳の差は、それくらいは考えるほどにある。
それでも、あなたと生きていたいと思えたから。
きっとあなたは、残されたわたしが笑顔で生きられるように言葉を残してくれるから。
これは、そうして残る予定のほんの一部なのだ。
「かなわないなあ」
大きくため息を吐く彼の顔は穏やかな笑顔だった。
「奥さんなので」
得意気に言うと、笑ってくれた。
「ありがとう」
「どういたしまして。それで、その人、なんて言ってたの?」
紅茶を飲み干して、続きを促す。
何を隠そう、わたしはこういうエピソードも大好きなのだ!
だって物語みたいじゃない!
「やけに納得して、これを渡された」
そう言って立ち上がった彼は、かけてあるコートの中から一枚のメモを持ってきた。
「……連絡先?」
「なんか、世話になったからなんでも相談してくれって」
ところがだ、このメモ、不自然なところがひとつあった。
「名前、聞いたの?」
「いや、それがすぐにその人の奥さんが来ててんやわんやで行っちゃって、その後すぐ俺も君のところに向かったから」
「あら…」
「連絡をくれと言われても……なあ?」
「そうねえ……」
まあ、おいおい連絡したくなることもあるだろう、と夫はそのメモを財布にしまい込む。
そして、そういえば、と続けた。
「奥さんが来てから、すごかったんだ。結構な大声で言い合いをして、かと思ったら、外に出たら腕を組んで歩いていったし」
それは……
「それは、きっと二人ともあなたの前で格好つけたかったのよ」
「えっ」
「だって、聞いてればあなたのご両親くらいの歳なんでしょ?」
ああ、と納得する彼。
「なるほど。なんだか今日はすごいね。まるで探偵みたいだ」
「だって、今わたしは推理小説の世界に羽ばたいてますから!」
あはは、と声を出して笑う彼の顔は穏やかで、もう何も不安はないみたい。
やれやれ、しょうがない人。
なんて、思ったけどわたしだってじゅうぶんにしょうがない人なのだ。
だって、安堵したら、本が気になって仕方ない。
「ああ、読んでおいで。ありがとう」
そう言って、手渡される本。
やった!
おかえり、わたしの本!
「今日は一日、ゆっくり読みなよ」
「いいの!?」
子どもみたいだ、と言われながら、本を抱いてくるくる回る。
そしてソファにごろんと寝転ぶと、早速開いてページを捲る。
「洗濯や晩御飯は任せていいから。
あ、俺が読み終わるまでネタバレするなよ?」
はーい、と間延びした返事をして、文字に目をやる。
本が好き。
子どもの頃から、ずっと。
彼のとなりで寝る前に読む物語。
途中で寝ちゃって、最後までは読めないけれど
彼が作業しているのを横目に眺める雑誌
読むっていうより、見るだけだし、何より彼に見入ってしまうけど。
彼が気まぐれでで買った名作。
同じ物語を読むのは、経験を共有しているみたいで嬉しくて、ちょっとくすぐったい。
彼の書斎の小説たち。
あなたのことを知っていく勉強のような気がして、なんだかとても嬉しい。
今日あったことを話してくれる彼の話。
まるで一緒にそこにいたかの様な気持ちになれる。
本が好き。
好きなのだ。
どうしようもなく。
とんでもなく。
そして、それ以上に彼が好き。
足の先から頭のてっぺんまで。
彼の物語が好き。
彼の話が好き。
だからこれはしょうがない。性分だから。
幸せになってしまって、しょうがない。
わたしはそう思いながら、本の世界へ渡っていく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
