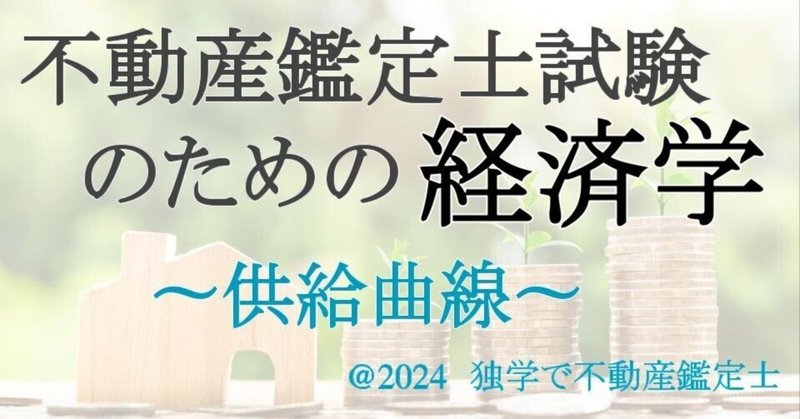
【ミクロ-03:不動産鑑定士試験のための経済学】 供給曲線 をわかりやすく(企業の行動)
1. 固定費を考慮しない場合の供給曲線
供給曲線は、商品の価格とその供給量の関係をグラフで示すものです。企業は価格が変わることによって、どれだけの量を市場に供給するかを決定します。固定費を考慮しない場合の供給曲線は、生産に関連する変動費だけを基にした供給の意向を示します。
この時の供給曲線は、価格と供給量が比例的に増加する傾向にあります。言い換えれば、価格が上昇すれば供給量も増え、価格が下降すれば供給量も減少するという関係性が成り立ちます。これは、価格が上昇すると企業の収益も増加するため、より多くの生産が行われるという経済的判断に基づくものです。
1.1. 生産停止点
固定費を考慮しない場合の生産停止点は企業は変動費=価格(平均費用・限界費用)となる点です。商品の価格がどれだけ低くても生産を続けることができる最低限の価格の点を指します。この点では、変動費と商品の価格が等しい状態となり、生産停止することと生産することは同じ(無差別である)と言えます。この点では、企業は生産を継続するものとします。
例えば、ある商品の生産に関する変動費が1個あたり100円であるとすると、その商品の価格が100円を下回ると、企業は1個あたりの生産に関して損失を出すことになります。その結果、企業は生産を続けるメリットを感じず、生産を停止する可能性が高くなります。
1.2. 生産停止価格
生産停止価格は、生産停止点での商品の価格を指します。この価格が市場価格となった場合、企業は生産を停止し、新たな生産活動を行わない選択をするでしょう。
価格が生産停止価格よりも高ければ、企業は利益を上げることが期待できるため、生産活動を継続する可能性が高くなります。逆に、価格が生産停止価格を下回ると、企業は生産の損失を避けるために生産を止めることを検討するでしょう。
2. 固定費を考慮した場合の供給曲線
固定費とは、生産量に関係なく発生するコストのことを指します。例えば、工場の賃料や機械の減価償却費などが該当します。固定費を考慮すると、供給曲線の形状と意味が変わってきます。この場合、生産を続けるための最低価格は変動費と固定費の合計となります。この価格を「閾値」と言います。閾値は企業が市場から撤退を考えるか、または生産量を縮小するかを判断する重要な価格ポイントとなります。
固定費を考慮した供給曲線は、変動費だけでなく固定費も加味して、企業が市場にどれだけの商品を供給するかを示します。この時、生産を続けるための「閾値」は非常に重要となり、これを下回る価格では企業の経済活動が非効率的となる可能性が高まります。
2.1. 生産停止点
固定費を考慮した場合の生産停止点は、変動費と固定費=価格(平均費用・限界費用)となる点となります。この点よりも低い価格では、企業は生産コストを回収することができず、経済的に不利な状況となります。生産停止することと生産することは同じ(無差別である)と言えます。この点では、企業は生産を継続するものとします。
長期的な戦略や市場の期待、その他の要因により、生産を一時的に継続することが考えられます。価格がこの点を持続的に下回ると、企業は長期的には生産を継続することが難しくなるでしょう。
2.2. 損益分岐点
損益分岐点は、固定費を含めた全てのコストと総収益が等しくなる価格の点を指します。この価格で商品を生産・販売すると、企業は利益も損失も発生しない状態となります。ここで重要なのは、損益分岐点では企業は固定費を回収するために生産を続けるということです。この点を理解することは、企業が市場での競争を継続するための戦略を考える際の重要な指標となります。
2.3. 生産停止価格
固定費を考慮した場合の生産停止価格は、生産を継続するための最低限の価格となります。この価格を下回ると、企業は変動費と固定費の合計を回収することができず、経済的損失を受けることとなります。この生産停止価格を知ることは、企業が市場での競争を継続する上での戦略を立てる際の重要な指標となります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
