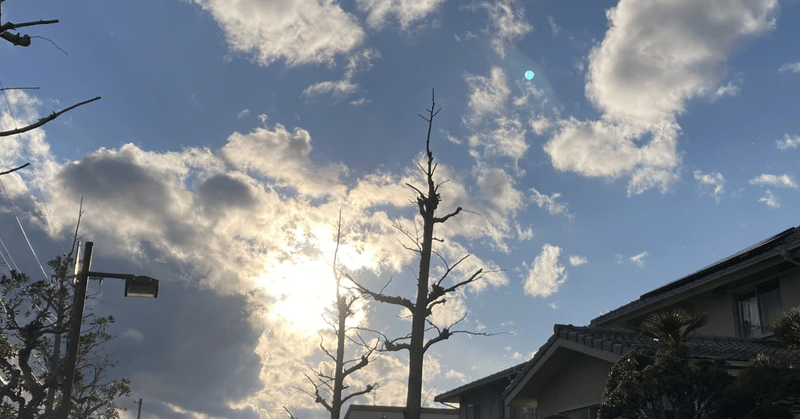
風にさらわれた恋(2)
―今から40数年前の、まだ携帯もSNSもない頃のオールド・ファッションなラヴ・ストーリー
ロング・ディスタンス・ラブ(18)
すぐに会えると思っていた。が、そうではなかった。二人とも雑事に追われていたのだ。
帰京した翌週、指導教授の研究室を訪ねた。こういう呼び出しは珍しいというか初めてだった。何だろう。ひょっとしてクビの宣告かも知れない。どう考えてもいい話ではなさそうだ。そう考えると足取りも重くなった。が、それは穿ち過ぎだった。扉を開けると、机の上にぶ厚い本が置いてあった。
「バンベニストって知ってる」
「はい、ミツバチ言語で有名ですよね」
「ラカンが『盗まれ手紙』で引用している。しかしラカンにも手出してるんだ」
構造分析はどうしても静態的になってしまう。動的なものを取り戻すにはどうしたら良いのだろう。その時思いついたのがラカンだった。ラカンは二重否定と強調構文の嵐だ。文脈を抑えてないとYesとNoを間違え、簡単に道に迷う。
「読み始めたばかりです」
「ラカンが読めるのにどうしてボードリヤール読めなかったんだい」
語気を強めて言った。先生が怒るのももっともだった。ボードリヤールは試験で出題された。自分向きだとは思った。が、不思議なくらい読めなかった。
「今年度の授業でバンベニストを読む。参加資格はないが、君にも出席してもらう。端的に言うと、今年度の紀要にバンベニストに関する論文を載せて欲しい。勿論査読はするけれども」
「秋までにですか」
「修論の代わりとして取り組んで欲しい」
「何故ですか」
「君の提出した、数式だらけの論文なんて、文学部じゃご法度だ。誰も分らんよ」
グレマスの語りのプログラムの書式に、「モーヌの大将」を落とし込む。数式の変化で物語の運動を証明する。その試論を修論で実践したつもりだった。
「それに、私の弟子だったら、多少は言語学知っとらんとな。記号学だけじゃだめだ。そういう事だ」
「分かりました」
帰路はもっと気分が重かった。いままでだったら喜んでこの課題に取り組んだ事だろう。が、今はフランス語を読む事が軽いトラウマになっていた。「出来るだろうか」という心配よりも、どうでもいいやという気分が勝っていた。どうしても力が湧いてこない。
その日の夕方、久々に院の仲間と飲む事になっていた。平田のアパートへ行った。
「よー、久しぶり。何か暗いぞ、まだ引きずってるのか」
確かに試験の日以来会っていなかった。千恵子にもらった焼酎を九州土産として差し出した。
「お前らしいよな。封が開いた焼酎持ってくるなんて」
「九州行ってたんだって。どうだった。飯田君はどうしてた。元気だった?」
馬場さんの声が平田の背後から、奥の部屋から響いた。
「あいつ、もうしばらくしたらフランス行くってさ」靴を脱ぎ部屋に入ると、見知らぬ女の子がいるのに気づいた。どこかにあどけなさを残した深窓の令嬢風の子だった。
「ゴミために鶴か」聞こえないように小声で言ったつもりだった。
「ゴミためで悪かったな」平田が突っかかってきた。
「お前の彼女?」聞いた。
「違うよ。安田の彼女だよ」
安田とは同期だがうまがあわない。お互いに嫌な奴と思っていた。奴はイケメンで優秀だが少し気難しいところがある。後でわかった事だが、安田とうまくいってないので、平田が相談に乗っていたのだそうだ。その時に、ちょっとした集まりがあるので、気晴らしに来ないかとこの飲み会に誘われたそうだ。これも後で分かった事だが、彼女は社長令嬢だった。
「こいつが今噂していた松本さん」
ちなみに「さん」は私達の間では蔑称だ。どうせろくな噂はしていなかったに違いない。
「こいつ等のせいで、私、男ってものに全く幻想抱けなくなった。去年の秋だっけ、松本さんがバイト先の女の子からもらったラブレターを飯田君も入れて三人で読んで、あーだこーだ言い合ってた。書いた娘の身になって考えてみなよ。酷いよ。腹立った。あの時は男の醜い本性を見たような気がした」馬場さんはその時の怒りを一瞬思い出したようだった。彼女はフェミニズムのエキスパートだ。あの時は彼女の尻尾を踏んでしまったのだった。
「その後、あの子とはどうなったんだよ」平田が言った。
「逃げた」
「どっちが」
「俺が」
「あんた達最低」馬場さんが怒った。
深窓の令嬢は少し困ったような顔をしていた。こんなかわいい子の前でする話ではない。
「松本です。よろしく」明るく言った。
「上野とも子です。よろしく」
「まったくなあ。これだよ。さっきまであんな暗い顔していたのに。かわいい子見ると急に態度変えるんだから」と平田は言った。
「そうだよ。私と話すときはいつも仏頂面で、優しさの欠片もないんだから」と馬場さんも口撃した。
「うるさいな。お前ら、黙れ」
このじゃれ合いを見て、始めは困惑していたとも子さんもだんだん笑顔になっていった。
「ところで、今日お前呼び出されたんだって。クビの宣告?」
「そう思ってたら、論文書き直せってさ。バンベニストについて何か書けって。頭痛いよ。半年で500ページ強読むのか」
「よかったじゃない。ところで、バンベニストって誰」馬場さんが言った。
「言語学者。ディスクールの言語学の創始者。バンベニストがいたから言語学の他分野への応用もより容易になったんだ。まあ首の皮一枚つながったってところかな。でも駄目なんだ。今はそれどころじゃない」
「何がダメなんだよ。さっきから気づいてたけど、お前ちょっと様子変だぞ。挙動不審っていうか。心ここにあらずって言うか。九州で何かあったのか」
「ちょっとした事があってね。今はもう学校どころじゃないんだ」
「財布拾ったとか、何かあったの」馬場さんが冗談半分に聞いてきた。
しばしの沈黙の後、意を決して言った。
「財布でなくて、恋を拾った」
平田、馬場さんは口に含んでいた焼酎を派手にふきだした。
「お前ら、汚いな。お嬢さんに失礼だろう。上野さん、大丈夫だった」
「ええ。それと私の事、ともちゃんと呼んでください。みんなそう呼んでいるから」
「お前、女の子に取り入るの上手くなったな」平田は言った。馬場さんはテーブルの下で、私の足を思いっきり踏んだ。
「痛いな。何すんだよ」
「お前の事だから、どうせ片思いなんだろう」という平田の言葉に馬場さんは大きくうなずいた。
「ところがそうでもないんだ。『カレン』の主人公から『Fun ×4』の主人公になりつつあるんだ」
「えっ、散歩に誘われたの。お前を誘うような奇特な女の子なんて絶対いない。妄想だろ」
「違うよ。鹿児島で私と一緒に旅行行かないって誘われたんだ」
「メンタルに問題ある子じゃないの」
平田はメンタルが少しおかしくなった娘と付き合った事があった。ぽっかり空いた心の空洞を酒と男で絶えず満たそうとするやばい娘だった。その後その子を熱烈に愛する男が現れ、結婚した。今はかつての姿が考えられないくらい良い奥さんになっていると風の噂に聞いた。
「違うよ。千恵子は普通の子だよ。長野から傷心旅行に来ていて、同じ匂いのする俺と話しが合ったって事だよ」
「ほう、千恵子さんていうのか。何してんの。学生?」
「臨床検査技師」
「私よりきれい」馬場さんが聞いた。その根拠のない自信はどこから来るのだろう。馬場さんは化粧品屋の娘だ。彼女の部屋には化粧品が山ほどある。が化粧っ気はほとんどない。表情が豊かな子だから、化粧すればそれなりに映えるとは思うのだが。私が化粧したら、松本さんのような悪い虫が寄ってくるから、絶対にしないと変な理屈を言い張っている。
「月とすっぽんだよ」
「そうか、私が月か」馬場さんが言った。
令嬢がクスクス笑いながら、このやり取りを見ている。
「でもまだプラトニックなんだろう」平田が言った。
「だから『Fun ×4』だって言ったじゃん」
「Kiss in the Dark?(19)」
平田と馬場さんはちょっと驚いた風だった。令嬢は目を伏せていた。
「その日の夜、いろいろあって、ホテルの部屋で二人で焼酎飲んでたんだ。そしたら千恵子が急に泣き出しちゃって、慰めているうちに、気がついたら二人でベッドの中にいたんだ。この焼酎、その時のだよ」
令嬢のほほが少し赤らんだのは、焼酎のせいなのか。私の話のせいなのか。
「いやだ、会ったその日にやっちゃったの」馬場さんがあきれたという顔をして言った。
「女の子がそういう事言っちゃダメ」平田が馬場さんにきつく言った。
「その娘、遊び慣れてるんじゃないの。松本さん変に純情なところあるから遊ばれたんじゃないの」馬場さんが真顔で言った。
「違うんだ。千恵子は遊び人じゃない。会ってすぐに昔からの知り合いのように打ち解けられたんだ。お互いに全然気を遣わずに済んだんだ。二人でいると居心地がいいんだ。安心できるんだ。トキメキもするけど、落ち着きもするんだ。何か運命的なもの感じるよ」
「私そういう出会い憧れる」あまりしゃべらずにじっと三人の話を聞いていた令嬢のとも子さんが珍しく口を開いた。
「こいつマジで恋してる」平田はあきれたという感じで言った。
「よかったねー。君にもやっと春が来たんだねー」馬場さんはそう言うと、こらえきれずに爆笑した。続いて平田も大爆笑した。令嬢だけが困ったような顔をしていた。
「で、これからどうするんだよ」平田がぶっきらぼうに聞いてきた。
「千恵子が旅行から戻ったら、すぐに会いに行く」
「首の皮一枚でつながった学校はどうするの」今度は馬場さんが心配気に聞いてきた。
「千恵子とうまく行ったら長野で暮らす。学校は辞める」
「その考え方おかしいよ。どっちかという選択じゃないだろう。何で学校辞めなきゃいけないんだい。結婚して院生やってる先輩沢山いるじゃん。ちょっと頭冷やした方がいいよ。これまで積み上げてきたキャリアを棒に振るつもりかい」
冷静に考えれば確かに平田の言う通りだ。間違った二者択一にしてしまったのかもしれない。はじめは記号学という強い光源に向かって一直線に飛んでいった。そこに達したかもしれないと思った瞬間、光源を見失った。その後、ジョイ・ディビジョンの音楽のような真っ暗闇の中を漂流し途方に暮れていた。その時突如として現れた強い光源、それが千恵子だ。今はその強い光に惹きつけられている。千恵子しか見えない。
気がついた時はもうかなり遅い時間だった。とも子さんを誰かが送っていかなければ。平田は明日のバイトの関係で無理だったので、私が送っていく事になった。
「一人で大丈夫です」
「送ってきます。もうかなり遅いから、一人だと危ないよ」
「すいません」
「お前、送り狼になるなよ」平田が余計な事を言った。
「私は誰が送ってくれるの」酔っぱらって、トロンとした目をした馬場さんが言った。
「ここから10分とかからないだろ」平田が冷たく言い放った。
「じゃー、平田君泊めてくれる?」私の話は馬場さんにも刺激的だったようだ。女になっていた。
「帰れ!」平田はかなり怒っていた。
平田のアパートから、最寄りの私鉄の駅まで15分ぐらいかかった。そこから各駅停車で6駅、降りた駅から12~3分でとも子さんの住む豪邸だった。数年後、この道は目をつむっていても歩けるくらいになっていた。
「馬場さん、大丈夫かしら」
「多分、平田が送って行ったと思うよ。ところで、ちょっと驚いたでしょ。口の悪さというかののしり合いに」
「少し」
「でも、みんないい奴なんだよ」
「でも、私少し腹が立った。松本さんの真剣な恋愛を茶化すなんて、ひどい」
「ああいう風にしか祝福できない奴らなんだ」
「あれだけ言われて腹立たないんですか」
「慣れた。奴らの方が正しい時もあるし」
大きなお屋敷の門の前に着いた。犬が吠えていた。突然、サーチ・ライトが点灯し、門の奥の玄関を照らした。門から玄関までかなりあった。想像以上に大豪邸だ。
「ここで結構です。じゃー、お休みなさい。今日はどうもありがとうございました。楽しかったです。気をつけて。それと、うまく行くといいですね。私応援しています」
可愛い娘だと思った。抱きしめたら折れてしまうかもしれないくらいに華奢な娘だった。一瞬、安田が羨ましく思えた。
「良かったら、みんなでまた会わない。連絡するよ。じゃー、お休みなさい」
後5分という所で終電に間に合った。自宅に戻ったのは、1時近くになっていた。気分は、「酔い」と「とも子さん」のおかげで、少し軽くなっていた。長い一日だった。
数日後、私は「コミュニケーション・ブレークダウン(20)」に陥ってひどく混乱していた。何度電話してもつながらない。落ち着け。自分に言い聞かせた。階下の台所に行き水をゆっくり飲んだ。うまく行かない時は深追いしてもだめだ。「止めなさい」というサインなのだ。何か切迫した他の用件に追われると、一時的にその事を忘れてしまう事がある。他の用事を作るんだ。ピース・オブ・マインド、それが一番重要なんだと、何とか自分を捻じ伏せた。
今切迫した用件はバンベニストだ。まだバンベニストには全く手をつけてなかった。というかここ一ヶ月フランス語は1ページも読んでなかった。遠ざけていたのだ。まだ本は読む気が全くしなかった。レコードでも聴くか。イーグルスの「テイク・イット・トウ・ザ・リミット」にしよう。ランディ―・マイズナーのハイ・トーン・ヴォイスも良いが、デイブ・メイソンのヴァージョン(21)の方がより好きだ。見事なカントリー・ソウルと化している。去年一年Over Limit Every Timeだったから、もう一度リミットを目指すのは今はつらい。明らかにバッテリー不足だし、脳神経回路もずたずただ。時間の経つのを待つしかない。次に「ピースフル・イージー・フィーリング(22)」を聞いた。イーグルスがバーズの遺伝子を受けついでいる事が明瞭に解る歌だ。作者のジャック・テンプチンは、サン・ディエゴのとあるコーヒーハウスのスタッフの女の子に失恋した直後に、帰る家もないので、そのコーヒーハウスの固い床の上でこの曲を書いたそうだ。どんな気分でこの曲書いたんだろう。そんな惨めな状況を全く感じさせない、タイトルそのままの穏やかで爽やかな歌だ。この歌を聞くと不思議と気分が軽くなる。
次の日から研究室通いを始めた。とにかく、バンベニストを読もう。今私に与えられたミッションに専念しよう。まず、一日で何ページぐらい読めるのかを知りたかった。それが分れば読破するのに必要な日数がわかる。何を主題にすべきかもその作業の中から浮かび上がってくるだろう。
久々にフランス語漬けの一日だった。精読すると一日10ページがやっとだった。頭の中のハードディスクが回転し過ぎて熱を帯びているのが分った。頭の芯がしびれるまで集中して本を読むのは本当に久しぶりだった。火照った頭に夕方の冷気が心地良かった。
駅へ向かって歩いていると、何処からか「松本さん」と呼ぶ若い女の声が聞こえた。いかん幻聴だ。千恵子の幻聴が聞こえるほど病んでしまったんだろうか。心療内科に通ったほうがいいんだろうかと真剣に考えていると、「松本さん。私、とも子です」という声がはっきりと聞こえた。嘘だろうと思って、歩を止め、振り向くと、とも子さんがこちらへ走ってくるのが見えた。
「この前はお疲れ様。元気だった」咄嗟に私は言った。そうあの集まりから二週間たっていた。
「元気です。でも、あまりに偶然なんで、ちょっとびっくりしちゃった。学校で何か用あったんですか」
「教授からの例の課題。研究室でずっと本読んでたんだ。久々だったんでちょっと疲れた。ともちゃんはどうして…」
「私はサークルの帰りです。これから飲み会だけど抜け出してきたところです」
帰りの電車は一緒だった。言うか言うまいか迷ったが、聞かれるのは惨め過ぎると思ったので、こちらから切り出した。
「千恵子と全然連絡取れないんだ。気が変になりそうだから、今は課題に没頭してできるだけ考えないようにしている」
「まだ旅行から帰ってきたばっかりで、いろいろ用があるんじゃないですか。そのうち連絡取れますよ。心配しないでも大丈夫ですよ」
社交辞令かもしれない。が、優しい子だと思った。まさか年下のこんなかわいい娘に慰められるとは。平田や馬場さんだったら「夢でも見てたんじゃないの、諦めて課題に専心したら」と嫌味たっぷりに言われた事だろう。
突然思いつめたような顔をしてともちゃんが言った。
「松本さん、少し聞いて欲しい事あるの」
「じゃ次で降りて喫茶店でも行く」
「時間大丈夫ですか」
10分後、喫茶店でなくファミレスにいた。条件反射でオムライスを注文してしまった。思わず苦笑してしまった。
「どうしたんですか」ともちゃんは聞いてきた。
「御免、何でもない。ところで話って」とごまかした。
ともちゃんの話は案の定、安田との事だった。デートで映画を見に行っても、自分の趣味の難解な映画ばかり見せられて、全然つまらない。趣味というか考え方が全く合わない。合わせようともしてくれない。人前だと必要以上にイチャイチャするくせに、二人きりになると何故か冷たくなる。何か私を連れている自分を世間に見せびらかしているみたい。初めは「私は愛されてるんだ」と思った。けれどだんだんと、この人は私を通して自分を愛しているだけなんだという事が分ってきて、一緒にいるのが苦痛になってきた。
こんなにしゃべる子なのかと思うくらい、一気にまくし立てた。
ともちゃんのいう通りだ。安田はそういう奴だ。強烈な上昇志向というか野心が彼の中に渦巻いている。それも学問的なものではなく、政治的な野心が。フローベルが敵視するような典型的な俗物だ。が、安田の専攻はフローベルだ。何たる皮肉。言ってみれば彼女は戦利品なのだ。こんなかわいい子とつき合っている自分に酔っているのだ。しかも、その子が必ずしもともちゃんである必要はない。かわいければ誰でもよいのだ。何かルサンチマンがあるのかもしれない。それにしても、「かわいい」って事も必ずしもアドヴァンテージにならないのか。とも子さんもいろいろと大変だなと思った。
「徐々にフェードアウトっていうのが一番いいと思うけど」
ともちゃんの話を一通り聞き終えて、そう言った。
「平田さんもそう言ってた」
時計を見るともう10時過ぎだった。
「送ってくよ」
「一人で帰れます」
「でも一人じゃ危ないよ」
二週間前と同じく、とも子さんの住むお屋敷まで送っていった。犬が吠えていた。大豪邸を見て、安田とうまく行かない理由を確信した。育った環境が違い過ぎるのだ。かなり難しいだろうなと思う。人の恋の行末は手に取るようにわかる。
「松本さん、ずっと研究室に詰めてるんでしょ。遊びに行っていい」
こんなかわいい娘にまた会えるのなら大歓迎だ。
「いつでもいいよ」
「じゃー、行きます。相談に乗ってくれて今日はどうもありがとう。お休みなさい」
「お休み」
気分は軽くなった。必要以上に落ち込まないで済む。さあ明日も研究室だ。
二ヶ月経った。相変わらず連絡はとれずにいた。葉書を一度出したが、なしのつぶてだった。どうしたんだろう。平田や馬場さんの言うように、単に遊ばれただけなのか。もう諦めた方が良いかもしれない。でも諦めきれない、気が狂いそうな日々が続いた。それでも、何とか読書に専心していた。それに時々ともちゃんにも会える。それが唯一の救いだった。映画を見たり、買い物に付き合ったり、食事したり、動物園に行ったりしていた。彼女の笑顔や明るい振舞いには本当に救われた。が、この時は不思議な事に恋愛感情は全くなかった。単にかわいい妹のように思っていた。この件を後に知った平田は、「あの子を好きになると大やけどするよ。止めとけ。お前惚れっぽいから忠告しとくよ」と言った。その通りだった、後年、私は大やけどを負った。
梅雨ももうそろそろ終わろうとするある日、夜半、今日読んで気になった箇所を反芻していると、突然電話が鳴った。どうせ平田か馬場さんからだろう。今度はいつ飲もうかと聞いてきたんだろう。そう思って、
「何だよ」と威嚇した。
「松本さんのお宅ですか。広太さんいらっしゃいますか」緊張気味の女性の声がした。すぐに誰だかわかった。千恵子だ。狂喜した。が、悟られぬよう抑えた声で言った。
「私です。ひょっとして千恵子さん」
「そうです」
「さっきは御免。悪友から飲みの誘いだと思ってあんな風になってしまったんだ。御免なさい」
「良かった。間違い電話したのかなと思ってしまった。君、私に間違った住所教えたでしょ。写真を送ったのに帰ってきてしまって。電話まで間違っていたら連絡つかない。どうしようかと思って一瞬焦ってしまった。でも良かった。元気だった」
声は明るかった。いきなり君呼ばわりか、千恵子らしい。全く連絡取れなかったのに元気なわけないだろう。
「一応元気。何度か連絡したんだけど、全然だめだった。もう会えないのかと思ったら悲しくなったよ」
「御免なさい。旅行から帰ってきていろいろあったんだ。今実家だけど、来週長野市内に引っ越す。電話番号も変わるから、引っ越したら電話するね。それより、ちゃんとした住所教えて。写真送るから」
葉書に書いた筈だけど変だなと思ったがここは千恵子に従おう。正しい住所を伝えた。私が指宿で教えた間違った住所には町名が抜けていた。「まったく」という千恵子の声が久々に聞けて嬉しかった。「まったく」と言った時の千恵子の表情が鮮明に浮かぶ。
実家の電話だと兄貴が聞き耳立ててるから、公衆電話から電話している事、引っ越す事情は手紙に書いたからそちらを読む事などを早口でまくし立てた。
思い切って言った。
「長野に遊びに行ってもいい。会いたいんだ」
「私も同じ気持ち。でもちょっと待ってて。後一ヶ月ぐらいしたら落ち着くと思うから」
げんきんなものだ。この電話一本で私は有頂天になってしまった。目の前の霧が見事に晴れた気がした。今夜は一人で祝杯をあげよう。寝た子が起こされてしまったのだ。ここから東京と長野の遠距離恋愛が始まった。
しばらくして千恵子から手紙が届いた。
葉書どうもありがとう。連絡遅くなってごめんなさい。ちょっと急いで片付けなければならない用事があって、そちらに追われているうちに遅くなってしまった。御免なさい。ところで、相変わらず君大変そうだね。大丈夫?
君と別れた後の九州旅行では出会いが無かった。あんな出会いがそうそうあったら大変だけどね。あの後周った中では高千穂、国東半島の五百羅漢が特に素晴らしかった。何か神々しかった。宮崎に行ったけど、ここを君と歩いていたら、また新婚さんと間違えられたかもしれないと考えると何故か可笑しくなった。
実言うと旅行に出た時は不安でしようがなかった。まだ自分に自信が全然持てなかった。自分を変えなくっちゃと思っていた。でも、あなたに出会って、ありのままの私を受け入れてくれて、このままの私でいいんだという事に気づかせてくれた。誰かがどこかで私の事を思っていてくれる。そう思うと嬉しくてしようがなかった。何か勇気のようなものが湧いてきた。その思いが元気のなかった私の背中を押してくれた。旅行から帰ってきてすぐ、偶然に友達に会った。その時「明るくなったね。九州で何かあったの」と言われてしまった。「好きな人ができたんだ」と言うと少しびっくりされた。「冗談よ」とあわてて否定したけど、怪訝な顔をされた。友達にあなたの事思わず匂わせちゃったかも。気に障ったら御免。謝ります。
それで、実家を出て、また一人暮しをしてみようという気持ちになった。でも両親や兄貴を説得するのはちょっと大変だった。時期尚早だと言って首を縦に振らない。お前は器量良しだから、そのうち良縁もくるだろうから、それまで実家にいて家業を手伝えって。だから頑張って職探しをしたんだ。幸いな事に私、国家資格持ってるから、仕事は条件さへ選ばなければある。いろいろあったけど、結局、長野市内の病院で嘱託として働く事に決めた。その近くにアパートも借りた。両親も兄貴も「仕事決まったんならしょうがない」と渋々家を出る事認めてくれた。来週引っ越すから、改めて電話するね。
P.S. 君にオムライスを食べさせてあげるという、指宿での約束もやっと実現できるね。元気出してね。
手紙には、鹿児島、長崎鼻、指宿の海岸、吹上浜の写真が同封されていた。今のところの「我が人生最良の日」の記録だった。はたして、これ以上に幸せな日々は私に訪れるのだろうか。
週末の夜、平田と馬場さんが家にやってきた。定例の飲み会だ。部屋に入るなり、躁状態の私を見て、
「お前、今日どうしたの。何か良い事でもあったのか」と平田が聞いてきた。
「千恵子とやっと連絡取れたんだ。電話もあったし、手紙も届いた。だから、俺今ちょっと舞い上がってる」
「単純な奴」平田と馬場さんは同時に、嘲るように言った。
「でも良かったじゃない」馬場さんがいつになく優しい。何が彼女に起こったんだろう。
「今日、ともちゃん、サークルあるからダメだって」酒の用意をしながら言った。
「お前、ともちゃんとこの頃頻繁に会ってるらしいじゃないか。この前、偶然安田に学校で会った。その時、奴に詰め寄られたぞ。お前とともちゃんが、大きなキリンのぬいぐるみを抱えて、楽しそうに歩いてるの見たんだって。あんな楽しそうなともちゃん、俺見た事ないって、安田ショック受けてたぞ。お前、安田に殴られるぞ」
「そんなんじゃないんだ。俺、本当あの子には救われたんだ。あの子がいなかったら、俺どうなっていたかわからない。酷いうつで人生棒に振っていたかもしれない。あの時はともちゃんの買い物に付き合っていたんだ。そしたらぬいぐるみ専門店の前で急にとまって、ショーウィンドウの中のキリンのぬいぐるみをじっと見ている。よっぽど欲しいんだなと思った。うつ病になっていたかもしれないと考えれば、治療費よりも安いものだと思って、ちょっと高かったけど、迷わず買って、その場でともちゃんにプレゼントした。そしたら予想外に喜ばれちゃって。あんなにはしゃいだともちゃん俺も初めて見たよ。そういう事だよ。他意はないよ。しかし安田がそれを見ていたなんて」
「私にも何か買って」馬場さんがトロンとした目をして言った。本領発揮だ。
「何でだよ」
「私にも救われてるんでしょ」
「良く言うよ」
「地主の馬鹿息子と社長令嬢か。案外いい組み合わせかもしれない」馬場さんは真顔で言った。
「確かに、あっているかも知れない。でも、あの子、あまり甘やかさない方が良いよ。エスカレートするとお前大変な目にあうぞ」平田が抑えた口調でアドヴァイスしてきた。その通りだった。後年私はこの子に振り回され、ひどい目にあった。
「ところで、写真あるんだろう。見せてよ」平田は直球を投げてきた。
「嫌だよ」
「私の方がきれいだから、見せたくないんでしょ」馬場さんの自信は本当にどこから来るのだろう。今度改めて尋問してみたい。
「ほら、これだよ。自分の目で確かめてみな」少し怒ってしまった私はまんまとこいつらの挑発に乗ってしまった。
「どれどれ」
平田と馬場さんは一瞬沈黙した。
「俺が思ってたより、きれいだ。こんな美人がどうして、何の取り柄のないお前なんかを選んだんだ」平田の声音には少し嫉妬と怒りがにじんでいた。珍しい事だ。
「平田君、ちょっと言い過ぎ。嫌だ。私より美人じゃない」馬場さんが目を丸くして言った。
「でも、もうかなり経ったから、彼女の熱はもう冷めているんだろ」
「そんな事はない」咄嗟に言った。
「証拠は?」
「これだよ。読んでみろ」
また、私はこいつらの挑発にまんまと乗ってしまった。手紙を差し出してしまった。
読み終えると、平田と馬場さんは顔を見合わせ、肩をすくめ沈黙した。さっきより長い沈黙だった。何とか茶化してやろうと思ったようだが、あまりにストレートな思いに、隙が見つからず、困惑しているようにも思えた。
「お前、どうやってこの子丸め込んだんだい」と嫌味をいうのが精一杯のようだった。
「いいなあ、私も恋したい」馬場さんが珍しく本音を吐いた。夢見る少女になっていた。
イーグルスの「ならず者」がかかっていた。何もかも悲しくしてしまうドン・ヘンリーのヴォーカルは最高だ。リンダ・ロンシュタットのヴァージョンも有名だが、この歌は力任せに歌いあげてはダメだ。説得力がなくなる。ラスト近くの「You better let somebody loves you, before it's too late.(23)」というフレーズが印象的だ。お前を思っている人がいるんだから、そう自暴自棄になりなさんなという歌詞だ。Somebodyは私で、Youは千恵子だ。この歌詞と違って、千恵子は私の思いを受け入れてくれている。その事が私の自信にもなっている。すぐにでも会いたかった。抱きしめたかった。
それから2~3日して千恵子から電話があった。嬉しかった。引っ越しが無事終わった事、今は段ボールの山に囲まれている事、来週から勤め始める事、そして新しい電話番号と住所を伝えてきた。いつ会えるかという話になった。千恵子は新しい環境に馴染むまでには2~3週間かかるだろうから、その後の方が良いと言った。私も7月中旬までに、教授に論文のドラフトを提出しなければならなかったので、それを終えるまでは動きたくても動けなかった。残念だけどしようがない。7月下旬に会えるまでは、頻繁に電話で連絡を取り合おうという事になった。少し悲しかった。
ロラン・バルトに出来事的エロス、姉妹的エロスという対概念がある。出来事的エロスとは単刀直入に言えば、ひとめぼれの事だ。この偶然的出会いの対概念が姉妹的エロスだ。戦国時代、許婚同士を幼い頃から同居させて、お互いを兄妹のように慣れさせるというのがそれだ。テュケー的な邂逅から、アウトマトン的な日常へと、恋愛を移行させる事ができれば、その恋愛は成就したと言える。というような事をバルトはラシーヌ論で書いている。この裏にはバルト自身の苦い失恋体験があったのかもしれない。鹿児島での出会いはテュケーだった。それをアウトマトン的なものにする事、つまり相手の日常の一部になる事が問題だ。私は長野に頻繁に通うようになった。
その年は梅雨が明けるのが遅かった。が明けると同時に猛烈な暑さと陽光が襲ってきた。
「これなら論文には及第点出せる」という教授の言葉にほっとした。でも内心では「こんなの要約というか単なる紹介じゃないか。誰にでもできる。目指すべきはプラクティスだ。単なるジャーナリズムは嫌だ。バンベニストのディスクールの言語学を熱力学の第二法則で何とか読み取れないだろうか」と思ったが、それを口に出したら本当にクビだ。我慢した。趣味でなく職業としての学問に徹する事だ。が今はそんな事はどうでもよかった。これで心おきなく長野に行けると思うとひどくうれしかった。私の気持ちも夏空のようにスカッと晴れていた。
ついにその日が来た。金曜の晩に長野に入り、土曜は朝から観光という段取りだった。いきなり千恵子の部屋に押しかけるのも悪いので金曜の夜は長野市内のビジネスホテルに泊まった。遠足の前の夜のように、興奮してなかなか寝付けなかった。
凡そ4ヶ月ぶりの再会の待ち合わせ場所はホテルのロビーだった。ソファーに座っている若い女性を千恵子と画像認識するのに、コンマ何秒かの遅延が生じた。千恵子は九州で出会った時とちょっと印象が違っていた。ここ長野は彼女の生活圏だ。その地に足がついている感が、千恵子を旅先とは違った感じに見せていたのだろうか。それとも髪型を変えたせいだったのだろうか。肩まであった髪をバッサリ切ってショートにしている。凛としている。一瞬誰だかわからなかったが、九州で私を射抜いた微笑みを見て千恵子と分かった。相変わらず千恵子の微笑みは眩しかった。夏空に負けないくらいに輝いていた。
「久しぶり。やっと会えたね。会いたかった」
「私も。元気だった」
「一応元気。ちーちゃんは」
「一応ってどういう意味。私は元気よ」いたずらっぽく笑った。
「髪切ったんだ。でも相変わらずきれいだね」
「当たり前な事言うな。私の質問にもちゃんと答えなさい。一応ってどういう意味」
「だって何か月も会えなかったんだもの。そりゃ落ち込むさ。でもやっと会えた。嬉しいよ」
「君って単純。で、学校の方は順調」
「順調。気持ち悪いくらいにね。でも何かやる気が出ない。やらなきゃいけない事は何とかこなしているけど。やらされている感が半端ないんだ。腹の底から力が湧いてこないんだ。暗くなるからこの話止めない」
「呑気そうな顔してるくせに、君もいろいろ大変なんだね」
この台詞で二人とも大爆笑した。九州で出会った時の台詞だ。バカップルに戻るのには大して時間がかからなかった。
千恵子と一緒にいるとあっという間に時間が過ぎて行く。戸隠の神秘的な荘厳さも、野尻湖のサマー・ブリーズの爽やかさも、千恵子の微笑みの眩しさには負けていた。人気のない場所へ行くと、会えなかった時間を取り戻すかのように抱き合った。戸隠の散歩道の森の木陰で、野尻湖の誰もいない湖畔で、抱き合ってキスを繰り返した。
「もう。何度口紅塗り直させる気」千恵子は半ば呆れていた。
気がついた時は、夕闇迫る長野の街に戻っていた。駅方面に向かって歩きながら、
「今日は楽しかった。おなかすいた。何か食べない」と私は言った。
「それよりシャワー浴びたい。汗でベトベトして気持ち悪い。誰かさんがこの暑いのにべたべたくっついてくるんだから」
「じゃ、ホテル探すよ」
「馬鹿にしないでよ、私ラブホなんて行かないからね」千恵子は怒った。
「勘違いすんなよ。俺が今夜泊まるビジネスホテル。そこに荷物おいて、シャワー浴びる。その間にちーちゃんは家に戻って、シャワー浴びて、着替えておいでよ。それからどこかで祝杯あげるっていうのはどう」
「ビジネスホテルならビジネスホテルって言ってよ。びっくりするじゃない」
千恵子は何処か思案気だった。急に止まると、私の方を向いて言った。
「じゃ、こうしない。家に来ない」
唐突過ぎる誘いだった。心臓がバクバクした。勿論千恵子の家に行く事はウェルカムだ。否熱望している。が、いかんせん早すぎる。心の準備ができていない。どういう顔をしたらいいんだろう。
「君、変な事考えてるでしょ。顔に書いてあるよ。そうじゃないからね。ちょっと疲れたでしょ。だから家で少し休んで、それから街へ繰り出そうと思っただけ。ホテル探すのもその後で大丈夫だよ。勿論シャワー使って良いよ」
「でも悪いよ」と言いながら、千恵子について行った。心の中はウキウキしていた。10数分程歩いて、千恵子の部屋に着いた。女の子の部屋に入るのはいつでもドキドキする。が例外もある。馬場さんの部屋に入っても全くときめかない。数年後、彼女は彼女の部屋に入るとドキドキする男を見つけた。
さすがに長野だ。陽が落ちると涼しかった。夏の熱気をためた部屋に、窓を開け、網戸にするといい風が入ってきた。シャワーを貸してもらい、冷えたビールを飲んでるうちに、昨夜の睡眠不足のせいか、寝てしまったらしい。
「目さめた。君ほんとよく寝るよね。私が片付けしてる時、妙におとなしいからどうしたのかなと思って話しかけたら返事なかった。猫みたいに寝落ちしてたよ。指宿のホテル思い出しちゃった。案外無邪気な寝顔してるんだね」
「御免。寝ちゃった。急いで食事いこう」
「もうどこもやってないよ」
「えっ、何時」
「もう少しで10時半。とりあえず祝杯あげましょ。やっと会えたんだから」
テーブルの上には、簡単な食事というか、酒のあてが用意されていた。俺が居眠りしている間に用意してくれていたんだ。疲れてるだろうに。この気づかいは嬉しかった。歓迎されている。
「ありがとう。でも俺ホテル探さなきゃ」
「もういいよ。泊っていきなさいよ。でも変な事はしないでね」
「分かった。ありがとう。これからホテル探すのしんどいなって思ってた所だから、助かるよ。ところでちーちゃんはシャワー浴びたの」
「さっきと服違うでしょ。もうとっくに浴びたわよ。君が寝落ちしてる間にね」
「良かった。もしこれからだったら、鼻血止まらくなるところだったよ」
「何考えてんの。バカ」千恵子の常套句だ。
念願の祝杯だった。この時をどれほど待った事だろう。指宿の夜から数えておよそ172,800分ぶりの二人だけの酒宴だった。彼女は新しい環境に馴染みつつあるようだった。職場での人間関係のコツを前回の失敗から学んだようだった。良かった。後は、たわいのない会話の連続だった。たとえ、会話が途切れ沈黙が訪れても、いやな沈黙ではなかった。見つめ合っていればそれだけで思いが通ずるように感じた。一緒にいるだけで嬉しかった。トキメキもあったが、穏やかな気持ちだった。ユーフォリアの球体が二人を包んでいた。アンティームな空間だった。
「一つ教えて」私は言った。
「何」
「鹿児島で列車が出発する時、『私決めたんだ』と言ってたでしょ。あれ何を決めたの」
「手紙に書いたでしょ。もう一度、働いてみようという勇気を誰かさんにもらったの。これで満足」
「俺も人の役にたつんだ」
「実はもう一つあるんだ。でも今は言えない。秘密」
知りたかったがそれ以上問いただすのは止めた。彼女の目を見て分かったような気がした。
「それより、もう寝ましょ。2時よ」
ベッドから少し離れたソファーで寝るように言われた。消灯とお休みの言葉の後で、千恵子がパジャマに着替える衣擦れの音が聞こえた。たまらず、千恵子をベッドに押し倒してしまった。初めは「何するの」と抵抗していたが、彼女の身体からだんだんと力が抜けていくのが分った。
翌朝目を覚ますと10時過ぎだった。指宿の時とは違い、千恵子が隣で寝ていた。人の寝顔を見てあどけないって言っていたけど、千恵子の寝顔も十分あどけなかった。思わずキスしてしまった。「何するの。今何時」「いいからこうしてよう」強く抱きしめ、キスと愛撫を繰り返した。唇が彼女の身体を這いまわるナメクジと化していた。愛を何度も交わした。快楽の海に漂っていた。溺死寸前だった。
二人でベッドから出たのはもう昼過ぎだった。猛烈に空腹を感じた。と同時に狂喜するくらいの幸福を感じた。
「もう、誰かさんのおかげで今日の予定台無し」
「御免。でも幸せだよ」
「バカ。今日は早起きして小布施案内するつもりだったのに。栗のジェラートが食べたかった。どこか行きたいところある」
「善光寺。それとどこかでランチしない」
「君に約束のオムライス食べさせてあげるよ。材料は冷蔵庫にあるから。その後で散歩行きましょ」
「嬉しい」念願のオムライスだ。
今の私は「Fun ×4」の主人公の階段を駆け上っている。このままだと5年後には「4人の子持ち(24)」になっているかもしれない。こんなに順調に事が運んでよいのだろうか。経験上、あまりにも事がうまく進み過ぎた後には空前絶後の落とし穴が待っているのを知っている。そう考えると酷く不安になった。が、シャワーを浴びた後、バスタオルを巻いただけで、ベッドの上で如意輪観音のようなポーズで、髪を乾かしている千恵子の無防備な姿を前にした時、将来どんな事があろうと、俺はこの子に賭けるんだと決心した。Crazy about Chiekoだ。と突然、バスタオルがほどけ、乳房があらわになりそうになった。一瞬淡いピンクの乳首が見えたような気がした。
「スケベ」私の視線に気づいた千恵子が言った。同時に枕が飛んできた。
「御免。あんまりきれいだから、つい見とれちゃった」
「当たり前な事言うな」千恵子の常套句だった。
「それより君もシャワー浴びてきたら」
浴室から出ると、千恵子がオムライスと格闘していた。
「何度試しても、卵が上手く焼けないんだ。ちょっと焦げたのと、形が崩れたのと、どっちがいい」
「半分ずつしない」
「名案。君って時々いい事言うね。さすが大学院生」
千恵子のオムライスは、卵の焦げた部分を除いて、味はまあまあだった。ケチャップライスはほぼ完璧だった。
「私、卵が上手く焼けるようになるまで作るのやめないからね。君にいつか完璧なオムライス食べさせてあげる。それまで待っててね」いたずらっぽく微笑んだ。
これから先、私は何皿オムライスを食べなければいけないんだろう。完璧なオムライスへの道のりは遠そうだった。
食事と片付けが終るともう夕方だった。善光寺ももう閉門間近の時間だった。二人でソファーに横に並んで座っていた。長崎鼻へ向かう列車のボックス席を思い出した。
「結局、今日はどこも行けなかったね」不満気に千恵子は言った。
「御免。寝坊させちゃったもんね。栗のジェラートは今度来た時食べよう」
「これからどうするの」
「ちーちゃん明日仕事でしょ。もうそろそろ帰るよ。なごり惜しいけど。もう少ししたら一緒に出かけよう。駅近くの居酒屋で祝杯あげて、それから俺は東京に帰る」
「分かった」
別れる前に長いキスを交わした。キスがエスカレートしてしまった。暮行く部屋の中で愛を交わした。「一」に回帰した。
「本当君好きだね。今日一日こんな事ばっかしている。何か頭おかしくなりそう」
「大好きだよ。ちーちゃん。好きすぎて気が狂いそうだよ」
「私に惚れたな。千恵子様に惚れると大変だぞ」
「えっ、何で」
「だって、千恵子様は小悪魔だぞ」
「誰がそんな事言ったの」
「元カレ」
「…」
「嫉妬したでしょ」
「何で分るの」
「だってムッとした顔していたもん。でも安心して、元カレとは何も無かったから」
嘘だと思った。でもそんな事はどうでもよかった。今千恵子の心の中の住人は私だけだ。
5時過ぎに出発した。夕方の涼風が疲れた体に心地よかった。駅近くの居酒屋に入り、祝杯を挙げた。鹿児島の時と違ってまたすぐに会えると思うとあまり感傷的にならずにすんだ。同じだったのは、「何かあったら責任取ってね」という千恵子の台詞だった。違ったのは「信じて。君を不幸にするような事は絶対しないから」という私の返事だった。
「本気にしていいの」と千恵子は言った。
「Trust me(25)」
「え、なんていったの」
「俺を信じて」
テーブルの上の千恵子の手に、自分の手を重ねながら言った。この時千恵子の頬が一瞬紅潮したように思えたのは、私の錯覚だったのだろうか。もう覚悟はできていた。
帰りの列車では、千恵子とアルコールに酔ったせいか、または甘美な疲れのせいか、それともその両方のせいか、あっという間に寝落ちしてしまった。千恵子が見ていたら「君ほんと良く寝るね」とあきれただたろう。今日「我が人生最良の日」が再び訪れたのだった。眠りの中でその余韻に浸っていた。
18 Littre Feet, Long Distance Love, Last Recorded Album
19 Fun × 4(作詞:松本隆、作曲:大滝詠一)の歌詞
20 Led Zeppelin, Communication Breakdown(Jimmy Page), 1st
21 Dave Mason, Take It to the Limit(Randy Meisner), Certified Live
22 Eagles, Peacefull Easy Feeling(Jack Tempchin), 1st
23 Eagles, Desperado(Don Henry, Glen Fly)の歌詞, Desperado
24 Fun ×4(作詞:松本隆、作曲:大滝詠一)の歌詞
25 Hal Hartelyの映画
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
