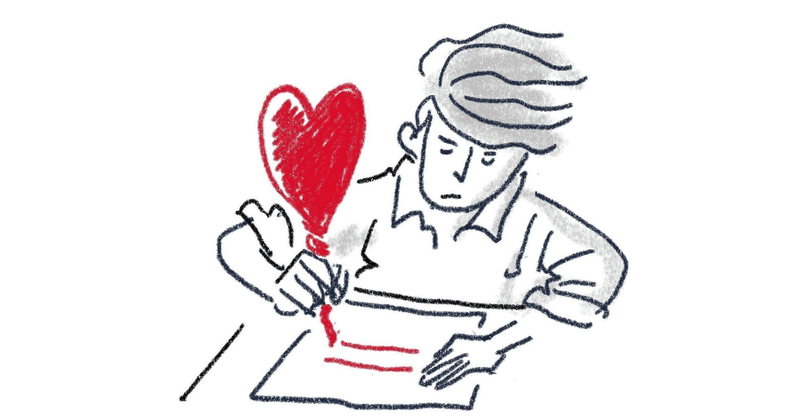
需要を作ろう。 5月12日 The Manufacturing Paradox 製造業のパラドックス
人それぞれ、頑張ろうという動機があるものです。
例えば、かつての昭和のサラリーマンの中には、うまいもん食いたい!家族に美味しいものを食べさせたい、を動機にバイタリティもって働くお父さん、みたいなことです。
本日、#5月12日日曜日 の #ドラッカー365の金言 のテキストは、『ネクスト・ソサエティ』(2002年発刊)第4章 製造業のジレンマ>雇用の減少と社会不安 32〜37ページより
本日のテーマは
#The_Manufacturing_Paradox
#製造業のパラドックス
そして、金言は、
#はるかに少ない労働力ではるかに大きな生産量を実現しなければならない 。
ACTION POINT :
#あなたの組織も生産と雇用のパラドックスを経験していますか 。
#早速再教育プログラムをつくってください 。
2年前にも紹介しましたが、長年、製造現場で積み重ねてきた生産性向上が実を結び、現在では、全就労者のうち製造業従事者は割合が多いとはいえ、かつての割合から右肩下げりで減少。最新値(24年2月21日)ではわずか16.8%ほどとなっています。

日本社会の安定は、雇用の安定、特に大規模製造業における雇用の安定に依存するところが大きかった。いま、その雇用の安定が急速に崩れつつある。(中略)社会心理的にも、日本は製造業の地位の変化を受け入れる心構えができていない。日本は20世紀の後半、製造業の力によって経済大国の地位を獲得した。
近年、医療福祉従事者が増えており、881万人、14.5%と大きな割合となってきました。ただし、これらの多くが公金による補助事業のため、医療福祉事業が増えても国富にはつながりません。医療福祉事業の原資が公金のため、この事業が伸びるには、勤労世代の社会負担を増加させ、彼らの可処分所得を減る政策となるため、すでに、負担率が50%に近い現在、これ以上の勤労世代の負担は現実的ではなく、日本社会の成長への阻害要因になりえます。
ここ20年、我が国が経験していることから言えば、生産性向上→従事者が減る→雇用が減る→収入を得る人口が減る→金を払える人口が減る→需要が減る→デフレ価格にして売る→利益率の悪化→年収減の雇用者増→生活保護や社会保障で喰わせる→就業者には増税・増負担→就業者手取りが減り消費需要も減る→更なるデフレ、というサイクルにあるように思います。
新しい需要を掘り起こすことが重要に思いますが、供給が需要を大幅に上回った今の日本。マーケッターは「隠れた需要を見つけよう」と言うけれど、需要が隠れているだろうか?「需要がないなら作り出せ」なのかもしれません。
こちらへの投資もよろしく↓
良い日曜日となりますように。
サポートもお願いします。取材費やテストマーケなどに活用させていただき、より良い内容にしていきます。ご協力感謝!
