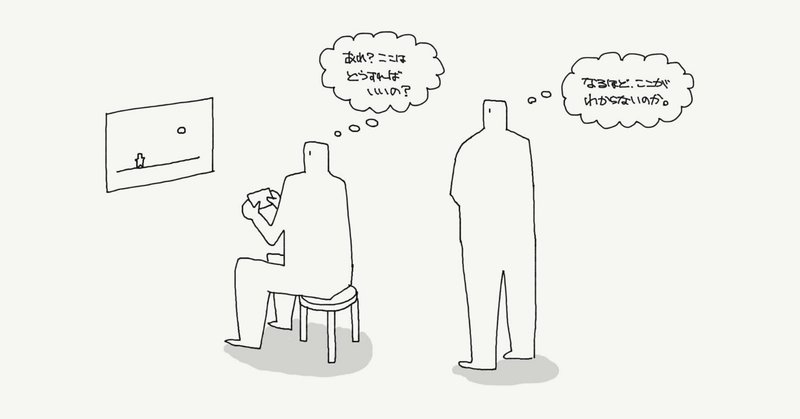
宮本茂さんはゲームで教える:学習のデザイン19
学習のデザイン12人目は、ゲームクリエイターの宮本茂さんです。
このような人です
もはや説明不要、マリオやゼルダを生み出した、ゲームの神様といえる人です。宮本さん、実は学生時代は金沢美術工芸大学で工業デザインを学んでおり、歩み的には自分の大先輩にあたります。

ただ、まわりがみんなモノづくりのメーカーに就職するなか、本人はコンセプトに興味があったようで、任天堂に就職したのはこんな理由だったそう。
いま自分が勉強しているものは、何かあるコンセプトを置いて、架空のものをでっちあげるもの。それをたくさんの人に売りたいっていう欲だけあったんです(笑)。それで、オモチャっていうものがいちばん面白いジャンルで、ぼくが考えてつくったものを量産してくれるスポンサーがほしいと思ったんです。
宮本さんの発想のルーツは、幼少期に裏山にあった野山・川・洞くつで遊んだ体験なのだそうです。マリオもピクミンもゼルダの伝説〜ブレス・オブ・ザ・ワイルドの世界も、ルーツは宮本さんが子どもの頃の遊びにあります。
宮本さんは実務者なので、教育には直接関わっていませんが、ゲームを通じて学習のデザインをしている人だと、僕は勝手に思っているので、どのようにデザインしているかを、ここにメモしておきます。
スーパーマリオの学習デザイン
スーパーマリオが今日のゲームの作法をつくった、ということはあまりにも有名です。あらためてデザインという意味で整理してみます。(画像はニンテンドーswitchで撮影したものです)

スタートするまえに、ゲームの世界観が見えているので、これからどんな内容かが少しわかります。

主人公は右を向いているから、とりあえず右に進んでみよう。

進むと「?」のブロックがあった。何かもらえるのかな?

すると、なんか敵っぽいキャラがこちらに歩いてきた。この敵をなんとかしないと「?」のブロックに近づくことができない。

何か他のボタンを押してみよう。あ、ジャンプできる。

踏みつけられた。なるほど、これで敵を倒すのか。

じゃあ「?」もジャンプで。上にのっても何にもならないので下から。あ、コインが取れた。下からたたくと取れるのか。

今度の「?」はキノコがでてきたぞ。これはとってもいいのかな?

大きくなった(スーパーマリオだ)。この状態でブロックをたたくと壊すことができるし、敵をやっつけることもできるんだ。

と、このようにプレイヤーは説明書を読むこともなく、ゲームの遊び方を覚えながら進めることができます。
今日、あたり前になっている説明書なしの製品、アプリやウェブサービスの使い方は、ほとんどこのスーパーマリオの作法がもとになっています。100年に1度の大発明といえる、素晴らしいユーザー操作の作法です。
今回、特に注目したいのは、実際のプレイを通じてプレイヤーは学習をしていることです。ガイダンスや人の指導なしにかなり高い習熟を、本人が無自覚の中で行えていることです。
これを学習に取り入れない手段はないと思います。
マリオの素晴らしさはこちらの本にも解説されています。

ゲームはおもしろいから遊ぶのではありません。「つい思いついちゃった、ついやっちゃった」から遊ぶんです。私たちの脳はいつだって仮説を探し求め、思考させようとします。
観察で学習効果を検証
宮本さんは誰もが認める優れたクリエイターでありながら、自分を疑って普通の人が楽しく遊べるための検証を怠りません。

宮本さんはなんにも知らない人をつかまえてきて、ポンとコントローラー渡すんですよ。で、「さあ、やってみ」って言ってね、何にも言わないで後ろから見てるんですよ。わたしは、それを「宮本さんの肩越しの視線」と呼んでたんですけど。
学校の授業は、先生が教えることに一生懸命になって、生徒が習得できているかを見る機会が、実はそう多くありません。計算問題をノートに書いている過程を先生にずっと見られるのは嫌だし。
でもゲームであれば、つくった本人は一歩引いたところから見られる。この仕組みを、授業に組み込むことってできないかと考えます。

ゲームと授業の関係は次のように置き換えて考えることができます。
プレイヤー=生徒
ゲーム=教科書・ノート・黒板
開発者=先生
学校の授業ではつい原因を生徒に目を向けがちですが、ゲームであれば、プレイヤーに問題を見出すのではなく、ゲーム自体に改善要素を見つけて、それを開発者が改善しています。ここから学べることはたくさんあります。
宮本さんは、自分がどんなに実績のあるゲームデザイナーであろうと、「お客さんがわからなかったものは自分が間違ってる」というところから入るんですよ。
面白いを見つける
宮本さんのすごいところは、マリオやゼルダなど王道のゲームだけではありません。これまでゲームにあまり興味を持たなかった人にも、ゲームの面白さを伝えて、遊ぶ人の数を増やしています。それも健全なカタチで。

例えば、どうぶつの森は、ゲームをしない奥さんがどうしたら遊んでくれるかから生まれています。
宮本の妻は昔からゲームにまったく関心がない。だがある日妻は、娘が《ゼルダの伝説 時のオカリナ》で遊んでいるのを珍しく眺めていた。「もしかしたらゲーム機に触ってくれるかもしれない」と思った宮本は、動物たちが暮らす小さな村で生活を楽しむだけのゲーム《どうぶつの森》を「敵が出ないよ」といって差し出す。すると妻はコントローラーを握って遊んでくれた。
他にはWii Fit。これは自身が健康を気にしているうち、「健康ってたのしいぞ」ということに気づいたのがきっかけだそうです。
水泳を続けていると体重は自然と落ちていく。その時、初めて「健康になるのは面白い」と感じた。(中略) 風呂に入る前の儀式のように習慣となり、「毎日体重を量るのは面白い」と気づく。(中略) 宮本はついに「体重を量る」「健康になる」ことをコンセプトとしたゲームのプロジェクトを立ち上げる。
学校の授業は楽しくないものでしたが、いま僕は勉強はとても楽しいものだと思ってます。授業の目的が知識習得ではなく「楽しい」「面白い」といった好奇心をより重視したものだったら、ゲームのように、ほっといても自主的にやるのではないかと思います。
あとはそれをどうデザインするか次第です。
何でこんな考えができるのか
宮本さんがこんな風に、多くの人に楽しんでもらえるゲームをつくれるのはどうしてなのか。本を読んで印象に残った一文をいくつか引用してみます。ここから学習に役立てられる何かがあるかもしれません。
「いつも、これからゲームに引き込もう、という人を相手に作っているので、今、ゲームに熱中している人の意見は当てにならないところがある」
「1つのテーマについて、長くしつこく考え続けることが大切で、考え続けていることの蓄積の量が、ヒットを生んでいる部分というのもあるんだなと、私は思っています」
宮本さんって、めちゃめちゃロジカルなんですよ。かといってそれだけではない。ものすごく左脳的な理詰めの思考と、美術系の道を目指した人ならではの、ぶっ飛んだ飛躍的な思想とか、両方、あたまの中にあるんですよ。あれは、悔しいけど、うらやましいですね。
というのも、やっぱり、原理と機能をわかってしゃべっている人なんですね、宮本さんは。だから、専門の知識がなくても、プログラマーとやりとりできる人なんですよ。自分がやりたいことを実現するために、「できない」と思い込んでいるプログラマーのかわりに、どうすればできるかを提案できるんです。
「アイディアというのは、複数の問題を一気に解決するものである」
学んだこと
今回学んだことは3つあります。
説明書を使わない、プレイを通じた学習
プレイの観察による改善点の発見
面白いに気づく視点
共通する点は、ゲームをプレイする人に負担を強いないことです。どうすれば自然にゲームの世界にのめり込めるか、つまずく要因はないか、何が動機となってゲームをやる気持ちにさせるか。
このような開発者の配慮が結果、ゲームがこれほど世界中の人たちを夢中にさせています。ゲームを学習に活かせることはたくさんあるはずです。強い可能性を感じるので、研究していきたいと思います。
・・・・・・
ここまで12人を取り上げました。次回は一年の1/4の区切りとして、一度これまでの内容をまとめてみます。
デザインとビジネスをつなぐストラテジーをお絵描きしながら楽しく勉強していきたいと思っています。興味もっていただいてとても嬉しく思っています。
