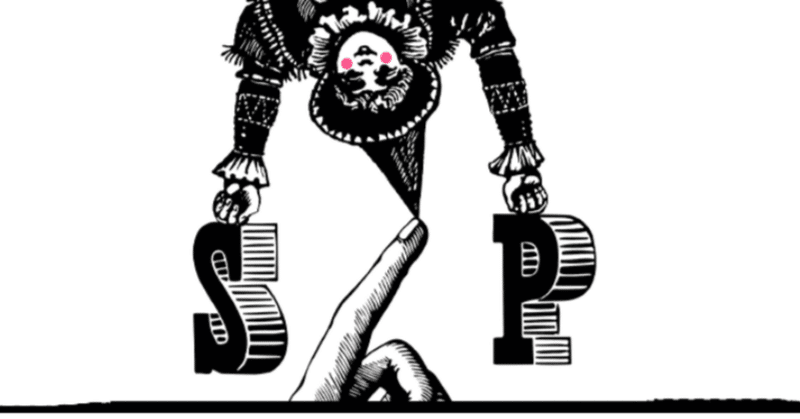
チェコ最大の人形劇祭スクポヴァ・プルゼニュ2024は、今回もまたすごい詰め込みの5日間だった・・・
今年もスクポヴァ・プルゼニュ(https://www.skupovaplzen.cz/)が無事に終わった。今年はケガ人が出なかった、何よりだ!
2024年6月12〜16日。たったの5日間に52回の公演(さらに3つのワークショップと、10の野外公演)を詰め込む大忙しの人形劇祭。会場間にはフェスティバル専用バスも走っていて、観客へのきめ細かい対応が非常にありがたい人形劇祭である。それでも(運営側はもとより)観客も5日目にはへとへとだったが。
2020年の七転八倒→中止、の時には人形劇はどうなってしまうんだろうと思ったりしたが(死ぬほど長い拙記事「サスペンス! チェコ人形劇フェスティバル、中止の記録」をご参照)、早いものでコロナ後もう二回目の開催。
これまでチェコ語がわからない観客にはイヤフォン同時通訳で対応していたところ、今回からすべて字幕を導入してくれた。ありがたいことだ。(ちなみに「世界人形劇祭」を名乗っているシャルルヴィル・メジエールの人形劇祭は非仏語話者向けの字幕もサービスも一切無いので、ちょっと本気で考え直して欲しい。本気で。)
以下は、気になった作品の報告。
LOUSKÁČEK. Zeleninový balet.(「くるみ割り人形。野菜バレエ。」)
Borshch theatre, Praha (チェコ)

ニンニク、生姜、ナス、クルミを用いた「野菜バレエ」。前回も話題になった「Dinopera」と同じDarja Gostevaの作品。まだDAMU(プラハ芸術アカデミー演劇学科人形劇・オルタナティブ演劇専攻)で学んでいる学生なんだけど、本フェスティバルで上演されるような佳作を連発している。
生野菜に、チェコ人形劇らしい金属棒を取り付けて、ろうそく火の中で丁寧に踊らせる。音楽は素敵なアナログ盤を爆音で鳴らす。やっていることはそれだけ。爆音で『くるみ割り』を聞きながら、蝋燭越しにちいさなプロセニアム舞台の中でゆらゆらする野菜を眺める・・・・・・これで酩酊しないわけがない。「くるみ割り人形。野菜バレエ」というタイトル以上でも以下でもない作品だが、マリオネットならではの心地よさをうまく引き出している。日本から来た20代の若者たちは、これをとても気に入っていたようだった。
これと、次の作品とをあわせて、「イリュージョニズムの復権」とでも呼べるような流れを感じた。
TŘETÍ RUKA(「第三の手」)
Handa Gote Research and Development, Praha (チェコ)

プラハのオルタナティブシアター「中庭のアルフレッド」(https://www.alfredvedvore.cz/)を主宰するトマーシュ・プロハースカの劇団ハンダゴテ。いつもオタク魂を極めた、スケールの大きいような小さいような、何をやっているのかよく分からないが不思議な凄みのある作品を発表し続けてきたプロハースカ。つかみ所の無い彼のキャリアの中でも、これはその集大成あるいは最高傑作、そう呼んで差し支えない作品だった。
相変わらず出てくるものの意味は分からない。しかし、ここまでやられたら平伏するしかない圧巻の物量、ただ有るだけで面白さを放つ個々のオブジェクト、そして<間奏>として度々登場する鉄面皮のプロハースカ自身の強烈な個性とおかしみ。豊かな70分間だった。

装飾過多のプロセニアムが観客を出迎える。しかも上演が始まるとこの開口部の中にさらに小さな人形劇プロセニアムが二重、三重と現れる。チェコ式ふすまからくりというか。プロセニアムという舞台装置そのものに絵心を加える、あるいは作品のなかで意味を持たせるのは人形劇では定番の手法ではあるが、ここまでやりきったのは見たことがなかった。
また、タイトルにあるとおり「第三の手」の登場が面白い。演者が見えないマリオネット劇で、ふと人形遣いの手が見えてしまうとき、人形と比べていやに大きく・恐ろしく見える。シュヴァンクマイエルの『レクツェ・ファウスト』(1994)もこの錯覚を効果的に使用している。プロハースカはこの「手」を、船の櫂や孫の手のような別の物に置き換えることで新しい効果を生み出していた。非出遣い人形劇(イリュージョン形式)の必要悪というか、伝統的にはあまり面白く演出されてこなかった、①プロセニアム、②不意に見える手、という二つの要素が、現代におけるマリオネット劇では格好の遊び場となっている。
KAZU
Singe Diesel (フランス/ アルゼンチン)
前評判がとてもよかったので、第二回SIPFの招聘候補として意気込んで見た作品。確かに素敵な作品だった。操りも上手い。
15〜20ほどの人形を用いて、それぞれがとても短い、ほんの1〜2文くらいの物語を語る。いずれも、マジックリアリズム的な、虚実ない交ぜの美しく哀しい話。南米では、コロナ禍中に「microcuentos」(英語だとflash fiction)と呼ばれる、超短編フィクションという新たな文芸形式がSNS等で流行ったそうで(Cordova, "Microcuentos: very short Latin American fiction in and for pandemic times")、この作品もその形式を用いている。
ZAPSANÝ SPOLEK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH LOUTKÁŘŮ UVÁDÍ: KAŠPÁREK A ZBOJNÍK (「チェコ・スロヴァキア人形劇ユネスコ登録協会プレゼンツ:カシュパーレクとズボイニーク」)
Divadlo Drak Hradec Králové (チェコ), Bábkové divadlo Bratislava (スロヴァキア)
このフェスティバル「スクポヴァ」では、東欧らしく最後に優秀作品の授賞式があるのだが(審査対象になるのはチェコ・スロヴァキア圏内の作品に限る)、この作品が演出賞、演技賞、等々一番多くの賞を受賞していた。
チェコのフラデツ・クラーロヴェーのドラク劇場と、スロバキアのブラチスラバ人形劇場の共同制作。2023年初演の作品で、チェコスロバキア解体30周年記念作品(笑)とのことだ。あらすじは、「チェコとスロヴァキアの人形劇団が力を合わせて一つの人形劇を一緒に作ろうとするのだが、演技のスタイルも価値観もジョークの好みもまったく違うので、紛糾し、しまいには喧嘩別れ。舞台装置も1/3と2/3に分けて(ちょうど1993年の分割のように)、アッサリサッパリと決別して、二度と元通りには戻らなかったのでした(ちょうど1993年の分割のように)、めでたしめでたし」というもの。
両国が双方に対して持つステレオタイプをすべて詰め込み、観客の絶え間なき爆笑を誘っていた。スロバキアの峻厳な山々、荒々しい盗賊たちの生き様、情熱とロマンチシズム・・・ を語るヤノシーク人形(スロバキアの有名な義賊)に対して、チェコのカシュパーレク人形が、ヨゼフ・ラダ調のほんわかメルヘンした世界を背景に、ひたすら下品でおバカなギャグをくり広げ続ける。この両者が噛み合うはずが無い。舞台の最後は、これまたテンポも曲調もまったく違うチェコとスロバキアの国歌が同時に流れる。失笑してしまうほどの不協和音。あるチェコの批評家に言わせれば、「チェコスロバキアの解体を描いたものの中で、最もリアルな作品だった」とのこと。笑
この作品の脚本はドラクのディレクターであるヤルコフスキー、演出はドラクの芸術監督であるヴァシーチェク。彼らは、いまクリエーションの真っ最中で、今年の8月に初日を迎える日本&チェコ共同制作人形劇『チャスラフスカ・東京・1964』(https://caslavska-puk.amebaownd.com/)と同じアーティスティックチームであり、また同じく国際共同制作作品。なので、『チャスラフスカ』出来の命運を占うつもりでみたが、これは傑作だった。果たして日本・チェコ共同制作は、日本で予定されているあと二週間のリハーサルで、どこまでこの作品の出来に迫ることが出来るだろうか?
A SHOW WITH STRINGS
Long & Short Company (韓国)
去年の飯田で見て、「ああ〜、伝統人形劇ではなくまったくの現代人形劇でも、世界で戦える人が韓国の若い世代から出てきたのか〜〜」と衝撃を受けた作品。人形やオブジェクトの形状・技法・扱い方など、人形劇史からみて目新しいところはべつに無いのだが、彼が自家薬籠中とするオブジェクトである「糸」の見事な操りと、人好きする無言の顔芸が見事。なんだかみているだけでこころをほっと暖かくさせるような魅力がある。上記の『KAZU』を演じたSinge Dieselにも通じるようなカリスマ的笑顔。
フェスティバル終了語に少しゆっくり話せたのでバックグラウンドを聞いて見たら、もともとヨーヨーのデュオとしてストリートパフォーマンスをしていたんだそうな。彼はヨーヨーだけでなくもっと広く演劇やマイムなどを学びたいと考えてフランスに留学することにしたが、デュオの相方は拒否(その相方はいまでもソロでヨーヨーパフォーマーを続けているらしい)。一人でフランスの演劇・マイム学校に通い始めたが、一年ちょっとでお金が尽きて韓国に帰国。今に至るらしい。ヨーヨー・パフォーマーという異色のバックグラウンドもうなずける、鮮やかな糸の手さばき、はっとさせられる糸の使い方。「糸」を追究した作品を作り続けるのかと思ったんだけど、昨年発表した第二作目のティーザーを見せて貰ったら、木製の馬の人形と影絵の技法を使った作品のようだった。どこかで見てみたい。
PUPPET SLAM INTERNATIONAL(第二回国際パペットスラム)
MCs: Vladimír Sosna and Valerie Meiss

下北沢で第一回を行った「インターナショナルパペットスラム」の第二回がここでも開催されました。下北沢国際人形劇祭からは角谷将視さんを派遣したんですが、全体でも1、2を争う笑いをとってました。(ちなみに1、2を争っていたもう一人は、シカゴのManual Cinema(https://manualcinema.com/about) という著名なグループのメンバー。「典型的なアメリカン・デート」を表現したという3分こっきりの顔芸人形劇で、圧巻でした。また見たい。)あと日本からさらに「はと」さんの異色着ぐるみ芸が登場し、これまた大きな笑いを誘っていた。アメリカからきたパペットスラム関係者も「あれ好きだわ〜」と言っていた。私の横で見ていたネヴィル・トランターも「ハッハッハ(笑)」と笑っていて、よかった。日本から出場の二組ともかっこよかった!
第三回はいよいよ本場ニューヨークで行われます。今年の十月。ニューヨークのパペットスラムを何十回も主催してきたキュレーターたちによると、アメリカでは「7分間」という時間制限が絶対なのだそう。というか7分でも長すぎるくらいらしい。時間をすぎると、袖に用意しておいたゴングで「ゴ〜ン!」と鳴らして退場を迫ったりするらしい。「下手な人ほど長くやる」という辛辣なコメントを聞いた。「3、4分くらいでまとめられる人が、一番高評価を得ることが多い」とか。下北沢国際人形劇祭の時、本場のパペットスラムを映像でしかみたことがなかった私は「10分くらい」と曖昧な設定をしてしまい、キュレーターチームの皆さんが15分以内というフレームでまとめてうまく形にしてくれたが、しかしそれだともう全然長すぎるようだった。これは今後の改善点としたい。
STICKMANもスクポヴァで上演したよ
チェコ人形劇界のうるさがたの意見をいろいろと聞いて回ったが、今回のスクポヴァを通して、最大の成功を収めたのはKazu(フランス)とSTICKMAN(アイルランド)のようだ。チェコ国内では、チェコ・スロヴァキアの共同制作が最も評判がよかった。私も同意見でした。STICKMANは下北沢でも大成功だった。いま、ダラー・マクローリンはSTICKMAN 2を作成中だという。近いうちに進捗を見に、ベルリンへ訪ねに行きたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
