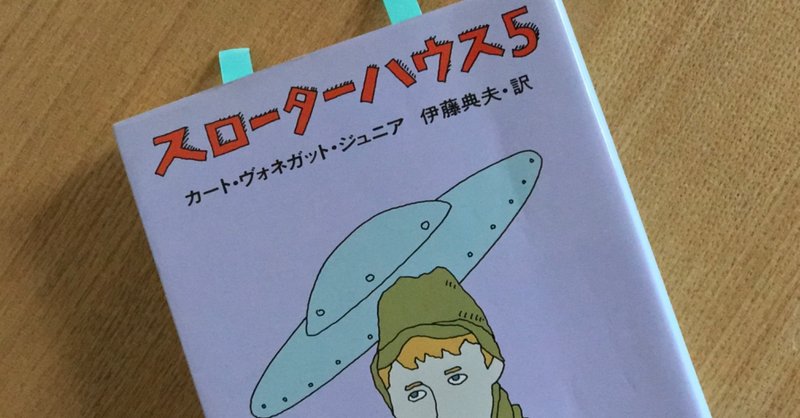
『スローターハウス5』と永劫の存在論
存在論の文学装置
カート・ヴォネガット・ジュニア『スローターハウス5』(1969年)は、ヴォネガットの半生を第二次大戦において戦争捕虜となり、ドレスデン無差別爆撃を受けたビリー・ピルグリムの語りを借りて物語る小説だ。
ただの小説ではない。ビリー・ピルグリムは「トラルファマドール星人」にさらわれ「時間から解き放たれる」。どういうことか?
トラルファマドール星人は独特な存在論––––あるものがいかにしてあるのかについての論––––を啓示する。
ビリー・ピルグリムはいう。トラルファマドール星人には、宇宙は明るい光の点をちりばめた暗い空間とは見えない。彼らは、ひとつひとつの星のこれまでの位置、これからの位置を手にとるように見わたすことができるので、空はか細い、光るスパゲッティに満たされている。またトラルファマドール星人は、人間を、二足の生き物とは見ない。彼らの眼には、人間は長大なヤスデ––––「一端には赤ん坊の足があり、他端には老人の足がある」ヤスデのように見える、とビリー・ピルグリムはいう。(119)
トラルファマドール存在論は、作品内のガジェットには収まらない。それはこの作品の語りの構造そのものとなっている。時間から解き放たれたビリー・ピルグリムは、現在からの記憶の回想ではなく、実在する過去と現在を行き来する。ある時は老い、娘から子ども扱いされた老人として、ある時は収容所で、死の匂いに包まれた捕虜として、ある時は、妻を交通事故で亡くした瞬間の夫として。
過去の苦しみは決して消え去ることなどない。それは、永遠に存在し続ける。それも、痕跡としてではなく、現在として、現存し続ける。アウシュヴィッツの惨禍が決して古びることなく、事実として残り続け、いままさに、彼らは処刑され続け、ひとびとは悪行をなし続ける。トラルファマドール星人なら、右手が挙がり続け、Heil Hittler!の口になったヤスデ人間たちを目の当たりにするのだろう。トラルファマドール存在論は、永劫回帰の苦しみを帰結する。
時間の表現にはもう一つ印象的なものがある。逆回しのスローモーションによって、爆撃が救済されていくシーンは、この作品のなかでもっとも美しく、そして、深い悲しみを覚えさせさえする。映画的な語りでは、行為に属性を付与できない。だが、小説ならば、生きていないものの動き、出来事にさえ、慈悲と思いやりを付与することができる。このシーンは、すぐれて小説的な技法を利用している。
『スローターハウス5』はそのシャッフルする語りを戦争の記憶と結びつけることで、過去の苦しみが存在し続ける世界を描き、同時に、苦しみに生き続けることの意味へと読み手を引き込もうとする。同時に「良い面だけを見る」トラルファマドールの格言を繰り返しながら、ニヒリズムとそれでも存在し続けることを受け止める。SFの価値のひとつが、科学的・哲学的文学装置を導入することで、ここではない世界を描きながらも、この世界に生きるわたしたち読者への何かを伝え、揺さぶろうとするのなら、『スローターハウス5』は優れて自覚的なSF作品だ。と言うと、ヴォネガットは嫌がるだろうか?
難波優輝(現代美学・SFスタディーズ・批評)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
