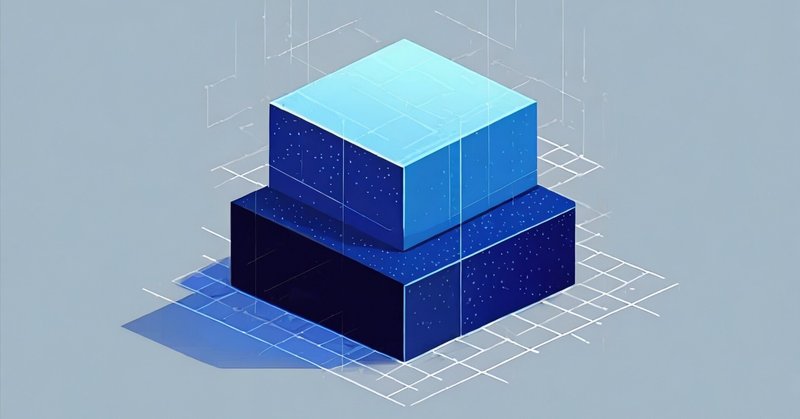
なぜレイヤー2なのか?Web3業界で何が起きているのか?
ここ最近のWeb3業界では「レイヤー2」という単語を聞く機会が増えています。
レイヤー2とはEthereumなどのブロックチェーンのスケーラビリティ問題を解決するために開発された技術で、Ethereumのようなチェーンをレイヤー1として、そこでのトランザクションやスマートコントラクトの処理を外部=レイヤー2で高速に処理した上で、その結果を安全にレイヤー1へ伝達する仕組みです。
1,2年前だとOptimismやArbitrum、zkSyncなどがEthereumを拡張するレイヤー2として有名でしたが、その後、CoinbaseがOptimismの仕組みを利用したレイヤー2であるBaseをローンチしたり、直近だと、4月にMetamaskを開発するConsensysのLineaが、7月には既存のレイヤー2の機能をモジュールとして分離して効率化を図るMantle Networkがメインネットのアルファ版をローンチするなど、レイヤー2市場は益々活況となっています。国内でもAstarNetworkがPolygonと共同でAstar zkEVMというレイヤー2を立ち上げることを発表しています。
また以下の記事で紹介されているCeloのように、新規参入だけでなく、既存のレイヤー1がレイヤー2への移行を計画している例も出てきています。
なぜレイヤー2への参入・ピボットが相次いでいるのでしょうか。
増えすぎたレイヤー1とEthereumの寡占

上記のレイヤー2へ移行したCeloの例からも明らかですが、現在のレイヤー1の領域は供給過多です。
これはデータからも明らかで、DeFiデータアナリティクスサービスのDefiLlama(※)に現在登録されている分だけでも215のブロックチェーンが存在しており、レイヤー1だけに絞っても198本が存在しています。これをTVL順で並び替えると56位以下のチェーンのTVLは$10mを下回り、大半のチェーンが非常に小規模に稼働していることがわかります。
※DefiLlamaはDeFi市場の分析に特化したサービスであるため、分析対象のチェーンはDeFiアプリケーションを有するものに限定されます。
ブロックチェーンは規模の経済が働きやすい領域ですから、下位のレイヤー1が単独で豊かなエコシステムを継続的に提供するのはあまり現実的ではありません。
またブロックチェーンの領域は、上位5つのレイヤー1だけで全体の8割弱のTVLを占める寡占市場です。とりわけEthereumは全体の過半を占めており、加えて、Ethereumを拡張するレイヤー2のTVLは、シェア第3位のBSC単体よりも大きく、EthereumのTVLと合算するとシェアは62%を超えます。まさにEthereum一強の時代といってよい状況です。

かつては「イーサリアムキラー」と言われる新興チェーンの性能や特色の比較が、そこかしこで行われていた記憶がありますが、最近はそういった記事を見かけることも少なくなっています。最近は、Ethereumとの共存を前提として、Ethereumのエコシステムが提供できない機能をどのように補完できるか、という議論の方が活発なのではないでしょうか。
Ethereumレイヤー2の開発環境の整備
またレイヤー2がホットな理由として、またEthereumの寡占がより強固になる理由として、Ethereumのレイヤー2を開発するハードルが一気に下がってきている点も挙げられます。
レイヤー2の代表格でもあるOptimismは、2023年6月にOP-StackというOptimismが採用するOptimistic Rollupという技術を利用したレイヤー2を簡易に構築できる仕組みをローンチしました。
Coinbaseの運営するBaseというレイヤー2はOP-Stackによって構築されていますし、Celoのレイヤー2への移行においても利用が検討されています。OP-StackはOptimism同様にEthereumにフォーカスするレイヤー2を構築するためのソリューションであるため、OP-Stackが利用されればされるほど、Ethereumの寡占もより強固となります。
OP-Stack以外にも2023年8月にはPolygonがPolygonCDKというEthereumのレイヤー2構築にフォーカスしたソリューションをローンチしており、こちらもCeloのレイヤー2移行計画において利用が検討されていますし、9月には国内発のレイヤー1であるAstar NetworkがPolygon CDKを利用したEthereumレイヤー2の開発計画を発表しています。
今後も様々なレイヤー2のプレイヤーが同じようなソリューションの提供を目指すことが予想されるため、レイヤー2競争とEthereumのシェア拡大は今後、ますます激化していくものと予想されます。
そもそもなぜレイヤー2なのか

ここまでレイヤー2の活況の理由として以下の3点を挙げました。
レイヤー1の供給過多
Ethereumの寡占
レイヤー2開発環境の整備
しかしこれらは基本的に供給の問題であり、レイヤー2の需要側を説明しないままでは片手落ちです。なぜWeb3プレイヤーはレイヤー2を求めるのでしょうか。
レイヤー2が生まれてきた根本の理由は、当時のブロックチェーンのスケーラビリティの低さにありました。ブロックチェーンは合意形成プロセスの複雑さゆえにどうしても処理速度を犠牲にせざるを得ず、DeFiの黎明期を振り返ると、1回の取引で数万円のガス代がかかったり、トランザクションの実行に数十分待たされたりと、その利用環境は過酷なものでした。
そこで当時、様々な簡易的なスケーリングソリューション方法が試行されましたが、それらはどうしてもデータの安全な利用(専門用語でデータ可用性といいます)や、取引の安全性を大きく犠牲にしてしまうためにあまり普及しませんでした。
いっそのこと、Etheruemのパブリックチェーンをスケールさせるのではなく、その公共性を極端に狭めることで処理速度を向上させるコンソーシアムチェーン(プライベートチェーン)の活用も検証されましたが、こちらも使い勝手が悪く一部の企業主導のPoCで利用される他ではあまり普及しませんでした。
つまりスケーラビリティの問題は、需要という面では常に存在し続けていたといえます。
今になってレイヤー2の黄金期が訪れたのは、開発者らが辛抱強く研究を行い、ゼロ知識証明やRollupというレイヤー2のコアテクノロジーを成熟させ、安全性をかなりの程度担保しつつ、現実的なレベルのスケーラビリティを実現するレイヤー2を構築できるようになった、というタイミングがたまたま最近だった、というしかありません(※)。
かつてはブロックチェーンのビジネス利用はコンソーシアムチェーンこそが本流であるかのような論調も多かったですが、レイヤー2が脚光を浴びるに連れて、パブリックチェーンのオープンな仕組みの上で、いかに効率的にビジネスを行うか、あるいはそのオープンな仕組みを自らのビジネスに持ち込むか、というような議論に移りつつある印象です。
実際、投資効率という面でも、コンソーシアムチェーン上に自社のサービスを載せて、そこにユーザーを集めるよりも、レイヤー2に自社のサービスを載せたほうがレイヤー1との相互運用性などの面で、ユーザーの移行コストや心理的障壁が低くなることが期待できます。
そういう意味ではタイミングだけでなく、すでにユーザーの多く集まっている場所でビジネスをしたい/使い慣れたUXで色んなアプリケーションを触りたい、というWeb3企業とWeb3ユーザーの双方の需要がマッチしていたとも言えそうです。
※レイヤー2黄金期の前夜として、AvalancheやCosmos、Polkadotなどの単一エコシステム内でのレイヤー構造によるスケーラビリティの向上を目指すプロジェクトの存在や、それを意識したEthereumやBNB Chain(旧BSC)の2.0へのアップデート計画などにも本来触れるべきでしょうが、ここでは割愛します。
おわりに
ここまでレイヤー2の興隆について供給と需要の両サイドから説明してきました。
現在は、Ethereumをいかに打ち負かすかというような議論が盛んだった過去とは異なり、Ethereumとの相乗効果を狙うためにどのような技術スタックを選択するべきかという議論がWeb3領域の中心にあります。
今後Web3領域に参入する事業者も、大穴狙いをするのでなければ、レイヤー2によって拡張されたEthereumエコシステムのなかで事業を展開していくのが基本的には妥当でしょう。もちろん目的や理由が明確であるならば、別の技術やエコシステムを利用するべきですが、少なくとも大半のWeb3ビジネスが必要とする「ユーザーの規模」はEthereumのエコシステムが圧倒的です。とりわけ、ビジネス上の理由でアプリケーションだけでなくインフラも独自に構築する必要がある場合には、開発者にとって障壁の低いレイヤー2ソリューションを選択するのが賢明なのではないでしょうか。
Decentierでは適切な技術スタックの選定も含め、Web3事業の広範なサポートをさせていただいております。ご感心のある方は以下のリンクからお問い合わせください。
お問い合わせ
ビジネスのご相談や取材のご依頼など、当社へのお問い合わせはこちらから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
