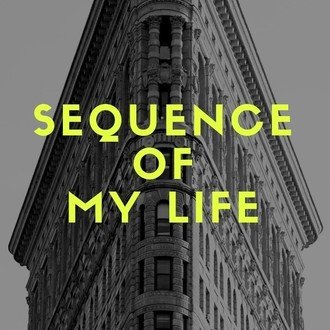つくえ
ごォん、といつものように鐘の音が鳴り響き、私の昼食は終わりを告げた。ゆったりとした時間は元に戻り、私は頭ががァんとなる。鉛色のフォークを皿の上に乗せ、食器を片付けるために立ち上がった。ぞろぞろとすぐに人の列ができて、その一本の長いロープに私も加わる。ひどくのろまな、だらだらとした遅い足取り。ザぁザぁとした足音。いつまで続くのだろう、と無意識にそう思っていたが、実際のところ、二分もかからずに私は片付け終え、他の人々は私が分かる前から分かっていたようだ。
昼食が終わると言うことは仕事が始まるということだ。食堂の出口には役人が二人待ち構えていて、スコップを手渡している。一人が手渡しして、片割れは後ろに立って見守っている。二人とも満足そうな顔をしていた。
「今日の仕事は影掘りだ」と手前の男が言った。「お前たちには自分の影を掘ってもらう」彼はスコップを手渡しながら事務的な口調で言った。
「なんのために」
私が言うと、役人はちらと私を見て、きっぱりと言う。
「質問は受け付けない。お前たちは与えられた仕事をこなしていればいい」
「じゃあそいつの仕事はなんだ。立っているだけだろう」
「こいつはスペアだ。他人のためにこいつはいる」
もういいだろう、と役人は私から意識を外し、スコップの手渡しに集中した。人々はそれを受け取り、ふらふらと列を作り、外へ出て行く。スペアと呼ばれた役人は誰かのために立っている。私はどうしようもないので列の流れに加わり、仕事場に行くことにした。
「影掘り」は別室で行われた。別室、と言ってもほとんど自然の洞窟に近い。ここに来て暫くになるが、仕事で案内される部屋はいつもとても人工だとは思えない。のっぺりとした白い壁の向こうには洞窟があった。広い空間で天井はうすぼんやりと闇に閉ざされている。でこぼこの岩肌がひんやりとした冷気を放ち、固い茶色の土が足元に広がっている。そして至る所で、人より大きく巨大な薪が無秩序に組まれ、私と人々はその前に立たされていた。
「影を彫れ」
役人の言葉は端的だった。その言葉を合図に、薪に火が次々と点火され、洞窟中がとても明るくなった。
炎を背にして影を掘る。特にどう掘れとはいわれていないので、心臓めがけてスコップを突き立てた。周りからも人々が影を掘る音が聞こえる。それは均等なリズムで土を刻み、規則正しい動作で作業をこなしていく。額から滲み出た汗がそれぞれの間隔で勝手に影に吸い込まれ、人々はそれを外に汲み出した。
私は体力に自信はない。あっという間に彼らのリズムから引き離され一人ぼっちになった。腰が軋み始め、指は喘ぐ。背中が膨らんだように張り詰め、足は鼓動に強迫されがくがく震える。後ろの炎は私を急かし、ぱちぱちと爆ぜる薪は私を嘲笑っているかのようだった。
「遅れているぞ」
役人は私の緩慢な動作に目をとめ、「周りに合わせろ」とうながした。
「あのね」私は乱暴にスコップを地面に突き刺す。「目的も分からずに仕事なんてできるわけないだろ」
「お前たちは与えられた仕事をこなしていればいい」
「またそれか」洞窟に私の張り上げた声が反響する。
「仕事に戻れ」
「戻りません」
「お前に罰を与えねばならない」男は冷静に私を見据える。「規則に従わないやつは規則にのっとって罰を与える」
役人は警棒を振り上げ、私に殴りかかろうとした。しかし役人はのろかった。まるで男の体は粘土に覆われているように速さを失っている。ただ、役人の殺気や勢い、洗練された動きはそのままだ。それがひどく不気味だったので、私は恐ろしくなり役人の顔をスコップでしたたか殴りつけると、同時にその体は速さを取り戻し、役人は地に伏し気を失って沈黙した。
(なんてことをしてしまったんだ)
頭から出血しながら気絶している役人を眺めていると、私は恐ろしくなった。役人を傷つけることは規則で固く禁じられている。私はそれを破ったのだ。
(こうなったら後には引けない)
ここで他の人々を説き伏せ、皆で力を合わせれば今の生活も少しは改善されるかもしれない。幸い一連の騒ぎで人々の目は私に向いていた。
「どうだ、爽快だったろう!」いくつもの灰色の結晶が私を見た。「君たちの心の悲鳴を聞いていると、私は胸が張り裂けんばかりだったのだ。無意味で無価値な労働に一日中従事させられ私は死にそうだった。君たちも同じことだろう。こんな悪魔の理想郷のようなところにいたら、いずれ肉体は塵と化し、魂は闇を彷徨う。そう、大人しくしている必要はない。我々の力を思い知らせてやろうじゃないか」
私は気分が高揚して唇がほとばしっていた。しかし、灰色はそのままで、色が変わることは無い。躍起になって声を一段と張り上げる。
「仕事を放棄するぞ!」
すると他の小人々は体を震わせてもぞもぞと動き出した。
「そうだ、その調子だ」微かでも反応があったので嬉しくなる。人々は私の周りに集まり深くうつむいて胸を大きく波打たせていた。「力を合わせよう!」そう言って私が人々に背を向けたのと同時に、誰かの振り下ろすスコップが私の背中を激しく打った。息が詰まり、地面に倒れそうになったが、手が無理矢理私を立たせ、無骨な拳で腹を殴った。ようやく地面に引きずり倒され、嘔吐感に身をよじり、頬に濡れた土埃をまみれさせ、ぼんやりと熱い目玉で上を見た。人々が見下ろしていた。不気味さをまとい、規則正しい呼吸音だけが聞こえる。そして暴力が始まった。蹴る者、殴る者、スコップを使う者、沢山いた。衣服は裂け赤い血が地面を湿らし、飛び散ったいくつは壁や人々の腕や胸に紋様を作る。「やめてくれ!」私は悲鳴を上げる。嵐の夜に吹き荒れる風のような力の奔流には、羊のようにやり過ごすしかできない。羊はやがて屈する。まぶたを閉ざし、自分を深くしまい込んだ。風はまだ羊をいじめていたが、時の流れに沿って役割を思い出し、それぞれの場所に戻っていった。
しばらくすると、霧のように二人の役人が現れた。そろって荷車を押している。一人が荷車を脇へ停めている間に、もう一人が羊を抱き起こして運ぼうとした。けれども一人ではどうすることもできない。
するともう一人が駆け寄り、やっとのことで羊を立たした。羊は足を宙ぶらりんにして不安定に首を垂れている。役人たちはあっちこっちにふらふらしながら、羊を荷車に詰め込んだ。役人達は汗を拭わない。役人達は休まない。重い荷車を押し洞窟を後にした。洞窟の外には変わらず直線の廊下が四方八方に伸び、網目のようになっている。役人達は脳に記されている通りにその網目を進む。役人達は迷わない。レールの上を走っていく。列車のように目的地まで荷車を押していく。詳しい描写は省こう。変化なんてないのだから。
役人達は「ごみ箱」に着いた。ベルトコンベアが上にも下にも空中にも張り巡らされていて、そこに様々なガラクタが乱暴にぶちまけられている。役人達は一本の古いコンベアを選び、そこへ羊を放り出した。重さでコンベアが軋む。コンベアは文句も言わずに羊を乗せ、どこにつながるともしれない暗闇の中へ連れて行った。役人達はそれを駝鳥のような瞳で見送る。
☆
塔は僕にしか見えない特別なものです。人類の英知の結晶であるそれが、緑と生命力に溢れたこのような場所で、空と海をしっかりと繋ぎ、どこまでも聳え立っている様を窓の外から見ていると、この不変が僕にもたらされるのではないか、このまま生きながらえるのではないか、と空想してしまいます。
そんな風に僕が間抜けな顔で湖を眺めている様子をつくえは見逃しません。「何か見えるのか」葉先の朝露のような儚さで問いかけます。
「いいや」
「嘘付け」
「ごめん」
「何が見えたんだ」
「塔が見えた」
「そんなものはどこにもないぞ」
「僕にしか見えないんだよ」
しばらく不毛な問答が続きましたが、同じ病人でも体力の面では僕の方にやや分があります。やがて、つくえは溜息を吐疲れた様子で、ベッドにどかっと腰を下ろし、コトンと横たわりました。
「もしこの病院を抜け出すつもりなら」つくえは枕に顔をうずめ「わたしも連れて行ってくれ」と言いました。
病院内にチャイムの音が響きます。いつものように看護婦が霧のように現れ、僕をつくえの部屋から連れ出しました。天敵の時間です。つくえは食べ物を受け付けません。ですから、こうして一日に何度か天敵を打ち、どうにか日々を過ごしているのです。
僕はやんわりと、しかし頑なに看護婦の手を拒み、部屋から出ました。直前に「約束だぞ」とか細くすがるような声が重い鎖として僕に巻き付きます。逃げるように、振り払うようにしてその場を去りました。
自分の居場所に戻り、僕は電話を待ちます。その間外に意識を向けます。木々が風と戯れ、不安げに揺らいでいました。まだ青い葉がいくつかこちらに滑ってきて、窓を叩きます。僕は窓を開け放ち、彼らを迎え入れました。彼らは飛び込んでくるなり、くるくると、おじぎをして足元でダンスを始めました。
時間通りに電話が鳴りました。受話器を取ります。
「久しぶり」
受話器の向こうで、女が気さくに話しかけます。
「今日はいい日だわ。暑くも無いし、寒くも無い。散歩にはうってつけの日だと思わないかしら」
女のもったいぶった回りくどい言い方には心底うんざりしています。
「そうですね」
「そうよ。でも部屋の電球が今にも切れてしまいそうなのが玉に傷ね」
「そんなことより」女の戯言には付き合っていられません。「僕はどうすればいいんですか」
「船を造りなさい」
断固とした口調です。
「それでつくえが助かるのですね」
「そんなの分からないわ。あなた次第よ」
女は悪戯に笑います。不快感が、黙々と僕の内にブロックを積み上げていきます。
「あなたってお人好しねぇ」狐のような撫で声。「それにとっても残酷」
「彼女の気持ちに気付いているのに」「無関心を装って」「はっきり言葉にする勇気も無く」「怠惰で愚かで油断しているわ」「友達でいたい」「むしろ特別でありたい」「なんて愚か」「素晴らしい感情ね」
どの言葉も僕にとって耳の痛いものばかりです。余計に腹が立ちます。
「何か問題でも」
「事実を突きつけられると開き直る。まるで子供みたい」
クスクスと声が聞こえ、僕の手が震えていくのが分かりました。
「そうやって実は僕はゲイなんだって彼女に開き直ればいいじゃない。そうすれば楽になれる。そこで嘘はおしまい」
「そんなの関係ありません」その言葉はまるで僕以外の誰かが言ったみたいに、すんなりと口から出たのです。「つくえは性別を超えて大切なんです」
「ふーん。ま、いいんじゃない」
女はつまらなそうに言いました。
「いずれあなたはその意味に気付いて打ちのめされると思うけど」
もういい加減限界なので、電話を切ろうと耳から受話器を離します。直前に「あらぁ。とうとう電球が切れてしまったわ」と女の落胆か聞こえました。どうやら光を失ったようです。僕はほくそ笑みました。
僕はほこり一つ無い廊下を横切り、屋上へ向かいます。ここが病院であることを忘れてしまうくらいに静かで、ただの足音も楽器のように弾みます。風がカーテンをさらってはためき、その一部が僕の側面に当たってけざやかな心地良さをもたらしてくれました。
屋上へ続く扉を開くと、陽光が途端に内側に溢れ出して影を削りました。影の彫刻は多様を作り出し、僕のぼやけた後ろ姿を形作ります。外に出るとペンキをぶちまけたような空が広がり、下には平然とコンクリートの床が横たわっていました。
屋上の中央には「船」の材料がぽつんと置かれていました。その大きさからして一人がらくらくと乗れる大きさにはなるのでしょう。僕はその内の一つを手に取り、しげしげと見やりました。もちろん「船」なんて乗ったことはおろか、造ったことなんてある訳がありません。しかし電話の女は造れ、と言いました。
鼻から大きく息を吸って材料の傍らに座ります。ジグゾーパズルのようなものです。そう思うことにしました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?