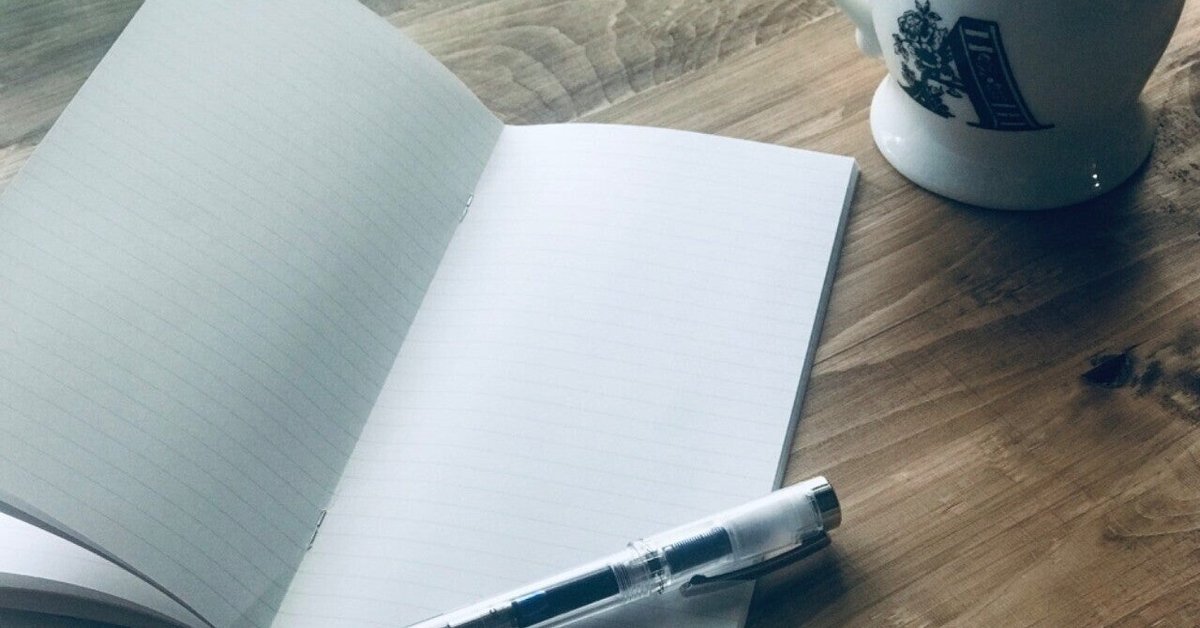
私に何ができるかわかるということ
小さい会社だけれども何人か社員が出たり入ったりする中で、社員に出て行くまでに自分に何ができるかわかってもらいたいと考えるようになりました。うちが提供できるものとしてはそれが一番生きていく上で役に立つだろうと考えたからです。
自分に何ができるかわかるということは自分が社会に対し価値を提供する手段(武器)がわかるということなので、格段に仕事がしやすくなります。社会正義の観点を外してみると、実際の社会が必要とする人というのはドライに言えば役に立つ人間だということです。役に立つということは何かを通じて価値を提供できるということです。
自分に何ができるかがわからないなら、それは仕事をする上でとても不利なことです。何を売っているかわからないのに何かを売らないといけない状況に似ています。普通はそれを欲しがっている人を探してその人に商品を売るわけですが、自分に何ができるか分からないということは、誰が自分の顧客かもわかりません。顧客がわからなければ、どこにいけば自分が役に立ち活躍できるかもまたわかりません。これができるのでこのぐらいをいただきたいという交渉もできません。
自分で何ができるかわかるということは、二つの段階に分けられます。できるようになる、できていることが何なのかを理解して言葉にできる、です。私はよく引退した選手にこういう質問をします。
「競技名を使わないで自分がやってきたことを説明してください」
選手は戸惑います。長く競技をやってきた選手が対象なので何かはできています。ところが「陸上競技をやってきた」「ピッチャーをやってきた」は言えても、それは具体的に何なのかがわからない。競技名というのは職業や活動の一般的な大きな枠組みです。その中で自分がやってきたことや提供してきた価値があるはずで、それを理解しないと何ができるかがわかりません。人によっては目標を立てそれを達成すること、仲間と役割分担しうまくいかせること、人を感動させることと言ったりします。大事な点はそれを言えるようになることです。もうちょっと欲を言えばそう意識しながら行うスポーツはもう少し汎用性のある能力を高めてくれていたはずです。
笑い話で「何をやってきましたか」というと「部長をやっていました」と答えるものがあります。これは要するにあるシステムの中に組み込まれて機能していたものの一体自分が果たしていた役割は何で、そこで意識して提供したユニークな価値は何なのかがわかっていないということだと思います。当然欠如していれば普段の仕事の中でも、自分なりに考えて価値を提供することはしていない可能性が高いです。
この視点を手に入れる上で重要なのは抽象化です。つまり「陸上をやっていました」から、「目標を立て努力していました」になり、さらに言えば「目標を立て自分自身を把握し理想とのギャップを埋める作業を行っていました」ということになります。抽象化ができれば、何ができるかがわかりやすくなります。自分が何ができるかわかるというのは抽象化能力に、視点の多様さに、自分自身を客観視できるメタ認知能力に影響されます。ですから、説明する様子を見て、相手は能力を見てもいます。
どのような技能を持っているかと、何ができるかはまた別の話でもあります。技能があるのは大事ですが、それを使いこなさないと役に立ちません。ここでいう何ができるかわかるということは自分の技能を自分なりに考えて使う方法がわかるということです。技能は持っているけれどもどう使っていいかわからない人は、自分の使い方を人に委ねることになると私は考えています。それでもまあ生きてはいけますが、自分の道を切り開くことはできません。
自分が何ができるかわかるようになるために具体的にできることとしては、結局良い質問をもらう機会と、要するにそれはこういうことだよねという言語化の機会をもつこと、自分が何をしているかを知ろうとすること、ではないかと考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
