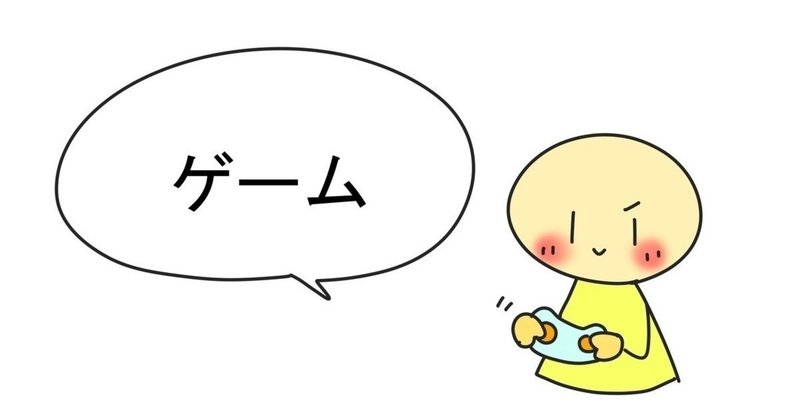
ゲームの選び方
この長期間の休みで、子供たちがゲームを長時間することを心配されている親御さんに少し考えていることをお話しします。私は小学生ぐらいからファミコンをやり始めた世代でして、その後はずっとゲームと共に生きてきました。少しはゲームに親しんできた身としてその弊害と利点をお話しします。
まず、どのゲームを選べばいいかの判断に、重要なのは楽しんでいるか、楽しまされているのかの違いです。楽しんでいるのであれば弊害は少なく利点もあります。一方で楽しまされているのであれば弊害は大きいです。違いは主体的に考える(推論する)行為があるかどうかです。私もその基準で息子のゲームを決めています。
人間は反応に弱い生き物です。ピカピカ光ったり刺激があるものが好きです。人間が夢中になるかどうかは要するに報酬の仕組みで決まります。この報酬の仕組みを自分を観察しながら組み立てられる人は主体的に考えられる人間です。うまくいけば、自分の反応パターンを知り、うまく外部環境を組み立て自分を連れて行きたい方向に連れていくことができるようになります。一方外部の報酬に操られる人間は、基本的に受動的な人間です。依存しているかどうかも私はこれで見ています。
社会における仕事上の優秀さとは、ゲームのルールと、目指すべきゴールを察知(決定)し、試行錯誤しながら理想に近づけていく能力だと私は考えています。パッと見たときに、これを押さえた方が勝ちだとわかる人間とわからない人間がいます。主体的に考える人間はゲームのルールがわからない複雑な状況を喜びますが、受動的な人間は複雑な状況で混乱します。
自分という存在はどのような報酬に対しどういった反応を示すのかを理解し、この自分すら含んだ環境をどう設計すればこのゲームは勝てるのかを考えることが大切です。私はこれをセルフコーチングと呼んでいます。私はこれをゲームをやりながら手に入れることができると思っています。
具体的には繰り返しさえすれば勝てるゲームではなく、混沌として勝ちパターンが見えにくいゲームを選んでいます。また、そもそもの作りたいものすら自分で決めないといけないマイクラのようなものは推奨すらしています。横顔を見ながらうまくいかない時に考えているような仕草をするものは基本残しています。一方、ボーとしながらでも進んでいくものはこっそりアプリを消しています。
私がゲームから得たものは自己把握と勝ちパターンを考える力です。どんなゲームが好きかで自分の性質がわかります。友人と比較して人と競い合って相手を倒す格闘ゲームより、一人で考えて進めていく戦略ゲームが好きだった経験が、自分は一人で考えたいタイプなのだろうと理解する一つのヒントになりました。失ったものは時間です。決めた時間だけやれればいいですが、それをなかなかコントロールできないのがゲームの難しいところです。これは試行錯誤しかないですね。
城を構築していくゲームの中での話です。赤いクリスタルを使えば一つ一つの建物を作る時間が短縮できるのですが、一定量貯めてから建築家を一人増やすと人手が一人増えるので最終的に合理的だということを息子に教えていました。久しぶりに見ると最近それを少し理解していました。私はこれも一つの学びだと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
