
Ghoti
Ghotiと書いて何と読むかご存知でしょうか?
これ、魚っていう意味らしいですよ。
そうです、フィッシュ(fish)と読むんだそうです。
「は?」
て思いますよね。僕も思いました。
いや、「ゴッティ」やん。て思いました。
ちゃうらしいです。フィッシュらしいです。
誰がなんというと、フィッシュらしいです。
絶対ゴッティやと思うんですけどね。
調べてみると、『英語の綴りの不規則性を示すために作り出された言葉』とのこと。
は?
え、今の意味わかりました?
要するにあれです。
laughって書いて「らふ」って読みますよね
womenって書いて「うぃめん」って読むし
stationって「すていしょん」って読みますやんか
散々英語に触れてきた今でこそさらっと読めますけど、そういえばghはf音やし、oはi音やし、tiはsh音を表しているわけで、
「英語は表音の言語で綴りと発音が一致するんですよね?ほななんでっか、合体させてghotiで書いたら「fish」って読みまんのか?」
という昔のエラい人が言った屁理屈から生まれた言葉らしいです。要するに自然に存在しないものをロジックで人工的に作りあげたと言うわけです。ポケモンで言うところのミュウツーみたいなもんですね。
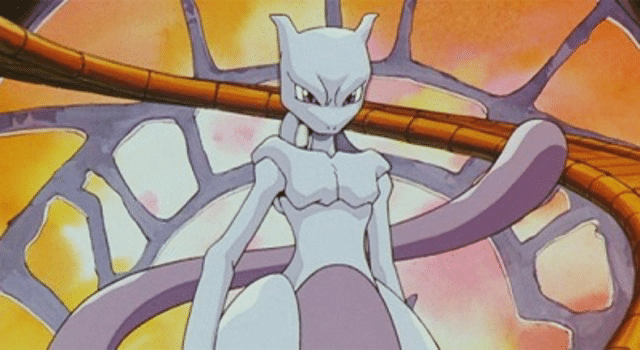
「誰が産めと頼んだ。誰が作ってくれと願った。私は私を産んだ全てを恨む。」
あ、これはミュウツーの名言です。
ミュウツーの逆襲ってご覧になりました?
人間でもないけどポケモンにもなりきれない存在というアイデンティティに苦しむミュウツーが人間たちに逆襲する話なんですけど、ものすごい深いです。よくあれを子供向けに映画化したなと思うほどに。
結局ミュウツーはこの世界に馴染めずどっか消えたし、ghotiもいくらフィッシュと読めるからと言ってfishの代わりに使う人はいません。どうやら、机の上だけで作られたものは、この世界にフィットしないようです。
今の世の中はあらゆる知識が体系化され人間の手の中にあります。人間の論理的思考力も著しく向上しました。自然界に存在し得ないものを、人間は知識の組み合わせで作り出せるようになりました。あらゆる産業で"Ghoti"が生まれています。
サラリーマンで、よくいるじゃ無いですか。
いろんなフレームワークや理論を持ち出して、お勉強の世界の話ばかりする人。特に若い人。お勉強は結構なんですけど、教科書と現実のビジネスシーンの間には、それはそれは大きな溝があることを、誰か教えてあげて欲しいものです。しかし会社のおじさんたちもそういう横文字の名前の理論をソラで唱える若者に右に倣えしてしまう。そうやって生み出された"Ghoti"的な経営戦略が後を断ちません。結局、現実世界にはフィットしない、という意味です。
「誰が産めと言った。誰が作ってくれと願った」
会議室からそんな声が聞こえてきそうです。
その点、スポーツやアートの世界ではほとんど"Ghoti"的なものは生まれません。
なぜか?
いかなる種目においても、一定の理論はもちろんあります。しかし、スポーツやアートの世界では理論に意味がないこともみんな体感的にわかっているのです。現実世界という文脈と、机の上で整理された理論をいかに融合させるか、どうやって基本の理論から外してやろうかと競っているのがそれらの業界だと思います。
もっと卑近な例でいうと、ファッションなんかもたぶんそうなんじゃないですかね。おおよその基本形があって、それをどうやってハズすかでおしゃれかどうかを測っているような印象です。
ちなみに「おしゃれ」を漢字で書くと「お洒落」
ですが、この洒落とは、日光や風に晒されて風合いが落ちることを表すらしいです。つまり、あるべき形、基本の形から、ハズれる様子を指します。
さらに面白いのは、ダジャレも漢字で書くと駄洒落。洒落が入っています。
お笑いが好きな人は体感的に理解してもらえると思うのですが、お笑いも極論を言えば「基本形をいかにハズすか」というこの一点を様々な手法で表現しているだけなのです。会話の流れで特定の発言を連想させておいて、その期待からズレた回答をする、というのがミソです。
ダウンタウンの漫才の名作「誘拐」にこんな掛け合いがあります。
松本:「お前んとこにな、
小学2年生の息子がおるやろ」
浜田:「は、はい、いますけど・・・」
松本:「うちには6年生がおるねん」
(浜田:その大きな手を駆使して怒涛のツッコミ)
最もわかりやすい例だと思います。「誘拐犯といえばだいたいこういう感じのことを言ってくるだろうなー」という基本の型に対して、ハズす。
ズラす、期待を裏切る、など色んな言い方はありますが、笑いを誘うという営みは要するに、基本の型をハズすという作業に他なりません。そしていうまでもなくお笑い・演芸もアートの一種ですよね。
というわけで、
元の"ghoti"の話に戻ってくるわけですが、
この「基本理論を学び、自分の物にし、それを外す。」といういろんな普遍的に求められる振る舞いを一言で表す言葉が、武道の世界にもありました。
「守破離」です。
今風の言葉で解釈すると、
ルールに則り、それを破壊し、それらを経てオリジナリティが確立されてゆく。というその道の極め方を端的に表した言葉だそうです。武道経験者は一度は耳にしたことがあるかと思います。
これも同じことで、セオリーを否定していく姿勢は、どの業界においても普遍的に美学とされていることがわかります。
さて、だらだらと何が言いたかったかというと、
"ghoti"が教えてくれるのは、机の上だけで作られた何かは実生活では必ず役に立たないということ。むしろそういうものを現実世界の文脈の中でどう解釈していくか。基本の理論を自分の手で握り直して、万物流転の現実世界に当てはめていく。その握り直し方にあなたの手腕が問われる、というわけです。
そういう意味で"ghoti"は『悪い例の良い例』を表しているのだなと、私は解釈しましたとさ。
というわけで、
「Ghoti」
とかけまして
「こういう理屈っぽいことつらつら言う男」
と解きます。その心は、
どちらも、
『みんなきっとよめない(読めない・嫁無い)』でしょう。
お後がよろしいようで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
