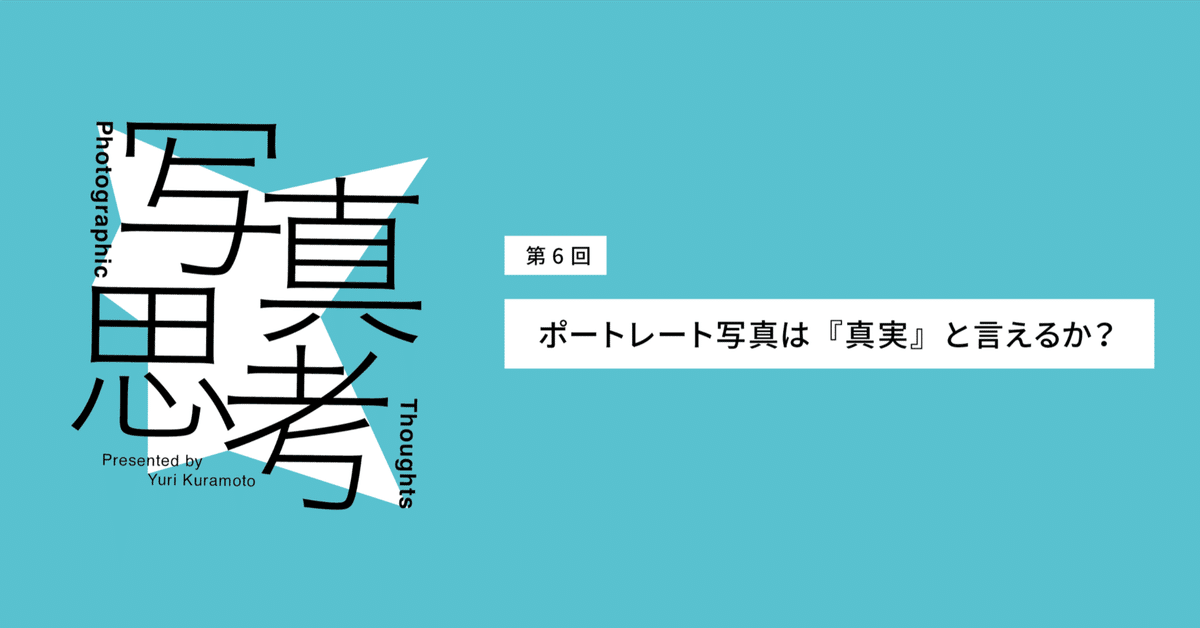
ポートレート写真は『真実』と言えるか?
ポートレート写真は『真実』と言えるだろうか?
一般的に写真は『真実』を写すメディアであると認識されていると思う。写真表現は『真実=世界がありのままに写る』という特殊な性質ゆえにこれまで独自の発展をしてきたのだろう。写真術が興った初期こそ、写真も伝統的な絵画表現の範疇に収まってはいたが、人々は次第に『世界がありのままに写る』この特殊性に気づき始め、ついには絵画から独立していった。そしてこの性質は、今日でもなお写真術の根幹に揺るぎなく立ち続けているものである。今回私が書いていく話は、この写真を写真たらしめているこの性質を念頭に読み進めてほしい。
写真表現の中でも特に人気が高いカテゴリの中に『ポートレート』がある。ポートレートとは要するに『人』がメインで写った写真のことである。ポートレート写真を考えるとき、私はいつも『真実が写るポートレート写真は存在しないのではないか』という疑問が浮かぶ。これは私が前提として挙げた『世界がありのままに写る』という写真の性質から考えると全く矛盾している疑問だ。この矛盾はつまり、『ポートレート写真の被写体が、カメラを向けられた時点で自分が『被写体』になることを自覚してしまう』ことに起因するものだ。これはカメラや撮影者の存在が被写体の自覚状態を確実に作り出してしまうということであり、誰かのポートレートの撮影を行なった時点で被写体の『ありのままの真実』は既に消え去っていると言えるのではないだろうか。
これは写真術最大の矛盾だと言える。この世で唯一、世界がそのまま写る不思議な機械を使って、目の前の人の完全なるありのままの姿を写そうといくら努力したとしても、その機械を向けてしまったが故にその人が纏っていた真実はその瞬間に剥がれ落ちてしまうのである。

この疑問について、写真家 桑島智輝の『我我』を例にとって考えてみる。
これは写真家 桑島智輝が女優であり妻である安達祐実との私生活を赤裸々に撮影した非常にプライベートで日記的な写真集であり、写真からは普通の夫婦の間に保たれる絶妙な距離感と、その距離感にあえてレンズを向けた桑島のその人への愛情を感じ取ることができる。そして安達もその眼差しに応えるように眼差しを送る…。そう、ここに見ることができる『赤裸々』はふたりの『真実ではない』のである。『真実を装った日常劇』と言えるかもしれない。赤裸々な関係値を見せるように作られた写真集だが、そこには『カメラを向ける』と言う作為と『その作為に応える』と言う被写体の自覚が前提として存在している。それが顕著に表れている写真が、泣く安達をアップで撮影した写真。仮にこれが『真実である』ことを目指す写真集とすれば非常に不思議に映る写真である。泣いているパートナーにカメラを向ける桑島も、泣いている瞬間を写真に撮られることを受け入れる安達も、お互いがその瞬間は撮影者として、被写体として存在しているように見える。その時は夫婦と言う関係値からは一瞬距離を置いていると言えるかもしれない。つまるところ、すでにその写真から『夫婦の日常として』その場に存在したであろう真実は消え去ってしまっているということだ。(本当の意味で夫婦の関係の真実を撮ろうとすると、そもそもレンズを向けることができないのではないか。矛盾しているが、カメラを向けると撮る、撮られる自覚が発生してしまうからそういうことになるだろう。)
ポートレート写真のためにカメラを持つ、ということはもともとなにもなかったその空間に極小劇場を急に設置するようなものだ。被写体と撮影者がお互いを認識している限り、その舞台では作られた『お話』が演じられることになる。このような面から逆にいうと、ポートレート写真は『被写体の真実を写す』というミッションを永遠に達成できないもどかしさがあるからこそ、写真家を惹きつけるし、同様に見るものも惹きつけるのかもしれない。私の中にもまだ答えがなくて申し訳ないが、ここまでを踏まえて『ポートレート写真は『真実』と言えるだろうか?』と、もう一度問いたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
