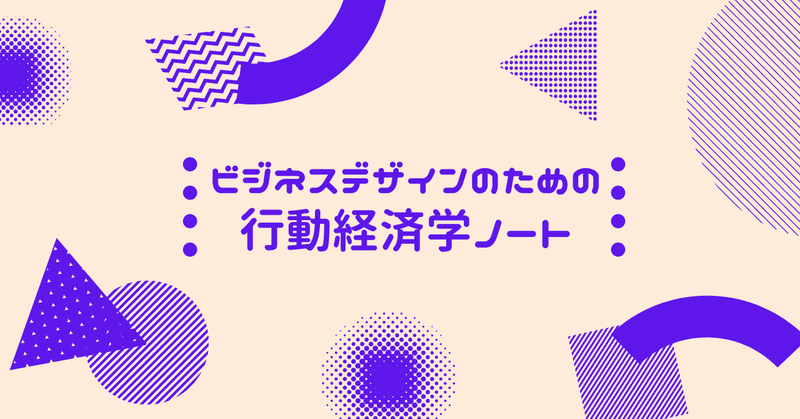
#04 読書録「ビジネスデザインのための行動経済学ノート」
こんにちは。webディレクターの金子大地です。
今回は「ビジネスデザインのための行動経済学ノート」の読書録。
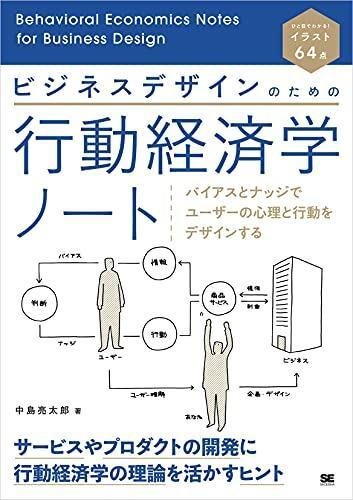
早速ですが余談
この読書録は、そもそも自分が「本を読んでも2日後には中身を忘れてしまう問題」を解決したかったのがきっかけ。
それが何のミスか、今期(2022年10月〜)の個人目標に「2023年9月までに20冊の本を読んで、それを読書録にまとめます」と書いていた。人間の勢いって怖い。。(一応書いておくと、決してミスではない)
というわけで、その1冊目として書いていく。
もう一つ余談
ちなみに今回この本を読もうと思ったきっかけだが、社内での雑談で「行動経済学とか勉強してみたらどう?」という話が出たことだった。ある程度、体系化された人の行動心理を学ぶことで、ウェブサイトの制作や運用、コミュニケーションに何かしら役立てるのではないだろうか?といった具合。
とりあえずネットで色々と見ていたら「シンプルにおもしろっ!」となり、その日の帰り道に本屋で購入。
行動経済学の本って色々出ているが、なんとなく図解がたくさんあってわかりやすそうだったのと、全体のデザインが好きでこの本にした。本を選ぶ理由なんてそんなもん。多分。
というわけで本題
商品やサービスを提供する会社は、つい完璧なユーザー像を想像しがちです。「機能はたくさんあった方が、ユーザーにとっていいに違いない」「論理的に設計しているから、ユーザーが間違えるはずがない」と、このような思い込みをしてしまいます。その結果、ボタンが多すぎて使いこなせない商品や、難しすぎてエラーが続出する申請書類や操作画面などが、世の中には数多くあふれています。
ウェブサイトを作る人間として、耳が痛いお話。これに似たよく聞く誤解として
ユーザーは一言一句、文字を読んでくれる
目立つ色でボタンを置いておけば、ユーザーは押してくれる
メルマガは月に1、2回送っておけば読まれる
こんなものもある。自分がウェブサイトを見る時は文字なんてほとんど読まないのに、なぜか自分が作る側になると「読んでほしいから書き連ねたい!!!」となってしまう。
完璧なユーザーなんてこの世に存在しない。まずはこの前提を持つことが大切。
行動経済学は、ユーザーである人を起点としています。実際のユーザーをよく観察して、使い方や気持ちを想像できれば、受け入れられる商品やサービスをつくることができるはずです。デザインの取り組みでも、最初にユーザーはどんな人かを考えて、そこから商品やサービスを思い描きます。どんなにカッコよくても、ユーザーが使いにくいと感じるなら、それはよいデザインとはいえません。このように、行動経済学とデザインは、機械のような相手ではなく感情を持ったユーザーの視点に立って考える、という共通点があります。
行動経済学とウェブサイト制作に親和性を感じる理由を示した文章だと思う。すべての起点はユーザーである人である、行動経済学を学ぶ意義を強く感じた一文だった。
仕事や試験などでミスを防ぐためのトリプルチェックは、実はダブルチェックに比べて、同等かむしろ品質が下がる可能性があります。1人に比べて複数品が関わると、責任意識が弱くなってしまうからです。他にも、意思決定をみんなで行おうとすると無難な結論になりがちで、決定の質が落ちる集団浅慮に陥ることもあります。これらはいずれも、1人が主体的ではない傍観者の立場が影響しています。
行動経済学に「傍観者問題」という理論がある。端的にいえば「見て見ぬふり」だ。集団の中で人は自主的な行動をとらず、他人に任せてしまう傾向にある。
何か物事を決める時や会議を開く時、参加者が多い方がより良い意見が集まると思ってしまいがちだが、どうやらそうとも言い切れないらしい。誰かが考えてくれる、発言してくれるから自分は関係ない、そんなふうに思ってしまったことがある人は少なくないと思う。私自身も経験がある。
人に本気でその物事に向き合ってほしい時は、少人数制をとることも一つの手かもしれない。
RIZAPは短期間の「2ヶ月で結果にコミットする」という広告で、注目を集めていました。これが、もし1年だったら印象は変わります。〜略〜サービスの内容にもよりますが、なるべく短い期間でリアリティのある結果を示すことは、現在バイアスの心理のはたらきかけに効果的です。
人は将来が不透明だと、すぐ目先にあることを優先してしまう生き物。例えば明日10万円もらえるか、1年後11万円もらえるかでは、前者を選んでしまいがち。
逆を言えば、短期的な成果を明示することは非常に重要。一概には言えないが、Web活用で成果が出るまで1、2年かかることは少なくない。「すぐに成果が出るものではないので、長い目でコツコツがんばりましょう」と言われても、理解はできるが納得はできないクライアントの気持ちもわかる。
目標設定、成果の見えるタイミングは中長期のものはもちろん、短期的なものも設定した方が良いと思われる。
MAYA理論はこの「先進さ」と「馴染み」を組み合わせて、「人は驚きを与えられたい一方で、心地よさを望む」というユーザーの心理を刺激します。先進的すぎると不安を抱くけど馴染みすぎると飽きてしまう、という絶妙なバランスで成り立っています。
MAYA理論とは「Most Advanced Yet Acceptable」の略で、「最先端だけど、まぁ受け入れられる」という意味。デザインや技術、考え方などさまざまなものにおいて共通している。
時代の最先端すぎると取っ付きにくいけど、ありふれすぎると刺激的でない。この両方のバランスを考えることが重要。新しさの中に懐かしさ、古きものの中に目新しさ。
心理的リアクタンスは、ユーザーの自尊心にはたらきかけるためのトリガーです。否定ばかりでは疲れてしまうし、嫌な気持ちになります。むやみにあおったり禁止したりするのではなく相手の意思を尊重して、本来の「自己効力感を肯定するもの」という意味に立ち返って、活用方法を考えてみましょう。
「リアクタンス」は「抵抗」という意味で、「心理的リアクタンス」はダメと言われると反抗したくなる人の気持ちを指す。ダチョウ倶楽部でいう「絶対に押すなよ」である。
身近な例でいうと「おひとりさま2点まで」「絶対に見ないでください」的なやつだ。LPとかのファーストビューで使われていたりする手法。見覚えがある人も多いと思う。
人が反抗したくなる理由の根本には「自分のことは自分で決めたい」という人本来の特性がある。これは生まれたばかりの子どもにも備わっている。
ユーザーとは「あなたの意思を尊重しています。決定権はあなたにあります」というコミュニケーションをとることが望ましい。
心理的リアクタンスはその前提の上で上手に使う必要がある。言いすぎには注意が必要。自分の意思を蔑ろにされているように感じさせてしまい、むしろ逆効果。
ついさぼってしまいがちな勉強や、つまらない事務作業、やる気を出して楽しんでもらうために認知的不協和を使ってみてはどうでしょう。本人は「つまらない」「意味がない」と思っても、それに対して「さすが!」「すっごい助かる!」と伝えると、認知が変わるかもしれません。アカウント設定など、面倒と感じる操作に対しては、大げさなくらい褒めてみましょう。
これもめちゃくちゃ大切。過度に褒めるのは逆効果になるが、それでも「褒める」はコミュニケーションにおいて超重要。何かしら指摘したい時も、まず褒める。頭ごなしに指摘したり否定したりしない。それだけで人は心を閉ざしてしまう。「この人には何も言わないでおこう」という心理が働く。
ウェブ制作においても、特にディレクターは誰かに何かをお願いすることが仕事の一つ。対社内でもそうだし、社外でもそう。例えばクライアントにコンテンツを書いてもらう。どうやったら書いてもらえるか、色々なアプローチはあると思うが、「褒める」は欠かせないはず。大事。本当に。
ビジネス側の理論で考えた商品やサービスが、実際には意図した通りに使ってもらえない、といったことはよくあります。その要因の多くは、ユーザー側の目的があまり考慮されずにデザインされているからです。あなたが、何か企画や提案をしようとしているなら、まずユーザー側とビジネス側の異なる目的を、それぞれ書き出してみましょう。そして、2つの異なる目的を満たす解決策は何かを考えてみましょう。
仕事には2つの視点がある。
1つは「ユーザーにとって嬉しいことは何かを考える視点」
もう1つは「商品やサービスを提供するビジネス側の人が、ユーザーに起こしてほしい行動は何かを考える視点」
そして引用文にも書いてあるように、この視点は多くの場合、一致しない。ビジネス側がユーザーに起こしてほしい行動が、ユーザーにとって嬉しいこととは限らない。当たり前のことではあるのだが、ビジネス側は往々にしてユーザーを置いてけぼりにしてしまう。
この2つの視点をどう結びつけるかが大切であり、頭の使いどころとなる。
例えばハエの絵がついた男性用トイレがある。ハエに気がつくと、ユーザーは思わずハエをめがけて当てたくなる。ユーザーにはただ楽しいからやってみたいという目的がある。
一方でビジネス側には、衛生的に使ってもらいたいという目的がある。2つの目的は異なるが、ハエの絵という一つの解決策が両者の目的を結びつけている。
私たちはウェブを通して「ハエの絵」を作り上げなければならない。
まとめ
本の表紙にもあるように、サービスやプロダクトの開発に行動経済学の理論はヒントになり得ると感じた。思考の出発点が「ユーザー」であるところは、ウェブサイト制作とも近しい。
またウェブサイト制作に限らず、人とコミュニケーションをとる上でも役立つ知恵が詰まっているとも思う。ディレクターとかは特に学んでおくとよさそう。

個人でTwitterをがんばっています。よかったら覗いてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
