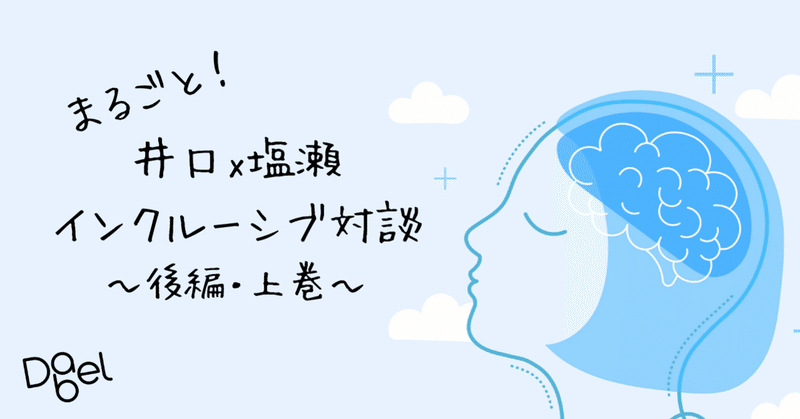
イグ塩インクルーシブ対談後編【上巻】
インクルーシブのDabelアンバサダー、京都在住のAkemi(@MaoThanks)です。読み応えがあると好評をいただいている前編に続き、井口x塩瀬対談、後半も、まるごと!解説付きでお届けします!

前編まで
タカさんがDabelの利用者の獲得に悩んでる中、突然、ひとりのユーザーとの出会いから、視覚障害者というリードユーザー達の存在を知り、インクルーシブという考え方にたどり着く。その研究をされているのが、以前にご縁のあった京都大学の塩瀬先生であったことから、Dabelでの対談が実現しました。Dabelの開発舞台裏を垣間見れる対談、お楽しみください!
●用語の説明●
インクルーシブというのは巻き込むとか、包括するという意味。ここで話されているインクルーシブは、視覚障害を持つユーザーが多いことから、そうしたユーザーも包括できるデザインや、ユニークなユーザーとの関係性などについて話しています。
あまりの濃さと長さに息切れする!というご意見をいただいたので、息継ぎできるように、後編は3部に分けてお届けします!
「お助けモード」では投資家は刺せない!

Akemi:対象者母数で見ないことの大事さにもうちょっと触れたいなと思って、インクルーシブデザインを考える上で、キー入力などに障害がある人向けのタッチパッドが、iPhoneのマルチタッチになって世界を大きく変えたり、視覚障害者向けの製品開発が健常者に向けても、大いに普遍的価値があったとか。例えば、マザーハウスさんが乳がん経験者の方向けに優しいバッグを作ったら一般の人にも優しいから大ヒットしたような。
Taka : チャレンジし甲斐のある課題でして。やっぱりシリコンバレーの投資家とかにもピッチするんですけど

これだけHearableが普及して、AirPods Proがめちゃめちゃ売れて、その Audible のソーシャルネットワークって世界に絶対普及するよねみたいな話をするんですけど、そのブラインドの方に向けて頑張って作ってるんですよって話がなんていうんですかね、「ユーザー少ないじゃん!」てなっちゃうんですよ、やっぱり。
ていうのと、もう一個は周りに(視覚障害者が)いらっしゃらないから想像できないらしくて、「ふーん」で終わっちゃうんですけど。そのなんでしょうね、確かにその Audible(オーディブル) とかHearable(ヒアラブル)に対応する上でブラインドの方ってある意味一番先端を走ってるので。
エクストリームユーザー、どう付き合う?
Taka:ヒアリングしてフィードバックを受けて、製品を作っていく上では、最高のパートナーかなと思ってやってるんですけど。それが、その実は、普遍性があって、72億人にメリットがある話なんだっていうことを、僕らが十分説明しきれてないっていうね。
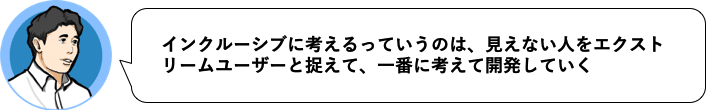
Shiose : そうすね。だからバリアフリーデザインもユニバーサルも、大半は多分障害対応だと思われてる節もあるので、メーカーからするとやっぱりマーケットの小さい所を狙ってると思われるんだと思うんすよね。
インクルーシブも、普及当時は多分そうで、例えばさっきの視覚障害のある人、日本だと視覚障害手帳持ってる人、30万人ぐらいなんで、そうするとやっぱ規模が桁として小さいと見られるんですよね。
でも、インクルーシブに考えるっていうのは、見えない人をエクストリームユーザーと捉えて、一番に考えて開発していくので、究極見えない人にとっては解決しない課題もあるんですよね。
危ないカーナビを安全にするアイデア
Shiose:例えば、カーナビゲーションのデザインとかで考えると、見えない人は、自動車が直接は運転されないから利用者ではないんだけど、助手席でカーナビめっちゃ楽しみにしてる人とかいて。カーナビで次どこどことかでそこで間違えたドライバーとのやり取りも含めてずーと話を聞いてる人がいるんだけど。
それって、結局、見えない方でもカーナビで今どこどこに着いたって事がちゃんと期待化も含めて分かるような音声で、ドライバーにとっていうと視覚情報を使わずにカーナビが見れることになるんですよね。
日本のカーナビってすごく特殊でやたらカラフルで3D使ってってやるんですけど海外のやつは矢印だけなんすよね。

で日本だけすごく特殊に視覚効果に至ってるんで、すごい余計危ないんだと思いますけど、音声でちゃんとドライバーをナビゲートできれば、こんなに安全なカーナビゲーションて存在しないわけなんですよね。
Taka : そっかぁ、なるほど。
Shiose : だから見えない人にとってどこに行くかってのが理路整然と伝わる、情報として上からシーケンシャルに伝わるように伝えることができればドライバーも視覚情報を使わずに運転できるカーナビができることになるんで。
そうなると、エクストリームユーザーとしての ビジブル な(見える)人とインビジブルな(見えない)人の考え方の違いを考えると、避けてた見えない人、特別な人だと思うから、そこで出来上がった成果が特別な人のためのものって思うんであって。
Taka : はいはい
●用語の説明●
シーケンシャル:シーケンシャルとは、順次的な、逐次的な、連続的な、一連の、などの意味を持つ英単語。 ITの分野では、対象が複数ある場合に、並んでいる順番に処理することや、連続して立て続けに処理することを意味する。
Shiose : もともとベーシック、自分の中に持ってるセンサーは一緒なので使い方の違い、修練した、使い方の違う人だって言えば、そのユーザから習うだけだからエクストリームに音を使いこなしてる人達から僕たちが学んでるっていう姿勢だと思う。
Taka : 説明の仕方でかなり変わりそうっすよね。
Shiose : そうそう。助けてあげるって所から来てるから、すごい福祉の分野で片付けられてしまうと思うんですけど、製品としての機能を最大限引き出そうとした時に一番音を巧みに使っている人たちに習うっていう。
Taka : なるほど、なるほど
Shiose : そう考えれば極めて真っ当なデザインロジックだと思います。
片仮名の「クレーム」から逃れられない悩み

Taka : 塩瀬さん、すいません、その流れでちょっと民族性って言っていいのかどうかわかんないすけど国民性って言っていいのかわかんないんすけど、そういうフィードバックをする側のモチベーションというかDESIREについてちょっと聞きたいんですけど。
何かアメリカで(Dabelの中で)タウンホールって隔週でやってんですよ。で、その、要するにバージョンアップした内容とか色々アップデートをお伝えするんすけど、そこで鬼のように(笑い)笑っちゃうんですけど、ものすごいストームって感じで、プライベートメッセージ投げたい!、とか、バイノーラル早くやれよ!とか、エラーで落ちるとか、ちょっともう殺す、とか。
タウンホールとは
Dabelとユーザーをつなぐラウンジ。ダベル市民の公聴会のようなもの。英語と日本語、別々に、ほぼ隔週開催されている。
CEOのタカさんと、彼の右腕とも言える日本生まれの昭和が好きなベントン(Dabelマーケティングディレクター)がホストする。毎回特に製品アップデートの共有と様々な質疑応答の機会となっている。

Shiose : (笑)
Taka : Co-Hosting早くやれ!とか、そのすごいんですよ。
それはね、もちろんありがたいんですけど、なかなか日本では、そうならなくて、みんな優しいし、Takaさんもがんばってるからほどほどにしとこうか、とか許してくれるんで。
アメリカにしたって言うことが、何て言うのかな、言い方悪いですけどその悪意ではないじゃないですか、その人も相手を傷つけようと思ってるけど何でもないのですけど、その、デマンドを伝えることに対して、すごくなんかね、その公平性っていうか、大事だと思ってやってる節があって。
その辺のモードというか、スタイルの違いっていうのはどうなってるのかって、ちょっと非常に気になってるんですけどね。ちょっとそのインクルーシブとは関係ないんですけどね。
●用語の説明●
Co-Hosting
Dabelのラウンジは、今、その配信を立ち上げたユーザーひとりがホストをしている。Co-Hostingというのは、そのホスト以外にも、配信をマネージするホストという意味で、メインのホストが席を外したり、ネットの接続が不安定な時などに便利。
Shiose : いや、めっちゃ関係あると思いますけどね。
Taka : あ、そうですか!
Shiose : 巻き込まれた側にとっての問題もあって、日本だとそれは「クレーム」という言い方になるんですよね。
Taka : あ、そうそうそうそう!それです!炎上っていうじゃないですか
Shiose : で、クレームもカタカナのクレームなんですよね。英語の方のクレームは「主張」っていう意味じゃないですか、訳すとね。
Taka : そうですね。特許の申請もクレームって言いますからね。
文化の違いから見えるインクルーシブデザインのポイント

Shiose : クレームは主義主張だから、「自分が伝えたいことを主張する」なんだけど日本はカタカナのクレームがすごく踊るので、「文句」って訳されると思うんですよね。だから、文句を言うひとっていう。内閣府がやっている若者調査ってので、13歳から29歳ぐらいの人の国際比較ってのがやられると、いろんなスコアは日本人の子は高いんですけど、例えばアメリカ人の子とかフランス人の子とかいろんな国の子と比較すると、現象を自分で変えられるかもしれないって比率が日本は突出して低くて。
Taka : おぉ、まじか。
Shiose : (日本の若者は)ルールは与えられるものでルールは変えられるものだと思ってないっていうのもスコアが突出してるんですね。
Taka : まじかー。なるほど。そっか。
Shiose : つまり、(日本では)何かを変えるために自分が主張するっていう経験が学校の中でも通じてねじ伏せられてるんで、言うことはいけないと洗脳された状態にあるんだと思うんですね。
Taka : そういうことですね、なるほどね。
Shiose : その抑圧からはみ出た時に、今度クレームとして言うてしまうので、主張じゃなくて文句として。
だから相手に対して主張する時にも少し敬意が足りなかったり、なんかすごい悪口と炎上の集合体になるので、主張する人としない人の間その垣根がありすぎて。
Taka : なるほどね。
Shiose : ユーザーの声をちゃんと聞こうと思った時にメーカーも苦労する。
だからインクルーシブを最初に普及する時にもバリアフリー調査とかユニバーサルデザイン調査は色んなとこでやりましたと、「やったんだけども、もうクレームがたくさんでもやりたくないです!」っていう風になるんですよね。
Taka : なるほどなるほど。
Shiose : つまり、メーカーとかベンダー側も、改善したいし修正したいし、良い物届けたいと思ってるんだけど、言わない文化の中でギリギリ言う人ってのは、一番文句言う人しか来ないので、最前線で文句を言う人しか出会えないってのが、日本の悪構造になってるんですよね。

Shiose : そうですね、もともと村八分文化なので。
Taka : そっかそっか。
失敗を許すという作法=インクルーシブは「輸入概念」
Shiose : 僕、ずっとインクルーシブやってて、インクルーシブデザインのインクルーシブってよく日本語にしろって言われるんですよね。そんなカタカナばかり使いやがってって言われて。
で、ずっと考えた結果、「インクルーシブでいきます!」ってなったのは、日本には無い。
Taka : なるほど。なるほど。
Shiose : 日本は違いを許さないし、村八分で弾こうとするし、だからインクルーシブってのは「輸入概念」として受け取った方がいい。
つまり、自分と違う人をちゃんと作法として受け入れるとか、スキルとして受け入れるってのが大事で、最近は失敗を許す文化とかっていう人が一番失敗のこと怒るでしょ?
Taka : ハハハ!(笑)そうっすよね。あれなんでなんですかね。不思議ですよね。
Shiose : 無礼講っていう人が一番気にしいじゃない?
Taka : そうっすね。僕を含めて(笑)
Shiose : だから許す気はないんですよね。で、許さないと格好つかないなぁ、とかいって無理やりやってるだけなんで。
そういう意味でいうと、失敗を許すのも作法が必要だし、なんかその、許すための技術っていうのが足りてないので、だから、インクルーシブデザインで作る時に大事なのは、集まる場所をちゃんと作るんだけど、そこはあけっぴろげに自分のデマンドを主張していいっていう「関係性」から作らなきゃいけないですよね。

Taka : なるほどね〜、そうか〜。
リードユーザーは開発パートナー
Shiose : 良きリードユーザーの集合体を作らないといけないし、そのコミュニティを作らないといけないし、で、主張は自分で思うことを素直に言っていいんですね。
ただしそれは100%改善してくれるわけではないし、改善するためコストもかかるしリスクもかかるので、そういう意味で普通にバリアフリー調査をすると無責任な要求の集合体になるんですよね。
「ここにもエレベータつけてくれ」「あっちにもエレベータ付けてくれ」って車椅子の人に聞くとなるんですけど、でも、車椅子の人もデザイナーとして一緒に迎えるんですよね。
そうすると、それが観光地で、もみじの風情豊かなお寺だとすると、ここにエレベーターがあると興ざめするよねって車椅子の人が言うんですよね。
だとするとこの坂道がいつまで続くのかわからないから、この坂道は500 M 過ぎると上までたどり着けますってあると、友達に頼みやすいと。押してくれと。
でも、それが2キロ続くんだともうやめるかってなりますよねっていう。なんでもかんでもエレベーターをつけるんではなくて一緒にデザインする側に巻き込むことが出来ればここの風情を壊さずにみんなが使えるようにどうすればいいかと一緒に考えてくれるので。ただ自分ごととして巻き込む手段ってのがちゃんとコミュニケーションとして取れないと、さっき言ってたカタカナのクレームから逃れられないんですよね。
Taka : なるほどなーーー。わかり味が深いっすね。
後編【中巻】に続きます。
当日の音声はこちらで聞くことができます。
対談記事
デザイン協力:cappaさん(@CAPPAYA)、西岡克真さん(@kaduma2010)、てつやさん(@car_designer)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
