
【11/8】わたしの中に巣食うリヴァイアサン
彼の優しい気質が、結婚生活にプラスに働いたことは間違いない。が、この側面についてはあまり強調しすぎないほうがいい気もする。優しい人柄とはいえ、サックスの考え方は時としておそろしく硬い独善に陥ることがあったし、たまに荒々しい怒りを爆発させたときなど、その激怒の噴出ぶりたるや、実に恐ろしいものがあった。その怒りは、まわりの人々に対してというより、むしろ世界全体に向けられていた。世界のさまざまな愚かしさは彼をうんざりさせた。彼の陽気さ、上機嫌さの奥に、時たま、不寛容と軽蔑の深い池が広がっているのを私は感じた。
ポール・オースター、柴田元幸訳『リヴァイアサン』新潮文庫、p34-35
この文章を読んで「ああ、あいつのことか」とすぐさま特定の人物を頭に思い浮かべることが、よくあることなのか、珍しいことなのかはわからない。ただ私の場合、ここを読んで「ああ、あいつのことか」と心当たりのある人物をつい思い浮かべてしまったし、もっといえば、その「あいつ」とは自分自身でもあった。
優しく陽気に振るまっているのは表面上だけで、心のうちには世界に対する尽きない怒りと軽蔑を抱え続けている。無鉄砲で捨て鉢、希望なんて1ミリも持っちゃいない。それが、ポール・オースターの『リヴァイアサン』で、「自由の怪人(ファントム・オブ・リバティ)」としてアメリカ各地の自由の女神像を破壊し続けたテロリスト、ベンジャミン・サックスである。
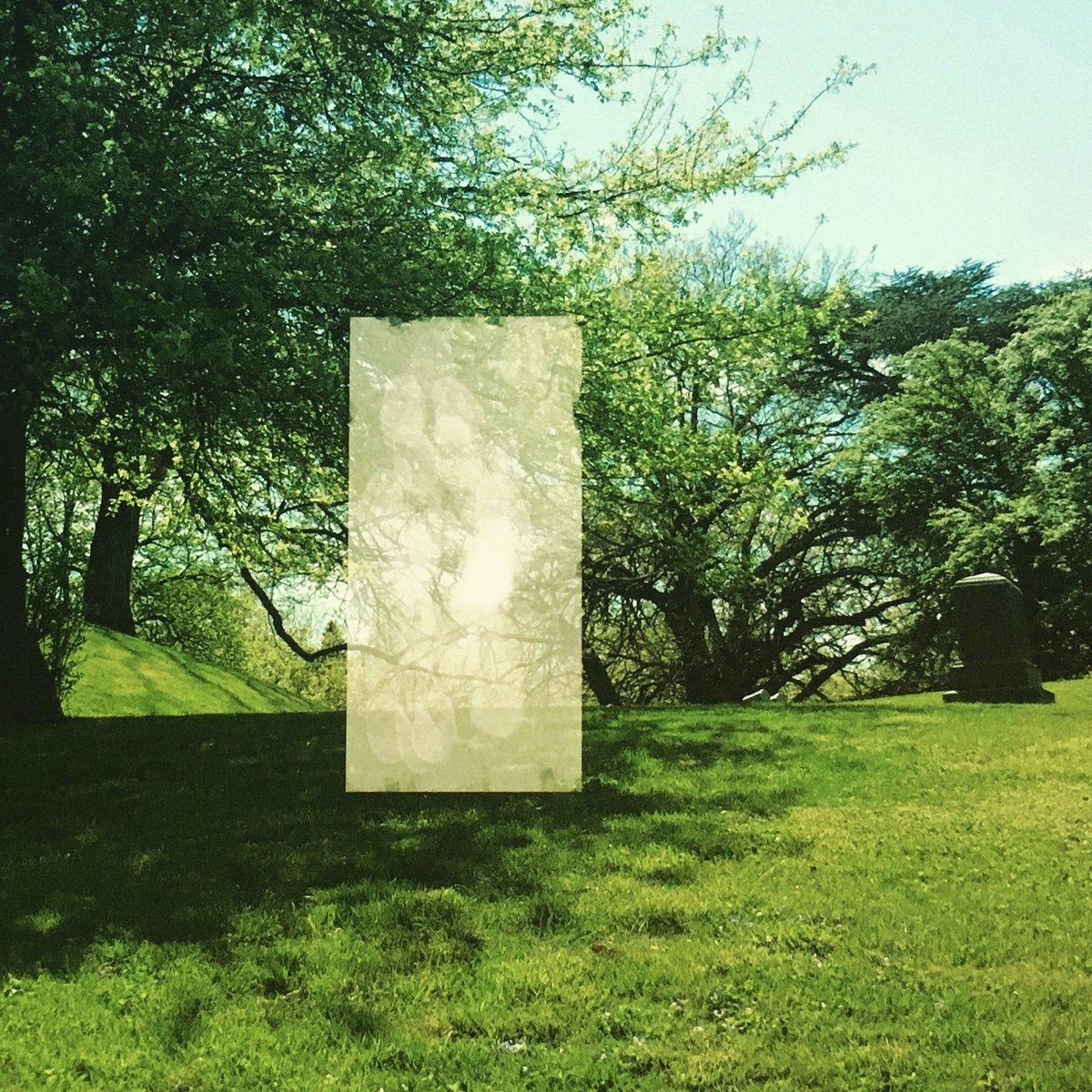
さて、小説の中に自分と似た人物を見つけてしまい、さらにその人物がテロリストとなり最終的に道端で爆死してしまったとなると、これは大変である。ベンジャミン・サックスという男の考えていることが、セリフ1つ1つの意味が、私には手に取るようにわかってしまうのだ。なぜなら、それは自分自身が毎日のようにイライラしながら考えていることだからである。
私はどうすればテロリストにならずに済むのか。どうすれば道端で爆死せずに済むのか。ベンジャミン・サックスという男がたどった道を観察すれば、それがわかるかもしれない。
『リヴァイアサン』は、2020年に読んでいちばん面白かった小説だ。ただ、ぐいぐいと読み進められたのは単に面白かったからというほかに、そういう切実な理由もあったのである。
「いままで生きた人生を終わりにしたいのさ。すべてを変えたいんだ。それができなかったら、どうしようもなくひどいことになると思う。いままでずっと、僕の生涯はただの無駄だった。阿呆なジョーク、しけた失敗のみじめな連なりだった。僕は来週四十一歳になる。いまいろんなことをきちんと把握しておかないと溺れてしまう。石みたいに、世界の底に沈んでしまう」
ポール・オースター、柴田元幸訳『リヴァイアサン』新潮文庫、p204
ベンジャミン・サックスは、なぜ「自由の怪人(ファントム・オブ・リバティ)」となったのか? 爆死した死体はあちこちに飛び散り、両手がないから指紋も採取できない。歯形をとるにも時間がかかる。なぜ道端で爆死するという、そんな無惨な最期を遂げたのか?
結論から言ってしまえば、それはあらゆる玉突き事故による不運な結果でしかなかった。ああしていればこうはならなかった、こうしていればそうはならなかったーー現在から過去をそんなふうに眺めるのは、ただの傲慢だ。なぜなら、過去は過去で、その時点で持っている判断材料をフルに活用して、その時点における最適解を選んでいるはずだから。よって私自身も、そして思い浮かべた「あいつ」も、ああしていればテロリストにならずに済む、こうしていれば爆死して死体がバラバラにならずに済む、なんてことはとても言えない。玉突き事故による不運な結果を完全に避ける方法なんてありはしないと身に染みてわかったことは、『リヴァイアサン』を読んで得たひとつの教訓である。人生の問題に対して、あらかじめ用意しておくことなんてできない。生きている人間にできるのは、起きたことについて対処することのみだ。
ところでこの小説のタイトル、または主人公のピーター・エアロンが友人ベンジャミン・サックスについて書く本のタイトルが、『リヴァイアサン』である理由はいったいなんなのだろうか。

リヴァイアサンとは、旧約聖書に登場する巨大な幻獣である。あるいは、トマス・ホッブズによる近代国家論についての書物のタイトルである。ベンジャミン・サックスや彼が殺害したリード・ディマジオがやがては「国家」の問題に行きあたるからーーと解説で訳者の柴田元幸さんは書いているが、もちろんそれもありつつ、私としては、ある種の人間の内面には「リヴァイアサン」が巣食っているから……みたいな平易な解釈のほうが、しっくり来るのだった。
ジョン・レノンを殺害したマーク・チャップマンがJ・D・サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』の熱心な読者であったことは、有名な話として知られている。ヘミングウェイは現代アメリカ文学はトウェインの『ハックルベリー・フィンの冒けん』から始まると言ったけれど、ハックルベリー・フィンはまだ子供だ。ハックは子供だから、彼の無垢さは無垢さのまま見過ごせる。だけどハックが大人になったとき、それはホールデン・コールフィールドやベンジャミン・サックスのように、その無垢さは悪魔となって、彼の内面を食い潰してしまうことがある。
私が『ハックルベリー・フィンの冒けん』の系譜を継ぐアメリカ文学が好きなのって、結局はこの「悪魔のような無垢さ」というか、「未熟と紙一重の無垢さ」というか、「身勝手な絶望」というか、そういうものが自分の中にあるからなんだろうなと思う。青臭さといってもいい。で、ある種のアメリカ文学にそういう傾向があるってことは、この国の成り立ちとも無関係ではないんだろうなと思う。無垢な子供の内面が、成熟とともに悪魔に食い潰されること。新世界として始まった国家が、成熟とともにリヴァイアサンに食い潰されることーー小説『リヴァイアサン』では、個人の問題と国家の問題が対になっているように見える。
しかしそれはいいとして、私たちにできることは、玉突き事故による不運な結果が訪れないよう祈ることしか、本当にないのだろうか?
『リヴァイアサン』はベンジャミン・サックスの物語だけど、それを語るのは主人公のピーター・エアロンだ。『華麗なるギャツビー』が、ジェイ・ギャツビーの物語をニック・キャラウェイが語るという構造になっているのと、これは同じである。
小説の中では別々の人物だけど、文学の解釈としては、これは1人の人間の内面が分離したものだと考えていいと思う。ベンジャミン・サックスとピーター・エアロンは裏と表のような存在だ。ベンジャミン・サックスはテロリストになって爆死したが、ピーター・エアロンは作家として生き延びた。一方は「こんなこと続けたって無駄だ」と自由の女神像を破壊するという行動に出たが、一方は「人生は我々の手からすり抜けつつある(p.181)」と感じても、最後まで書くことを放棄しなかった。

「玉突き事故による不運な結果」を完全に避ける方法などありはしない。生きている人間にできるのは、起きたことについて対処することのみだ。
だけど、「無駄だ」とわかっていても手放さないこと。それは希望を捨てるな、なんて楽天的なメッセージじゃない。そうではなくて、希望なんか1ミリもないとわかっていても、手放さないことだ。
それが、自分の中でリヴァイアサンを飼い慣らさないといけないある種の人間にできる、祈る以外の唯一の方法なのだろう。
※書影以外の写真は「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク インターネットアートへの再接続」展のもの。
※『リヴァイアサン』に登場するマリア・ターナーはアーティストのソフィ・カルがモデルである。ソフィ・カルは2019年の「限局性激痛」展と2013年の「最後のとき/最初のとき」展を見たことがあるので、これについても書きたかったけど、力尽きました。
شكرا لك!
