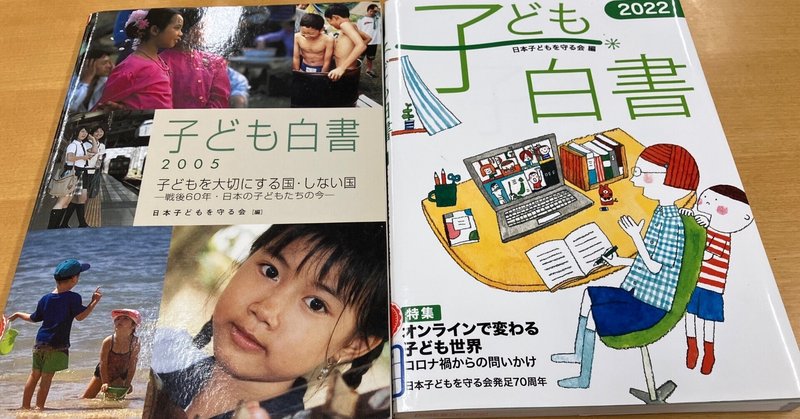
紹介
今回は私が読んだ二冊の白書について紹介していきたいと思います。
一冊目はこちら↓

戦後から60年経った2005年の子どもに関する情報が書かれており、「子どもと医療」や「子どもと地域」のように項目ごとにテーマが変わっており、ときにはデータを表しながら当時の子どもの状況が分かりやすく語られています。
二冊目はこちら↓

こちらも一冊目と同じシリーズの2022年版であり、コロナ禍での子どもの状況を項目ごとに分けて示しています。
この二冊の白書の内容を比べてみたところ一番変化が大きかったと感じる部分は、メディアやインターネットと子どもについての記述でした。
2005年の子ども白書では、ネットやメディアというものが子どもに広がり始めていることが書かれていました。そして、メディアが子どもに健康問題を及ぼすことについても言及されており、そうした状況の脱却に力を入れいたことが読み取れました。
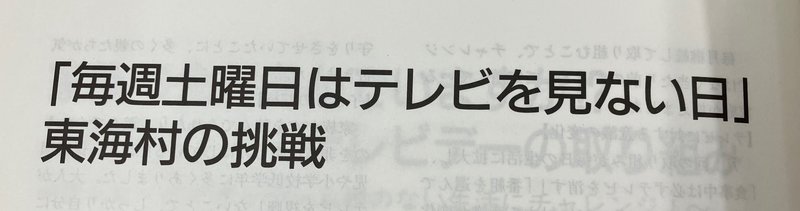

そして、2022年の子ども白書では、コロナ禍によって切っても切れないツールとしてインターネットやSNSが子ども社会に浸透していることについて書かれていました。

オンラインが当たり前となった環境となったため、安易にスマホ等を制限や禁止することが難しくなってしまいました。そのため白書では、インターネットをどう活用していくかについて考えられていることが書かれています。
二冊の白書から、コロナウィルスの影響はそれだけ大きいのだと改めて感じました。教科書や本のデジタル化、遠隔授業の拡大、リモート会議の普及などと人と人との距離は遠ざかる原因も増えました。そんな中でも、家族は自分にとって一番近しい存在だと思います。2005年、2022年どちらの子ども白書にも、インターネットに子どもがどれだけのめり込んでいても家族の時間をしっかり確保することが大切だと書かれていることから、スマホに関する規制が緩くても厳しくても、この点だけは子どもにとって外せないことだということが伝わってきました。
今回は子どもとメディアを中心に紹介しましたが、他にも「ブラック校則の見直しについて」や「15歳金メダル候補の選手のドーピング問題について」、「日本の子どもの睡眠事情について」など興味深い内容が載っているので、気になった人はぜひ読んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
