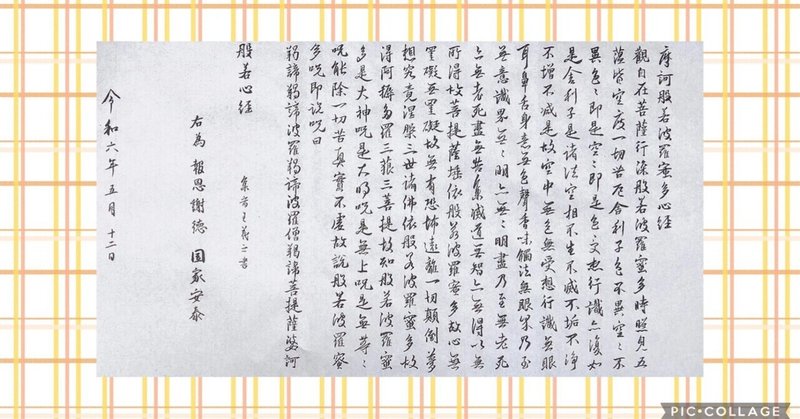
【続いてる写経 1497日め】『大吉原展』、一体何を見せたかったのか
東京藝術大学大学美術館で開催中の『大吉原展』を観賞。
展示作品数がとても多く解説も細かいため、観るのに時間がかかり、さらに大混雑で、展示物の前で押し合いへし合い。
入ったのが夕方だったのもまずかった、、急ぎ足でなんとか全部見切りました。
見終わること前提になってしまったのが良くなかったのか、
結局、この展覧会何を示したかったのかな??
何にも残ってませんでした。
ワタシ自身、歌麿の浮世絵を観たかった程度の気持ちで出向いてしまったのも、浅はかだったなあ…と反省。
最初の解説映像で、
この展覧会では、女性に対する搾取を許しません
といった内容のことが宣言されてました。
前半は吉原遊郭の歴史と、遊女の一日、遊郭が当時のカルチャースポットであった側面を紹介。
明治時代になって、遊郭が廃止された後の遊女を取り巻く環境についての解説や、高橋由一画伯の《花魁》のような生々しい絵画、大正時代に撮影された写真などが登場。
浮世絵に描かれた、それこそ浮世離れした存在ではなく、遊女は”生身の女性”であることが映し出される展示になりました。
明治以降になって、ようやく吉原の負の側面が実感できるのです。
考えて見たら、今回展示されていた絵にはね、遊女が”実際何していたか”は全くないのですよ。(春画っぽいものは全くなかった)
吉原=遊郭=公認・売買春宿
遊女として働いていた女性は、親の借金の前借りのカタとして売られ、借金返済のために自由を奪われていた。
遊女は「人権」という考え方の無かった時代の犠牲者だったのです。
吉原というと、浮世絵に残されている華やかな太夫や花魁のイメージ先行で頭が侵食されていたので、ハッとさせられました。
この展覧会、そこ主張したかったのか!!
が、この展示の問題提議のあと、3階の第二会場に移ると逆にびっくり。
吉原入りを再現した流れでブースが区切られ、衣装や調度品、年中行事の紹介など、鑑賞者は煌びやかな吉原に”物見遊山にきた客”になってしまうような展示。
なぜこちらに揺り戻す??とても違和感がありました。
アノ”東京藝術大学”が主催する展覧会だから、”遊び心”が前面に出てしまった?
吉原の遊郭が、芸術や文化の維持・発展を担った側面を強調したかった?
吉原遊郭がもつ二面性、
・人権無視の幕府公認売買春宿
・着物、書、芸能、絵画、工芸品等、当時の文化の”粋”が結集した場所
展示においてのバランスが取れてなかった印象です。
さじ加減は難しいと思われますが、東京藝術大学が開催するのだったら、”真面目”に”芸術面”に寄せるべきだったのではないか?と思いました。
国立民族学博物館が”吉原”をテーマにしたら、また違うのでしょうね。
江戸時代と明治時代のギャップを観て、負の側面をもう少し知りたいと思った人は多かったのではと思います。
ワタシもこのもやっと感を解消したい…。
せっかくだから、もうちょっと自習してみよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
