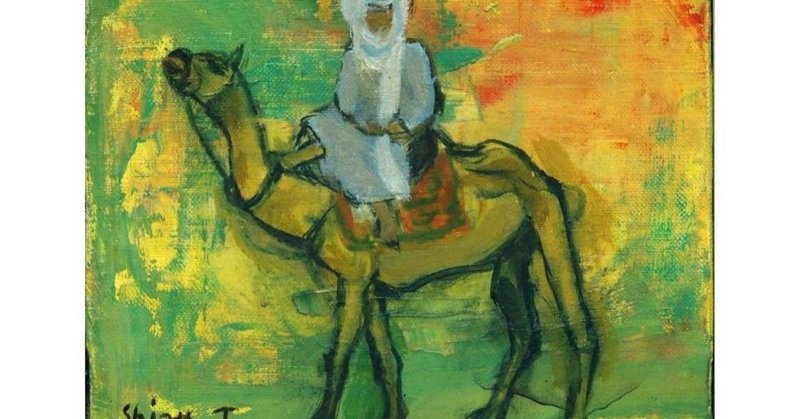
日雇いアルバイトでイラクへ行った。そこで見た地獄【記事まとめ】
日雇いアルバイトでイラクへ行った。そこで見た地獄
この記事を書いた人
西川司
25歳のときにラジオのニッポン放送の新人シナリオコンクールで入選し、脚本家としてデビュー。以降、テレビ・ラジオ・漫画原作・小説・エッセイ等々ジャンルを問わず執筆を続けている。
こちらの記事を少々コンパクトにして、重要だと思うところを太線にしております!
*
*
私たちを乗せた飛行機はパキスタンのカラチ空港で給油し、二十時間ほどのフライトでバグダッド空港に着いた。
タラップを降りたとたん、私は激しい息苦しさを覚えた。
私がアルバイトでイラクの建設現場に行くことになったのは、1980年の七月半ばのことだった。当時、大学を中退した私は、日雇い労働で食いつなぐ生活をしていた。
そんなある時、顔馴染みの手配師が、「にいちゃん、外国の現場があるんだけど、行かねかぇかい?金はいいよ」と誘ってきた。聞くと、契約期間は七月末から三か月。旅費は勿論、衣食住付きで三百万円を支払う。仕事は日本の大手建設会社が建てているビルに資材を運び入れる外国人労働者の監督をするのが仕事だという。
「こんなにうまい話があるのかな……」と多少疑心暗鬼にはなったが、「前金として百万円払うぞ」という手配師のおいしい誘いに勝てず、即座に引き受けることにした。
私と同じように寄せ場で声をかけられてイラクに行くことになったのは、私とほぼ同い年の学生崩れ三人だった。私たちを乗せた飛行機はパキスタンのカラチ空港で給油し、二十時間ほどのフライトでバグダッド空港に着いた。
イラク北部最大の街モスル
タラップを降りたとたん、私は激しい息苦しさを覚えた。七月末の真昼のイラクは、気温が五十度を超え、汗が出る間もなく蒸発し、皮膚は塩分で白くなってしまうのだ。
私たちを空港で待っていたのは、三十半ばくらいの阿部という男だった。阿部は、私たちを市内のホテルに連れていき、「明日は朝一番の飛行機でモスルという町に行く」とぶっきらぼうに言った。
モスルはイラク北部の最大の街ということだったが、街らしき場所は本当に小さく、広大な砂漠に囲まれていた。私たちが働く建設現場は、私たちの宿泊するホテルからタクシーで十分ほど走ったところにあった。これから毎日、朝日と同時にタクシーで現場に行き、灼熱の昼間は作業は中止し、日が落ちてから真っ暗になるまで作業しなければならない。
エリートと曾孫請け
広大な砂漠には、すでに大きな四階建てのビルがいくつも建てられていた。阿部の話によると、病院と看護学校だという。そして、私たちの仕事はそのビルの更衣室に設置するロッカーを組み立てることだという。モスルの建設現場を取り仕切る、日本を代表する大手ゼネコンのC建設の社員たちが寝泊まりする宿舎や食堂だということだった。だが、私たちがそこの食堂で食事をとることはできないという。
「俺らは下請けのさらにその下の曾孫請けみたいなものだからな、彼らエリートとは住む世界が違うんだ」
翌日、日の出とともに軽い朝食をとると、すぐに建設現場に向かった。すると、建設現場では、C建設の所長が壇上に上がり、近くに建てられている高い棒に日の丸の国旗が掲げられると日本の国歌である「君が代」が流れはじめたのだった。
そして、C建設の所長のすぐに前には社員たちが並び、そのうしろにフィリピン人たちが並んでいて、一緒になって歌いはじめた。
そして、それが終わると、所長がなにやら訓示めいたことを話して解散となったのだが、その様子は、私には昔に見た太平洋戦争のときの日本兵が占領した現地の人たちの前でなにやら偉そうにしていた映像と重なって見えた。
「あれ、どういうことなんですか?」私がそばにいた阿部に聞くと、「どうって、見ての通りさ。こんな国で長いこと働くには、ああいうことでもしないと日本人としてのプライドみたいものが保てなくなるらしいぜ。他の現場でも建設会社は違うけど、同じことやってるよ」
と、阿部はせせら笑うように言った。
フィリピン人たちとの交流
そして、仕事が始まった。私たちひとりにつき、外国人労働者として雇われているフィリピン人5人が預けられ、一日五十個の鉄製のロッカーを組み立てるノルマを課せられたのだが、砂漠に放置されていたロッカーはヤケドするほど熱くなっていた。
私たちは、少しずつ日陰にロッカーを運び、そこからまたさらにそれぞれの階に運び入れ、そこで組み立てるという方法を取った。
だが、モスルの暑さはバクダッドの比ではなく、水をびしょびしょに湿らせたタオルを頭に巻いても十分もしないうちにカサカサに乾いてしまうのだ。
それでも一か月ほどすると体も仕事にも慣れ、フィリピン人たちとも下手な英語でコミュニュケーションが取れるようになった。
私には最初から彼らに凶暴性のようなものはまったく感じなかった。それを阿部に言うと、阿部は自分がその場にいたわけではないが、一年ほど前にフィリピン人たちが反乱を起こして、ここのC建設の前の所長が朝の訓示をしようと壇上に上がったとき、ひとりのフィリピン人が所長をめがけて走っていき、壇上に飛び上がってナイフで刺すという事件があったとM物産の人間から聞いていると私たちは聞かされていた。
砂上の楼閣
その他にもいろんなことがわかってきた。バグダッド、モスル、アマラ、バスラに建設している病院や学校の建設費は日本のODAから出ている。
サダム・フセインが一年前に大統領に就いた時、日本政府が石油の供給をつづけてもらうための、いわば貢物というわけだ。
「こんなしょっちゅう砂嵐が吹く砂漠の真ん中に、どんな立派なビルを建てたって、十年ももちゃしないってよ」
阿部が私をホテルのバーに誘ったとき、酔いに任せて白状した。イラクは基本的には禁酒なのだが、外国人がホテルで酒を飲むことは認められている。
「このロッカーの組み立ての仕事だけどな。これで、俺たちの会社にいくら入ると思う?」
阿部が突然訊いてきた。阿部の会社は元M物産の子会社にいた同僚たち三人で作ったもので、M物産の元上司から仕事をもらっているという。私が答えられずにいると、阿部はニヤッと笑って、「一億円だよ」と自慢げに言った。その当時の一億円といったら、途方もない巨額な金だ。その一億円が、私たちのような学生崩れに三百万円払って、フィリピン労働者を使い、買い叩いた売れ残りのロッカーを組み立たせれば手元に入るという。
「ロッカーだけで一億だぜ。じゃあ、あのビルの建設費はいくらだって話だよ。しかも、十年も経たないうちに砂漠に埋まるって、まさに砂上の楼閣だよな。しかもそれ、全部、俺たちの税金だぜ。世の中、狂ってんのよ、おかしいのよ」
阿部が酔って言った言葉が私の頭の中でいつまでもこだましていた。
悪夢のような一日
あと一か月もすれば、日本に帰れるという九月二十二日のことだった。いつものようにタクシーで現場に行くと、フィリピン人たちがいるだけで、大手ゼネコンのC建設の社員たちの姿はどこにもなかった。
フィリピン人たちの話によると、昨夜のうちに彼らはトラックに荷物を積み込んでどこかへ行ってしまったという。阿部は次の現場であるバスラにまだロッカーが届いていないという連絡を一週間前に受けて、バスラに行ったきりだった。
そして、ホテルに戻り、昼寝をしている時だった。突然、ドーン!という地響きがして、目を覚ました。ホテルのロビーに行くと、イラク人たちが外に両手を向けて泣き叫んでいた。外に出てみると、近くの民家という民家が、跡形もなく吹き飛ばされていた。そして、ホテルの前の道路には、戦車や兵士を乗せた軍用トラックが長蛇の列を作っていた。と、そこへ耳をつんざくような音を立てた戦闘機が飛んできて、戦車や兵士を乗せた軍用トラックめがけて小型ミサイルを撃ち込んだ。阿鼻叫喚というのは、ああいうことをいうのだろう。
手や足を吹き飛ばされて血まみれになった兵士たちは大声で喚き散らしながら、物陰に隠れた。空からの空爆は止まらず、私たちの目の前に内臓らしきものや、腕や足、眼球が飛んで落ちてくる。一瞬、吐き気を催す強烈な生臭さが鼻を衝くが、すぐに消えてしまう。おそらくあまりの暑さのせいで、生臭さも乾燥してしまい、臭いも消し去るのだろう。
私たちはいつも現場まで行くタクシーの運転手に有り金のすべてを渡し、バグダッド空港に走らせた。途中で見えた、沙漠に建っていたビルはすべて破壊されていた。
丸一昼夜、タクシーを走らせ、ようやくバグダッド空港に着いたものの、兵士たちによって封鎖されていた。空港の中には、私たちの知らないフィリピン人たちが大勢いた。イラク各地で働いていた人たちだろう。兵士に、「俺たちは日本人だ。どうすればいい?」と必死で訊くと、明日、ここに国際赤十字社のバスがくるから、それに乗って脱出しろという。
イラクからの脱出
翌朝、赤十字社のバスが二台やってきた。空港の中にいたフィリピン人たちは、いっせいにバスを目指して走り出した。私たちも負けじと走り、二手に分かれてなんとかバスに乗ることができた。しかし、発車したとたん、ドーン!という音ともに反対方向に走っていったバスに戦闘機からの小型ミサイルが命中し、粉々に破壊された。
私ともうひとりの学生崩れを乗せた国際赤十字社のバスは、ヨルダンまで走り、私は命からがら日本政府が用意した専用機で帰国することができた。あとでわかったことだが、誤爆されたバスはクゥエートに向かう予定だったらしい。帰国して数日後、私は阿部の会社を訪ねてみたが、その事務所は引き払われていた。結局、私はタダ働きをしたことになる。だが、命が助かっただけでも儲けものと思わなければならないだろう。
あれから四十年
あのイラン・イラク戦争に巻き込まれてからちょうど四十年になる。あれから私は、大手ゼネコンがODAを食いものにしていたこと、一緒に行った学生崩れの二人が乗った国際赤十字社のバスにイランの戦闘機が放った小型ミサイルが命中し、彼らが死んでしまったことなど、その真実をなんとかして世間に知らせたいと思ったのが物書きになろうとしたきっかけだった。
しかし、日々の生活に追われているうちに、いつの間にか私は初心を忘れてしまっていた。
ところが、数年前、イスラム国が支配している地域が私がいた、あのモスルだということを知った。さらに日本人ジャーナリストが彼らによって首を落とされて殺されるという残忍な映像を見た私は、一大決心をして依頼されてもいない小説を書いた。勿論、あのイラン・イラク戦争に巻き込まれた体験を書いた小説である。
しかし、その小説は、私が書いた中でもっとも売れない作品になった。だが、私の中ではもっとも力を入れ、もっとも書きたかったものだったという気持ちは今も変わらない。
講談社から出した「異邦の仔」という小説である。私はこの一冊を書けたことで、それまで職業を聞かれるたびに「物書きです」と卑屈な物言いしていたのだが、今は職業を聞かれると「作家です」と答えることができるようになった。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました^^ サポートいただいた資金は、記事のまとめ活動に時間を割くための資金とさせていただきます!
