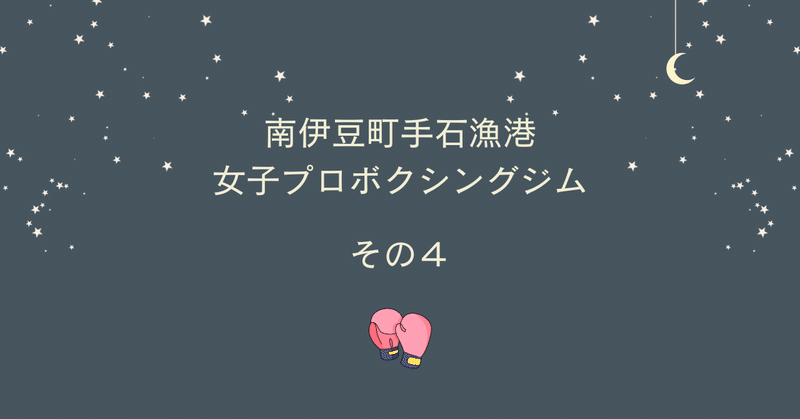
小説:南伊豆町手石漁港女子プロボクシングジム その4
ばーちゃんたち
漁協長が軽トラックで段々畑の中の道を走っている。港の山を登った次の山に作ってある段々畑なので、海は見えない。ふと見ると、キヨシと友人二人が木に何かを巻いてパンチを打ち込んでいる。漁協長、トラックを止めて近づいていく。
「よー、がんばってんなー」
キヨシと友人二人は、なんとなく警戒しながら「あ、どーも」と挨拶した。漁協長は軽トラの荷台に積んでる未完を3つ掴んで3人に渡す。
「ほれ。食え。ちょっと早いけど、今年もうまくできそうだ」
3人、黙って受け取った。漁協長、ことさら笑顔を作って言う。
「キヨシも大変だなー。ヘンな試合決まっちゃって、、、」
キヨシが「いやー」と言ってはにかんだ。漁協長、キヨシの様子を観察しながら言う。
「ま、男が女に負けるわけにはいかねーわな」
キヨシが微笑した。漁協長、キヨシの様子を観察しながら尋ねる。
「だいじょぶそうか?」
友人二人が説明する。
「さっきジム見てきたけど、たいしたことなかったっすよ」
キヨシが不服そうに言う。
「負けるわけねーんだから、偵察なんて必要ないのに」
漁協長が破顔する。
「そら、そーだ。負けるわけねーよな」
キヨシが同意する。
「そら、そーすよ」
漁協長が真面目な顔になって言う。
「でも、ルミはいい左フック持ってるらしいぞ。見たか?」
と友人二人に尋ねる。友人二人は少し驚いて言う。
「あれ。オレたち行った時はやってなかったな、、、」
漁協長、考えてるような顔をして言う。
「そーら、隠してんだよー。あっちも必死だからなー」
キヨシが納得したように言う。
「そっかー。左フックかー」
キヨシは友人と左フックのシミュレーションを始めた。漁協長は笑顔でうなづく。
「ま、がんばってくれよ。男の威信がかかってっからな」
軽トラックが漁港に入っていく。漁協長、ジムのそばに車を止めて、ジムに入っていく。「おーす」と声をかけると、ジム内で練習している奥さまたちから「ちーす」という声があがる。コーチが寄ってくる。
「どうしたんですか?」
漁協長が、笑顔であたりを見回しながら言う。
「今日、男二人見学してた?」
コーチが応える。
「えぇ。いましたね」
漁協長が、やっぱり笑顔であたりを見回しながら言う。
「そいつらに会ったんだよ。みかん畑で。キヨシが一緒に練習してた」
二人で、並べてあるイスに座る。コーチが興味深そうに尋ねる。
「どうでした?」
漁協長、苦笑して首を振る。
「ま、たいしたことねーな。あいつは、昔っから、ほんと口ばっかりで中身ないんだ。ルミのパンチの方が全然迫力あるわ。でも、ま、念のためにさ、打ち合わせ通り左フックのことも吹き込んどいたから」
コーチ、笑う。
「ありがとうございます」
漁協長立ち上がる。
「じゃ、それだけ知らせようと思って。あんまり女の園にいるとかーちゃんに怒られるから」
漁協長が「おつかれー」とジム内に声をかけて出て行く。練習している奥さまたちから「ちーす」と声があがった。
「スナックゆうこ」の看板に灯りが入っている。ユー子がカウンターで酒を作っている。谷間は出していない。
「はい」
カウンターに3つグラスを置いた。キヨシと友人二人がカウンターに座って、パンチを出したりしている。ユー子、心配そうに尋ねる。
「あんた、だいじょぶなのー?誰か専門家に見てもらった方がいいんじゃないのー?」
キヨシがグラスから一口飲んで、半笑いで手を横に振る。
「そーんな。楽勝だよ。女相手なんて」
ユー子も半笑いになる。
「まーねー。そーだよねー。相手は女だもんねー」
ユー子、カウンターにボトルを出しながら中を見る。
「あ。もうなくなるよ。前祝いにボトル入れる?」
キヨシが言う。
「前祝い、いいね。入れよう」
ユー子、ボトルの残りをキヨシのグラスに入れて「いえーい」と両手をあげる。キヨシも友人二人も「いえーい」と両手をあげる。みんなでハイタッチを始める。
朝に手石漁港から太平洋を見ると、水平線が黄金色に染まる。朝焼けを見ながら、ルミとマリが漁港のそばをランニングしている。マリが言う。
「今日も朝焼けキレーだねー」
ルミも同意する。
「なんか神々しいよねー。毎日見ても飽きないよ」
酔っ払いが騒ぐ声が聞こえた。漁港の向こうを、酔っ払った3人組がヨタヨタと歩いている。
ルミが立ち止まって、3人組を凝視する。
マリ、ちょっと先まで行ってルミが止まっているのに気づいた。後ろ足でもどってきて、ルミが凝視している方向を見る。
「あ、キヨシさんだ」
キヨシと友人二人は、よっぱらってふざけあってる。ルミはそれを見ていたが、パッと切り替えて走り出した。マリも急いで走りだした。
昼前、ジムのまえに「南伊豆町手石ケアサービス」と側面に描かれたミニバンが泊まった。運転席からミッコが降りてくる。助手席からルミが降りてきて、後ろの左側のドアに回って開けると、おばあちゃんたちが6人次々に降りてきて、ジムに入っていく。
リングの前にばあちゃんたちを集めて、ミッコが言った。
「はーい。ここが「手石漁港女子ボクシングジム」でーす。みなさんの「手石漁港婦人部」からも資金援助いただきましたー」
ばーちゃんの一人がまわりを見回して言う。
「誰もいないよ」
ミッコが答える。
「練習は午後からなの」
別のばーちゃんがサンドバッグを叩いてみる。
「あたいもできるの?」
ミッコ、笑顔になる。
「できるよ。いい運動になるじゃない。週何回か希望者送迎するから、やってみれば?」
ばーちゃん、リングを見ながら言う。
「やってみよっかなー。プロ目指しちゃおっかなー」
ルミが笑いながらツッコむ。
「プロテストは32歳まででーす」
ばーちゃんたち、驚いて、次に笑う。
漁港の駐車場に漁協長の軽トラが入ってきた。車を降りると、ジムの方から嬌声が聞こえる。「まだ練習時間じゃないのに」とジムの窓から中をのぞいてみた。ルミがコーチしながら、ばーちゃん達がボクシングみたいなことをしている。漁協長はビッグスマイルになった。ばーちゃんの一人が漁協長が窓から見ていることに気づいた。
「おー、イチロー、なーに笑ってんだ。お前もやれ」
漁協長がビッグスマイルで答える。
「ダメだよー。ここは女子ボクシングジムだからよー」
ばーちゃんが言う。
「ぢゃ、見るな」
漁協長、笑いながらジムの中に入り、座っているミッコの横に座った。
「ミッコおばちゃん、いい企画だね」
ミッコは得意そうに言う。
「だろ?そして、お前の応援でもあるがな」
漁協長、少し驚く。
「そうなの?」
ミッコが言う。
「男どもに評判悪いんだろ?このジム」
漁協長、苦笑い。
「うーん。まー」
ミッコが苦々しげに言う。
「しょーがねーなー。宴会にはコンパニオン何人も呼んで漁協の金使うくせに、、、」
ばーちゃんたちがキャッキャと嬌声をあげながら練習している。ミッコは厳しい顔で言う。
「だから、女ども全員、ばーちゃん達まで味方につけるんだ。わかったね」
漁協長、子どものように答える。
「はーい」
ミッコ、うなづいて、思いがけず少し大きな声を出す。
「そいで、再来年の町長選だ!」
漁協長、うろたえる。
「お、おばちゃん、声がデカいよ」
ミッコ、うなづいて、冷静になるようにつとめる。
「お、思いがけず、気が高ぶったわ。あんたの死んだかーちゃんに頼まれたこと思い出して」
漁協長が苦笑する。
「「よろしく頼む」って言っただけだろ?」
ミッコ、床を見ながら言う。
「ま、そうだけど、言葉としては、そうだけどもね。でも、あんたのかーちゃんとあたしの長い長い日々からの「よろしく頼む」なのよ。わかる?あんたのかーちゃんは、中学校に入ってからあたしに頼み事なんかしたことなかったのに、最後にそう言ったのよ。あんたのことだけを、あたしに頼んで息を引き取ったのよ」
ミッコ、少し涙声になる。漁協長、何百回も聞いた話なので、少しあきれる。ミッコ、気を静めて言う。
「だからさ、ここまできたら町長っしょ。それ以上は望まないよ。あんたが町長にまでなったら、あっちに行った時、あんたのかーちゃんに顔向けできるよ。そのためにもジム成功させないと、、、」
一人のばーちゃんが近づいてきて、話しかけた。
「おい、イチロー、ルミは勝てるか?」
漁協長、腕を組んで考える。
「うーん。どーかなー。がんばって練習してるけどなー」
ばーちゃん、真剣な顔でつぶやく。
「勝ってほしいなー」
14時頃、コーチがいつものように歩いてジムに向かっていると、「南伊豆町手石ケアサービス」と側面に描かれたミニバンがジムの前に止まっていた。「見たことない車が止まってんな」と思いながらコーチがジムに入って「おいーす」と言うと、あちこちから「うぃーす」と声があがり、ふと見るとばーちゃんが3人イスに座っていた。ばーちゃんたちは、コーチを目を合わせて黙礼した。コーチも黙礼した。コーチは急いでマリを探した。いた。小走りでシャドーをやっているマリに近づいて、尋ねる。
「マリちゃん、マリちゃん、ちょっと、ちょっと。あの方たちどなた?どなた?」
マリ、シャドーをやめてばーちゃんたちを見る。
「大雑把に言うと、漁協婦人会のお偉いさん。ミッコちゃんとこの老人ホームに住んでるの」
コーチはマリを見る。
「じゃ、ミッコさんが連れてきたの?の?」
マリもコーチを見る。
「なによ。なんでおびえてんの?そう。午前中みんなでジムの見学来て帰ったら、あの3人が「ジム行きたい。ルミの練習が見たい」って言い出したから、また連れてきたんだって。ルミちゃんが」
マリがばーちゃんたちを見る。コーチにも見るようにうながす。マリが説明する。
「左からハツさん、タツさん、ミツさん。みんな89歳の同級生。子どもの頃からの友だちなんだって」
リングの上で、ルミのパンチをコーチが受けている。ドスン、ドスンといい音で右ストレート、左フックが入っている。ゴングが鳴る。コーチは、小さい声で「いいよ、すごくいい」とルミを褒めて、リングを出てイスに座って休んだ。ふたつイスをあけて、ばーちゃん3人が座っている。3人がコーチを見ている。ハツが声をあげた。
「コーチ?」
コーチ、ビックリする。ハツが尋ねる。
「ルミは勝てるら?」
コーチ、ちょっと困る。
「うーん。それは、やってみないとわかんないですね」
タツが尋ねる。
「勝てないのに、男と戦わせるんか?」
コーチ、しょーがないなー、という顔をする。
「おばあちゃんね、スポーツってのは、勝つ負けるは重要じゃないんだよ。目標に向かって、必死に努力することが重要なんだよ。それがその人を成長させるんだ、、、」
ばーちゃん3人、返事もせずにじーっとコーチを見てる。
じーっと見てる。
じーっと見てる。
思いがけない反応にコーチはドギマギする。ゴングが鳴ったので、ドギマギから逃げるように、近くで練習している奥さまに「よーしミットやろう」と言って近づいていった。ばーちゃん3人、コーチを目で追う。ハツが話し出す。
「あいつは、いい都会モンだな」
タツがうなづく。
「そーだなー。たまーに、あーゆー、ちゃんとしたヤツがくんな」
ミツが笑いながらハツに言う。
「あんたが昔追っかけてた立教の学生も、いい都会モンだったな」
ハツ、笑う。
「あぁ、あいつは良かった。アレもよかったしな」
3人でゲラゲラ笑う。ミツが問いかける。
「ありゃ、いつの話ら?」
ハツが答える。
「オリンピックの頃ら?」
タツが言う。
「いやいや、もっと前ら?朝鮮で戦争が始まったあたりじゃなかった?「こんな時にノンキだなー」って思ったもの(笑)」
ハツが驚く。
「ありゃ。もうそんな前ら?」
ミツが笑う。
「ひどい昔だねー」
ばーちゃん3人がゲラゲラ笑った。
幸せについて
漁港の前の、コーチが住んでいる別荘地とは並行してある坂道を登っていくと、一番上に手石ケアサービスの建物があり、その横に大きく立派な家が建っている。その家に夜の灯りがついていて、食卓にミッコ、ルミ、マリ、コーチが座っている。今夜のコーチの食事当番はミッコで、ルミはあの日以来、ミッコの家に居候して働いている。ミッコが料理をしながら言う。
「あのばーちゃんたち3人もね、暴力ふるわれてたんだって。ダンナに。でも、時代が時代だから、周りに言っても警察に言っても、とりあってもらえなかっんだって。だから、ルミのこと他人事だと思えないんだって、、、」
ミッコがオカズを出した。ルミがごはんをよそって、みんにわたした。みんな、それぞれに「いただきます」と言うと、ミッコが続けた。
「それに、男どもがうるさいのよ。「なんで女どものジムに漁協が金出すんだ」とか言って、「イチローは母レーコに惚れてるからだろ!」なんて陰口言って。だからさ、イチローのためにも婦人会味方につけないと、、、」
マリがゴハンを食べながら笑う。
「ミッコちゃんは、いつでも漁協長の味方だからね」
ミッコが憤然と言う。
「当たり前じゃない。たった一人の身内なんだもん。妹がさ、40歳で亡くなっちゃったんだけどさ、弱ってるベッドの上から一生懸命頼むのよ。「イチローを頼むね」「イチローを頼むね」って、何度も何度も頼むのよ。中学に入った頃から、あたしに頼み事なんかしたことなかった妹が、一生懸命頼むのよ」
ミッコ、涙ぐむ。なにか涙をふくものがないか見回すと、ルミがテーブルの上を拭いたフキンを渡そうとする。ミッコは「バカ」と小さく叱る。マリはこの話を何百回も聞いて飽きているので、別の方向に話を進めようとする。
「ミッコちゃんは、漁協長を町長にしたいんだって」
コーチ、驚く。もう何回もミッコの家で夕食を食べているのに、初めて聞く話だ。
「え?そうなんすか?それはミッコさんが薦めてる話なんだ。漁協長も言ってたけど、なんか他人事でしたね」
ミッコが結局フキンで目頭を押さえながらうなづく。
「そうなのよ。あいつ、イマイチ熱が入ってないんだ。でもさ、あいつを町長までしたらさ、妹にいい手向けじゃない」
コーチ、明るい声で言う。
「そりゃ、いいかも。あの人、アイデアマンだし、実行力あるし、古くさくなくて賢いし」
ミッコ、ボーッとコーチを見る。
「あら。コーチ。気に入ったわ。前から気にいってたけど、さらに気に行ったわ。飲む?いいお酒飲む?」
コーチ、すまなそうに言う。
「飲めないんですよ。すいません。このやりとり、5回目くらいですけど」
マリが手をあげる。
「あたし飲む」
ルミも手をあげる。
「あたしも飲む」
コーチ、驚く。
「えー!プロを目指していながら、飲むの?」
マリが真面目に言う。
「ミッコちゃんとこのお酒は高いいいヤツだから、だいじょぶだよ」
ミッコが言う。
「いーぢゃない。たまには。息抜きも必要でしょー」
コーチ、仕方なく同意する。
「しょーがないなー。ミッコさんがそう言うなら。キミたち、せめて週2回くらいにしろよ。それ以上は飲むなよ」
マリとルミが声を合わせた。
「はーい」
「はーい」
ミッコの家の前に漁協長がやってきた。玄関を開けて「オース」と声をかけてズカズカあがっていく。リビングに入ると、コーチの膝の上にミッコが座って飲んでいる。向かいの席では、マリとルミが楽しそうにケラケラ笑いながら指相撲をやっている。コーチが、すがるような目で漁協長を見る。
「あー、よかったー。やっと来てくれたー」
漁協長、苦笑する。
「コーチ、悪いね、ほら、ミッコおばちゃん、コーチは帰って仕事あんだから、、、」
コーチの膝の上でミッコがぐずる。
「えー、なんだよー、もっと話させろよー。チューしよう。チュー」
漁協長、ミッコを抱きかかえる。
「ダメダメ。ほらほら。じゃ、オレんち行って飲むか?」
ミッコがイヤイヤする。
「ヤ。あんたの嫁キライ」
漁協長、苦笑する。
「なんだよー。仲良くやれよー」
ミッコが尋ねる。
「なんで母レーコと一緒になんなかったんだよー」
一瞬、みんな凍り付く。アセった漁協長が、みんなの様子をうかがうように言う。
「まーた、そーゆーこと言ってー。マリの前でそーゆーこと言うなよー」
漁協長、ミッコとルミをソファに座らせる。二人でケラケラ笑っている。そのスキに、漁協長はコーチとマリを玄関にせきたてていく。リビングから「コーチー、コーチィ」と二人の声が聞こえる。漁協長がすまなそうにコーチに言う。
「悪いね。たまに悪酔いすんだよ」
コーチ、心配そうに言う。
「いやいや、全然かまわないんですが、だいじょーぶですか?」
漁協長、笑いながら言う。
「だいじょうぶ、だいじょうぶ。馴れてっから。ルミもいるし。今のうちに帰っちゃって」
リビングから「コーチー、コーチィ」と呼ぶミッコとルミの声が聞こえる。
夜の手石の小さな住宅街の坂道を、コーチとマリが下っている。月が明るい。マリが言う。
「ミッコちゃんも、若い頃、横浜出てって、男に散々ダマされて帰ってきたんだって」
コーチが感心する。
「へー。なんとなく都会的だもんなー」
マリが続ける。
「それから男に目もくれずお土産屋さんやって、コンビニやって、老人ホームやってお金貯め込んでるらしいけど、それだけじゃ満ち足りないのかねぇ?」
コーチが、何となく同意する。
「そーなのかねぇ?」
マリが言う。
「人の幸せって、なんだろうねー」
コーチ、何となく答える。
「うーん。何だろうなぁ」
マリ、半笑いで言う。
「なによー。ちょっとは名前の通った小説家なんだから、もっと気の利いたこと言ってよー。迷える十代に道を指し示すようなさー」
コーチ、ドギマギして言う。
「えぇー?牧師じゃないんだからさー、そんなこと、よく考えないと、、、」
マリがビッグスマイルになり、急にコーチと腕を組んだ。コーチがさらにドギマギした。
「な、なんだよ、、、」
マリ、幸せそうに言う。
「いいの。このまま家まで送って、、、」
夜の漁港を二人が横切る。何となくぎこちない。月が明るい。
後楽園ホール
ジムの中。ルミがサンドバッグを打っている。少し離れた所に立って、ガムテープで作った小さな的に向かって、一発一発狙いながら、ドスン、ドスンと鈍い音を響かせている。サンドバッグがよく揺れる。
ゴングが鳴る。
ルミが休憩のためイスに座ると、ハツばーちゃんとタツばーちゃんが右と左から腕を揉む。ミツばーちゃんは、正面からウチワであおぎながら水を出す。
少し離れた入口から、コーチとミッコが見ている。コーチが苦笑しながら言う。
「世界チャンピオンみたいな扱いだ」
ミッコも苦笑する。
「ばーちゃん達が生きがい見つけたんだから、許してあげて。さ、ついでだから、あたしも練習しよー」
スキップしながら更衣室に入っていく。
場面が変わる。
「はー、これが後楽園ホールかー」
エレベーターを降りた踊り場で、透明なドアの向こうの劇場みたいなドアを見ながら漁協長が言った。
「そうです。これが聖地です。懐かしいなー」
横に立っているコーチが言った。
「ここのリングに立たれたことがあるんですね?」
横に立っているJBC事務局の人が言った。コーチが答える。
「えぇ。3度ほど。懐かしいです。昔とあんまり変わらないですね」
JBC事務局の人が漁協長に話かける。
「中をご覧になりますか?今日はリング片付けてますけど、、、」
漁協長、目の前に手をあげて左右に振る。
「いえ、それは、しかるべき時を待ちましょう」
JBC事務局の人が言う。
「では、事務局で話しましょうか。座って」
JBC事務局の応接ソファーに3人が座っている。事務局の人が話だす。
「実はボクシング人口減ってましてね、ですから事務局としては、これからジムを出す方をすごーく応援したいんですよ」
向かいに座っている漁協長とコーチが何度もうなづく。事務局の人が続ける。
「ただしですね、やっぱりですね、最初のハードルは皆さん越えてらっしゃるんでね、平等性っていうか、やっぱりね、そーゆーことがね、、、」
なんか話しづらそうなので、漁協長が引き取る。
「ごもっともです。1千万円、どーしても必要なんですね」
事務局の人が困りながら言う。
「えぇ。やっぱり、そのー、加盟金ですのでね、世界チャンピオンが300万円、日本チャンピオンが500万円、その他の方が1千万円、皆さん、お振り込みいただいた後にジム開かれてますのでね、、、」
漁協長が引き取る。
「なるほど、なるほど、そこは、もー、どーしても頼むよ、と。他のことは何となく融通してあげるけども、そこだけは頼むよ、と」
事務局の人、困ったような笑顔で言う。
「そーなんですよー。そこはね、どーしても融通できないんですよー」
漁協長が引き取る。
「いや、ごもっともです。ごもっともです」
東京駅から伊豆下田駅に向かう踊り子号が走っている。左側に海が見えている。あまり明るくない顔で漁協長が話し出す。
「スポンサー見つかんないんだよー。南伊豆も下田も、平成に入って以降ずっと景気悪いからさー、、、」
コーチもあまり明るくない顔で「はぁ」とうなづく。
二人は少し海を眺める。眺めながら、漁協長が言う。
「でもさ、コーチには感謝してるよ。女どもがイキイキしてていいよ」
コーチが答える。
「そうすか?」
漁協長が深くうなづく。
「うん。今から考えると、前はみんなドンヨリしてたよ。何となく」
コーチが尋ねる。
「そんなもんすか?」
漁協長が深くうなづく。
「うん。だからさ、プロ加盟できなくても続けてよね」
コーチが作り笑いで応じる。
「もちろん。でも、だいじょぶすか?漁協長の立場みたいなものは、、、」
漁協長、笑顔でコーチを見る。
「なんかルミ対キヨシの試合が大好評でさ、あーゆーの何だかんだとやってけば、何とかなるんじゃねーかなー。婦人部は味方だし」
コーチが「そうすか」と言う。
漁協長が海を見る。コーチも海を見る。少したって、漁協長がポツリと言う。
「でも、プロがいた方がいいよねー?」
コーチもポツリと言う。
「そうっすねー」
踊り子語が、伊豆下田駅に向かっている。
プリン
夜の手石。母レーコの家に灯りがついている。普通の家。リビングの机に母レーコとマリとクミとコーチが座って食事をしている。コーチが話している。
「だから、もしかしたらマリちゃん、伊東に通ってもらうかも」
マリが困り顔で言う。
「あたしはいいけど、伊東は無料じゃないんでしょ?」
コーチも困った顔になる。
「そりゃ、無料じゃないだろーなー」
母レーコも困った顔になる。
「電車代もかかるしねー。伊豆急高いから」
みんな、モグモグ話し出す。コーチが気づいたように言う。
「オレが車で送迎してあげよか?」
母レーコ、すぐに言う。
「やめてよ。そしたら誰が手石で教えんのよ。だいじょぶよ。そーなったら電車代とジム代くらい出すから。マリに才能があるもんなんて初めてだから。しょーがないよ。かーさん、がんばる」
マリが喜ぶ。
「えー!出してくれるの?」
母レーコ、作り笑顔でマリに言う。
「自分でも出しなさいよ」
マリ、何も言わずにゴハンをほおばる。コーチがそれを見て喜ぶ。
「ガン無視だ」
みんな、モグモグ食事をする。コーチがすまなそうに声をあげる。
「あのー?」
母レーコがコーチを見る。
「はい?おかわり?」
コーチが言う。
「いや、そーじゃなく、聞きにくいこと聞いていいですか?」
母レーコ、ゴハンを口に運ぶながら言う。
「はい。どーぞ。コーチなら許す」
コーチが尋ねる。
「この前、ミッコさんちで夕食いただいた時、彼女すごい酔っ払っちゃって、そしたらミッコさん「あんたの嫁は嫌いだ。レーコと一緒になればよかったのに」って言ったんすよ」
母レーコ、オカズを見ながら言う。
「はい、はい」
コーチが尋ねる。
「一緒になりそうな時あったんですか?」
母レーコ、目を細めてコーチを見て、言う。
「あなた、ほんとに聞きにくいこと聞くのね」
コーチ、作り笑いで母レーコを見る。
「小説家なもんで、すいません」
母レーコ、ゴハンを口に運びながら、言う。
「うーん、お互いに、なんつーか、行かなきゃいけないとこがあったのよ。若い頃って、そーゆーのあるじゃない?」
コーチ、茶碗を置いて真剣に聞いてる。
「えぇ、えぇ、わかります。人生色々ですよねー」
母レーコ、笑う。
「色々よー。マリなんかさ、高校にも行かないで働くって言うから、「あんた、なんかやりたいことないの?」って聞いたら「ない」って言うのよ。ぢゃ、高校くらい行けばいいのに「勉強好きじゃないし、かーちゃんも大変だから働く」って言うのよ」
コーチがマリを見て言う。
「いい子なのか、そーじゃないのか、、、」
マリが笑う。
「えへへへ」
母レーコが続ける。
「いい子だけどもさー、もーちょっと何かさー、高らかなものっていうかさー、そーゆーモン欲しいじゃない?」
コーチが言う。
「【少年よ大志を抱け】みたいなもの?」
母レーコ、すごく同意する。
「そーそー、そーゆーの、そーゆーの」
コーチが尋ねる。
「いいお嫁さんになるとかを望んでるわけじゃないんだ?」
母レーコ、目が少し鋭くなる。
「あたりまえでしょ。いま西暦何年よ。女もココロザシを抱くのよ。そーゆー女を選ぶのがいい男ってもんよ」
マリが声をかける。
「くー。かーちゃん、かっちょいー」
母レーコ、マッスルポーズで応える。
食事が終わり、マリとクミが食器を洗っている。
リビングの机では、母レーコとコーチがお茶を飲んでいる。
コーチの前にプリン。母レーコ、プリンを見ながら話し出す。
「でもさ、ボクシング始めて、よくなったよ。マリね」
コーチ、プリンを食べようとスプーンを手にしたが、母レーコの話題に付き合う。
「そうすか?」
母レーコ、プリンを見ながら続ける。
「うん。本気になって。本気になることって、なかなか見つけられないじゃない?だから、本気になれることを見つけられたのは、素晴らしいことよ。コーチ、ありがと」
母レーコ、プリンに一礼する。コーチ、笑う。
「母レーコさん、さっきからプリンをガン見してるよね?」
母レーコ、プリンから視線をコーチに移して、言う。
「見てないよ」
コーチ、笑いながら尋ねる。
「食べたいんでしょ?」
母レーコ、お茶碗を持って遠くを見る。
「食べたくないよ」
コーチ、笑いながら言う。
「食べていいよ」
母レーコ、お茶碗を持って遠くを見ながら言う。
「食べないよ」
コーチ、笑いながら言う。
「食べたいでしょ?」
母レーコ、お茶碗を持って遠くを見ながら言う。
「食べたくないよ」
コーチ、一段と笑う。
「あ、また見た」
母レーコ、お茶碗を持って遠くを見ながら言う。
「見てないよ」
厚木ワタナベボクシングジム
小田急線の本厚木駅から5分歩いたところのビルの一階にカレー屋がある。そのビルの5階に厚木ワタナベボクシングジムがある。ルミとコーチがエレベーターを降りて、ジムの入口を入って「こんちはー」と挨拶すると、「ちはーす」と四方から元気のいい男女の声がした。
「おぉ、いらっしゃい」
人当たりの良さそうな、ほんとは50代半ばなのに、見た目は30代後半といった風情の厚木ワタナベボクシングジム種川会長が近寄ってきた。コーチが頭を下げる。
「会長、お久しぶりです。今日は、よろしくお願いします」
種川会長が笑う。
「直木賞のパーティーで会ったから、そんなに久しぶりじゃないだろ?なに?南伊豆に引っ越したの?」
コーチが答える。
「はい。で、LINEご説明した通りなんですけど、地元の人に頼まれてジムみたいなこと始めたんですよ。で、この子、ルミっていうんですけど、なかなかいい感じなんで、会長に見ていただけたらと思いまして、、、」
種川会長、ルミに微笑みかける。
「そう。がんばってね。今日はマスボクシングやってみようか。プロの子、呼んだから。おーい、石川さんと上岡選手〜」
少し大きめの女性と少し小さめの女性が寄ってきた。種川会長が紹介する。
「こっちの少し大きめの人が石川さんね。この前、プロテストに合格したばっかり。こっちの少し小さめの人が上岡由美選手ね。女子ミニマム級の日本ラインキング3位」
女性二人が黙礼をした。ルミも黙礼を返した。種川会長が言う。
「じゃ、あそこ入って手前が女子の更衣室だから、着替えてアップしよう」
ルミが3ラウンドほどシャドーをしたところで、種川会長がヘッドギアとグローブを用意しながら言う。
「じゃ、まず石川さんとやろう。次のラウンドね」
マス・ボクシングは、パンチに最後の力を入れずに打ち合うスパーリングだ。パンチは出すが、相手には当てない。これによって、パンチの出し方や受け方、相手との距離感や相対した時の感覚を知ることができる。
ルミは、種川会長に、ヘッドギアと重めの10オンスのグローブをつけてもらって、リングに上がった。
ゴングが鳴る。
石川選手が左右に動き始める。ルミは、なるべく一緒に動いてパンチを出していく。マス・ボクシングはパンチを当てないので、ハタから見ると何となくおかしくて、炭酸のないソーダのようだが、本人たちは「今のは当たった」とか「今のは避けられなかった」とかが割とわかり、一人で行うシャドーボクシングでは得られない学びがある。
石川選手と2ラウンドやってから種川会長が言う。
「はー、じゃ、1ラウンド休んで。次、上岡選手とやろう」
コーチは喜色を浮かべた。種川会長に一礼し、サンドバッグを打ってる上岡選手にも頭を下げた。リングから出て休んでいるルミに語りかける。
「上岡由美子選手だからな。日本ランカーだぞ。日本タイトルに挑戦経験もある人だぞ。いい経験だから、人生で一番集中してけ」
ルミは、上岡選手を見た。ルミよりも小さかったが、半袖のTシャツから見える腕の筋肉が、女性としては見たことがないくらい締まっていて、筋張っていた。「これが日本ランキング3位の筋肉か」と思った。
本厚木駅のホームに特急ロマンスカーが入ってきた。先頭車と最後尾車が2階建てになっている。運転席が2階にあるため、1階の座席は車両の最も前まであって、前方の景色が展望できる。
一番前の座席で、ルミとコーチが並んで座って、アイスを食べている。ルミは、前方に流れる景色を見て感極まった。
「いやー、すげーっす。今日は、なんか、楽しいことが一杯で、どーしよーって感じ」
コーチが苦笑しながら言う。
「上岡選手、スゴかっただろ?」
ルミが声を一段あげる。
「いやー、すげーっす。さーすが日本ランカー。アタシたちとは動きが違うよー。ぜーんぜん違う。早い早い。何もかも早い」
コーチが同意する。
「そーだよなー。ほんと、そーだよなー。すごかったなー」
ルミが言う。
「でも、石川選手なら多少対応できますかね。対応できるっつっても、何とかついていけるっていうか、、、」
コーチが笑顔になる。
「ま、馴れてくればな。よし。何とかなるな。プロが見えてきてるな」
二人はアイスを食べた。前から流れる景色を、楽しそうに目で追う。
コーチが口を開く。
「質問していい?」
ルミ、不審げにコーチを見る。
「な、なんすか?」
コーチ、笑顔で尋ねる。
「いや、なんで石原裕次郎好きなのかなー?って前から思ってて。だって、オレのオヤジか、下手すると祖父さんの頃の人じゃん?」
ルミ、やっぱり不審げにコーチを見る。
「え?真面目に聞いてます?」
コーチが真顔でうなづくので、ルミも真顔になって答える。
「じゃ、真面目に答えますと、あたしには生まれた時から父も母もキョウダイもなくて、あたしの育ったところは灰色で、見せかけのやさしさと紋切り型の思いやりしかなくて、そんな時、小学校の高学年の頃かな、裕ちゃんの歌を聴いたの。
なんて言ったらいいのかな。うーん、はじめて美しいものに触れたっていうのかな、ま、つまり感動したの。とーっても。
それからずっと裕ちゃんの歌聞いて、裕ちゃんの映画見て、裕ちゃんみたいな人を探してるの。だから変なのにダマされちゃうのかな。へへ」
ルミがアイスを食べ続ける。ルミがふと気づくと、コーチのアイスを食べる手が止まっている。コーチを見ると、何だかウルウルしている。
「あれ?なんでウルウルしてんすか?」
コーチ、答えられない。ルミにアイスを渡して「これ食え」と細い声で言って、自分はカバンからウェットティッシュを取り出して目に当てている。ルミが笑う。
「なんすかー?やだなー、もう。人目があるんだから、やめてくださいよー」
ロマンスカーが「キンコンカンコン カンコンキンコン」と補助警報音を鳴らした。
※続きはこちら↓
