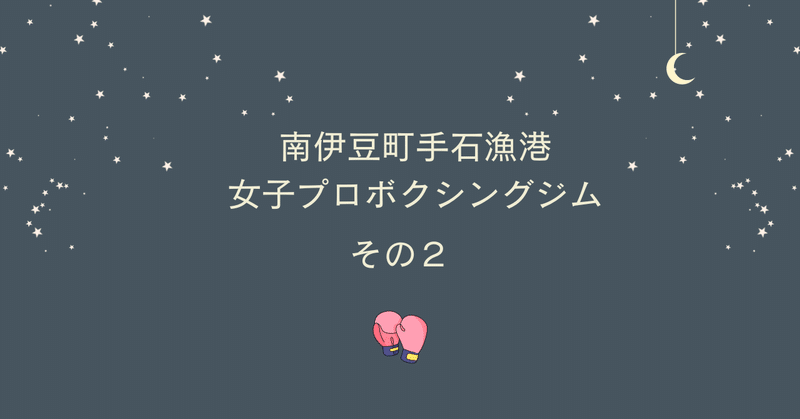
小説:南伊豆町手石漁港女子プロボクシングジム その2
漁協長
「えぇ!?16人ー!?」
コーチは、自分の家の駐車場でビックリしている。背後でクミとマリがシャドーボクシングをしている。
コーチはイスに座った母レーコにバンデージを巻いている。コーチの横にはトモ子が立っている。母レーコは微笑しながら、困ったように言う。
「いやー、なんかさ、このトモ子がね、「他にも希望者いるか聞いてみる」なんつってね、コーチ、都会の人にはわかんないだろうけど、漁村はみんな仲良くしないといけないのよ。みんなにも一応お伺いたてないと」
コーチは母レーコのバンデージを巻きながら困った顔になる。
「でもさー、16人て、オレ、素人コーチだよ?だいたい、ここで16人も練習できないでしょ?」
笑顔のトモ子が、よくできる営業員のように口を挟む。
「いやいやいや、コーチ、コーチィ、漁協に協力してもらうから。いまの漁協長は、昔っから母レーコのシモベだから」
母レーコ、はにかむ。
「そんなことないよぉー」
トモ子が話しを続ける。
「それに、アタシ達が順番で夕食作っから。コーチ、毎日違うメニューを食べられるよ。夕食に困らなくなるよ」
コーチ、バンデージを巻く手を止める。感じいったように顔をあげて、二人を交互に見る。
「それ、魅力」
母レーコとトモ子が微笑む。コーチが続ける。
「ご飯炊くボタン押したけど、炊飯器に水入れてなくて、さぁ食べようと炊飯器あけたらご飯炊けてなくて、ただ米があったまってただけってことありますよね?」
母レーコとトモ子、口を揃える。
「ありません」
コーチ不満そう。
「ない?」
母レーコとトモ子、うなづきながら口を揃える。
「ない」
「ない」
コーチ不満そう。
「私にはあります。だから、あなた方のご提案は魅力的。とーっても魅力的」
母レーコとトモ子、悪そうにニヤッと笑った。
1階が母レーコ達の作業場になっている建物の2階が漁協の事務所だ。事務所の中は簡素な作りだが、三方から南伊豆の海が見えて、とても落ち着く。そこには古いが造作の良いソファーが置いてあって、母レーコとトモ子とコーチが座っている。そこへ男が近づいてくる。
「どーも、どーも、どーも。お話は伺ってます。なんか、奥さまたちがご迷惑おかけしてるようで、すいませんね」
日に焼けた、ひげ剃り後の青い、若いんだかトシ取ってんだか、よくわからない筋肉質そうな男が、笑顔でコーチに名刺を渡しながら向かいの席に座った。
「どーせ、トモ子が「漁協長はレーコに惚れてるから、何でも言うこときくんだ」とか言ったんだら?」
と漁協長はトモ子を見た。トモ子はキョトンとしている。
「言った」
漁協長が笑う。
「ぶははははは」
母レーコとトモ子も笑う。
「はははは」
「はははは」
コーチは笑っていいのかどうか、よくわからないので、難しい顔をしてみた。
事務員の若い女性がお茶を持ってきて4つ置いた。4人とも一口飲んだ。漁協長が茶碗を置いた途端に声を上げる。
「わかりました。ボクシングジム作りましょう」
コーチはお茶碗を持ったまま、心からビックリした。
「えぇぇえ!そんなに簡単にぃ!」
漁協長が微笑んでいる。
「だって、ほら、奥さまたちのタメになるでしょ?ここら辺、ほら、何にもないし。町にも補助金出すよう言ってみますよ」
母レーコとトモ子が悪そうに微笑しながら言った。
「さーすがー。さーすが、イチローくん」
漁協長、まんざらでもないように、照れくさそうに、
「オオヤケの場で名前で呼ぶならー」
母レーコとトモ子が悪そうに微笑している。
「そうだそうだ。さーすが漁協長」
「よっ、漁協長」
漁協長、マッスルポーズで受け止める。ちょっと照れくさそうにコーチの方を向く。
「じゃ、さっそくジムの候補地お見せしますら。ご意見ください」
コーチが茶碗を持ったまま、さらにビックリ。
「えぇぇ!もう候補地もあるんですか!?」
漁協の建物のすぐ横に平屋のプレハブが建っている。漁協長が引き戸をあけてプレハブに入っていくと、色んな古いモノが置いてあって、特有の古い匂いがする。漁協長が説明する。
「ここね、昔、魚がもっといっぱいとれた頃に作業場として作ったんだけど、最近、魚減っちゃってさ、何十年か前から物置になってんだけど、ここ片付ければジムできるら?どう?」
コーチ、中を見回す。
「リングのサイズが6m×6mくらいですから、どうですかね?入りそうですね」
漁協長が答える。
「入るかなぁ。あとで計っとくわ」
トモ子が楽しそう。
「眺めのいいジムになりそうねー」
コーチ、同意。
「そうですねー。日本一眺めのいいジムになるかも」
漁協長、手を打つ。
「いいね。いいら、それ。「日本一眺めのいいジム」。それで静岡新聞載せよう」
母レーコ、笑う。
「なーにー、町長選の実績作り?」
漁協長、笑う。
「まーな。ニュースバリューあるら?」
コーチが尋ねる。
「町長選?」
トモ子が解説する。
「次、狙ってんのよ。みんなで応援しなきゃ」
漁協長、作り笑い。
「コーチ、もう漁協長派だぜ」
コーチ、ビックリする。
「えぇぇ!?」
コーチ以外の3人が悪そうに笑った。
母レーコ、トモ子、コーチ、漁協長が漁協の事務所に戻って座った。すぐに事務員がお茶をもってきて、4つ置いた。4人ともお茶を一口飲んだ。漁協長が茶碗を置いた途端声を出す。
「で、コーチ、必要なものをさ、書き出して送ってよ。メールでいいから。メアド、名刺に書いてあっから。オレたち何が必要かわかんないからさ。なるべく何とかすっから、、、」
コーチが困り顔。
「そうですねー、16人もいるとなると」
漁協長がビックリしてトモ子を見る。
「え?もう16人も集まったら?」
トモ子が少し自慢げ。
「そうだよ。直木賞作家で元プロボクサーのいい男が無料で教えてくれる、って言ったら、すぐ集まっちゃった」
漁協長が首をかしげる。トモ子に尋ねる。
「直木賞ってなんら?」
トモ子、自信ありげに笑顔。
「さぁ?」
母レーコが口を挟む。
「エラい人しかとれない、エラい賞よ」
コーチが苦笑。みんなお茶を飲んだ。漁協長が茶碗を置いた途端声をあげる。
「そーかよー。男共に解放しようと思ったけど、そんなにいたらダメら?」
トモ子が勢いよく言う。
「ダメだよー。みんな友だち呼んで、もっと増えるだろうし、男たちのヤ〜らしい目あるとやりにくいしさ、、、」
漁協長が納得する。
「なんだらー。そーかよー。そしたら、女子ボクシングジムだな。「南伊豆町手石漁港女子ボクシングジム」にすっか?静岡新聞に載っける時は?」
母レーコがほほえんだ。それを見て、漁協長はちょっとうれしそう。コーチもほめる。
「いいですね。がんばってる女子が集まってる感じで」
漁協長、締まった顔で言う。
「よし。じゃ、急いで準備すっから」
母レーコとトモ子がはやしたてる。
「漁協長、ステキー」
「ステキー」
漁協長、マッスルポーズで受け止める。コーチは「この人、ほんとにだいじょぶなのかな?」と思った。
ジム開き
6月になった。
曇り空の水曜日。
コーチの家の駐車場で、クミ、マリ、母レーコがシャドーをしたり、サンドバッグを打ったりしている。コーチも一緒にやっている。
ゴングが鳴る。
みんな、それぞれに休み始める。母レーコがコーチに近づく。
「漁協のジム、土曜日に使えるようになるって。色々あるから、12時に来てほしいって」
「(喜ぶ)おー。できたんだー。楽しみだねー」
「(苦笑)みんな、早く練習させろってうるさいのよー。「あんただけ練習すんな!いい男独り占めかって」」
コーチも苦笑。ゴングが鳴って、みんなそれぞれに練習を始める。
次の土曜日。
別荘地の入口あたりをコーチが歩いていると、弓ヶ浜方面から子どもが8人ほど、自転車に乗って楽しそうに通り過ぎていった。子ども達を目で追ったコーチは、漁港の人だかりを見つけた。不思議そうな顔をして漁港に向かって歩いて行く。
近づいてみると、漁港は小さなお祭りのようになっていた。屋台も3つほど出ている。プレハブの方に目をやると、ピンク色に塗られていて、屋根の上にファンシーな雰囲気の看板がかかっていた。「南伊豆町手石漁港女子ボクシングジム」と記されている。
コーチは、呆然としてプレハブの前に立った。
マリが近づいてきた。
「ちーす」
コーチがマリに目をやった。
「お、おぉ、なんだよ。こんなニギニギしくやるんなら、言ってよ。もうちょっと、ちゃんとした格好でくるから」
「(微笑)ちゃんとした格好ってなに?」
「背広とかさー。Tシャツにサンダルで来ちゃったよー」
確かに、よく見ると、Tシャツには「働きたくない」と大書してある。マリが笑う。
「はははは。いーぢゃん。確かにちょっとチョロい格好だけどさ、コーチいなきゃ始まんないわけだしさ」
あっちから、漁協長が呼びかけながら寄ってくる。
「おー、コーチー、コーチー、」
マリはサッとコーチと腕を組んだ。漁協長がマリを見た。
「あっ、マリ、お前また酒飲んだな。顔赤いぞ。まだ未成年だろ?」
マリが可愛く笑う。
「エヘ」
漁協長がコーチを見る。
「ま、いいや、コーチ、コーチ、ちょっとお偉いさんに挨拶しとこ」
漁協長がコーチの手を引っ張って歩き出す。コーチの反対の手には、マリがくっついて一緒に歩き出す。
イカの姿焼きを食べているハゲた背広の70代くらいの紳士が立っている。漁協長が呼びかける。
「町長ー、まーたイカ食ってー」
町長が食べるのをやめて漁協長を見る。
「うっせーらー。イチロー、お祝いの席くらい心ゆくまで食わせろ」
漁協長がコーチを指す。
「この人、ほら、コーチ、直木賞の、、、」
町長、容儀をただす。
「あー、あなた。どーもどーも、町のためにありがとうございます」
町長、握手しようとするが、イカの姿焼きを持っているため握手できない。あたりを見回すと、コーチの横でマリが微笑んでいるので、マリにイカを渡す。ポケットからウェットティッシュを取り出して手を拭いてから、コーチの両手をとって、ぶらんぶらんと大きな握手をした。
町長、あたりをうかがって、漁協長とコーチに「近くに」という仕草をする。3人、顔を寄せ合う。町長が小声で言った。
「あのね、内緒だけどね、、、オレはボクシングに予算つけようと思ってっから」
コーチも小声で言う。
「えー、ありがとうございますー」
町長、やっぱり小声で言う。
「あんたのお陰でいいこと始まるよ。漁協長もいいことしたな」
漁協長も小声で言う。
「じゃ、ひとつ、後継指名、よろしくお願いします」
町長は寄せていた顔を離し、苦笑しながら普通の声で話し始める。
「そりゃー、別の話じゃらー」
ふと町長が横を見て「あっ」と言った。マリが町長のイカをモグモグ食べている。
「あ、おめー、なんでオレのイカ食ってんだ!」
マリ、モグモグしながら半笑いで言う。
「えっ?くれたんでしょ?」
町長、苦笑しながら言う。
「くれたんじゃねーべー。「ちょっと預かっといてね」って渡したんじゃらー。まったく、昔っからおめーわー」
漁協長が困り顔で間に入る。
「ま、ま、ま、町長、町長、あっちにイカ用意すっから。たーくさん、あっから」
町長と漁協長、マリに「メッ」という顔をする。町長がコーチに向き直って話し出す。
「そんなわけでね、コーチね、ひとつがんばってくださいね。ここら辺は、ほら、漁業と温泉と海水浴以外なーんもないからさ、コーチにがんばってもらって、地域の活性化をね、ひとつね、、、」
町長が漁協長と連れだって、イカを食べに屋根付岸壁の方に向かった。マリがイカを食べながら言う。
「手際良すぎるよねー」
コーチ、尋ねる。
「なにが?」
「ボクシングジムできるの」
コーチ、少し考える。
「うーん、漁協長が有能なんじゃない?」
マリ、イカを一口食べる。
「そーねー。それもあるわねー。そして、あの二人の選挙対策かも、、、」
コーチ、笑う。
「そーなのかな。でも、それもいいじゃない。ボクシングジムできたんだから」
「あら。コーチ。柔軟」
コーチ、作り笑顔。
「重要なのは、目的が達成されたか、じゃない?」
マリも作り笑顔になる。
「そっか。それもそうだね。めでたいね。見た?すごいリングあるよ」
コーチが急に走り出した。マリも負けずに走る。二人が小走りでプレハブの中に入る。たしかに立派なリングがある。コーチが驚く。
「すげー、すげー、高そー」
二人でリングの回りを回る。マリが尋ねる。
「コーチが選んだんじゃないの?」
「(微笑)違うよ。こーゆーやつ、ってアドバイスはしたけど」
コーチがリングに入る。
「うわー、すげークッションだー。オレの行ってたジムだって、こんなのなかったぞ。すげー」
コーチがシャドーし始める。マリのことを見つめながら、微笑してシャドーしている。マリが苦笑。
「やめてよー。気持ち悪いよー」
コーチが微笑してシャドーしながら、マリを見る。
「だってさー、スゴいよー、クッション効いてるよー。マリちゃんもやってみ。やってみ」
マリもリングに入って、一緒にシャドーを始めた。
「あー、ほんとだー、すごいクッションだー」
コーチがうれしそう。
「なー、なー」
マリとコーチ、微笑しながらシャドーしている。そこへ漁協長が声をかけた。
「コーチー」
マリとコーチ、微笑してシャドーしながら漁協長の方を見た。コーチが言う。
「あ、漁協長、こんな立派なリングをありがとうございます」
漁協長、ちょっと笑いながら、
「いーんだ、いーんだ。そんなこと、あと、あと。挨拶回りしよう」
漁協長がコーチの手を引っ張ってプレハブの外で出て行く。
プレハブの外で、マリがイカの姿焼きを食べている。トモ子がやってくる。いつもと違い、パートの面接に行くようなピッチリした服。
「マリ、イカ食べ過ぎだよ」
マリ、口を曲げる。
「まだ3本半目だよ」
「(少しあきれる)まったく、あんたは、小さい頃からイカばっかり食べるんだから。ま、いいや、コーチどこ?」
マリがイカの姿焼きで岸壁の方を指す。
「漁協長に連れ回されてる」
「(少し笑う)あ、ほんとだ」
「コーチ、大変だよー。町長にも挨拶して、警察署長、教育長、自治会長が4人、消防団長、小学校の校長先生、中学校の校長先生、片っ端から挨拶してたよ。コーチを町議選にでも出そうとしてるの?」
「ははは。あんたもジム入って入って。もうすぐ式始まるから」
マリがジムに入ると、酒樽が3つ積んであった。リングの前にロの字に机が並べられて、酒盛りの用意がしてある。当たり前のように、奥さま多数が座っている。リングの中にはマイクとマイクスタンドが立っている。
ルミ
トモ子に連れられて、コーチと漁協長がジムに入ってきて、一番上座に座った。
トモ子がリングに入って、マイクで喋る始める。
「えー、どうもどうも、ごきげんよう。本日はお日柄もよく、皆さん、よくぞお運びくださいました」
窓の外にも入口の外にも人だかりができていて、その中にいる酔っ払った男がヤジを飛ばした。
「結婚式じゃねーぞー」
トモ子がヤジを飛ばした男を見る。
「うっせータケシ、ボケー(笑)」
ジム内に笑いが起こる。トモ子がジム内に目をやる。
「あ、すいません。はしたない言葉づかいで」
ジム内、笑い。トモ子が続ける。
「えー、まずね、町長や漁協長からご挨拶をいただくところではありますが、お二方に打診したところ「オレはいいよ」とね。どうしたんですかね?スピーチ大好きのお二人が、いつ、どこで謙遜を身につけたのか、そーゆー奥ゆかしいことをおっしゃっておりますのでね、まずね、このジムを作るキッカケを作ってくれた、そしてこのジムで教えてくれるコーチをね、紹介しますね。どうぞ〜」
ジム内から大きな拍手。コーチは何となくイヤそうに立ち上がって、リングに入って、マイクの前に立った。
「いやー、こーゆーの苦手なんですが、何か挨拶しろ、ということなので、一言申し上げます」
ジム内から大きな拍手。コーチ、漁協長の方を向いて言う。
「漁協長、こんな立派なジムをありがとうございます。皆さん、これスゴいよ。オレが行ってたジムより立派だよ」
ジム内笑い。コーチが続ける。
「じゃ、これからボクシングを学ぶ皆さんに申し上げますね。ボクシングは、ルールに沿って行われる「スポーツ」です。スポーツは、自分を高めるために行うものです。ケンカに使ったり、弱いモノいじめに使ってはいけません。
このジムで学んだボクシングをケンカに使ったり、弱いモノいじめに使ったりした人がいたら、その人は破門です。
ま、奥さまが多いのでそーゆー人もいないとは思いますが、もしいたら、その人はその入口からこのジムの中に入れなくなります。わかりましたか?」
ジム内から「はーい」という声。コーチが続ける。
「じゃ、私の話は終わります。皆さん、がんばりましょう」
ジム内から拍手。その中で、ルミが手を挙げている。
「コーチ、コーチ、質問があります」
リングしたに降りようとしていたコーチはマイクのところに戻った。
「はい、はい、何でしょう?」
ルミが立ち上がった。
「わたしでもプロになれますか?」
思いがけない質問に、コーチは少し考える。
「えぇと、それは人それぞれなんですが、、、」
コーチは目を鋭くしてジッとルミを見つめた。上から下までジックリ見ている。ボーイッシュで80年代のロックンローラーみたいな服装で、「映画『恋したくて』のメアリー・スチュアート・マスターソンみたいだな」と思った。でも、よく見ると、彼女の来ているTシャツの絵柄は石原裕次郎だった。
「なにかスポーツしてましたか?」
ルミが答える。
「はい。中学校ではテニスと中距離を」
コーチが尋ねる。
「成績はどの程度?」
ルミが答える。
「静岡の県大会に何度か、、、」
コーチの表情がやわらぐ。
「なんだ。なれますよ。女性はもともと運動する筋肉が足りないことが多いんですが、あなたならだいじょぶでしょ。33歳以下ですねよ?」
「はい」
「じゃ、真面目にコツコツ練習すれば、だいじょぶです。なんか、前に母レーコさんにも同じこと聞かれたんですが、ここら辺の女性はアレですか?みんな強くなりたいんですか?」
ジム内、笑い。コーチが続ける。
「いいですね。そーゆー前向きな女性大好きです。えーと、何事もそうですが、「強くなりたい」「プロボクサーになりたい」と心から願って、毎日努力すれば、そうなれます。
ほんとですよ。簡単でしょ?
でも、願うだけじゃダメだし、努力するだけでもダメね。願って、努力するの。
あなた、質問してくれたあなた、それを証明して手石漁港女子ボクシングジムのプロ第一号になってください」
ジム内「おーっ」っと盛り上がる。
コーチがプレハブから外に出てきた。手に紙コップを持っている。ダメージを受けたように近くにある花壇のコンクリートに座り込んだ。
プレハブの中では宴会が始まっていて、大きな声や笑い声がする。
コーチは紙コップの中身を飲もうとして、顔をしかめた。水だと思ったら、日本酒だった。立ち上がってジムの入口に行き、中を見回してマリを探した。幸いマリは入口の近くの端っこに座っていた。マリに近づいて、肩をたたいて、顔を近づけて言った。
「あのさ、水ない?」
マリは顔をゆがめた。
「はぁぁ?みずー?」
コーチはジムのそばの花壇のコンクリートでグッタリしている。マリが紙コップを持ってきて渡す。コーチ受け取ると一気に飲む。マリは苦笑しながら尋ねた。
「なんでそんなにグッタリしてるの?」
「(グッタリしながら)なぜだろう?人にたくさん会ったからかな。普段、キミたち以外と会わないから」
「そんなの、ビールでも引っかけて調子よくやっちゃえばいいのに」
コーチが厳しい表情になる。
「ボクサーが酒なんか飲むわけないだろ」
マリ、ビックリする。すごくビックリする。
「えぇぇぇぇ〜!!」
すぐ振り返ってジムの方に走っていった。
コーチ、キョトンとしている。
海猫が鳴いているので、そちらの方を眺めていると、マリがみんなを連れて小走りに戻ってきた。漁協長も母レーコもトモ子も小走りでついてきている。漁協長が真剣な顔で尋ねた。
「コーチ、ボクサーって酒飲めないの?」
「当たり前です」
漁協長が困惑した顔で尋ねる。
「一滴も?」
コーチがうなづく。母レーコが悲しそうな顔で言う。
「アタシたち、お酒飲めないと死んじゃうんだけど、、、」
コーチ、苦笑して母レーコを見る。
「いや、プロよ。プロボクサーとかプロを目指す人の話」
どよめきが起こった。みんな、ゆっくりジムの中に戻り始める。漁協長、笑いながら言う。
「なんだ。プロの話か。じゃ、コーチ、あっちに一席用意してあっから、一杯いこう」
コーチ、驚く。
「えっ?オレ、あんま飲めないんすよ。だいたい、練習は?」
漁協長がしたり顔で言う。
「え?今日はジム開きでしょ?練習はジム開きしてからだら?お祝いなんだから、飲まないと」
コーチ、不安そうな顔で母レーコ見て言う。
「え??レーコさん、レーコさん、今日は練習ないの?」
母レーコは赤ら顔で言う。
「え?ないでしょ?お祝いでしょ?コーチも飲まないとダメだよ。一人でもお酒飲まない人がいると、不吉なことが起こるってここら辺じゃ言われてんだよ」
コーチ、絶望した顔で母レーコを見ている。
ユー子とミッコ
ジム開きが続いている。
コーチはジムの端っこに横たわって、酔いをさましている。ジムの中からは三方に海が見える。昼間から宴会するには最高の場所だ。みんな、すごく盛り上がっている。机はもう片付けられて、みんな床に座って飲み交わしている。
しかし、コーチは横たわっている。そんなコーチを、ちょっと離れた対角線上から母レーコとトモ子が見ている。トモ子が母レーコに言う。
「コーチ、お酒弱すぎじゃない?」
心配そうな母レーコが言う。
「思いがけず色んな人に会わされて、久しぶりに飲まされて、疲れちゃったんじゃない?」
トモ子が母レーコを見て、笑顔になった。当然、酔っ払っている。
「よかったねー。ジムができて。楽しくなりそー。母レーコのお陰だよ。ありがと」
母レーコが苦笑する。
「クミとコーチと漁協長のおかげよ」
トモ子があたりを見回す。「おっ」っと言って、母レーコの手をとって漁協長の近くに寄っていく。
「はいはい、すいません、すいません。ぎょきょぎょ、ぎょ、ぎょきょ、、、イチローくーん」
漁協長、笑顔でトモ子を見る。当然、酔っ払っている。
「おぉー、トモ子ー、トモ子ー、お前も飲んでるらー!まーた酔っ払いやがって。いいぞ、いいぞー」
トモ子、笑いながら漁協長の目の前に座る。
「そーれーす。イチローくん、ありがとね。ジム作ってくれて」
トモ子、急に涙ぐむ。漁協長、笑う。
「なんだよー、もー、やだなー、トシとると涙もろくなって。よせよ、おまえ、人が勘違いするだろ(笑)」
トモ子と母レーコ、笑う。漁協長も笑う。
「それに、オレのお陰じゃねーよ。クミとコーチのお陰だろ?みんなの金だし」
トモ子、漁協長を指さしながら言う。
「くー。カッチョいいなー。ね?母レーコ?ほら、イチローくん、母レーコ、母レーコ」
と、母レーコを指さし始めた。漁協長、笑う。
「わかってるよ」
母レーコがお礼する。
「ほんと、ありがとね」
漁協長、ビックリした顔になる。
「なんだよー。レーコまでそんなこと言って。ぢゃ、嫁に来てくれ」
トモ子がツッコむ。
「もう嫁いるだろ」
3人で笑った。
コーチは、やっぱりジムの端っこで横になっている。そこへマリが四つん這いで近づいてきて、コーチの肩をゆする。
コーチは起きない。
耳を引っ張る。
コーチは起きない。
ほほをつねる。
コーチは起きない。
マリ、「ちっ」とつぶやいて、コーチを揺り起こす。
「コーチー、コーチー、、、」
コーチの上半身が起き上がった。気づくと、マリが笑って見ている。
「なに?なに?」
「コーチー、ほんと?強くなれる?」
コーチ、ぼんやりしている。
「え?」
「コーチー、あたし父ちゃんいないけど、強くなれる?」
「当たり前だろ。さっき言っただろ」
マリ、腕を組んで考え始める。コーチ、苦笑い。
「聞いてなかったの?」
「(首をふる)うぅん。聞いてたよ」
コーチ、笑う。
「聞いてなかったでしょ?」
マリが「うひひひ」と笑って、スキップしながらジムを出て行った。
コーチはボーッとしてジムの中を眺めている。みんな楽しそうに宴会している。
急にマリが耳元でささやく。
「努力すれば強くなれる?」
コーチ、ビックリする。
「なんだよ。普通に話せよ」
マリが「エヘ」と可愛い子ぶる。コーチが言う。
「違うよ。願って、努力すんだよ。強ーく願って、最大限に努力すんだよ」
マリがコーチの横に座って言った。
「ふーん」
二人でボーッと賑わう宴会を見ている。マリがボソっと尋ねる。
「コーチは、幸せってなにか知ってる?」
急に深遠な問いかけが行われたので、コーチはドギマギした。マリがジッと見ている。コーチはドギマギしながら言った。
「えぇー、わかんないよぉ。そんな急に、、、」
マリはがっかりした顔をする。
「えー?少しは名前の通った小説家なんだから、もうちょっと、ちゃんとしたこと言ってよー」
コーチが顔色が悪くなり、黙ってしまった。今度はマリがドギマギした。
「あ、怒った?」
コーチが絞り出すように言う。
「気持ち悪い、、、」
マリがビックリする。コーチがさらに絞り出すように言う。
「、、、ゲロしたい、、、」
マリが急いでコーチを手を引いて、漁協のトイレに急いだ。
ジムの中で酒を飲みながら、母レーコとトモ子が適齢の女性の相談を受けている。
「だからさ、ヘンな客やっつけたいのよ」
トモ子が同情したように言う。
「ユー子さんとこ、面倒そうなお客いそうだもんねー。でもさ、男相手に勝てるのかな?どーなんだろ?」
ユー子、残念そうに言う。
「無理かな。コーチに聞いてみようかな」
母レーコが口を挟む。
「ダメだよ。そんなことコーチに聞いちゃ。さっき言ってたじゃない。「ケンカに使ったら破門だ」って」
ユー子とトモ子が納得する。
「そうだ。言ってた」
「そうだ、そうだ」
トモ子が提案する。
「護身術ってことにすれば?「お店で襲われそうになったとき、身を守れますかねー?」なんて方向で質問すれば?」
母レーコ、トモ子を指さす。
「それ、ナイス」
ユー子、よろこぶ。
「いいね、いいね。それで聞いてみる」
ユー子、あっちの方を見ると、コーチが横になっている。横になっているコーチに、クミとマリがじゃれついている。ユー子、モンローウォークでお尻を左右に振りながら、コーチに近づいていく。
「コーチぃ、コーチぃ、いまちょっといいですかぁー?」
コーチは、語りかけてきたユー子を見て「日劇ダンシングチームにいそうな美人だな」と思った。そして、目が釘付けになった。胸の谷間が深いのだ。深い谷間に向かって言った。
「はい。どうぞ」
ユー子は、魚が餌にくいついた釣り人のようにニヤリと笑って、少し高く甘い声で尋ねる。
「あたしね、この近くで寄るのお店やってるユー子です。どうぞ、よろしく」
コーチが上半身起きあげて、一礼した。ユー子が続ける。
「でね、お店の中で男に襲われたらどうしよう?って、いつも心配なんです。ボクシングやると、そんな男やっつけられますかね?」
コーチがユー子の腕に目を移した。
「うーん」
コーチはユー子の体を凝視した。上から下まで、なめ回すように凝視している。ユー子はちょっと恥ずかしそう。コーチが尋ねる。
「なんか運動やってましたか?」
ユー子が恥ずかしそうに答える。
「いいえ」
コーチがやっぱり体を凝視しながら言う。
「ちょっと右腕を横に上げてみてください」
ユー子は少しためらいながら、右上で真横にあげた。コーチは10秒ほど凝視してから言った。
「うーん。ちょっと、どーかなー。筋肉が足りないかなー。週2日、一年練習すれば何とか」
ユー子の目が輝いた。
「やっつけられるの?」
コーチが微笑しながら答える。
「えぇ。男は油断してますからね。「女なんか」って。だから襲うわけじゃないですか?」
ユー子が真剣な顔でうなづく。
「えぇ、えぇ」
コーチが真顔で言う。
「油断してるとこにスパっとパンチ入れるのは簡単ですよ。ただ、やっぱね、どーしてもね、パンチ力が必要なんですよ。相手を倒すには。だから、必要な筋肉つけるのに週5日練習すれば半年、週2〜3日練習すれば一年かな」
ユー子が真剣な顔で言う。
「へー」
急に、マリがコーチの手を取った。
「コーチー、あっちでお偉いさんが呼んでるよー」
コーチ、ウンザリする。
「なんだよー。またお偉いさんかよー」
マリがコーチを引っ張って外に出てくると、一緒に花壇のコンクリートに座った。コーチが不思議そうに尋ねる。
「どこ?お偉いさん」
マリが半笑いでコーチを見た。
「あれはウソ。あの人ね、ユー子ちゃん、昔「ミズウオ」って呼ばれてたの」
コーチがつぶやく。
「ミズウオ?」
マリが半笑いでうなづく。コーチが不思議そうに尋ねる。
「なんで半笑いなの?」
マリが半笑いで答える。
「なんでも食べちゃうから「ミズウオ」。最近そーでもないんだけど、昔の話らしいけど、さっきはユー子ちゃんの目の色が変わってたから。コーチ、危なかったね」
コーチ、憮然とする。
「んなこたないよ」
マリ、相変わらず半笑い。
「コーチ、巨乳大好きなんだね?」
コーチ、ビックリする。
「ドキ。なんで知ってるの?」
マリがビックスマイルになった。
「なーに言ってんの。さっきので丸わかりだよー。ユー子ちゃんにもわかっちゃったよー」
コーチ、恥ずかしそうに言う。
「そ、そう?し、しまったなー」
マリ、うなづきながら言う。
「わかるよー。ユー子ちゃんのオッパイは強力なんでしょ?でもね、コーチ、ユー子ちゃんは一回食べちゃうと、あっちでもこっちでもコーチの諸々を批評しだして、翌日には漁港の婦人会全体に知れ渡ってるよ。さっきのままだったら、明日にはもうみんなコーチ見て半笑いだよ」
コーチは目をつぶって空を仰いだ。
少しして、今度はうつむいて首を振った。
少しして、シンミリとした口調で言った。
「ありがとう。マリちゃん。ほんとに、ありがとう。今後とも色々と教えてね」
その光景を、ルミが立って見ていた。思い切ったように話かけた。
「コーチ、あの、、、」
マリがさっとコーチの耳元でささやいた。
「ルミさん。浜松出身の20代前半。ダンナは手石の漁師。子どもナシ」
コーチが立ち上がって握手を求めて、爽やかに言う。
「やぁ、さっき質問してくれた方ですね」
握手をしながら近くで見ると、彼女の来ているTシャツには、石原裕次郎の顔と「オレは待ってるぜ」というロゴがプリントされていた。
「はい。ルミです。よろしくお願いします。あの、プロになるには週に何回くらい通うといいんですか?」
コーチは笑顔で答える。
「そりゃ、毎日だけど、とりあえず週3日かなー。県大会は何の種目で出たの?」
ルミが答える。
「800mで」
コーチは笑顔で言う。
「そしたら体力的な問題はないね。だんだんと週5日練習できるようになれば、プロはすぐそこだよ。一緒にがんばりましょう」
ルミはコーチと握手して、ニッコリ笑って去っていった。というか、ジムの中に戻って、また飲み始めた。ルミが去ったあと、マリがつぶやく。
「ルミちゃん、可愛そうなんだ。ダンナがダメ男で暴力男で、殴るの。子どもも出来ないからダンナの実家からもイジめられて、、、」
コーチ、ジムの方を見ている。
「ふーん。なんで石原裕次郎のTシャツなの?若いのに」
ルミが、シンミリ気味に答える。
「会ったことないお父さんが港の人だったんだって。それで港が好きで、港と言えば裕次郎じゃない?」
コーチ、ルミを見る。
「そうなの?」
ルミが力強く答える。
「そうでしょ?他にいないでしょ?だから裕次郎が大好きなんだって」
コーチが「へー」と言った。マリが続ける。
「コーチ、プロにしてあげてね」
コーチ、真面目な顔でジムの方を見ながら言う。
「オレはプロにできないよ。彼女が自分で努力しないと。オレは手伝いしかできないんだ」
マリ、真面目な顔でコーチを見る。
「コーチ、時々いいこと言うね。さーすがピューリッツァー賞受賞者」
コーチ、吹き出す。
「なんで外国の賞なんだよ」
マリがケラケラ笑っていると、低めの声で呼びかけられた。
「コーチー」
コーチが声の方を向くと、高そうな洋服を着たご婦人が立っていた。マリがコーチの耳元でささやいた。
「ミッコちゃん。町の実力者」
コーチ、立ち上がって、満面の作り笑いで握手を求める。
「よろしく。ボクシングやるんですよね?がんばりましょう。あれ?」
ミッコが言う。
「えっ?」
コーチが言う。
「奥さま、グロリア・スワンソンに似てますね。映画の、『サンセット大通り』の」
少し間があいた。マリが「コーチ、何言っちゃってんだろう」と思っていると、ミッコがうなるように声を出した。
「うあ、、、」
コーチが言う。
「あ?」
ミッコがやっと笑い出す。
「うあ、、はははは。コーチ、お上手、、、」
ミッコは表情を変えないで笑って、そして去って行った。マリがコーチに教える。
「ミッコちゃん、お金持ちで色んな美容してるから、笑っても表情変わらないんだ」
コーチが言う。
「ちょっと怖かったね」
マリがうなづきながら言う。
「でも、町の実力者で、70歳以上の老人たちのほとんどは彼女が押さえてるの。老人ホームとかデイサービスとかやってるから。年寄りって、あんまりこーゆーとこ顔出さないからわかんないんだけど、実は最大勢力」
コーチは感心した。
「マリちゃんは、物知りだなー。スゴいなー」
マリが照れる。
「あとね、漁協長のおばさんね」
コーチが驚く。
「え?親戚なの?」
マリがうなづく。
「うん。漁協長の亡くなったお母さんのお姉さんがミッコちゃん」
コーチが驚く。
「へー。あんまり似てないね」
マリが苦笑する。
「昔は似てたけどね。ミッコちゃんが美容にすごくお金使い始める前は」
ジムの中からドーッと歓声があがった。まだまだ宴会は続くようだ。「いつまで続くんだろう」とコーチは思った。「今夜の食事はどうなるんだろう」とも、コーチは思った。
※続きはこちら↓
