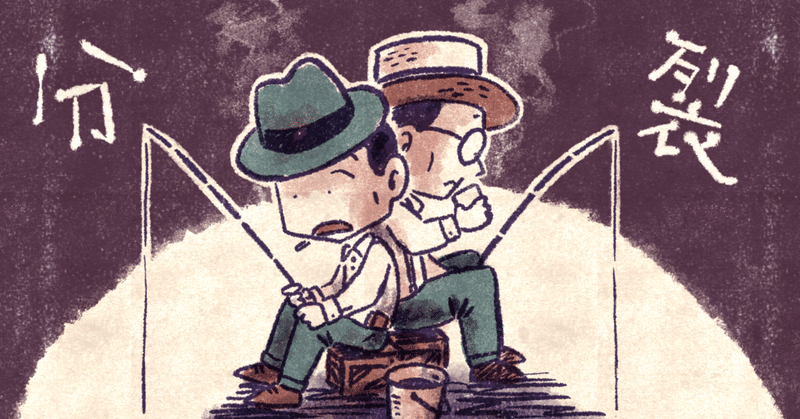
(37)分裂:引抜き騒動③/あきれたぼういず活動記
(前回のあらすじ)
吉本興業と新興キネマの板挟みになり身の危険が迫ったあきれたぼういずはバラバラに姿を隠した。
まもなく、坊屋と益田は新興キネマのある京都へ到着。
※あきれたぼういずの基礎情報は(1)を!
【カンヅメの川田と芝】
芝利英も一度は姿を隠したが、吉本側に見つかり連れ戻された。
坊屋 ここにあわれをとどめたのは私の弟芝利英で、あいつは二度ばかり捕って缶詰に会っています、一度はうまく逃げ出したが、よせばいいのに性来の呑気者、帝劇で映画を見ていると、すぐ前の席にいたのが吉本東京支社長の奥さんです、「オヤ、芝利英さんじゃありません、まアお珍しい」かなんか話をしているうちに、会社の方へ通知され、捕手がやって来、あっさり取ッつかまって熱海へ缶詰です
そんなわけで、川田とともに吉本側に押さえられ、監視付きで一日おきに温泉宿を転々とさせられる日々を送っていた。
映画や芝居を見に行くわけにもいかず、二人で釣りやピンポンや、五目並べばかりして気を紛らわしていた。
田舎の宿では美味しいコーヒーもなく、駅のコーヒーを買ってきては飲んでいたという。
芝 いちばんお終いは、伊豆の伊東で、新聞を買ったら、兄さん(坊屋三郎)と右太衛門さんの並んでいる写真が出ていて、懐しかった。なにしろ、二十日間も、音信不通で、いったい、みんなどうしているのか、さっぱりわからない。
とにかく、お互いに連絡が取り合えないのではどうしようもない。
川田と芝は、なんとか四人で会って話せないかと吉本側に訴えてみた。
すると、その時我々(僕と芝君)について監視の役目を引受けていたY氏なる人が、早速会社の方へ電報を打ってくれたのである。
「ボーヤヲフタリヨコセ」と打ったのである。ところが、発信時間が夜の十二時頃だったので、電報を受け取った会社に宿直の人しか居なかった。そして、その宿直の人は気を利かした積りででもあったろう、Y氏の自宅へ届けたのである。
…
さて、その翌朝、我々は例の通り宿の附近にある釣り堀へ出掛けていると、宿屋の女中が使いに来て――。
『只今、坊やさんがお二人お着きになりました。』
それっとばかり、早速、釣竿を投げ捨て、宿の部屋へ帰ってみると――。
八歳位の男の子と五つ位の可愛い坊やが二人、キチンと座敷の真ん中に座っているではないか。
僕らは、何んのシャレかと思ったが、よろこんだのはY氏だった。
『おう坊や、よく来たね。』
成程、Y氏の家庭には二人の坊やちゃんが、事件以来、家を留守にしていたお父ちゃんの顔を、何れ程恋しく懐かしく思っていたか知れないのだ。
結局、四人が顔を合わせてゆっくり話せたのは、引き抜き騒動が収まったずっと後だった。
【結末】
こうしてしばらくは、坊屋と益田が新興側、川田と芝が吉本側という状態が続いた。
この時期に書かれた『モダン日本』の記事では、
川田は結局、結婚の媒酌を吉本の専務林弘高にやって貰っているし、個人の借金も相当あるので、結局吉本に帰るだろう。芝利英は気が弱いから、こう騒ぎが大きくなっては、それを押し切っても新興へ行くと言う勇気は失ったと見てよい。
と分析している。
また、都新聞は「川田、芝に例の声帯模写の木下華声を加えて、再編成しようという案もある」と報じる(4月12日)。
どちらも、このまま二対二で落ち着くだろうという予想だ。
しかし、そんな報道と裏腹に、吉本では木下華声を中心に新たな演芸グループ「ザツオンブラザース」を結成。
あきれたぼういずが舞台に出られないので、その代わりといったところか。
4月13日には初公演を行っている。
また新興側は「既に身柄を寄せて来た坊屋三郎、益田喜頓のほかに、芝利英も加えてこの三名の正式入社を発表」している(都新聞・4月16日)。
ここで、坊屋が動いた。
芝を取り戻すべく、友達二人に応援を頼み、カンヅメにされているという宿へ乗り込んだのだ。
坊屋 時刻は夜、寝静まった宿屋の表の戸をドンドン叩きました…(中略)…これこれこういう者がいる筈だがときいても「そんなお方は居りません」の一点張り、しかしこっちはいるのを内偵しているんだから一歩も引かない、「イヤいるに違いない」と頑張りました
坊屋の救出作戦の甲斐あって、4月20日、芝は宿を脱して新興側へ合流した。
このとき、川田も同じ宿にいたはずだ。
別の記事で坊屋は、沼津の宿で川田と会った話をしているが、それがこのときではないだろうか。
坊屋 川田さんも、我々と一緒に行動を共にする約束だった。一緒に来られなかったのは、我々としても、まことに残念なのですが、沼津の宿で会った時、「吉本に残っても、いい仕事はさせてくれると、会社では言うから、新興へ行く必要はないじゃないか」とあべこべに引きとめるので、やむなく、別れたのです。
益田 吉本で「いい仕事をさせる」と言うのは、この前、松竹楽劇団へ行きかけた時も、そう言ったので、帰ってみれば、中々、そうはしてくれない。その苦い経験があるので、我々としては、一思いに新興へ移ってしまったわけなのです。
最終的には、川田のみが吉本に留まり、あとの三人は新興演芸部へ移籍した。
あきれたぼういずの移籍騒動は、グループが引き裂かれるという最悪の結末となってしまった。
うん、しようがなかった、あのときはああするしかなかったとはいえ、確かに、川田さんと分かれたのは惜しかった。あの人はやはりリーダー格だったしね。比重は大きかった。東京に残ってミルクブラザーズを始めたとき、川田さんも、坊屋がいりゃあな、と言ったそうだよ。
《補足:すれ違い》
この引き抜き騒動について、実はあきれたぼういず一人一人の認識にはかなり相違がある。
益田は、川田が新興演芸部からの契約金を受け取っておきながら、吉本にバラしてしまった……つまり、川田が自分達三人を新興に売ったのだ、と感じているようだ。
のちに川田は契約金を返却しているが、そこは伝わらなかったのかもしれない。
対して川田は、「これは一言にして言えば、坊屋三郎君が、自分一本立でやって行ける自信を得て、僕と袂を別ったのである」(「あきれた自叙伝」/『中央公論』1940年春季特別号)と捉えている。
坊屋が先導して自分を裏切ったのだ、という思いが強かったようである。
川田は三人に去られたあと、かなり落ち込んでいたようだ。
坊屋は、自らの強い意志で移籍を決意し、行動したように見える。
ただ、川田を裏切る気持ちはなかったようで、当時の記事では川田も一緒に移籍して来てくれると信じている様子がわかる。
のちの回想でも、別れ別れになってしまったことをしきりに残念がっている。
芝は、最初は川田とともに吉本側にいたにもかかわらず、結局は新興へ移った。
四人の中でもとくに両社の間で揺れ動く立場だったといえる。
吉本での現状に不満はあったようだが、
この騒動の最中に彼がどう感じ、何を考えて動いたのか、その胸中は残念ながら手元の資料ではわからない。
結果的に道産子三人と江戸っ子の川田とで分かれたのも、偶然ではないように思える。
このnoteでも見てきたように、東京生まれ東京育ちの川田は幼い頃から浅草に親しんでいる。
浅草への思い入れが強かったのかもしれない。
吉本への義理を重んじる人柄も江戸っ子の川田らしい。
一方、北海道開拓移住者二世・三世である坊屋・芝・益田らは比較的近代的・合理的な価値観を持っているように感じる。
また、浅草を愛する気持ちは三人も変わらないが、経歴を見ていくと浅草以外にいた時期も長い。
芝は一度はグラン・テッカールの一員として浅草に出てきたものの、ひと月足らずで関西のオオタケ・フォーリーへ移っており、関西の空気も好きだったのかもしれない。
吉本での芸歴も川田に比べれば短い。
そのあたりにも、この分裂の要因がありそうに思える。
【参考文献】
『川田晴久読本』池内紀ほか/中央公論新社/2003
『キートンの人生楽屋ばなし』益田喜頓/北海道新聞社/1990
『キートンの浅草ばなし』益田喜頓/読売新聞社/1986
『これはマジメな喜劇でス』坊屋三郎/博美舘出版/1990
「あれやこれ・脱退騒ぎの真相」/『モダン日本』1939年6月号
「あきれたぼういず朗らかに語る」/『スタア』1939年7月上旬号/スタア社
「坊や」川田義雄/『実業の日本』1939年7月号/実業之日本社
「あきれた自敍傳」川田義雄/『中央公論』1940年春季特別号/中央公論新社
「ちょいと出ましたあきれたぼういず」坊屋三郎/『広告批評』1992年10月号/マドラ出版
「朝日新聞」/朝日新聞社
「都新聞」/都新聞社
「京都日日新聞」/京都日日新聞社
(次回10/22)続出するボーイズ達
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
