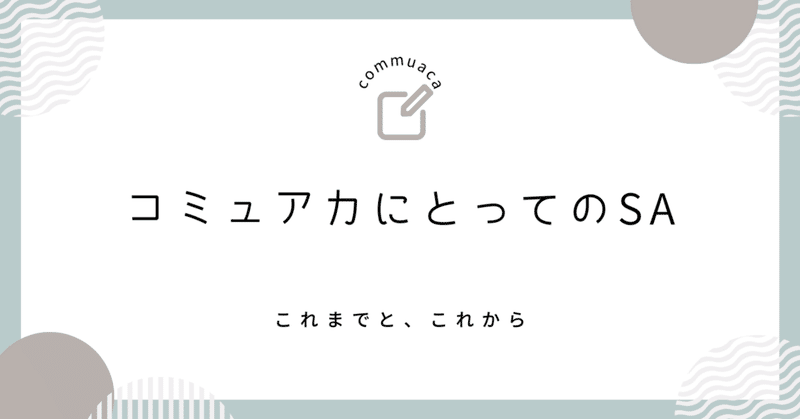
コミュアカにとってのSA 〜これまでと、これから〜
西本が授業を担当している京都精華大学「コミュニケーションスキル」「アカデミックスキル」(以下:コミュアカ)には、全40クラスの授業をサポートしてくれる学生アルバイト、通称SAがいます。
ありがたいことに、SAの募集には毎年たくさんの応募があります。エントリーシートと面接で合否を決めているのですが、西本がどういう基準で応募者を見ているのか、SAに何を求めているのか、そもそもなぜSA制度を作ったのか…などを言語化したいなとふと思い立ち、記事を書くことにしました。

下記に当てはまる人がいれば、続きを読んでみてください。
① 現役SAメンバー、OB・OG
② これからSAになりたいと考えている人
③ 単純に西本の頭の中をのぞいてみたい人
④ なんかヒマだから読んでやるよという人
1. SA制度を作った理由
SA制度のモデルは、西本の母校である立命館大学の「オリター(エンター)制度」です。以下、エンターと書きます(出身学部がバレますね)
オリター(エンター)とは、新入生の大学生活に関する不安を取り除けるよう様々な面からサポートを行う、2回生以上の学生で組織された団体です。
当時(今も?)は「基礎演習」と呼ばれる授業がありました。大学生活の心得やチームビルディング、レポートの書き方など、一般的に初年次教育で行われるようなことをひと通りやるという感じの授業で、各クラス(30名前後)に担当のエンターが3〜4人配置され、授業のサポートをしていました。
課外でもどんどんイベントを開催するなどして新入生を盛り立てていくエンターは、学部の中でも花形の存在でした。1回生が終わる頃には「エンター応募する?」という話題があちこちで出るほど。西本も応募して運良く採用となり、1年間活動しました。

そんな経緯があり、以前から「セイカでエンターみたいな制度作りたいな」と思っていたのです。そこであるとき会議で思いきって提案したところ、OKが出て、学内アルバイトとしてのSA制度がスタートすることになったわけです。(ちなみにエンターは学生自治会による活動で無給だったので、そこは少し違います)
2. SAの仕事とは?
SAって何するの?と聞かれることも多いのですが、主な仕事は次の3つです。
⚫︎ 個人ワーク、およびグループワークの補助
⚫︎ 留学生の日本語フォロー、通訳
⚫︎ 授業に関する公式SNSの更新、広報活動 など
グループワークが多い授業なので、話し合いが円滑に授業が進むように補助に入ってもらうことが多いですね。あと、留学生が多い(比率で言うと日7:留3くらい)ので、教員の指示が聞き取れているか、課題の内容を理解できているかなどを確認して、適宜必要なアドバイスをしてもらっています。
3. SAに必要なスキル
スキル① 「観察力」
SAとして活動する上で大切な能力はいくつかあるのですが、主要なものを挙げるとすれば、まずは「観察力」です。
表情や声のトーン、ちょっとした仕草などを手掛かりに、手助けが必要な学生の存在に気づく必要があります。逆に、自走し始めたと思われる学生、もしくはグループを見つけたら、過度に干渉せず、少し引いた場所から見守ることも重要です。

こうした動き方を「介入と傍観のバランス」ということばで表現してくれたSAのメンバーがいました。言い得て妙ですね。両者のバランスを上手く取るためには、相手をしっかりと観察することが求められるので、面接ではそのスキルがあるか(ありそうか)どうかを知るために、次のような質問をしました。
Q. グループワーク中、どのような場面で苦労したり、困難を感じたりしたか? それに対してあなたはどのように工夫や行動をしたか?
Q. 1・2クオーター(前期)と3・4クオーター(後期)の担当教員は、それぞれどのようなことを大切にして授業をしていると思ったか? また、それはどういった場面で感じ取れたか?
難しい質問だとはわかっていますが、こちらとしては聞いてみたいですよね。
スキル② 「他者への解像度」
「観察力」が研ぎ澄まされてくると、「他者への解像度」が高まります。スキル①と②は、連動していると言っていいでしょう。
例えば、全然グループワークに参加していない学生がいたとします。そうした学生を見つけた場合はSAとして介入が必要になるわけですが、そこでクエスチョン。
Q. なぜその学生はグループワークに参加していないのか?
理由はいくつか考えられます。
・授業自体に興味が持てず、無気力状態になっている
・グループワークが苦手で輪に入っていけずにいる
・グループの中に苦手な人がいて、あまり関わりたくないと思っている
・教員の説明や課題内容を理解しておらず、置いてけぼりになっている
・前日に十分な睡眠が取れておらず、眠くてぼーっとしている
・体調不良であることを言い出せず、じっと耐えている
・その他、何らかの事情で授業に集中できなくなっている
何が理由かによって、対処法が変わると思いませんか?
これが、西本の言う「他者への解像度」です。
ここで大切なのは、参加していない=やる気がないダメな学生、と断じてしまわないことです。僕たち教員もやってしまいがちなので、気をつけないといけません。目の前の事象の背後にあるものに気付こうとする眼差しを持つことが肝要です。
SAに応募してくれる学生は、コミュアカの授業でいい成績を取っていて、グループワークも得意だという人が多いんですね。それ自体は素晴らしいことなのですが、SAとして活動してもらうときには、グループワークが苦手な人の存在が視野に入っているか、そしてその人にどう手助けすればいいかをその場で考えて、自分なりの答えを出せるかが重要になります。
面接では、受け答えの内容や着眼点から、そうした解像度の高さを見ていたような気がします。

スキル③ 「一歩下がる力」
面接で「私がSAとして悩める1回生をまとめていきたい、良き方向へ導いていきたい」と話してくれる人がいます。自身が持つリーダーシップを発揮しようとしてくれる心意気はとてもうれしいのですが、西本がSAに求めているのは、むしろ逆の力なんです。
老子の格言に「魚を釣ってあげるのではなく、魚の釣り方を教えてあげる」という言葉があります。これを実践できる人が、SAになってほしい人です。
悩んでる1回生に「こうすればいいよ」と答えを教えてしまったり、強引に議論を取りまとめたりすると、その場では「先輩が全部解決してくれた、すごい!」となるでしょうが、それは相手が成長する機会を奪ってしまうことにもなります。
授業の主役はあくまで1回生。SAが目立ちすぎてはいけないし、彼らが活躍するための余白を勝手に埋めちゃいけないんですよね。「導く」「教えてあげる」のではなく、「気づきを促す」「後押しする」のが、SAの仕事です。

3. SAに期待していること
SA制度は4年目がスタートします。人数も初年度の12人から、倍の25人に増えました。学部・学科・学年・国籍 … 多様性のあるメンバー構成になりました。そんなみなさんに、西本が期待していることを書いていきます。
期待① 「自分なりのSA像」を創ってほしい
SAをしていると「さっきの声掛けはあれで良かったのかな」「間違ったアドバイスをしていないかな」と悩むときがきます。実際、過去の先輩たちも同じことで悩んでいました。「こんなときどうすれば…」という場面はたくさん訪れることでしょう。
そのとき、意識してほしいのは「こうすれば正解」なんてものはない、ということです。もちろん、過去の経験をもとに「あのときはこうして上手くいったから、次もこうしよう」と一定のマニュアル化をすることは可能です。資料化しているので、研修のときに紹介しますね。
しかし、「あのとき」と「今」で、目の前にいるのは同じ人ではない、ということを忘れないようにしてください。似たようなシチュエーションであっても、掛けてほしいことばや、とってほしい態度は、相手によって異なります。
もちろん、相手を意図的に傷つけるような言動や行動は御法度ですが、それ以外の「自分なりに捻り出した答え」は、だいたいどれも正解です。だから、正解を探すのではなく、自分で創ってみてください。それはきっと、相手にも届くはずです。仮に届かなかったとしても、そうした営みの繰り返しがコミュニケーションですから、落ち込む必要はありません。
物事の是非は、決断したときに決まるものではない。評価が定まるのは常に後になってからだ。もしかしたら、間違っているかもしれない。だからこそ、今自分が正しいと信じる選択をしなければならないと思う。決して後悔をしないために。
西本は、今これを読んでいるあなたに、「あなたにしかなれないSA」になってほしいと思っています。そのためには、逆説的ですが、どんどん失敗してほしいなと。試行錯誤しながら「正解」のストライクゾーンを広げていってほしいなと考えています。

あ、もちろん相談には乗りますし、必要な手助けはしますからね。
期待② 「原石」を見つけてほしい
これは個人的な願望なので、話半分で聞いてください。
セイカに限らず、大学という場所には「今までの自分を変えたい」と願い、その想いを胸に秘めている人がたくさんいます。夢の実現に近づきたい、もっと積極的になりたい、自分だけの個性を見つけたい…などなど。
そんな想いを持った人が、コミュアカの教室にもたくさんいるでしょう。でも、ちょっと尻込みしてしまっていたり、周りの雰囲気に呑まれてしまっていたりするかもしれません。「やっぱり自分はダメなんだ」と、挫けそうになっている人がいるかもしれません。
西本はそうした、今から大きく飛び立とうとしている人のことを「原石」と呼んでいます。コミュアカという授業を、そんな「原石」が未来へ羽ばたくための滑走路にしたいんです。だから、離陸しようと試行錯誤している「原石」を見つけて、そっとその背中を押してあげてほしいんですね。
「コミュアカがあったから」
「あの授業がきっかけで」
烏滸がましいかもしれませんが、そう思ってもらえるような授業にしたい。
たかが初年次のイチ必修科目に過ぎないけれど、それでもなお、7年間この授業を創ってきた人間として、滑走路の整備を続けたいと思っています。
だから、それを手伝ってほしい。
これが本音かなー

ひとりでも多くの学生に「受けてよかった」と思ってもらえる授業にするために、みなさんの力を貸してください。
よろしく!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
