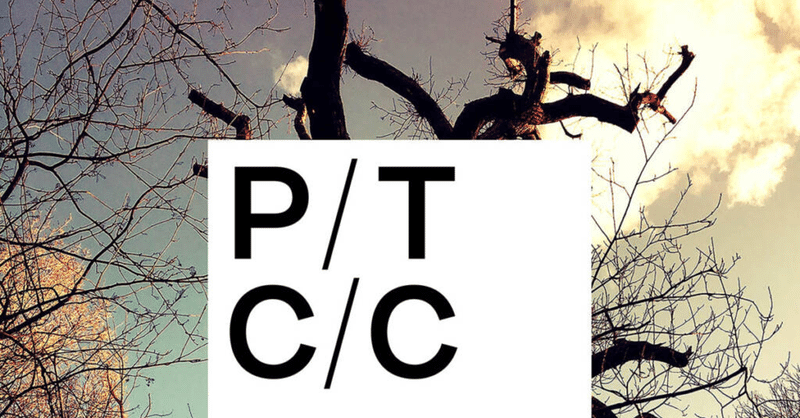
Porcupine Tree 『Closure / Continuation』 (2022)
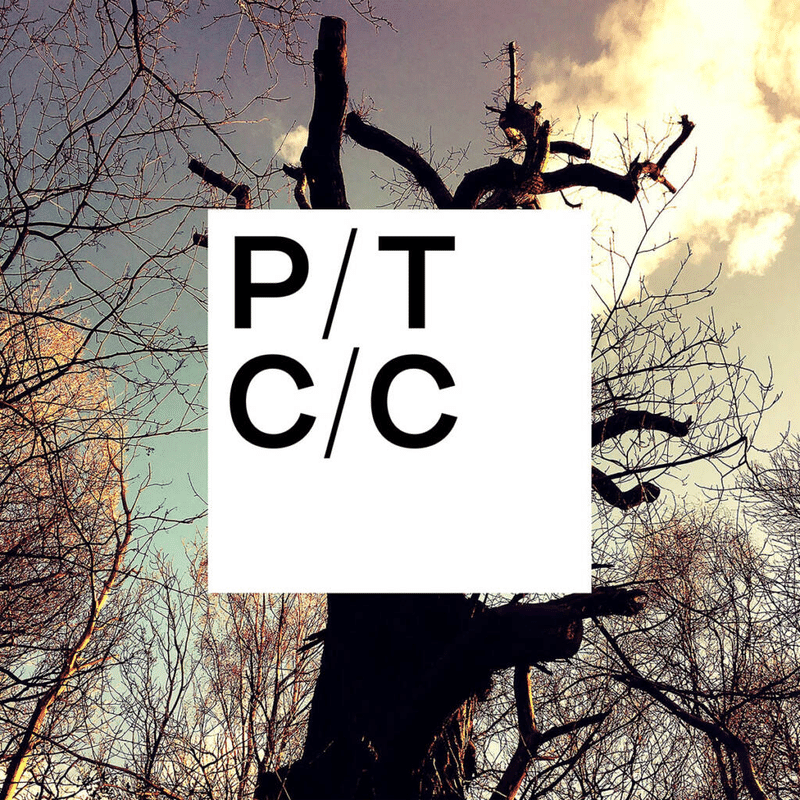
9/10
★★★★★★★★★☆
Porcupine Tree(以下PT)はポストプログレ史上最高のバンドと呼ばれることも多く、Pink Floyd, King Crimson, Rushといったレジェンドから、Dream Theater, Katatonia, Anathema, Opeth, Leprous, The Pineapple Thief, Hakenといった同世代/後進まで、数多くのバンドの賛辞を一身に集め続けたバンドだ。元々「架空の伝説のプログレバンドを再現する」というコンセプトの下、ボーカル/ギター/ベースのSteven Wilson(以下SW)が(ほぼ)一人で半ばジョークとして1993年に始めたプロジェクトだが、まさにそのコンセプトが現実になったバンドと言える。
アルバムを10枚リリースした後、各々の活動(特にSWのソロ活動)に集中すべく2010年頃から事実上の活動停止となっていたが、それ以降もSWにはPT用の曲のアイデアが浮かんでおり、それらを元にRichard Barbieli(キーボード、元Japan), Gavin Harrison(ドラム、現King Crimson, 現The Pineapple Thief)という手練れと再び集結し作り上げた13年ぶりの作品が本作だ。
*
何回か聴いて感じるのは、これまであらゆる音楽を飲み込み拡大を続けてきたPT、そしてSWのこれまでの音楽的冒険を統合する、集大成、そしてピラミッドの頂点としての作品なのではないかということ。そしてそれが、過去最も筋肉質で無駄のない強靭なバンドアンサンブルによって見事に表現されていること。
"Harridan", "Rats Return", "Herd Culling"では、PTの『Deadwing』(2005)やSWの『The Raven Refused To Sing』(2012)で花開いた、ヘヴィアンサンブルを単調に聴かせない工夫が散りばめられている。SWのギターは変幻自在。ヘヴィリフをかき鳴らした数秒後にはクリーンやディレイが静寂を支配している。Gavinのドラムは超絶技巧をひけらかさずSWの詩情に寄り添う。ただ緊張感抜群の"Harridan"や"Herd Cullig"の11拍子など、その巧さはとても隠し切れていない。"Harridan"のブレイクはSWのPaul Draperとの活動で得られた7th majorのコードプログレスの特徴が濃い。
また柔らかくメロディアスな"Of The New Day"や"Dignity"には、PTの『Lightbulb Sun』(2000)やSWの『Insurgents』(2008)までの雰囲気が生きている。この広い空間構築はRichardもSWも得意とするところ。そうかと思えば"Walk The Plank"をはじめとしてアルバム全編に敷き詰められたシンセアンビエントのエレメントは、SWのNo-Manでの活動、そしてソロ作『To The Bone』(2017), 『The Future Bites』(2021)で培われたものだ。
超モダンな音の鳴り/ミックスは絶対にソロ作での活動を経てこそのもので、かつてのPTのアルバムとは隔世の感がある。かなり進化している。特に『The Future Bites』での経験がかなり大きく活かされていると思う。あのアルバムのスーパーデラックス版を聴けば、まるで本作の試作品に聴こえるようなパーツも見つけることができる。
個人的なことを言えば、これまでPTのアルバムに心を掴まれたことはそこまで無いのだが、本作は全く別次元で、聴くたびにため息が出るほど圧倒されている。
*
このバンド、そしてSWという存在は、「プログレ」という狭い枠に押し込められるような閉じた才能ではない。広義のロックを代表する全能的なアーティストだということが、はやく一般層にも知られることを願うし、本作はその一助を担う決定的な作品だと信じている。
8,9,10はボーナストラック。8はバンドアンサンブルを見せつける迫力満点のインスト。9はバランスの取れたオルタナティヴロック寄りのプログレ。ソロミニアルバム『4 1/2』(2016)や、あるいはBiffy Clyroなんかも思い出させる。10はギタポ的なギターで始まりポップな清涼感を振りまく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
