
JIS Q14064-1 どう変わったの?(その1)
GHGに関するJISは複数存在します。
「ファミリー規格」とくくられますが、それぞれの関係については、このように整理されています。(それぞれの規格に同じ図が掲載されています)

その中でも、算定に関わるISOは、通称「64シリーズ」と呼ばれる3規格。
検証に関わるISOは、ISO14065及び14066が代表的な規格です。

企業のサスティナビリティ担当の方が多くお越し頂いていると思いますので、検証を受ける側についてご案内していこうと思います。また、製品のライフサイクル排出量であるCFPの規格(ISO14067)は、64シリーズと若干異なり、かつ、改訂も入っていないので、対象外とさせて下さい。
実際の業務では、ISOに準拠して策定されるJISに基づいて検証を行います。
JIS化されたISOは、単なる翻訳版ではなく、国内の事情(日本語の意味合いや、使用のされ方、認識・認知の程度など)を考慮されたものです。
ですので、ISOが改訂されてからJIS化されるまで、タイムラグがあるのが普通で、上記の4規格も例外ではありませんでした。
とはいえ、あくまでも、ISOが「正」ですので、検証機関は、独自に翻訳し、独自に解釈して検証業務を行っていたのが実情でした。
それが、2023年ようやくJIS化されました。
比較するとこんな感じですが、ISO改訂後、4〜5年かかっていますね。
ISO
14064-1 2006→2018
14064−2 2006→2019
14064-3 2006→2019
JIS
Q14064-1 2010→2023
Q14064−2 2006→2024
Q14064-3 2011→2023
規格は「著作物」なので、購入する必要がありますが、ウェブサイトでサンプルを参照することができます。いずれも、目次は見ることができますので、必要に応じて購入しましょう。(サイトから直接購入できます)
今回は、組織の排出量を算定して、第三者検証を受審する企業の担当者を想定していますので、「JIS Q14064−1」の2010年版から2023年版への変更について、見ていきたいと思います。
さて、ISO14064-1が、国際的に広く採用されている、算定方法であるGHGプロトコルの重要な概念及び要求事項を取り入れて改訂された一方、JISは旧版のままだったため、特に、グローバル企業から「整合した活動が行えるよう改正してほしい」という要請を背景に、今回の改正に至ったとあります。
とはいえ、前述したように、検証機関はJISの旧版を考慮しつつ、ISOの改訂版に基づいて検証していたと思います。今回、日本規格協会という大本営の解釈が出ましたので、次回以降の検証で、何がしらかの影響があるかもしれませんが、基本GHGプロトコルなので、ご心配には及ばないかと。
それでは、使用されている用語について見てみましょう。
新旧で項番が、2→3とずれているのは、「2.引用規格」が追加されたため。
ただ、「この規格には、引用規格はない。」とあるだけなので無視してOK。
加えて、新版には「0.序文」が追加され、人為的活動に起因する気候変動の認識が高まった背景が、説明されています。

ぱっと見、「この規格」の方が「旧規格」よりも馴染みがあるのでは?
ISOがGHGプロトコルを取り込んで開発されてきた経緯がよく分かります。
「一次データ」や「組織境界」など、今までなかったのが不思議なものもありますね。
個人的には「重要性(materiality)」が削除されている点が気になりました。
ですが、本文に当たって納得。
改訂版では、「組織の排出量の算定」に関わる要求事項のみを記載し、検証や検証機関、検証人に対する要求事項は、それぞれの規格を参照することとしていたのでした。

参照先である「JIS Q14064-3」を見てみると、用語の定義もしっかりされておりました。
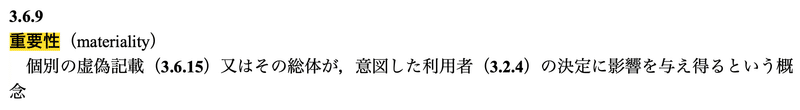
まぁ、この辺りは、実務には殆ど影響が無い改訂内容だと思います。
が、しかし、「3.1.11 間接的な温室効果ガス」については、手順・マニュアルの変更も必要となるほどの「インパクト」があるのではないでしょうか。
システマチックに算定していれば、問題ないかと思うところ、属人的な算定に頼っていたとしたら、ちょっと面倒な作業が発生するかもしれません。
ということで、次回は、その具体的な内容を、説明したいと思います。
お楽しみに。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。
